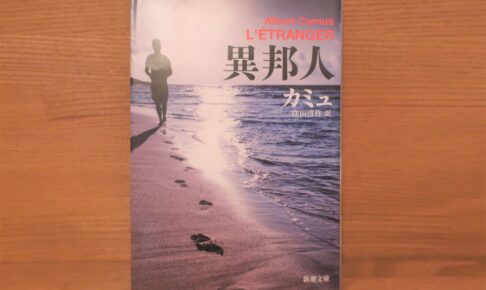ロシア文学史に残るドイツでのドストエフスキーとツルゲーネフの大喧嘩
1845年に初めて顔を合わせ、間もなく犬猿の仲となったドストエフスキーとツルゲーネフ。はじめての出会いは以前の記事「ツルゲーネフとドストエフスキーの出会い―因縁のはじまり」でも紹介させて頂きました。
彼らの因縁は2人の最晩年まで続くことになります。
そんな2人が決定的な衝突をした有名な事件が1867年、ドイツのバーデン・バーデンという世界的に知られる保養地で起こることになりました。

今回の記事ではドストエフスキーとツルゲーネフを語る上で外せない、その大喧嘩についてお話ししていきます。
1867年という年はドストエフスキーが『罪と罰』を発表した翌年にあたり、新婚の妻アンナ夫人と共にヨーロッパ外遊をスタートさせた年でした。
ドストエフスキーは新しい小説『白痴』の構想を練りながら外国生活をする予定でしたがドイツのバーデンバーデンでカジノに熱中し、ギャンブル中毒の発作に陥ります。
彼はあっという間にすってんてんになり、妻の大切な装飾品まで質に入れてなんとかその日暮らしをするという悲惨な状況にありました。
そんな中彼は同じバーデンバーデンにあのツルゲーネフがいることを思い出し妻にそのことを告げます。彼はかつてツルゲーネフから50ターレルの金を借金をし、まだ返していなかったのです。
カジノですってんてんの彼に返済など当然できません。しかし妻の勧めでツルゲーネフを訪ねることになったのです。事件はここから始まります。
ドストエフスキーは渋々、重い腰をあげる。彼にはツルゲーネフの洗練された、いかにも貴族の出といった、その優雅な立居振舞が、なんとも癪にさわるのだ。挨拶するときに、彼に優しく抱擁されると吐き気がする。
それに第一、その作家が最近発表した『煙』という長篇小説が気に喰わなかった。「ロシアが地球の表面から消え失せたとしても、地上の人間にとっては、なんの損失にもならないし、後悔もしないだろう」という一節が妙に引っかかった。会見が始まるとすぐに、ふたりの会話は張りつめてきて緊迫してきた。
「彼はわたしに自分は無神論者だときっぱりいいきったのです。ともあれ、理神論は、われわれにキリストを提示しました。それはいうなれば敬虔な宗教心がなければ理解できないし、永遠の理想だと信じるしかないほどの崇高な人間像にまで高められているのです!
それをあのツルゲーネフ、ゲルツェン、ウーチン、チェルヌイシェフスキーといった連中は、神の代りにわれわれになにを示してくれたというのです!
あの連中はそろいもそろって恥知らずなほど思慮が浅く、醜悪なほどひどいうぬぼれやぞろいで、こっちが呆れてしまうような手合いです。いったい彼らはなにな望んでいるというのでしょう?それにだれが彼ら支持するというのです?」(一八六七年八月二十八日、マイコフあての手紙)
どうにも腹にすえかねるのは、ツルゲーネフが、祖国を愛しているといいながらも、ロシアを蔑視していることだ。
「第一、あのツルゲーネフは、われわれはドイツ人の前で這いつくばらなければならない、といって憚らないのです。
この地上にあって、唯一の共通する道というのは、とりもなおさずそれは文明の道だから、やれロシア主義だ、スラヴ主義だ、とわめきたてるのは愚の骨頂だというんです。そこで彼はいま、あらゆるスラヴ主義者に向って、大論文を執筆中だと息巻いていました。
そこでわたしはついいってやったのです。どうです、便利でしょうからひとつパリの望遠鏡を取りよせてみては?と忠告すると、やっこさん、どうしてだね?と怪訝な顔をするんです。そこでこう応えてやったのです。「ここからではロシアは遠すぎますよ。望遠鏡をロシアに向けて、よくみてみることですね。そうでないとあなたには、どうやらわれわれのことがなかなかつかみにくいようだから』」
そのことばをきくと、ツルゲーネフは真赤になって激怒し、唇をぎゅっとかみしめたままむっつり黙りこんでしまう。するとドストエフスキーは、『煙』が寄ってたかって批評家にこっぴどく叩かれていたのを知っていたので、じつにさり気なく、無邪気な口調でまたこういった。
「『煙』の失敗や、あなたに対して悪意をむき出しにした批評なんかで、それほどまでに神経を立てていらっしゃるとは、思いもよりませんでした。そんなことに、いちいちふりまわされない方がいいですよ!」
「なんだって!きみはわたしが腹を立てているとでも思っているのかね!」と相手はますます力んでみせる。
ドストエフスキーは話題を変えようとして、今度はドイツ人をこてんこてんにこきおろし出した。ところがツルゲーネフは、怒り心頭に発して、わなわな震えて、
「そういうことをいって、きみはわたしを個人的に侮辱するつもりかね!わたしはここを永住の地と定めて、自分はもうロシア人ではなく、ドイツ人なんだと思って暮しているし、それを誇りに思っているというのに!」
根なし草の貴族をぐうの音も出ないほどやっつけたことがよほどうれしかったのか、ドストエフスキーは、意気揚揚と自宅に帰ってくる。
中央公論社 アンリ・トロワイヤ 村上香住子訳『ドストエフスキー伝』P285-287
これがドストエフスキーとツルゲーネフの大喧嘩の顛末です。ここでは2人の喧嘩が個人的な性格や意見の不一致によるもののように読めますが、モチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』ではこの喧嘩にもっと根源的な対立を読み取っています。せっかくですのでこちらも見ていきましょう。
バーデン―バーデンでドストエフスキーとツルゲーネフとの関係決裂が生じた。こうなる下地は遠く四〇年代に早くも作られていた。
バーデンでのツルゲーネフとの出会いは神の導きともいうべきものだった。
ドストエフスキーは新生ロシアについての長篇小説を計画し、ロシア人として、キリスト教徒として自覚しつつあったが、相手として論争できるような敵を、生きた具体的な人物を必要としていた。
彼のあらゆる創作は、公然・非公然たるを問わず内的な論争なのだ。彼が確固とした理想を創造するためには、否定的な現実を出発点とすることが不可欠だった。
彼のすぐれた才能はもっぱら闘争において発揮され、彼の本質は弁証法的なものだった。だからこそツルゲーネフは、ロシアの悪のシンボル、民族的宗教的変節の具現者とされたのである。『煙』の作者との論争をつうじてドストエフスキーの世界観は結晶化して行ったのだった。
モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』松下裕・松下恭子訳P355
ここでいう40年代の下地というのは、ドストエフスキーが文壇デビューしてから間もなくツルゲーネフが彼を嘲笑しいじめたことを指しています。ドストエフスキーはその時の憎しみを忘れることができませんでした。その時点でツルゲーネフは彼にとって乗り越えねばならぬ宿敵となったのです。
また、新生ロシアについての長編小説というのは『白痴』を指しており、ドストエフスキーはこの小説でキリストを描こうとしていたのでありました。
ここでモチューリスキーが指摘しているように、ドストエフスキーが思想を練るときはまず、敵を必要としていました。乗り越えなければならない悪があるからこそ、より善なるものを生み出すことができるのです。
これはなんとなくわかりますよね。私達も納得できない理不尽さや敗北を感じた時「何クソ!」と思いがけぬパワーを発揮するものです。強大なライバルの存在は自分も高めることになります。(その分憎らしさも強大かもしれませんが)
こうしてドストエフスキーはライバルツルゲーネフに対して向かって行くのです。
ドストエフスキーはマイコフあての手紙をこう結んでいる。
「きっとあなたには、わたしがツルゲーネフのことを描く底意地わるさや、たがいに侮辱しあった話を不快に感じられることでしよう。だが、神かけて誓いますが、わたしは耐えられなかったのです。彼はその信念によってあまりにもひどく侮辱したのですからね」。
この「侮辱」は、ドストエフスキーの「信念」にとっては試薬の役割をはたしたのだった。
無神論者、コスモポリタン、西ヨーロッパ主義者のツルゲーネフにみずからを対置させながら、彼は自分のキリスト教的、民族主義的・ロシア的世界観を作りあげて行く。
だがこの二人の作家の絶交の根底には、いっそう深い形而上学的な食いちがいがあった。
ツルゲーネフは優柔不断な運命論者で、歴史を没個性的な決定論的な過程としてとらえていた。ところがドストエフスキーのほうは、意志の自由と個人の力を確信していた。
ツルゲーネフは、「神というものがあるのかどうか、わたしは知らない。だが因果律はわたしにははっきりしている。二掛ける二が四であるように」と書いている。
いっぽうドストエフスキーは、絶望的な狂暴さで必然性に立ちむかい、意志的な行動で神への信仰を「つかみとった」のである。
ツルゲーネフは晩年、「ラ・レジニャシオン、ラ・イドゥーズ・レジニャシオン」(諦念、醜い諦念)にたどりついたが、ドストエフスキーは「人間の崇高な理想―キリスト」に到達している。
ドストエフスキーとツルゲーネフとの紛争は、たんなる文学的な論争ではなかった。そこにはロシア人の自覚の悲劇が現われている。
モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』松下裕・松下恭子訳P358
ドストエフスキーは深刻過ぎるほどに思索を進めていく人間です。ロシア人の未来はどうなるのかということをドストエフスキーは真剣に案じていました。
このツルゲーネフとの衝突は文学上の対立の枠を超えてロシア人の精神をめぐる衝突でもあったのです。
こうした面から見ていくと不仲の2人による単なる喧嘩で終わらないものを感じさせます。
さて、この一件に対して当のツルゲーネフはどう感じていたのかというのも気になるところです。ドストエフスキー側の本ではそのことにお目にかかることがなかったのですがアンリ・トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』にはそのことが書かれていましたので引用します。
二人は素っ気なく別れた。ドストエフスキーはこの根なし草の大殿様を追いつめて怒らせたことに有頂天になって、自国に戻った。
もしかしたらマイコフに報告する際、ドストエフスキーはトゥルゲーネフの反ロシア発言をいい気になって大げさに言い立てたのかもしれない。
またもしかしたら、トゥルゲーネフも、ドストエフスキーのあくまでスラヴ贔屓で、ギリシア正教派で、救世主待望論に凝り固まったその態度がしゃくにさわって、なんでもかんでも反論したい思いに駆り立てられたのかもしれない。
いずれにしても、ロシアでマイコフが受け取った手紙は、あいにくの形で公開されてしまった。手紙の何箇所かを、受け取ったマイコフが写し取り、雑誌『ロシア資料館』の編集長バルテーネフに手渡したのである。「この文面が後世まで残る」ように、というわけだった。
アンネンコフから知らせを受けたトゥルゲーネフは、バルテーネフに抗議の手紙を書いている。
「(ロシアおよびロシア人についての)私の内なる信念を、ドストエフスキー氏の前で披歴するようなことはすべきではなかった、とここに申し上げておく必要があると思います。それは病気の発作やその他もろもろの理由によって、氏が十全な心的能力を有していないと、私が考えているからにほかなりません。
しかも氏について同様の考えを抱いている者は多くいます。私がドストエフスキー氏と会ったのは一回きりです。彼は私の家には一時間もいませんでした。それもドイツ人と私、それから私の本にさんざん侮辱を加えて、気が晴れると出て行ってしまったのです。私には反論するいとまもありませんでしたし、その気も起こりませんでした。
繰り返しますが、私は彼を病人として扱いました。どうやらあの人が私から聞いたと思っている主張は、妄想でできあがっているようで、しかも彼は私を攻撃すべく、この……報告書を後世の人々に向けて書いているのです。
一八九〇年になれば、ドストエフスキー氏も私も同国人の関心を集めなくなっているかもしれません。それでも、もしも我々がまったく忘れ去られているのでなければ、偏った情報に基づいてではなく、全生涯、全作品という結果に基づいて、人々は我々を判断してくれるでしょう。」
水声社 アンリ・トロワイヤ 市川裕見子訳『トゥルゲーネフ伝』P144-145
これは極端を嫌う中道主義者、ツルゲーネフらしい言葉であるなとつくづく感じます。やはり彼には落ち着いた大貴族の余裕があります。
ツルゲーネフの言うことももっともだなと正直私は思ってしまいました。
たしかにこの頃のドストエフスキーはギャンブル中毒で精神的にかなり危機的な状況にありました。しかももともと神経質で極端から極端に揺れ動く不安定な混沌を抱えた人間です。狂気のごとくまくしたてるドストエフスキーに優雅で温和なツルゲーネフはさぞ面食らったことでしょう。
ツルゲーネフがそう思うのも無理はないような気がします。
ただ、忘れてはいけないことがあります。
1845年、ツルゲーネフは軽い気持ちでドストエフスキーをさんざんこき下ろし、いじめました。その時の憎しみをドストエフスキーは忘れられなかったのではないでしょうか。
その頃のドストエフスキーはまだまだ世間を知らない若造でした。世慣れた伊達男ツルゲーネフにはまったく太刀打ちできなかったのです。
しかしドストエフスキーはそれから20年、幾多の試練を乗り越えてきました。
死刑判決を宣告され、シベリア流刑では極限状態を生き抜き、ペテルブルクに帰還後作家として復活。『死の家の記録』や『罪と罰』で圧倒的な評価を得ます。彼は一回りも二回りも大きくなって復活したのです。
彼はもうツルゲーネフにいじめられていた頃のドストエフスキーではありません。
そうした自負が彼の中に本当にあったかどうかはわかりません。しかしツルゲーネフに対して感じていた複雑な感情を直接ぶつけたかったとしてもなんら不思議はありません。
ツルゲーネフのことを知った今となっては、私はもはや一方的に彼を悪玉として嫌うことはできません。ですがやはりドストエフスキーを応援したくなってしまいます。ツルゲーネフにも自分でこの衝突を招いてしまったところもやはりあるのです。
結果的には大喧嘩ということにはなってしまいましたがこの個人的、思想的対決があったからこそドストエフスキーの中に確固たる何かが生まれたのも事実だと思います。
そういう意味ではやはりツルゲーネフは巨大なる存在であり、憎々しい宿敵ではあるけれども彼のおかげでドストエフスキーはさらなる思想的高みに上っていくことができたのではないかと私は思います。
以上、「ロシア文学史に残るドイツでのドストエフスキーとツルゲーネフの大喧嘩」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら
関連記事