インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本~入門から専門書まで私がぜひおすすめしたい逸品を紹介します
この記事ではブッダやインドの仏教を知る入門書としておすすめの作品を紹介し、その後はもっと仏教を知りたい方におすすめの参考書を厳選してご紹介していきます。
私のチョイスする参考書は仏教書としては一風変わったラインナップになりますがきっと皆さんの新たな発見のお役に立てるのではないかと確信しております。
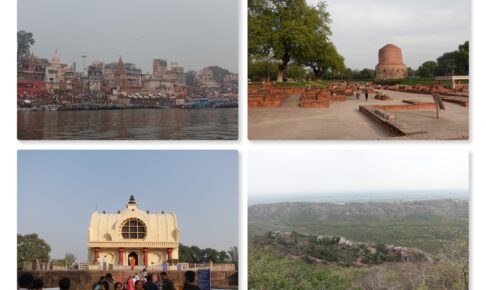 インドにおける仏教
インドにおける仏教この記事ではブッダやインドの仏教を知る入門書としておすすめの作品を紹介し、その後はもっと仏教を知りたい方におすすめの参考書を厳選してご紹介していきます。
私のチョイスする参考書は仏教書としては一風変わったラインナップになりますがきっと皆さんの新たな発見のお役に立てるのではないかと確信しております。
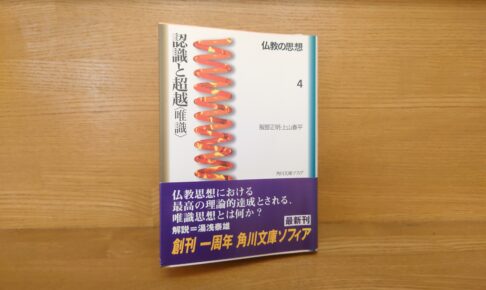 インドにおける仏教
インドにおける仏教前回の記事で紹介した『仏教の思想2 存在の分析〈アビダルマ〉』では上座部仏教(正確には説一切有部)の仏教哲学の頂点であるアビダルマについて解説されましたが、本作『仏教の思想4 認識と超越〈唯識〉』は大乗仏教思想の最高峰とされる唯識思想についてのおすすめの参考書です。
本書ではまず唯識とはそもそも何なのか、どのような流れから生まれてきたのかということを歴史的な側面から見ていきます。いきなり難解な思想の話から始まっても私たち読者からすると厳しすぎます。というわけで本書は入門書ということで、まずは唯識の難解な哲学よりもその成立過程を見ていき、その大まかな全体像を掴んでいくことから始まります。これは読んでいて非常に助かりました。
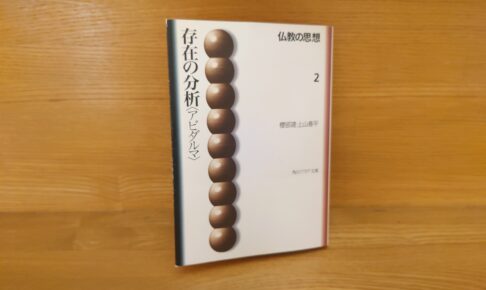 インドにおける仏教
インドにおける仏教本書『仏教の思想2 存在の分析〈アビダルマ〉』は「仏教の思想シリーズ」の第二巻になります。このシリーズは仏教思想入門として長らく愛され続けてきたベストセラーで、私が教えを受けている仏教学の先生もこのシリーズを推薦しています。
本書ではアビダルマという、一般読者だけでなく私たち僧侶にとっても巨大な壁となっている存在がテーマとなっています。「アビダルマ=難解、煩瑣」なイメージがすでに出来上がってしまっていますが、このアビダルマという仏教思想が大乗仏教を学ぶ上でもどれだけ大きな意義があるかを本書では知ることになります。
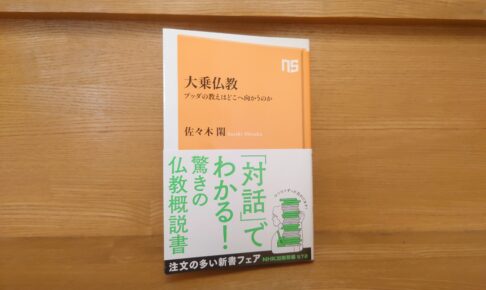 インドにおける仏教
インドにおける仏教「大乗仏教という言葉は知っているし、自分たちの住む日本が大乗仏教国であることも知っている。しかし、その大乗仏教というのがいったいどのような教えなのかは、さっぱりわからなかった。」
これは一般読者だけでなく、実は僧侶自身も同じ思いの方が多いのではないでしょうか。
と言いますのも、僧侶である私たちも仏教の基本を学ぶのでありますがやはり自分の宗派の教義の勉強が中心となってしまいます。
もちろん、大乗仏教とは何かや日本の主だった宗派の特徴などは習っていますが、その成立過程や経典、教義の細かい所まではなかなか立ち入れないというのが正直なところです。
そういう面でも本書はどの宗派の僧侶にとっても非常に意義のある解説書となっています。
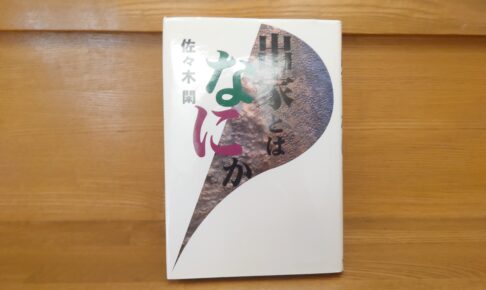 インドにおける仏教
インドにおける仏教本書『出家とはなにか』はその書名通り、出家とはそもそも何か、僧侶とは何かということを見ていく作品です。商品紹介の「律蔵やパーリ律を基本資料として」という言葉から本書は何やら難しそうだなという印象を受ける方もおられかもしれませんがご安心ください。佐々木閑先生の語り口は非常にわかりやすく、とても読みやすいです。
また、この本ではそうした日本仏教の独自性についても語られます。やはり比べてみるからこそ見えてくるものがあります。インドやスリランカの初期の仏教の生活実態もこの本では詳しく見ていけるのでとても刺激的です。
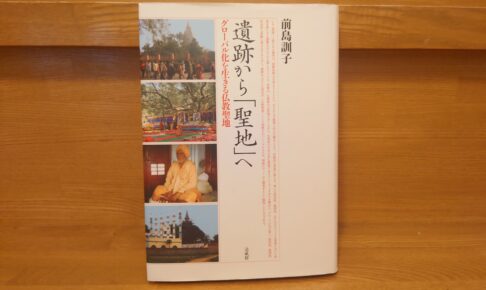 インドにおける仏教
インドにおける仏教本書はインドの仏教聖地ブッダガヤの衝撃の事実を知れる作品です。
ブッダガヤといえばブッダが悟りを開いた地として世界的に有名な聖地です。
ですがこの聖地がずっと忘れ去られていて、最近発見されたものだとしたらどうでしょう。
正直、本書で書かれている内容は日本人にはかなりショッキングなものかもしれません。
この地で何が起きていたのかを知ることは決して無駄なことではないと思います。それが仏教徒である私にとっていかに不都合なものでも・・・
 インドにおける仏教
インドにおける仏教今作『大唐西域記』はあの『西遊記』のモデルとなった作品です。
「三蔵法師=玄奘」というくらい日本で有名な高僧ですが、彼が世界的に有名になったのは三蔵(経、律、論という経典群)を求めて中国からはるばるインドへ旅し、大量の経典を無事中国へもたらしたという偉業にありました。
本作『大唐西域記』はそうした玄奘の旅路が記された書物になります。
ただ、この本を読み始めてすぐに気づくのですが、その語りがあまりに淡白・・・
私達がイメージする刺激的な冒険譚とはかなり趣が異なるのです・・・
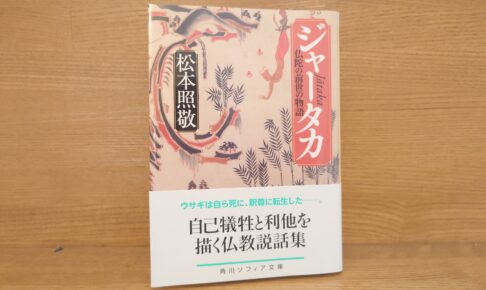 インドにおける仏教
インドにおける仏教本書はブッダ滅後2、300年頃に原型が出来上がったとされるジャータカのおすすめ入門書です。
ジャータカとはブッダの前世の物語のことで、利他や自己犠牲が説かれた素朴な物語です。そしてその代表的なお話が法隆寺の玉虫厨子にも描かれている「捨身飼虎」です。飢えた母虎を救うために自らの身体を与えたという有名な物語です。こちらももちろん本書に収録されています。
有名な物語以外にも興味深い説話がどんどん出てきますので、ジャータカの雰囲気を感じる上でもこの本はとてもおすすめです。また、こうした仏教説話から大乗仏教の流れが始まってくるという意味でもジャータカを学ぶ意義は大きいと思います。
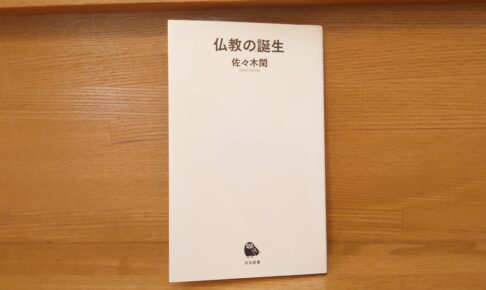 インドにおける仏教
インドにおける仏教今作『仏教の誕生』は仏教入門にぜひぜひおすすめしたい参考書です。仏教に興味があるけど何を読んだらよいですか?と聞かれたら最近はこの本を私はおすすめしています。それほどわかりやすく、読みやすいです。しかも仏教が私達の生活とどのように関わってくるかということも考えていけるので非常に実践的です。単なる知識で終わるのではなく、生きる智慧としての仏教を本書で知ることができます。
これまで当ブログでは様々な仏教書を紹介してきましたが、入門書としてはこの本がピカイチです。ぜひ私もおすすめしたいです。
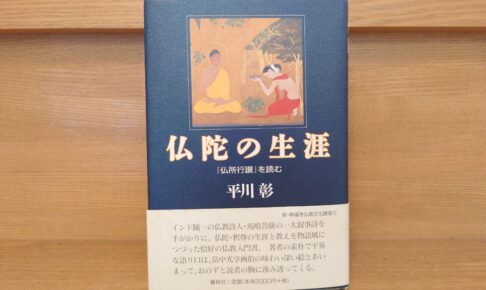 インドにおける仏教
インドにおける仏教前回の記事では2世紀頃に活躍したアシュヴァゴーサによる仏伝叙事詩『ブッダチャリタ』をご紹介しました。
この『ブッダチャリタ』は西暦430年頃に曇無讖によって『仏所行讃』として漢訳されました。これが日本にも伝来し日本の仏教者にも伝えられたのでありました。最澄や空海、法然や親鸞もこの仏伝を読んでブッダに思いを馳せていたのではないでしょうか。
本書はこの漢訳の『仏所行讃』の書き下し文を読みながらブッダの生涯がわかりやすく解説される仏教入門書になります。