インドのシヴァ・リンガ信仰~男根信仰が今なお篤く信仰されるヒンドゥー教の性愛観について

【インド・スリランカ仏跡紀行】(15)
インドのシヴァ・リンガ信仰~男根信仰が今なお篤く信仰されるヒンドゥー教の性愛観について
前回の記事「(14)【未成年閲覧注意】世界遺産カジュラーホー遺跡群を訪ねて~美しき天女の饗宴!性と宗教について考える」の最後にお話ししたように、今回の記事ではヒンドゥー教のシヴァ・リンガ信仰についてお話ししていきたい。

ヒンドゥー教の信仰を考える上でシヴァ・リンガは絶対に避けては通れない。前回の記事でも見たように、カジュラーホーでもこのシヴァ・リンガは重要な存在として鎮座している。性的にストイックな仏教との比較のためにもこのシヴァ・リンガを学ぶことは大きな意味を持つことだろう。
これから参考にしていくのは前回の記事でも紹介した辛島昇・奈良康明共著『生活の世界歴史5 インドの顔』という本だ。

では早速シヴァ・リンガについての解説を見ていこう。
性と宗教との結合自体は別に珍しくもないし、インドに限ったことではない。農耕の祭りとオルギー的密儀の結合とか、性器崇拝などがその例である。日本の各地にもあり、世界中どこにいっても、民衆の間に土の匂いをふりまきながら行なわれている。
しかし、そうした性と宗教の結合が民間信仰的な位置づけを脱して、一つの文化の表面に出てしまい、きわめてオープンな形で日常化しているのは、やはり、ヒンドゥー教だけではなかろうか。ヒンドゥー教のシヴァ=リンガ(男根)崇拝の例をそこにあげることができる。
リンガとはオーストロ=アジア語で、したがってアーリア人がインドにもちこんだものではない。現に『リグ=ヴェーダ』では男根崇拝を厳しくしりぞけている。
しかし、先にも見たように、シヴァ神が土着の信仰をふんだんに吸収して勢力を伸ばしてくると、シヴァ神とリンガが結合されるようになった。シヴァとは元来が破壊の神の要素を強くもっている。しかし破壊は創造につらなる。一方、リンガは生産、再生のシンボルで、これは世界中どこに行っても同じである。この両者はごく自然に結びつき、叙事詩『マハーパーラタ』では早くもその結合を記している。したがってシヴァ=リンガの始源は西暦以前にさかのぼる。
以降、リンガはシヴァ神を示す最重要な本体として広く信奉され、現代にまで及んでいる。ヒンドゥー教の最も普通で有力な崇拝対象である。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した。
河出書房新社、辛島昇・奈良康明『生活の世界史5 インドの顔』P239-240
たしかに男根崇拝や性器信仰はインドに限ったことではない。日本にも五穀豊穣や地母神など様々な信仰対象がある。

だがここで解説されたように、それが日常の位置にまでやって来るというのは考えにくい。やはりそれが生活のメインの位置までやってくるインドという国には何事かがあるのである。
「【現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】⒁仏教が生まれたインドの時代背景~古代インドの宗教バラモン教の歴史と世界観とは。カースト制についても一言」の記事でお話ししたように、古代インドにはインド土着の民族であるドラヴィダ系の人々とアフガニスタンやイラン方面から侵入してきたアーリア人が存在していた。
この侵入者アーリア人がインド全土に広がりこの地を統治したのだ。その彼らが信仰していた神々への讃歌がバラモン教の『リグ・ヴェーダ』という聖典になる。
しかしアーリア人がインドを支配したからといって土着の人々が全ていなくなってしまったわけではない。時を経るにつれて混血も進み、文化の融合も進んでいった。
それが上で解説されていたシヴァ・リンガの生成過程なのだ。
つまりインドを支配したアーリア人の宗教、バラモン教はあくまでアーリア人のための宗教だった。だから土着のものを退ける傾向があった。それは上の解説の通りである。
しかしやがてそれが土着の宗教と結びつくことによってアーリア人だけではなくインド人全体の宗教へと変化していったのである。こうしてインド全体へ広がって出来たのがヒンドゥー教なのだ。こういうわけでバラモン教とヒンドゥー教はまさにひとつながりの存在なのである。


シヴァ神は破壊の神であり、ヨガや踊りの神様である。シヴァは瞑想の達人であり、踊りながら世界を破壊し、再創造をもたらす神様だ。
あらゆるものの再生には先立って破壊がなくてはならない。破壊は悪いことばかりではない。破壊は滞った暗い世界を刷新し、新たな世界をもたらすのだ。ここにキリスト教的な一直線の歴史観とは異なる円環的な時間観が存在するのである。
キリスト教では世界の始まりから最後の審判まで歴史は一直線に進んでいく。しかしインド的な発想では時は一直線ではなく円環状に循環していくのである。ぐるぐる回り続けるループなのだ。右上の写真のシヴァ神もまさにそのイメージと言えよう。そうした時の循環の中心で踊り、円を回すのがシヴァなのである。
この破壊と再生、生命力が見事に結びついたのがシヴァ・リンガと言える。これはもはや単なる男根崇拝という言葉でくくれるレベルをはるかに超えている。宇宙論的信仰とすら言うことができるかもしれない。
では、引き続き解説を見ていこう。
ヒンドゥー教は仏教やキリスト教とちがって特定の教理をもたない。ここには実存探究の高いレべルの観念や行法もあれば、祖霊や鬼霊崇拝、通過儀礼、呪術といった民間信仰的な多様な観念と儀礼もある。
それらのうちのどれがヒンドゥー教の本質的部分で、どれが堕落した部分だ、といった区別は全くない。
だから仏教やキリスト教のような創唱的宗教ではしりぞけざるをえないような信仰も、ここヒンドゥー教では、人びとが普通に行なっていれば、それがヒンドゥー教信仰の主要なる部分となってしまう。リンガ崇拝がこの例で、これはいい悪いの問題ではないのである。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した。
河出書房新社、辛島昇・奈良康明『生活の世界史5 インドの顔』P240-241
ここも重要な解説だ。ヒンドゥー教には唯一絶対の教義がないのである。
これはどういうことかというと、ヒンドゥー教には正統というものがそもそも存在しないのである。つまり、何でもありなのだ。しかも何でもありでありながらヒンドゥー教というまとまりがあるのである。無限の多様性がありながら統一性も持っているのだ。これがインドの面白い点でもある。
それにそもそもヒンドゥー教という名称自体が「インドの宗教」という意味合いで、仏教やキリスト教とはその意味するところが全く違うのである。日本で言うならば、「日本の宗教」とひとまとめにしたようなものなのだ。
そして日本で言うなら各仏教宗派や神道など様々な宗教宗派があるが、それもインドも同じなのである。大まかに言えばヒンドゥー教にはシヴァ神を信仰するシヴァ派とヴィシュヌ神を信仰するヴィシュヌ派が存在している。だが、その区別は実際にはあいまいで、彼らは両派どちらの神様も大切にし、その他多くの神様も同様に信仰しているのだ。
さて、ヒンドゥー教というものの多様性を知ったところでいよいよ核心部分へ入っていこう。ここからリンガ崇拝の深い意義を見ていく。そしてこれがカジュラーホーのミトナ像にも直結していくのである。

「リンガ」は男根であるから、それ自体は性にかかわるものである。しかし「リンガ崇拝」はかならずしも性に関することをその内容とはしていない。
たとえば、リンガは通常、ヨーニ(女陰)と結合した形で示され、崇拝される。近代の一般感覚からいうと淫靡な感じを与えていてもいいはずである。日本の農村にみえる道祖神は、やはり一種のいやらしさが一般には感じられている。また愛知県の田県神社の祭りは男根の模型を用いる祭儀だが、ここにはかつての闇祭りのごときオルギー的祭礼の痕跡がのこっていよう。
インドのリンガ・ヨーニ像にかかる感覚はない。今も昔もなく、若い娘さん方でも平気で手でなでまわし、花や油を供えて礼拝する。それは単なる慣れの問題ではなく、リンガ・ヨーニ像のもつ内容とかかわっている。
ヒンドゥー教徒の根本的発想として、人間や自然の万物は、本質的には、一なる絶対者から派生したという考えがある。したがって現象世界の多様なるものが一つの絶対者に収斂してゆく時、いっさいの差別・多様性はまずニつの対立する観念にまとめられる。陰と陽、女と男といった具合に整理される。そしてこの二者がさらに一つに融合し合体するところに絶対者の現成が象徴されると考えた。
そしてヒンドゥー教ではこの二者をしばしば男(男性原理)と女(女性原理)という形で象徴する。
万象を男・女性原理で示すことは他の文化にもあるが、その方法や度合い、それに基づく哲学や宗教的行法の豊富さにおいてインドは群をぬいている。ここにはヒンドゥー教の性に対する禁忌が少ないことにも関係があろう。
とにかく、この男・女両性によっていっさいの現象世界を示し、絶対者との関係を示すことこそ、後に述べるタントリズムの根本思想である。
またシヴァ神を「半分男で半分女の主」と呼び、かく図示するのも同様である。そしてリンガ・ヨーニの結合もこうした世界観の上に成り立っている。それは具体的性愛の象徴ではなく、森羅万象の根元的実態のシンボルなのである。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した。
河出書房新社、辛島昇・奈良康明『生活の世界史5 インドの顔』P241-242


前回の記事でもお話ししたカジュラーホー最大の寺院、カンダーリヤ・マハーデーヴィ寺院の中心にはまさにシヴァ・リンガが祀られている。
このシヴァ・リンガの究極的な意味は上の解説のように、全世界の象徴でもあったのだ。

そしてカジュラーホーのエロティックなミトナ像も、まさにこうした絶対者との合一へとつながる神秘体験として描かれていたのである。このさかさまになって繋がる男女も単なる性愛ではなくヨーガの行なのだ。
ヒンドゥー教ではこうした性行為を通じたヨーガを究極の境地として考える一派が存在した。それをタントラ(またはタントリズム)という。そしてこのタントラは仏教、特に密教においても導入されたほどだ。それほどヒンドゥー教にとって性愛というのは重要なものだったのである。
ただ、こうしたミトナ像がカジュラーホー全体の10%以下しかないことからも明らかなように、タントラがヒンドゥー教の主流だったかと言われるとそれは難しいところだ。あくまでタントラが生まれるほど性愛に寛容な土壌があったということでとどめておく方が賢明であろう。こうした文化があるということ自体が私達からすれば十分驚異的なことである。
こういうわけで、カジュラーホーは単にセクシーな彫刻があるというだけで済まない恐るべきスケールの寺院群であった。宗教における性愛の意義を改めて確認する機会となったと言えよう。
主な参考図書↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら↓
※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。
〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」
〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」
〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」
関連記事
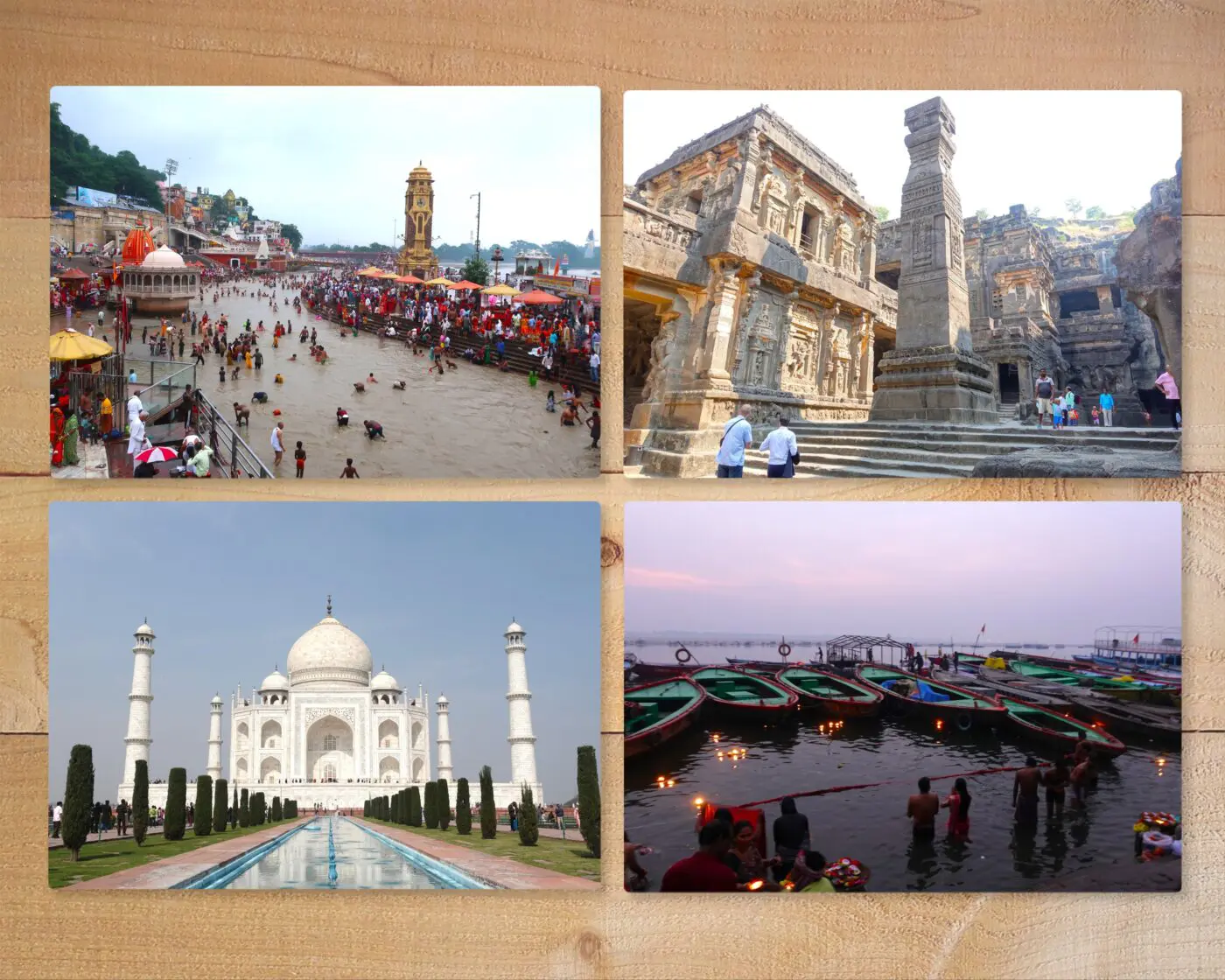















コメント