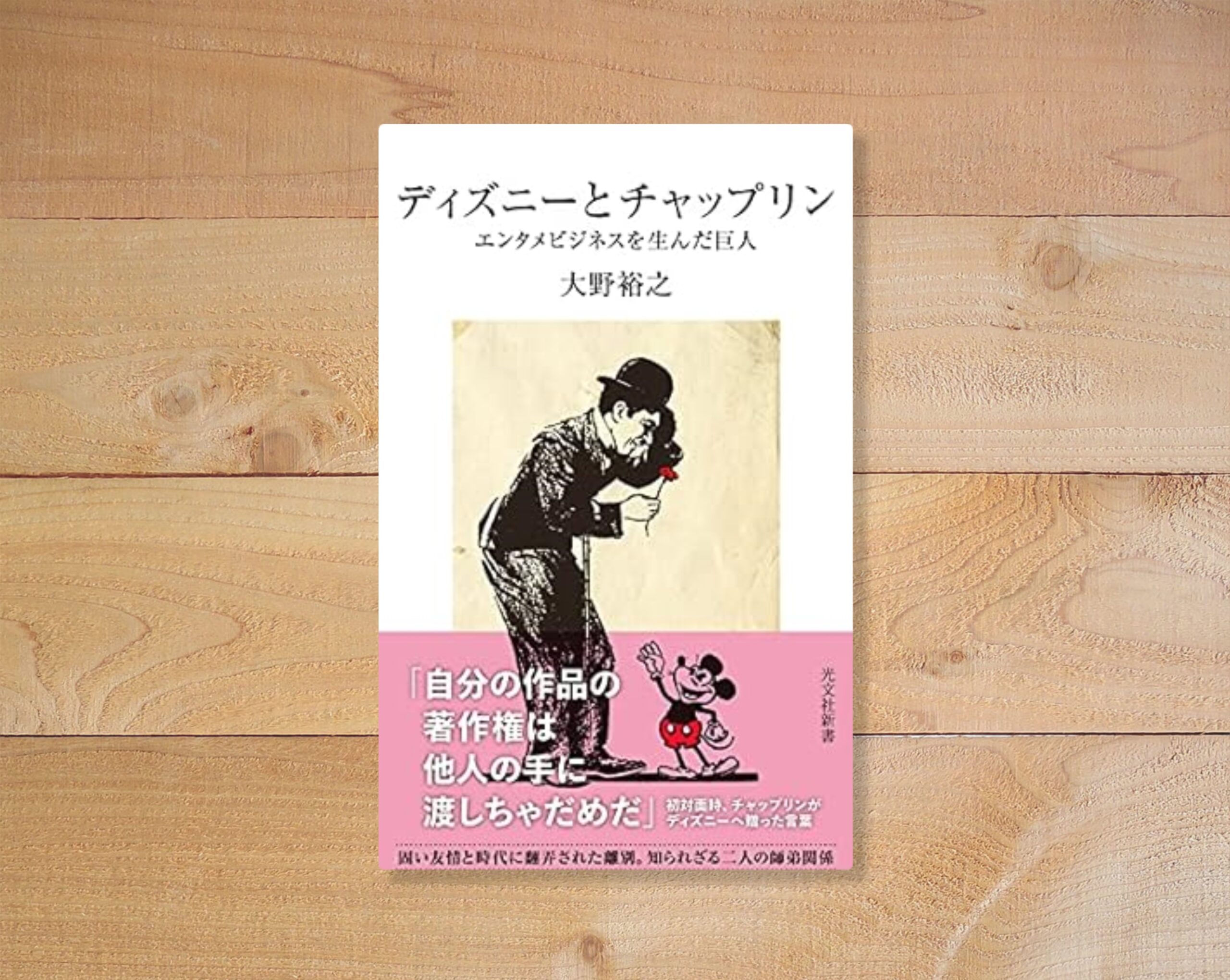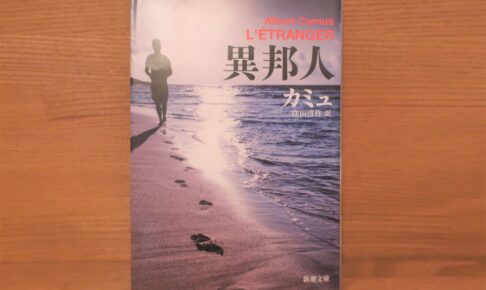大野裕之『ディズニーとチャップリン エンタメビジネスを生んだ巨人』概要と感想~ミッキーの誕生には師匠チャップリンの巨大な影響が!時代背景も知れる刺激的な作品
今回ご紹介するのは2021年に光文社より発行された大野裕之著『ディズニーとチャップリン エンタメビジネスを生んだ巨人』です。
早速この本について見ていきましょう。
ディズニーの生涯の野心は「もう一人のチャップリンになること」だった。俳優の道を諦めた代わりに、彼は「もう一人のチャップリン」をアニメーションの世界で創った。それがミッキーマウスだ。――固い友情と時代に翻弄された離別。知られざる二人の師弟関係を豊富な資料で明らかに! エンタメビジネス創世記としても読める一冊。
Amazon商品紹介ページより


本書『ディズニーとチャップリン エンタメビジネスを生んだ巨人』は喜劇王チャップリンとミッキーマウスの生みの親ウォルト・ディズニーの師弟関係を知れるおすすめ作品です。
本書について著者は冒頭で次のように述べています。
ウォルト・ディズニーにとって、12歳年上のチャールズ・チャップリンは、神様だった。小さい頃から彼に憧れ、彼の物真似コンテストの舞台にも立った。後年、ハリウッドに進出した時は、どうにかして彼に会えないものかと、チャップリン撮影所の前をうろうろ歩いてみたりもした。だが、駆け出しのアニメーターに、世界の喜劇王と出会うチャンスなどあるはずもなかった。
そんな彼が紆余曲折を経て、ミッキーマウスを世に送り出した後、長年待ち望んだ瞬間が訪れた。
チャップリンが、今目の前にいる—ディズニーは、それだけでも有頂天だったのに、思いがけず、「僕も君の作品のファンだよ」と言われた時の、彼の気持ちはいかばかりであっただろう。
ただし、チャップリンもだてに〈世界の喜劇王〉ではない。最初の面会で、自分の他にもう一人の天才が現れたことを見抜いた彼は、芸術上のアドヴァイスではなく、ビジネスについて、冷徹かつ簡潔に助言を与えた。巻頭に引用した「自分の作品の著作権は他人の手に渡しちゃだめだ」の一言は、ウォルトの、ひいてはディズニー社のその後を決定づけることになる。
チョビ髭に山高帽のおなじみの扮装で、世界中を笑いと涙の渦に巻き込んだ不世出の喜劇王。
愛くるしいキャラクターで子供たちに喜びを与え、この世に夢の国を生み出したアニメーションの帝王。
ともに、唯一無二の天才にして、他とは比べることができない存在であることは言うまでない。
二人が世に登場してから100年弱にわたる世界中の新聞記事を調べてみると、興味深いことがわかる。「チャールズ・チャップリン」ともっとも多く比較されている単語は、決して他のコメディアンではなく「ウォルト・ディズニー」であり、「ウォルト・ディズニー」ともっとも多く比較されているのは、他のア二メ監督ではなく「チャールズ・チャップリン」なのだ。すなわち、チャップリンとディズニー、この二人の天才に比較し得る存在は、彼ら自身だけなのだ。
しかし、意外なことに、映画が生んだ「たった二人の本物の天才」(フランク・ラスキー)についての比較研究は、これまで本格的になされてはいなかった。
まったく異なった環境で生まれ育った二人が、それぞれのジャンルを征服するまでのサクセス・ストーリーは、20世紀のエンターテインメントの歴史そのものとも言える。
光文社、大野裕之『ディズニーとチャップリン エンタメビジネスを生んだ巨人』P5-7
これまで当ブログではウォルト・ディズニーについてニール・ゲイブラー著『創造の狂気 ウォルト・ディズニー』やクリストファー・フィンチ著『ディズニーの芸術』など、様々な本を紹介してきましたが、やはりそれらの本でもウォルトとチャップリンの関係が書かれていました。ですが上の引用にもありましたように、それらの本ではそこまで深くは掘り下げて書かれていませんでした。それに対して本書はチャップリンとウォルトの生涯を概観し、さらに彼らの制作理念や二人の結びつきを詳しく見ていきます。これは刺激的です。
せっかくですので実際に2人の映像を観ていきましょう。
チャップリンの映像は彼の代表作『モダンタイムス』(1936年)、下はミッキーマウスのデビュー作『蒸気船ウィリー』(1928年)です。
『蒸気船ウィリー』は当時最先端の技術を用いたトーキー映画でした。音楽とアニメが完全に融合したこの作品でミッキーは一躍スターダムにのし上がります。私もこの作品やその後の初期のミッキー作品を見てみたのですが、たしかにキャラクターたちの動きはチャップリンを想像させるものがあります。
ただ、前回の記事で紹介した『ミッキーとそのライバルたち』にもありましたように、このチャップリン的あるいはバスターキートン的な動きというのは当時のアニメ界では『フィリックス ザ キャット』ですでに持ち込まれていたものでした。つまり、ウォルト・ディズニーは無からミッキーマウスを創造したのではなく、当時のアニメ界を参考にしながら自身のキャラクターを生み出したのでありました。
ではなぜ当時大人気だった『フィリックス ザ キャット』を圧倒してしまうほどの人気をミッキーマウスが得ることができたのか、それを本書で詳しく見ていくのですがまさにここにもチャップリンが絡んできます。ウォルトとチャップリンには誰にも真似できない究極の完璧主義、理想主義があり、さらにキャラクターに命と個性を吹き込む天賦の才があったのでした。その具体例については長くなってしまうのでここではお話しできませんが非常に興味深いです。
そして本書の中でも特に印象に残ったのが1937年に公開された『白雪姫』に関するエピソードです。この作品はウォルトが社運をかけた初の長編フルカラーアニメーションで、業界でも前代未聞の挑戦でした。少し長くなりますが非常に興味深い箇所ですのでじっくり読んでいきます。
ディズニーの次なる挑戦とは、初の長編アニメーションを製作することだった。『三匹の子ぶた』が成功を収めた翌年の1934年、ディズニー社の年間売上高は60万ドルにのぼっていた。しかし、ディズニー社の売り上げはすでにグッズ収入が大半を占めており、経費がかかる割には利益の少ない短編アニメにディズニーは限界を感じていた。また、恐慌後の映画館は、同じ料金でもたくさん見られるというお得感を出すために、従来の「長編+短編」の組み合わせではなく、「長編2本立て」の上映が増えていたため、短編アニメの上映回数が減少しつつあった。
もちろん、長編への野心は経済的な理由だけからではない。常に「誰もやっていなかったこと」を求めるディズニーの芸術的野心からだった。短編では、動物や草花のファンタジーを美しく描くことはできても、彼の求めるストーリーとリアリズムを追求できないと思い始めていた。
初の長編の原作として、いろいろな神話や伝承を検討した上で、1933年5月頃にはグリム童話の『白雪姫』のアニメ化を決意していた。
しかし、スタッフも含めて周囲は長編アニメの製作に大反対した。世界恐慌後アメリカ国内では消費購買力が落ち、ドイツでヒトラーが政権を握ったことで海外市場も縮小の一途をたどっていたが、当時のディズニーはグッズ販売と短編アニメで堅実な経営をしていた。リスクを背負ってまで冒険をする時期ではないというのが周囲の共通した意見だった。
そんな中、チャップリンだけがディズニーの冒険を応援した。ディズニーは1964年にインタビューでこう回想している。
「チャーリーは私にとても優しかった。私の最初の長編アニメ映画について、他の誰もが懐疑的だった時に、彼は前に進むようにと勇気付けてくれた」
チャップリンもかつてディズニーと同じ経験をしていた。短編喜劇で大人気を博していた1910年代末に、彼は長編喜劇『キッド』の製作を始めた。配給会社は、上映すれば必ずヒットを記録する短編喜劇がたくさんあれば良かったので、長編製作に反対した。しかし、チャップリンは信念を貫き、1年以上の時間を費やして『キッド』を完成させた。結果、『キッド』は公開後数年の間に世界100カ国以上で上映され、前述の通り世界規模でほぼ同時上映された最初の映画となり、映画の歴史を変えた。
その経験から、チャップリンはディズニーに長編を作る時の心得を授けた。それは、やはり人々が共感できる主人公、ストーリーとテーマの重要性であった。
「チャーリーは私に、最上のコメディにおいて、人は主人公に同情しなければならないということを教えてくれた。主人公の行ないに笑う前に、主人公のために涙を流さなくてはいけない、と」
喜劇王から助言を受けて自信を持ったディズニーは、1934年の冬のある日、50人のスタッフをスタジオに集めた。そして、真っ暗な部屋の一本のスポットライトの下で、チャップリン仕込みの演技で3時間にわたって『白雪姫』のすべての役を最初から最後まで演じきった。独演会が終わった時、スタッフたちは涙を浮かべていたという。一同は以降3年間の製作を、常にこの時のデイズ二ーの演技を思い出しながら進めることになる。
しかし、前代未聞の大プロジェクトには、大きな難関が立ちはだかった。なにより、ディズニー社の当時の年間売上高の3分の2にあたる40万ドルもの巨額の製作予算をどうするのか(そして、製作費は最終的には150万ドルに膨れ上がる)。しかも、その間は短編アニメの製作も抑えなくてはならないので売り上げも減る。またもや兄ロイがバンク・オブ・アメリカと交渉し、1935年8月に25万ドル、36年5月に63万ドル、37年3月にも63万ドル、同年9月に32万7000ドルの融資を受けた。
このように大変な借金を抱えながら、ようやく作品は完成したが、デイズニーには長編映画を公開するためのノウハウがなかった。頼みの綱のUAは『白雪姫』の公開をしないと決定した。チャップリン以外の取締役が反対したのだ。新しい配給会社RKOとの交渉の中で、ディズニー社に不利な条件を飲まされてしまう危険性があった。
その時助けてくれたのもチャップリンだった。彼はディズニーを励まし、「君の映画は長い間生き続ける。僕のアドヴァイスは全作品の権利を自分のものにすることだ。もし所有していない権利があれば買い戻すのだ」と言って、あくまで自分の権利を保持し続けるように言った。チャップリンは『白雪姫』の成功を信じていて、「僕がやったことを知ってほしい。連中は君の映画を買い叩くかもしれない。君は最高の条件以外は受け入れるべきではない」と、自分の帳簿を開いてロイに最高の条件の数字を見せ、「これより低い数字では売るな。君はもっと取るべきだ」と言った。
そして、彼はなんと『モダン・タイムス』を配給した時の資料一式を惜しげもなくデイズニーに提供した。RKOに対してチャップリンの条件を参考に商談をすることができたディズニーは、1938年5月31日付の手紙でチャップリンに感謝の気持ちを伝えた。(中略)
チャップリンは「皮肉屋や銀行家の奴らに、『白雪姫』について君のことを過小評価させてはいけない。この作品は、君の最大のヒット作になる」と言い続け、実際にその通りになった。
デイズ二ーは、「最上のコメディにおいて、人は主人公に同情しなければならない」というチャップリンの教えを忠実に守り、主人公・白雪姫を、誰もが心を寄せる美しい姫にして継母から謂れなき迫害を受けるキャラクターとして造形した。それは同時に、ディズニーの「少年時代の寓話」でもあった。「親の嫉妬、移り気な圧制におびえ、自分の世界(アニメというファンタジー)に逃避し、そこにいたわりと愛と独立と信頼を見出す。白雪姫はウォルト・デイズニーの成長の物語」だったのだ。(中略)
キャラクターとギャグの面では、とくに七人のこびとたちにチャップリンの影響が色濃く見える。七人そろって歩いていた時に先頭が急に立ち止まって、後ろを歩いている六人が順々にぶつかるギャグは『犬の生活』に出てくるし、スニージーのくしゃみで強い風が吹いて、他のこびとたちが風に逆らって走ろうとするも前に進まない演技は、『黄金狂時代』の山小屋のシーンの完全なコピーだ。なにより、一人だけ喋らないキャラクター・ドーピーを登場させることで、サイレント喜劇のギャグを引き継いでいる。
1937年12月21日に行なわれた『白雪姫』のプレミア上映に参加したチャップリンは、七人のこびとの一人であるドーピーのことを「史上もっとも偉大な喜劇人の一人だ」と感想を述べた。やはり、アニメーションこそ自分の後継者であると認識したのだろう。
『白雪姫』は、アメリカ国内で400万ドル、海外で400万ドルという未曽有の大ヒットを記録した。公開からしばらく経って、映画ビジネスを教えてくれたチャップリンがわざわざディズニー社の帳簿を見に来たことを、ディズニーは生涯の自慢としていた。
光文社、大野裕之『ディズニーとチャップリン エンタメビジネスを生んだ巨人』P147-153
ディズニーを学び始めて最初に読んだ一冊クリストファー・フィンチ著『ディズニーの芸術』で1937年に『白雪姫』がすでにフルカラーで上映されていたことに度肝を抜かれた私でありましたが、今回この作品の公開にここまでチャップリンが関わっていたことを知りさらに驚くことになりました。
チャップリンは単に作品の内容や制作理念に影響を与えただけではなく、ビジネス上の助言までウォルトに与えていたのでありました。
本書ではこうした二人の関係性を詳しく知ることができます。
残念ながら後年チャップリンとウォルトは道を違えることになるのですが、その経緯も詳しく知れる本書は非常に貴重です。いつもとは一風違った視点からディズニーを学べる本書はとても刺激的です。
ぜひぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「大野裕之『ディズニーとチャップリン』~ミッキーの誕生には師匠チャップリンの巨大な影響が!時代背景も知れる刺激的な作品」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事