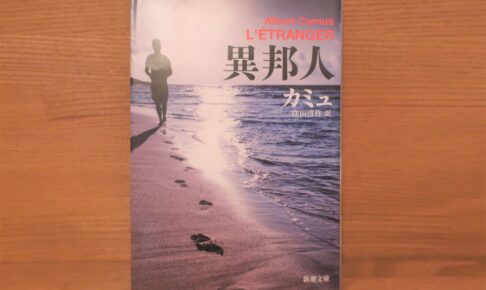チェーホフ文学の特徴を知るために~医者としてのチェーホフ

これからチェーホフの作品を見ていくにあたり、作家チェーホフの個性としてもっとも独特なのが、彼が医者であったということです。
医者でありながら作家として活動した。これは当時としても非常に珍しいケースでした。今回はそんな医者チェーホフについて少しお話ししていきます。
今回参考にするのはロシア文学者松下裕氏の『チェーホフの光と影』です。松下裕氏は筑摩書房版の『チェーホフ全集』の翻訳を手掛けており、チェーホフに非常に造詣の深い研究者です。そしてドストエフスキー界隈でもあのモチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』の翻訳をされたことでも有名です。
では早速松下氏の言葉を聞いてみましょう。
アントン・パーヴロヴィチ・チェーホフという人は、医者になると同時に作家となった珍しい作家の一人である。医者で文学者という人は、日本にも外国にも少なくないが、医者になったのちに物を書きはじめるというのが普通ではないかと思う。チェーホフのように、医者になり、同時に作家になったような人は、たくさんはいないのではないだろうか。
チェーホフは一八六〇年生まれで、一八七九年、十九の年にモスクワ大学の医学部に入学している。そして五年間の課業を終え、一八八四年、二十四歳で卒業して医師になった。彼は、入学四カ月後に処女作とされる作品「学のある隣人への手紙」を発表している。そうして、卒業までに二百篇ちかい小説を発表し、また「父なし子」という長い戯曲の習作も仕上げている。
しかし、卒業したてのころに彼がかなりの作家であったにしろ、それから三、四年は、医学で身を立てようか、作家として大成しようかという進路は必ずしもはっきりしてはいなかった。心のなかで揺れていたと言えるだろう。医学の課業を終えても、すぐに一人まえの医者として通用することは通常ありえないことで、チェーホフはモスクワで開業したが、彼に診察をたのむような人は稀だったという。
チェーホフは、一八八八年に、人のすすめもあって、かなり長い「曠野」という小説を書いて称賛を博し、それ以後、作家としての自覚的な道を歩むことになった。もし、医者としてそのころから意識的に進めば、一流の医師、医学者、医学史家―彼にはロシア医学史を書くもくろみがあった。そのためのノートが残っている―などになったにちがいないが、このとき文学を生涯の仕事としてやって行く覚悟を決めたのだった。
チェーホフが、医者となり作家となる二つの道を同時になしとげたということは、彼の非常に慎重な性格、計画性、努力を現わしている。医者になるだけでも大変な修業を必要とするのに、その間二百篇ちかい小説を書く、それも注文に応じて書くという仕事ぶりだったので、若いときから結核にとりつかれ、体をこわしたのはむりもなかった。
この、彼の慎重な性格や計画性をよく現わしている例として、故郷の中高等学校を出てモスクワへやってくるときに、あちこち奔走して故郷の町の奨学金を取って上京している、ということがある。また、モスクワに先に来ていた家族のもとへ、同じく大学へ入学する故郷の同級生を二人か三人つれてきて同居させ家計を成り立たせることもしている。十九歳の少年として、その計画性と実行力は相当なものだった。チェーホフという人は、若いときから人生を着実に歩んで行った人間だったということができよう。
筑摩書房、松下裕『チェーホフの光と影』P9-10
チェーホフは医者になって時間の余裕ができたから作家になったというのではなく、そもそも最初から両方の道を歩んでいたというのが彼の独特な所です。そして家もかなり貧しく、家族の生活の世話をしながらの勉学と執筆は想像を絶する厳しさだったと思われます。こうしたところからもチェーホフの並外れた意志と実行力がうかがわれます。
では引き続き、医者としてのチェーホフがどんな人物だったのかを見ていきましょう。
医師チェーホフが、患者、総じて彼と接する人びとの信頼をすぐさまかちえる人だったという証拠に、彼がサハリン島に行ったときに会った、ドゥーエ監獄の看守フェリドマンの短いメモワールがある。
フェリドマンは、「彼は囚人たちを巧みに引きつけ、囚人たちは珍しく彼を信頼した」と書いている。
ふつう、こういう苛酷な生活を送ってきて、たえず世間から裏切られつづけてどん底まで落ちてきた囚人たちが、外来者には決して心をひらかず、でまかせの話をしてたぶらかそうとしたりすることは、ドストエフスキーの「死の家の記録」にも書かれている。
いっさいの身分権を奪われて、他の徒刑囚なみの立場に置かれていたドストエフスキーにたいしても、囚人たちは、貴族階級の出身だというので容易に心を許そうとしない。「民衆のなかへはいって行って信頼され(とりわけこういう囚人たちのなかへはなおさら)、彼らの愛をかちえることほどむずかしいことはない」(「最初の印象」)とドストエフスキーは書いている。
だから、囚人たちがチェーホフにすぐに打ちとけるのを、フェリドマンは大きな驚きの眼で見ている。フェリドマンは、チェーホフの印象をこう語っている。
「わたしはすぐさま、チェーホフの顔が気に入ったことをおぼえている。立派な、気どりのない、学生ふうの若々しい顔つき。賢そうな眼はおだやかで、やさしく、わずかに愁いを帯びている」
チェーホフの若いころの写真に照らしてみて、フェリドマンの描写の的確なことがわかる。こういう描写力を持った人物の証言は信頼するに足りる、とわたしは思う。(中略)
医学は大きく基礎医学と臨床医学とに分けられるが、チェーホフは「自分は開業医だ」と言っていて、臨床医だったわけである。そして、患者と接する術にはチェーホフ自身かなり自信を持っていたようだ。
一八九五年から九七年にかけてのある時期、メーリホヴォに住んでいた時代に、チェーホフをモスクワ大学の教授に推そうという動きがあった。チェーホフ自身も、特殊病理学と内科学の講座を受けもつことに意欲を示している。そのときのことを、大学の同窓生でロッソリーモという神経病理学の教授だった人が回想記を残していて、チェーホフの言葉が記録されている。
「僕は、たとえば、腸カタルの苦しみを実感することができるし、そういう患者がどんな体験をし、どんな精神的な苦しみを味わうかがよくわかるが、ふつうこのことは医者にはなかなかわからないものだ。僕が教師だったら、学生たちをできるだけ深く患者の主体的な感覚の領域に引きいれるようにするだろうし、そうすることが学生にはじっさいためになるだろうがね」(「チェーホフについての思い出」)
患者の苦しみを見きわめ、その悩みの原因を見ぬくことは、医師にとって根本的に必要な能力だが、その能力を養う訓練は今の医学教育のなかでも格別独立した科目になっていないという。
もしもチェーホフのような人が大学に講座を持って、そういう学問領域を切りひらいていたらおもしろかったろう。と言うよりも、医師の全人的教育ということが言われ実践されはじめている今日、チェーホフの意図の正しさがわかり、それの実現しなかったことが残念に思われる。
筑摩書房、松下裕『チェーホフの光と影』P12-15
※適宜改行しました
そして次に語られるのがチェーホフのすごみを感じられるエピソードで、私が一番印象に残った箇所です。
だいたい、観察ということは、医師としても作家としても最重要の技能で、チェーホフがいかに観察力にすぐれていたかということは誰にも想像がつくにちがいないが、それについてはいろいろな人が書いている。たとえば、スタニスラフスキーは、「モスクワ芸術座におけるチェーホフ」という文章で、こういうエピソードをつたえている。
「アントン・パーヴロヴィチは、わたしの考えでは、すばらしい観相家(人相見)だった」と彼は書いている。
―あるとき、スタニスラフスキーの楽屋に彼の友人がやってきた。その友人がスタニスラフスキーと話していると、チェーホフは黙って、真剣なおももちでその人を見つめていた。
その友人というのは、しごく楽天家で、陽気な男で、いくらか道楽者のように見られていた人だった。チェーホフは、彼が帰って行くまで、ひと言も口をはさまずにまじまじとその顔を見つめていたが、その晩、何度も何度もスタニスラフスキーのところにやってきて、その人のことを根ほり葉ほりたずねたという。
スタニスラフスキーが、どうしてあの人物がそれほど興味をひくのかとたずねると、チェーホフは言ったそうだ。―「いいですか、あの人は、自殺する人ですよ」。
だがそういう楽天家で、陽気な男で、いくらか道楽者のように見られていた人なので、スタニスラフスキーにはそんなことはありえないことのように思われた。
ところが、何年かたって、たしかにその人が服毒自殺したと聞いたとき、スタニスラフスキーはひどくおどろいた、という。
こういった観察力は、作家としての観察眼と医者としての観察眼とがからみあって磨かれて行ったものにちがいない。そして現実から問題をとりだすときに自然科学の方法にしたがっておこなう、ということが彼の学問方法だった。
「物の考えかただけでなく、仕事のしかたでも、彼は他のいかなるロシアの大作家たちよりも学者ふうだった」(『アントン・チェーホフ』「学生時代」)とデルマンは書いている。
筑摩書房、松下裕『チェーホフの光と影』P15-16
※一部改行しました
一見陽気でまず自殺するなんて思えないような人の心の闇を見抜き、自殺を予言したチェーホフ。彼の並々ならぬ観察眼がこのエピソードに示されています。
チェーホフは、その短い「自伝」のなかで、「医者としての職業は、疑いもなくわたしの文学活動に大きな影響を与えている」と言っている。彼が、医者であることを自分の文学活動の核心だと考えていたことは、この言葉からもわかる。
チェーホフは、医者という職業についたことによって、多くの人びとの生活を観察する機会に恵まれた。さまざまな患者に接し、あるいは往診のさいに、人びとの赤裸々な状態を見、飾らない人間の苦しみを知ることができたのは、彼が医者だったからこそだった。
チェーホフの作品は十九世紀末から二十世紀初めにかけてのロシア生活の百科事典だといってもいいが、彼によってそういう人間の多面的な姿がとらえられたのは、彼が医者、とりわけ臨床医として多くの人びとに接触する機会を持ったことから来ていた、ということがいえる。
いまあげた「自伝」にも、彼自身、「それはいちじるしくわたしの観察の範囲をひろげ、知識をゆたかにしてくれた」が、「またわたしに指針となる影響を与え」たと言っている。
よく知られているように、彼は、「医学は正妻、文学は愛人」ということを言っている(一八八八年九月十一日づけ、スヴォーリンあての手紙)。この言葉を、言葉どおりに解釈せず、医学を重荷に感じていたので文学に逃れたのだ、というふうに取る人びともいるが、わたしは、チェーホフという人は、生きるうえで医師という職業に重きを置いただけでなく、医学に生涯執着して、それをごく大事なものと考えた文学者だった、というふうに解釈したいと思っている。
筑摩書房、松下裕『チェーホフの光と影』P18-19
以上、見てきましたように、医者としてのチェーホフは彼の文学作品を考えていく上で非常に大きなウエイトを占めています。
このことを念頭に置いておくとチェーホフ作品を読むときにより楽しむことができます。
少し長くなってしまいましたがチェーホフの特徴についてお話しさせて頂きました。次の記事からいよいよ彼の作品を読んでいきます。引き続きお付き合い頂けましたら嬉しく思います。
以上、「チェーホフ文学の特徴を知るために~医者としてのチェーホフ」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
チェーホフおすすめ作品一覧はこちら
関連記事