ツルゲーネフ『ファウスト』あらすじ解説―ゲーテの『ファウスト』に影響を受けた恋愛物語
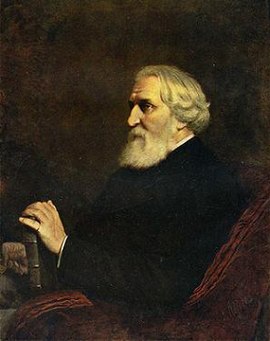
ツルゲーネフ(1818-1883)Wikipediaより
『ファウスト』は1855年ツルゲーネフによって書かれた中編小説です。
私が読んだのは新潮文庫、米川正夫訳の『片恋・ファウスト』所収の『ファウスト』です。
少し長くなりますが巻末解説にわかりやすいあらすじがありましたのでそちらを引用します。
『ファウスト』は一八五五年に書かれた中篇であるが、形式の完備していること、人生観照の目の落ちついていること、性格解剖の深刻で精緻を極めていること、作者の洗練された芸術的エモーションが優れた音楽のごとく全篇に浸透していること、その他多くの点に於いて、ツルゲーネフの全作品中でも、最高水準を形づくるものの一つである。
女主人公のヴェーラは祖母から熱烈な伊太利の血を受けついで、量り知れぬ情慾の力を内部に蔵していると同時に、祖父からは神秘的、超自然的な心的傾向を遺伝している。
いわば異常型の女性であるが、それと同時に、彼女はすぐれた頭脳と洗練された感受性を賦与されたインテリゲントである。
母親の不自然な人工的教育法によって、烈しい南国的な熱情を内部へ深く埋没されてしまったため、単純で無邪気な少女のように明るい心を保ったまま、人の妻となり母となった。
こうして、二十七の年まで、完全な自我の本質を自分でも意識せず、まして他人にもかつて示すことなく、一個の中間的存在として過して来た。
こういう不自然な状態が悲劇を招かずに終るはずはない。
たまたま芸術に対する目を開かれ、人間の愛慾の赤裸々な姿と、その人生における深い意義と、甘美なまよわしを知った時、彼女の内部に深く蔵されていた情慾は、忽然として長い眠りからさめた。
そして、否応のない暴君のごとき猛威を揮って、彼女を恋人の胸へ投じたのである。
しかし、祖父の遺伝として彼女の内部に潜む神秘的傾向のために、彼女は幼い頃からしみ込んだ母の謬れる教育を、振り払うことが出来なかったのである。
温室の花のように、人工的な条件のもとに育てられたヴェーラには、この矛盾相剋に対する抵抗カが全くなかった。彼女は人生におけるこの最初の試煉のもとに、空しく斃れてしまったのである。
新潮文庫、ツルゲーネフ、米川正夫訳『片恋・ファウスト』P173-174
※一部改行しました
この物語は書簡形式で描かれています。手紙の書き手であるP・Bという男性が親友に宛てて直近の出来事について報告していくという流れで物語が進んで行きます。
P・Bが思いがけぬ形で再会したのが女主人公のヴェーラであり、かつて彼は彼女に結婚を申し込むほどの仲でした。しかし彼女の母に断られてしまった過去があります。
再会したヴェーラは夫を持ち母となっていました。
P・Bは複雑な気持ちを抱きながらもヴェーラ一家と交友を復活させることになります。
そこでP・Bが大好きなゲーテの『ファウスト』を朗読することになり、そしてその本をヴェーラに貸してしまうのです。
これが悲劇の始まりでした。
上の解説に述べられていたように、彼女の中に抑え込まれていた感性が爆発し、悲劇的な結末を迎えることになってしまったのです。
『ファウスト』を読んだだけでそんなことが起りうるのだろうか。私は最初読んだ時そんな疑問を持ってしまいましたが、ツルゲーネフにとってはそれほど彼の感性に大きな影響を与えるものとして存在していたのでしょう。
そして、ヴェーラのような抑圧された圧倒的感性を持つ人間が急に人類の最高傑作たる『ファウスト』を読んだらそうなってしまうのも無理はない。そうツルゲーネフは考えたのでしょうか。
いずれにせよ、ツルゲーネフの思想を知る上でこの作品は非常に重要なものとして捉えられているようです。
感想―ドストエフスキー的見地から
この作品が出来上がる背景に非常に興味深い出来事があります。
実はこの作品を書いていた頃、ツルゲーネフはあのトルストイの妹に恋をしていたのです。しかもその妹も人妻だったのです。
ツルゲーネフは『ファウスト』の主人公P・Bの口を借りて次のように述べています。
「私は自分が四十近いことも知っているし、彼女がほかの男の妻であることも、彼女が夫を愛していることも知っている。私は自分をとらえている不幸な感情から、隠された心の傷みと、結局は生きる力の消耗以外には何も残されないことをたいへんよく知っている―私は何もかも知っているのだ。私は何も期待していないし、何も待ち受けてはいない。でも、だからといって私は楽にはならない。」
「私は、いま、やっと女性を愛するとはどういう意味なのかを知った。そのことを語るのは恥かしいことだ、しかし、実際そうなのだ。私は恥かしい……恋とはやはりエゴイズムだ、私の年齢でエゴイストになるのは許さるべきじゃない。三十七歳にもなれば自分のために生きるべきじゃないのだ。何かに役立つことをして、地上に目的を持って生き、自分の義務を、自分の仕事をなしとげるべきなのだ。」
ここには作品の重要テーマが集約的に述べられているばかりでなく、この時期の作者自身の自戒の響きさえある。
筑摩書房、佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P90
トルストイの妹マリーヤ・トルスターヤとの恋が『ファウスト』の執筆に大きな影響を与えたというのは驚きでした。
そしてこの作品に込められたメッセージがまた何とも物悲しいのです。小椋公人の『ツルゲーネフ 生涯と作品』では次のように解説されていました。
死を前にして、人間の欲求が空しいものであること、青春と共に消え去った幸福への期待が空虚であること、それを求めようとすることが無駄で利己的であることを、作者はこの作品で語っている。(中略)
彼は幸福に対する無益な熱望を捨て去ることが必要であることを主張している。
『ファウスト』のフィナーレには次のように書かれている。
「最近の数年間の経験から、僕は一つの確信を得たのだ。生活は冗談でもなければ慰みでもない。またそれは享楽でさえもない……。生活は苦しい労働なのだ。欲望の拒否、不断の拒否―これこそ人生の秘められた意味であり、その謎を解く鍵である。
たとえいかに崇高なものであろうとも、好きな想念や空想の実行ではなく、義務を履行すること、―これこそ人間が心がけなければならないことである。自分の体に鎖をかけなかったら、義務という鎖をかけなかったら、人間は人生行程を最後まで倒れることなしに行きつくことはできない……。」
この最後の言葉は、作品全体の芸術的構成から見れば決して理性的なひびきをもって伝わってはこないで、作品は美しい、詩的な、挽歌的な調子で書かれており、この意味で説話者は神秘的な力の前に淋しく諦めの境地に入っていく。
「お前はあきらめねばならぬ、あきらめねば」という題詞がそれを物語っている
法政大学出版局、小椋公人『ツルゲーネフ 生涯と作品』P105-106
ツルゲーネフの後半生の作品は憂鬱な気分にさせるものが多いです。そのきっかけとなった時期がまさにこの頃であると言われています。
上の解説にもありましたように「あきらめなければ」という諦念がツルゲーネフを強く覆っていくことになります。
この辺りでも激情家ドストエフスキーとの大きな違いを感じさせられます。ドストエフスキーは最後の最後まで諦めずに人生と戦い続けた男のように私は感じています。
それに対しツルゲーネフは時代を俯瞰し、達観した賢者のごとく静かな憂鬱に身を任せます。
こうした違いが文学の上にも明らかに出てくるのだなと思いながら私はこの作品を読んだのでありました。
以上、「ツルゲーネフ『ファウスト』あらすじ解説―ゲーテの『ファウスト』に影響を受けた恋愛物語」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら
関連記事





































