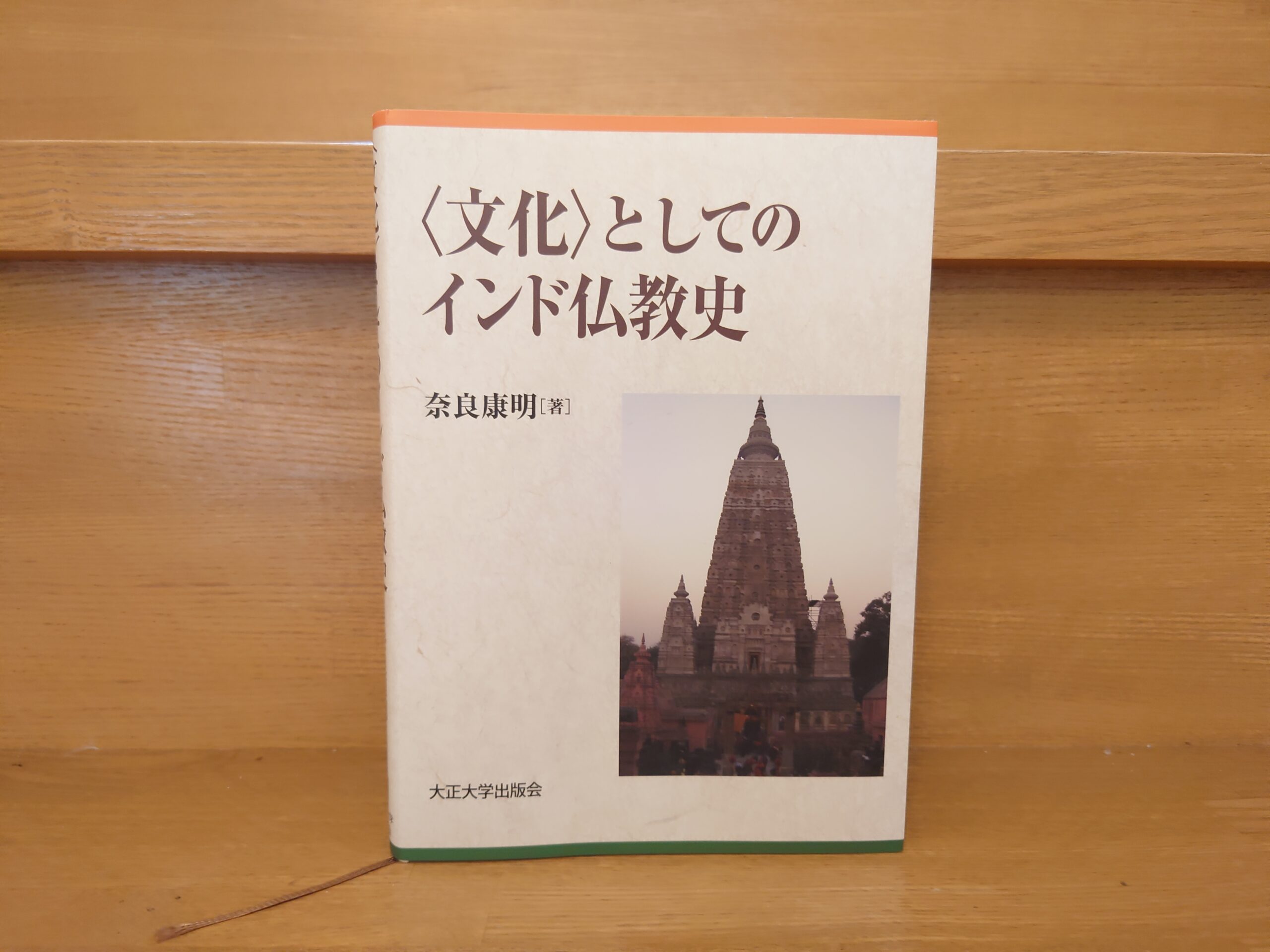奈良康明『〈文化〉としてのインド仏教史』概要と感想~葬式仏教批判に悩む僧侶にぜひおすすめしたい名著!
今回ご紹介するのは2018年に大正大学出版会によって発行された奈良康明著『〈文化〉としてのインド仏教史』です。
早速この本について見ていきましょう。
インドで発祥した仏教は、日本の現代社会に形を変えながらも伝えられている。インド仏教はインド社会ではその役割を終えている。草創期の仏教は、そして出家した僧侶や教団を支えた信者たちは、強固な身分制が存在したヒンドゥー社会の文化や思想とどう折り合いをつけたのだろうか。仏教を許容し、やがて仏教の中心思想ともなるヒンドゥー社会の文化を「業と輪廻」「縁起」「呪術」と「功徳」などをキーワードに解き明かす。仏教を含むインド思想・文化研究に広い視野を持つ仏教学者・奈良康明博士が問いかける「インド仏教史」。
Amazon商品紹介ページより
この本は記事タイトルに書きましたように、葬式仏教批判に悩む僧侶にぜひおすすめしたい作品です。これまでも当ブログでは『新アジア仏教史02インドⅡ 仏教の形成と展開』や辛島昇・奈良康明著『生活の世界歴史5 インドの顔』など仏教における葬儀の問題や仏教教団の実生活と一般信徒の関係などが書かれた本をいくつも紹介してきました。
これらの本を読んでいると原始仏教至上主義的な立場からの日本仏教批判がそもそも問題のある言説であることを強く感じることになりました。もちろん、私達僧侶ひとりひとりが僧侶として仏教に真摯に向き合うことは大切です。しかし「原始仏教でこう書かれているのだから今の日本仏教は間違っている」という批判に対しては明確に「ノー」と言うことができると私は感じています。
さて本書『〈文化〉としてのインド仏教史』ではそんな日本仏教批判をさらに踏み込んで論じていきます。
その切り口が書名にもなっている「〈文化〉としての仏教」です。
このことについて著者は第一章「仏教とは何か―問題提起」の中で次のように述べています。少し長くなりますが重要な箇所ですのでじっくり読んでいきます。
教理や信仰が社会に定着することは教団として定着することである。何らかの形で教団が存在しなければ、安定した環境のなかで出家修行者が法を修行し、学び、継承し、信者に生きる道を教えることは出来ない。インド仏教においても、出家修行者と在俗信者よりなる教団が成立して、仏教を伝承してきた。中国でも、日本でも、教団の形態は異なり、機能は同じではないが、とにかく仏法憎の三宝があり、教えをうけがいながら、三宝を外護する在俗信者の存在は欠かすことがなかった。
しかし、教団の立場から見るならば、出家修行者の説く仏教と社会生活をしている在俗信者の受けとめ方は乖離している。出家者は仏教の究極的目的である悟り、成仏を目指すものであるが、在俗信者にとって悟りは必ずしも人生の目的とはなっていない。出家者側の説く行法、自己節制、倫理的生活と実践、欲望の抑制などは「在るべき」仏教信仰としてその価値は認められているが、現実に十分機能しているとは言い難い。
また、在俗信者の社会生活には、当然、日常儀礼がなくてはならない。人生の成長諸段階の節目に行われる通過儀礼(Passinng Rites)、すなわち(日本でいえば)命名式、お宮参り、お食い初め式、誕生日、七五三、成人式、結婚式、葬式などは欠かすことが出来ないものであろう。その他祖先崇拝儀礼も重要であるし、農耕儀礼もある。また、多少なりとも呪術的な祈願儀礼等々は、いかをる民族、種族、部族にもあるし、社会生活において必須の宗教現象である。社会を出た出家者である比丘・比丘尼には必要なくとも、在俗信者の社会生活はこれがなければ成り立たないのである。
したがって、教団伝承の間に、仏教を受け入れた民衆側の種々な要請、あるいは安易な理解などに応じて、仏教教理のニュアンスが変わり、意味が改変されて定着していることは稀ではない。今日の日本語で通用している「因縁」、「縁起」、「無我」、「諦める」、「他力(本願)」など、仏教本来の教理的意味をはずれた形で使用されることの多い例である。また民衆の間に行われている民俗信仰的な観念や慣行、儀礼が教団の行事として浮上して来ることもある。葬祭儀礼などはその典型的なー例である。
「仏教教理」とこうした「仏教徒の生活に定着した観念と儀礼」は、タテマエとホンネとして対立し、歴史的伝承の間に、複雑に並列し、重層化し、融合し、相互の変容がもたらされることとなった。
そしてここに重要な現象は、こうした教理(伝統宗学をも含む)からはずれた観念や儀礼は「仏教ではない」と理解され、そのために仏教徒として行ってはならぬものと受け取られ、中には(教団側から)そう教理的に規定されるものも生じていることである。悟りにかかわるレヴェルこそが仏教であり、その他は仏教ではないとする「悟り一点主義」がインド以来伝承されている。この姿勢については以下の論述において多くの例を指摘していく。
だからこそ、現実に行われ、教団を支えている宗教観念・儀礼であるにもかかわらず、「非仏教」であり、「世俗化」だと切り捨てられ、したがって、その宗教的意味や機能がほとんど検討されず、ある時は仏教教団がなすべからざることをしていると非難される一因となる弊害が生じているのである。
ここに重要なポイントがある。仏教教理の面から「仏教でない」とされたものは、何故、「仏教徒が行ってはいけない」のであろうか。迷信あるいは倫理的な儀礼、あるいは仏教徒としてなすべきでない、とされたものは別である(例えばインド仏教における供犠は釈尊によって強く禁止された。それは不殺生の世界観に反するからである)。しかし、仏教でない、つまり悟りレヴェルの仏教信仰がないとされても、それが人びとを前向きに生きさせるものであるなら、行ってもいいのではないか。いや、好い悪いではなく行わなければ日常生活が成り立たないのである。現代日本における通過儀礼、葬祭、祖先崇拝はその一例にすぎない。
インド仏教においても同様の思考傾向が認められる。最初期の仏教伝承以来、エリート比丘たちは自らがこれぞ仏教である、と信じたもののみをとりあげて仏典に書き残した。その結果がいわゆる「原始仏典」である。簡明な教理、清澄な倫理、そして日常儀礼などを除去した世界、が展開されている。しかし、書かれていないから、現実になかったということにはならない。両者は区別されなければならない。
渡辺照宏博士は次のように指摘する。「あらゆる神秘性を排除し、神も奇跡もなく、宗教儀礼も行わず、ただ縁起の論理を理解し、信仰の裏付けのない倫理と禁欲生活とのみを要請するような宗教に、数千の無知な大衆がどうしてついて行けたであろうか。この理由一つから見ても、仏陀の時代の仏教は現在のパーリ文聖典よりも、もっとずっと宗教儀礼や信仰の要素が多かったに違いない」〔渡辺1967, 21頁〕。
事実、後代になるにつれ、仏教徒の間に行われていた功徳観念や死後の世界、霊魂、各種儀礼や呪術的祈願儀礼などが、特にジャータカやアヴァダーナ文献、南インドのタミル文学の仏教作品のような仏教説話文学のなかに隠しようもなく浮かび上がり、叙述されている。また、エリートたちの「悟り」こそが仏教の中核であり、それ以外は価値がないといわんばかりの思考方法は、教団が許容せざるを得なくなった民俗信仰的な要素を、「最終的には悟りに導くもの」と意味づけるようになった。四向四果、生天思想と禅定の深まりの結合、次第説法など、その例である。これに関しては本書で後にあらためて触れる。
「悟り」こそが仏教であり、日常儀礼は「仏教ではない」とする発想、「悟り一点主義」(Satori-oriented)は、仏教では歴史的なのである。
したがって、(「文献学的仏教学・宗学」と「信仰的仏教学・宗学」の)「教理」だけでは現実の社会に定着し、機能している仏教徒の思想と生活をカバーしきれない。過去の仏教史においても、また現代においても、社会に機能している仏教を正しく評価し、未来への展望を開くのに、教理学だけでは十分ではない。ここに、仏教を「教理」としてではなく、それなら包み込む「文化」として捉える視座が意味を持ってくる。
大正大学出版会、奈良康明『〈文化〉としてのインド仏教史』P10-13
「あらゆる神秘性を排除し、神も奇跡もなく、宗教儀礼も行わず、ただ縁起の論理を理解し、信仰の裏付けのない倫理と禁欲生活とのみを要請するような宗教に、数千の無知な大衆がどうしてついて行けたであろうか。この理由一つから見ても、仏陀の時代の仏教は現在のパーリ文聖典よりも、もっとずっと宗教儀礼や信仰の要素が多かったに違いない」
「したがって、(「文献学的仏教学・宗学」と「信仰的仏教学・宗学」の)「教理」だけでは現実の社会に定着し、機能している仏教徒の思想と生活をカバーしきれない。過去の仏教史においても、また現代においても、社会に機能している仏教を正しく評価し、未来への展望を開くのに、教理学だけでは十分ではない。ここに、仏教を「教理」としてではなく、それなら包み込む「文化」として捉える視座が意味を持ってくる。」
本書では「仏教文化」の最たるもののひとつとしてまず葬儀について語られます。本当はその概要をここで紹介できればいいのですが、断片的にその内容をお伝えしても逆に意味が伝わらなくなってしまう恐れがあります。著者は丁寧に丁寧に葬儀と仏教文化について解説しています。そのひとつひとつが大切な要素ですのでそれを要約してお伝えしても意味をなさないと私は思ってしまいました。
ですのでぜひ本書を読んでその内容を確かめてください。
確実に言えるのは「僧侶としてのあり方に悩む方」にぜひおすすめしたい作品だということです。
文献に書かれた教義だけが仏教なのではなく、そこに生きる人々と共に歩んできたのが仏教なのだというのがよくわかります。私自身、この本にたくさんの勇気をもらいました。仏教は現代においても必ずや生きる力に繋がるのだということを私は感じています。
僧侶以外の方でも、仏教における儀礼の意味に興味のある方には多くの発見がある作品です。
ぜひぜひおすすめしたい名著です。著者の信念が伝わってくる素晴らしい一冊でした。
以上、「奈良康明『〈文化〉としてのインド仏教史』~葬式仏教批判に悩む僧侶にぜひおすすめしたい名著!」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事