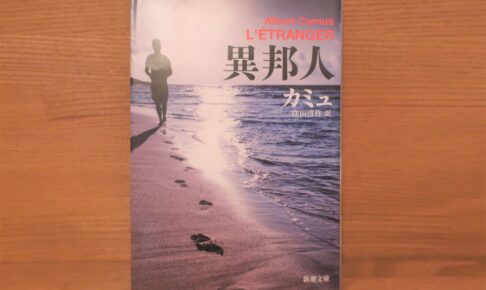ニーチェ『善悪の彼岸』『道徳の系譜』あらすじと感想~道徳の起源とキリスト教倫理の成立を分析した作品

今回ご紹介するのは1887年にニーチェにより発表された『善悪の彼岸』『道徳の系譜』です。
私が読んだのはちくま学芸文庫版、信太正三訳『ニーチェ全集11 善悪の彼岸 道徳の系譜』所収の『善悪の彼岸』『道徳の系譜』です。
早速この本について見ていきましょう。
大きな期待をもって世に送りだした『ツァラトゥストラ』の不評に心を痛めるニーチェ。『善悪の彼岸』は誤解と歪曲から自己の思想を救う意図をこめて、そのー種の注釈書として著わされた。本書では、19世紀ヨーロッパの道徳と宗教の価値が厳しく問われ、いわゆるく客観性〉〈歴史的感覚〉〈科学性〉〈同情〉という近代的信仰の対象物が鋭い批判のメスで解剖されている。ニーチェの哲学の円熟期を代表する重要な著作の一つである『善悪の彼岸』、その終楽章ともいうべき『道徳の系譜』の二作品を収録する。
ちくま学芸文庫、信太正三訳『ニーチェ全集11 善悪の彼岸 道徳の系譜』裏表紙
以下この2作品の成立過程と大まかな内容を見ていきます。
『善悪の彼岸』
一八八五年から八七年にかけて精力を注いだのは『善悪の彼岸』(一八八六年)とその補説として書かれた『道徳の系譜学』(一八八七年)である。ともに自費出版である。
ニーチェはそのころ、夏はシルス・マリアで、冬はニースですごすのを常とし、『ツァラトゥストラ』にたいする世間の無理解にひそかに堪えて、自然科学や法学の領域での広い読書によって寂寥をまぎらわし、とくにマキアヴェリを熱心に読んで、政治と道徳との根底について考えを鍛えた。その最初の成果が『善悪の彼岸』である。
これは十九世紀後半のヨーロッパの精神状況を多方面から批判して、多岐な思想をアフォリズム形式で表現したのである。いわば、ツァラトゥストラのいう、「大いなる正午」に自然に熟れ落ちた果実のように、独特な軽快さと美しい音調をもち、ドイツ語の言語的創造としてもっとも完成度の高いものと言われている。
しかし、それを受け入れる読者はいない。かつての親友ローデさえ、「この中に書かれた哲学的な部分は貧弱で、ほとんど児戯にひとしい。政治的な面はばかげているし、世間知らずだ……ただ人真似をし、寄せあつめの仕事をしているこの精神の不毛さ」といっている。
ベルンのある雑誌に「ニーチェの危険な書」という酷評文がのり、マルヴィーダ・フォン・マイゼンブーク嬢さえ、もうこの書を読まなかった。唯一の大きい例外がある。寄贈本に好意ある返書をよせたフランスの巨頭イポリット・テーヌで、ニーチェが感激したことはいうまでもない。
中央公論社、『世界の名著46 ニーチェ』P43-44
※一部改行しました
『善悪の彼岸』は不評に終わった『ツァラトゥストラ』の思想を挽回せんために書かれた作品でありましたが、上の解説にもありますように、この作品も不発に終わってしまいました。
ただ、この作品には有名な言葉も収められています。
怪物と闘う者は、そのためおのれ自身も怪物とならぬよう気をつけるがよい。お前が永いあいだ深淵をのぞきこんでいれば、深淵もまたお前をのぞきこむ。
ちくま学芸文庫、信太正三訳『ニーチェ全集11 善悪の彼岸 道徳の系譜』P138
やはりニーチェ節は健在です。
ただ、個人的にはこの『善悪の彼岸』よりもその直後に書かれた『道徳の系譜』の方がおすすめです。
こちらも解説を見ていきましょう。
『道徳の系譜学』
このような無反響や悪評にこたえるめに、主著の一部に予定していた材料をもとに、八七年夏、「一つの論駁書」という副題をもった『道徳の系譜学』を二週間で書きあげた。前作の無反響がアフォリズムという仮装的な表現形式にあることを見ぬいたニーチェは、この書でひさしぶりに一般的な論述の形式をとった。
第一論文では、世人がこれまで信奉してきた道徳的価値判断は、古代の支配者の高貴な道徳にたいするキリスト教的奴隷人の怨恨感情、後者の前者に対する大がかりな反乱にほかならないと説き、『アンチクリスト』に引きつがれる「キリスト教の心理学」を提出している。
第二論文は、一般に神の声と信じられている良心を、外への放出をせきとめられて内へ向かった残忍の本能とした「良心の心理学」。
最後の第三論文では、僧侶の禁欲主義は有害な理想であり、虚無への意志にほかならないのに、その理想がはげしく求められるのは、「人は何も欲しないよりは、むしろ無を欲する!」というデカダンの現われだと断じて、「僧侶の心理学」を試みた。
ツァラトゥストラのロをかりてなされたキリスト教攻撃は、こうして調子を高め、かれ自身のことばとして直叙されるようになった。
中央公論社、『世界の名著46 ニーチェ』P44
※一部改行しました
この作品には個人的な思い入れがあります。
というのも、学生時代、倫理学の授業の課題図書としてこの作品を読むことになり、ニーチェ作品で初めて手に取った作品が『道徳の系譜』だったのです。つまり、私の初めてのニーチェ体験がこの『道徳の系譜』だったのです。
この作品は上の解説にありますように、アフォリズムという形式ではなく論理的にわかりやすい形で展開されます。これまであまりに自分の論が理解されなかったことから、彼はその論述スタイルを変更してまでこの作品を書き上げたのです。
おかげでニーチェ作品の中では非常に読みやすく、わかりやすいものとなっています。(それでも難しいですが)
この作品でニーチェはキリスト教世界における道徳の歴史を分析し、考察します。
善人とは何か、悪人とは何か。
はて、そもそも善悪とは何か。それは立場によって変わってくるのではないか。
いや、キリスト教道徳は悪が善に変わったという前代未聞の試みなのだ。弱きものが怨恨感情(ルサンチマン)によって強き者を引きずり落したのだとニーチェは驚くべき論を展開します。
私の初めてのニーチェ体験は彼のとてつもない道徳論に度肝を抜かれっぱなしでした。
キリスト教の道徳観をこれでもかと批判するニーチェ。これには圧倒される他ありません。この猛襲にほとんど私たちは置いてけぼりを食らうほどです。
ニーチェのすごい所は単にキリスト教を「宗教は迷信だ」「科学的に神はありえない」と切り捨てるのではなく、その在り方を徹底的に分析し考察している点にあります。単に「宗教はまやかしだ」と述べる無神論者とはかなり違った色があるのです。
普通の人なら思いもよらないところまでニーチェは潜り、より深く根源へ根源へと突き進んでいきます。そうした所から生まれてくるキリスト教への疑問や問題点をニーチェはえぐっていくのです。
ニーチェは究極的なところまで行こうとするのでその議論はたしかに極論のようになってしまっているところもあります。ですが、だからこそ彼の言葉に力があるというのも事実です。この本は恐るべき作品です。
私は同じく学生時代、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官の物語」にも大きな衝撃を受けました。その時の顛末は以下の記事でもお話ししましたが、宗教における根源的な部分に戦いを挑む彼らの絶対的探究心、思想的闘いには本当に驚かされます。
『道徳の系譜』はニーチェ作品の中でも特に私の印象に残っている作品です。また、ニーチェの思想を知る上でもとてもおすすめな作品です。そして他の作品に比べて読みやすいというのもありがたいです。
ぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「ニーチェ『善悪の彼岸』『道徳の系譜』あらすじと感想~道徳の起源とキリスト教倫理の成立を分析した作品」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
ニーチェおすすめ作品、参考書一覧記事はこちらです
関連記事