ニーチェは発狂したから有名になったのか~妹による改竄とニーチェの偶像化
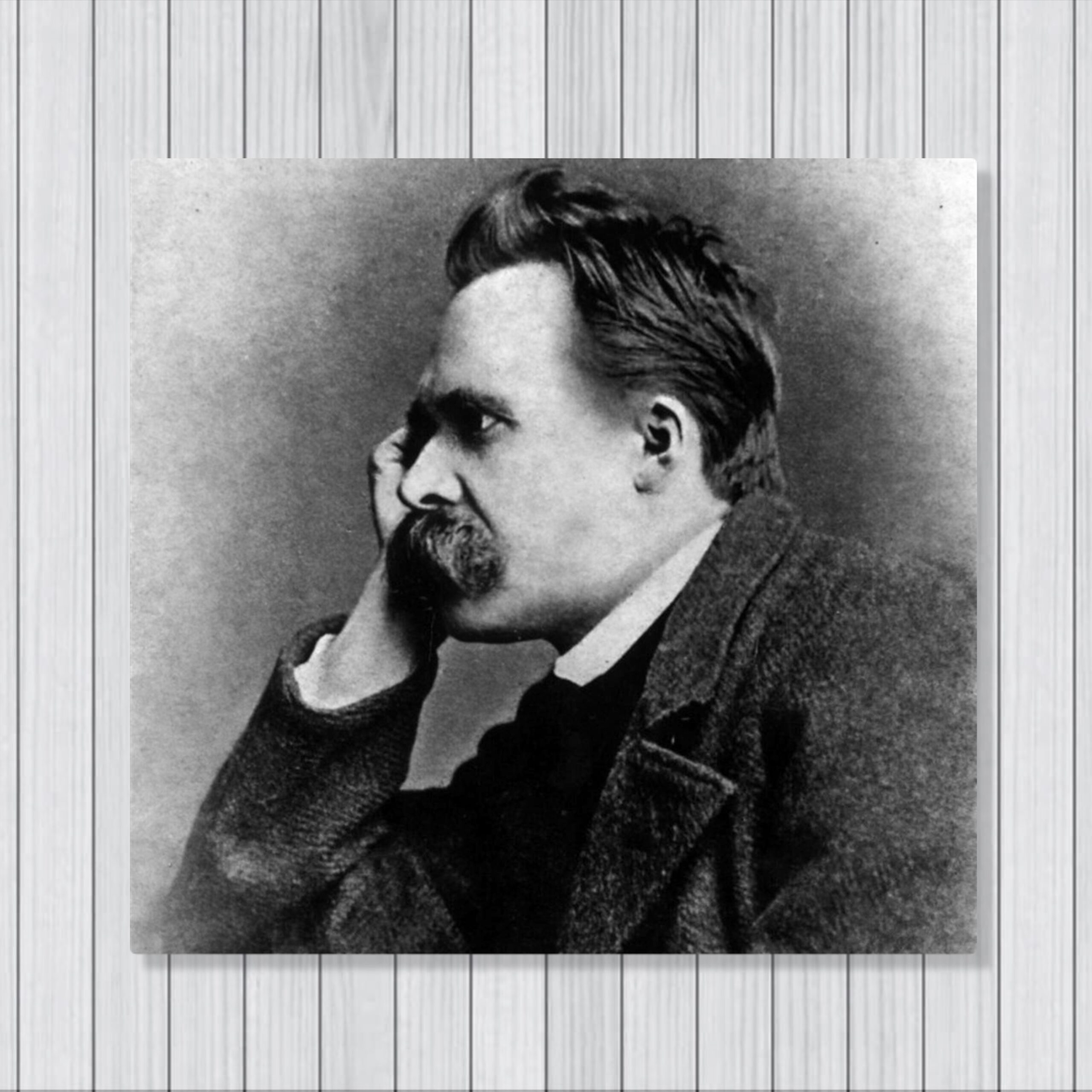
ニーチェは発狂したから有名になったのか~妹による改竄とニーチェの偶像化

フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)wikipediaより
ニーチェは偉大な思想家です。ニーチェが遺した作品は今もなお輝きを放ち続け、多くの人に読み継がれています。
しかし偉大な哲学者、作家にありがちなことですが生前は世間から理解されず不遇の生涯を送ることになりました。
そして彼はほとんど世間に知られることなく、1889年に発狂してしまいます。彼が45歳になる年でした。
ただ、皮肉なことにニーチェは発狂後に一気に有名になっていきます。発狂するまで思索した哲学者ということで世間の注目を引いたのです。ニーチェはその後重度の精神疾患から回復することもなく、1900年に亡くなっています。つまり彼は自分の著作が売れていることも知らずに命を終えていったのでした。
ニーチェ発狂後の顛末について参考書の記述を見ていきましょう。
精神錯乱に陥って後の何か月か経って、ポオ、バイロイト、エプソムにもその報が伝わった。上流の精神的な世界がニーチェを発見した。狂気のフィナーレがその著述に遡及的に一つの陰欝な真理を授けることになった。そこにいたのは、存在の秘密にそんなにも造詣の深い者であって、そのために彼は狂気に陥ったのであった。
ニーチェは『華やぐ智慧』の中の有名な個所で、神を否定する者を「狂人」と名づけていたが、今、その当人が狂気に陥ったのであった。このことは想像力を掻き立てずにはいなかった。
ニーチェの最後の書を出版したC・G・ナウマンは、これはいい商売になると感じ取り、一八九〇年にすでにニーチェの著作集の新しい版を出したが、これは飛ぶような売行きであった。一八九三年にパラグアイから帰国したニーチェの妹のエリーザべトは、兄の著書をはばかるところなく巧みに広く市場に売り込んだ。
彼女はニーチェがまだ生きているうちにワイマールにニーチェ=アルヒープを設立し、最初の全集出版の手配までした。その際、彼女は「カへの意志」を証明した。というのは、彼女は兄の特定の姿を世間に押しつけようと試み、捏造も辞さなかったからである。こうした捏造のすべてはその後すっかり知れわたることになる。彼女はニーチェをドイツ国粋主義者、人種主義者、軍国主義者に仕立て上げようとし、読者の一部では、とくに正統マルクス主義者の中では、彼女のこの試みは今日に至るまで成功したものになっている。しかし時代精神のより洗練された需要に応えるすべも彼女は持ち合わせていた。
法政大学出版局、リュディガー・ザフランスキー、山本尤訳『ニーチェ その思考の伝記』P357-358
もちろん、妹の存在だけでニーチェが有名になったというわけではありません。ちょうどこの頃、ニーチェ思想が世に受け入れられやすい土壌が育っていたのでした。少し長くなりますが引用します。
ニーチェの時代には、市民層の若者は歳より老けて見られたがった。当時は若いということはむしろ出世の妨げであった。顎髭が早く生える薬が薦められ、眼鏡がステイタスシンボルとみなされた。父親を真似し、「父親殺し」と言われる高くて硬いカラーを着けるのがはやった。思春期の若者もフロックコートを着せられ、それにふさわしい歩き方が教えられた。かつては「生」は何か興醒めなものとされて、若者は生の経験を積んで分別をつけるべきとされた。
しかし今、「生」は血気盛んに出発しようとしているもの、若者そのものである。「若いこと」はもはや隠さねばならない不名誉なことではなくなる。
そうではなく逆に、年寄りの方が弁明しなければならない。死に絶えて硬直しているのではないかと疑われているからである。一つの文化全体が、それはヴィルヘルム文化なのだが、「生の法廷」(ディルタイ)に呼び出されて、この生はまだ生きているのかとの問いに対決させられる。(中略)
こうした精神の姿勢は本質的にニーチェの影響から出たものである。ニーチェの影響を受けるためには、ニーチェを読まなくてもよかった。ニーチェの名前が識別標になった。自分を若く、活力ありと感じていた者、自分を高貴なと思っていて、道徳的な義務を厳格には考えなかった者は、自分をニーチェ主義者と感じることができた。
ニーチェ主義はすっかりポピュラーになって、九〇年代にはすでにそれに対するパロディーや風刺詩や誹謗文書が出されていた。たとえばマックス・ノルダウは、頭の固い手堅い市民層を弁護して、このニーチェ主義を「伝統的な規律からの実践的絶縁」と酷評し、「人間の中の野獣の解放」に警告を発している(アシュハイム二八)。こうした批判者たちにとってニーチェは意識を陶酔と衝動に沈ませた哲学者であった。ニーチェ賛美者の多くもニーチェを実際にそのように理解し、葡萄酒と女と歌でもってすでにディオニュソスのすぐそばに行き着いていたと信じていた。
こうした人たちの間で流通していたニーチェは、半値で手に入れたニーチェであった。忘れてはならないのは、ニーチェが「生」を創造的な能力と同一視し、それをその意味で「力への意志」と名づけていたことである。
法政大学出版局、リュディガー・ザフランスキー、山本尤訳『ニーチェ その思考の伝記』P360-361
※一部改行しました
ニーチェ思想は難解です。しかもその言葉はあいまいで、読者を困惑させることが多々あります。
しかし、ニーチェの言葉は強い。それは間違いのないことだと思います。
そうした言葉のあいまいさや強さは、受け取り手が好き勝手に解釈する余地を与えてしまいました。
「ニーチェの影響を受けるためには、ニーチェを読まなくてもよかった。ニーチェの名前が識別標になった。」という言葉はまさにそれを象徴しています。ニーチェの名を用い、断片的な言葉を掲げればそれで権威付けができてしまうのです。ニーチェの難解な思想を厳密に考える人はなかなかいません。こうしてニーチェが偶像化され、一人歩きしていってたのでした。
ニーチェ発狂後の展開について、今度はベン・マッキンタイア―著、藤川芳郎訳『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』の記述を見ていきましょう。

ニーチェの妹エリーザベトは凄まじい女性でした。彼女については以前紹介した上の記事をご覧頂きたいのですが、ニーチェを徹底的に利用しその偶像化を進めた人物です。では本文を読んでいきましょう。
ニーチェが倒れたとき、彼の著作を知っていたのは、一握りの友人やゲオルグ・ブランデスのような先見の明のある知識人だけだった。正常なときのニーチェは自分自身と著作を売り出すために多大な努カを払ったが、すべて失敗に終わっていた。しかし、正常ではなくなると、広く一般の注目を浴びるようになった。
ニーチェは書いている、「生きる意味、生きる権利が失われてからも、卑怯にも医者と薬にたよってただ生きつづけることは、社会の激しい侮蔑を呼び起こして当然の行為だ」。ニーチェの場合、社会はその正反対のことをしたのだった。新聞にもこのナウムブルクの狂気の哲学者に関する記事が載るようになった。
エリーザべトがひどく腹を立てたことには、ルー・(今はアンドレアス・)サロメまでもが、かつて知り合いだった偉大な人物について、その思い出を活字で発表しはじめた。
皮肉なことに、ニーチェの精神異常にたいするこうした覗き見的な好奇心によってはじめて、世間は彼の著作に広い関心をもつようになったのだ。ニーチェの友人たちが心配したとおり、エリーザべトはみずから介入することを決心した。法的にはそんなことをする権利はなかったのであるが。
白水社、ベン・マッキンタイアー著、藤川芳郎訳『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』P212
※一部改行しました
ニーチェの妹エリーザベトはニーチェを神格化するために伝記を書きました。これが後のニーチェ像に大きな影響をあたえることになりました。
おそらくエリーザべトがいなくてもニーチェ崇拝はあっただろう。しかし、彼女の傑出した宣伝能力なくしては、あれほど大衆的にも、またいかがわしくもならなかっただろう。(中略)
エリーザべトの伝記こそが、ニーチェをたんなる人間的な、あまりにも人間的な人物ではなく、超人らしきものの象徴に変えてしまったのである。哲学者というより、むしろ予言者に仕立てあげたのだ。
エリーザべトは一〇年以上の歳月をかけて、全二巻におよぶ兄の生涯の物語を書き上げた。(のちに短縮してニつの作品にまとめられる。『若きニーチェ』と『孤独なニーチェ』である。)伝記を書くに際しては三つの意図があった。兄についてはほとんど神のごときイメージを作り上げること、自分自身については、その唯一の心の友であり支援者というイメージを作ること、そして、兄の哲学にできるかぎり優れた解釈―彼女自身の解釈―を施すことだ。
できあがったのは、やたらと飾りたてた不正確なものだったが、とても評判がよかった。「驚くほど美しく、大きくて表情豊かな目」だの、「きわめて礼儀正しい振舞い」について、事細かな記述がふんだんに織りこまれていた。彼女の主張するところでは、「フリッツにはどこか類稀なところがあることを、幼いときから見て取り、その確信をロにしたたった一人の女の肉親が、妹のこの私なのである。」彼女だけが実体験にもとづいて、兄の生涯と哲学を語ることができるのだ。
「兄はどんな友人にも、私に話したほど率直にあるいはこっそり話したことはなかった。私はいつも疑っていた、兄は心に浮かんだことを、私よりも友人たちにもっと多く語っているのではないかと。〔明らかにエリーザべトの言うとおりだ。〕ここからいくつもの間違いが起こったのだった。」
それを訂正することが自分の義務だ、と彼女は主張する。「攻撃をはねつけ、間違いを取り除き、細大漏らさぬ正確さで事実と兄の生涯の経験を描き出す義務があるのは、だれよりもこの私なのだ。なぜなら、私ほど兄の近くにいたものはいないのだから。」
そして、自賛していないときには、兄の称賛の言葉を引用した。「『妹は女性ではない、友人だ』と兄は言ったらしい。―私のとても女らしい恰好と滑稽な対照をなす意見である。」彼女は、「役に立ち、信頼でき」、「兄の助手であり、非常時には慰めとなり」、「耳と頭だけでなく、心で聞く」人間だった。
白水社、ベン・マッキンタイアー著、藤川芳郎訳『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』P2218ー222
※一部改行しました
エリーザベトは兄ニーチェの伝記を作り上げました。
それは「妹である私こそ兄の全てを知っている」という立場で書かれたものでした。
しかし、これは事実とは全く逆でニーチェとエリーザベトは非常に仲が悪かったのです。ニーチェはエリーザベトが南米パラグアイで反ユダヤ主義の村を作りそこで人々を騙していたことを強く非難していました。しかも、独善的な妹に対し幾度となく批判を加えていました。明らかに彼女から距離を置こうとしていたのです。つまり、エリーザベトがこの伝記で述べていることは捏造だらけなのです。この伝記はニーチェを神格化しさらには自らをニーチェ崇拝の聖なる伝道者たらんとする意図で書かれていたのでした。
さらにはニーチェが遺したものの改竄や意図的な取捨選択もなされることになります。続けて見ていきましょう。
ニーチェは膨大な未発表原稿を残していた。何箱ものノートや走り書き、アフォリズム、ほかの本からせっせと書き写した引用、格言、思いつきや意見などだ。それが彼の書く方法だったのだ。思いつきが具体化するたびに、健康維持のために、ひっきりなしにばらばらの紙になぐり書きするのである。
ニーチェの遺稿、つまり刊行されていない彼の著述の遺産は、深遠と凡庸、貴重なものと無意味なものからなっている。保存しておこうという意図や後の著作に入れる意図がはっきりしているものもあれば、とっくに投げ捨ててしまってもよかったものもある。また、印刷に付されるばかりの完成した著作もいくつかあった。
白水社、ベン・マッキンタイアー著、藤川芳郎訳『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』P212-213
※一部改行しました
エリーザべトは、兄との関係のイメージを輝かしいものにするのに役立つとみれば、徹底して文書を偽造した。ニーチェがだれかほかの人に宛てた手紙でも、稀にみるような称賛の言葉を見つけると、手紙の冒頭の受取人の名前を自分の名前と差し替え、自分宛ての手紙だったように装ったことも一度ならずあった。
また、自分が受け取ったという手紙の《複製》を作り、もとの手紙はパラグアイにいるあいだに文箱のなかから盗まれてしまった、と言い張ったこともある。望み通りの印象をあたえてくれない手紙がどれほど破り捨てられたか、今となっては知る由もない。
フリッツ・ケーゲルが彼女のところを辞めるときには、二-チェが自分について考えていたことを記した手紙のコピーを持ち出すことを恐れて、ケーゲルの相続人にたいして出版を差し止める法的措置をとった。
しかし、間違いなくエリーザべトの最大の過ちは『権力への意志』の出版だった。これはニーチェの最高傑作で、最後の昏倒の前に書かれた大いなる《すべての価値の価値転換》だとされているものだ。たしかにニーチェはそのような著作の構想をもっていたが、おそらく断念していた。出版する用意はなく、したがって出版を望んではいなかったのだ。それが完成しているのを見たら、きっと驚いただろう。単純な事実は、ニーチェは『権カへの意志』という題名の本は書かなかったということだ。書いたのはエリーザべトである。
エリーザべトがペーター・ガストの助力をえて一九〇一年に『権力への意志・習作と断片』という題で出版した本は、じつのところ、ニーチェ自身が破棄したり別のところで用いたりした哲学的がらくたを寄せ集めたものにほかならなかった。
後年には断片がさらに追加されて大部の本になり、予言者もしくは(価値制定者)としてのニーチェの名声を確立するために、表題もいっそうどぎつい『権力への意志―すべての価値の価値転換』に改められた。
エリーザべトは、本来ならば関連のない走り書きや手記や箴言を寄せ集め、そこにあるはずのない秩序をもたせて、これがニーチェの代表作だと言い張り、この本にまったく偽りの重要性をもたせた。
たとえば、『権力への意志』の第四部は「陶冶と訓育」と呼ばれているが、これは誤解を招く。たしかにニーチェは、数多い草稿の一つでこの題名を使いはしたが、それは放棄されたのだ。実際のところ、彼はここで陶冶についてほんのわずかしか述べておらず、しかもそのことごとくが、控え目にいっても曖昧であり、(フェルスターやエリーザべトや、のちのナチスが考えたような)生物学的陶冶についてはほとんど何も言っていない。それでもなおこの題名が、ニーチェの《主要作品》と喧伝された著作のほぼ四分の一を指すものとして選ばれたのだ。
白水社、ベン・マッキンタイアー著、藤川芳郎訳『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』P237-238
※一部改行しました
いかがでしょうか。私はこの箇所を読んでかなり衝撃を受けました。手紙の改竄まで平気で行われていたとは驚きですよね・・・
また、ニーチェは膨大な遺稿を残しました。しかしそれはメモであり、作品ではありません。作品にするつもりもなかったような走り書きがニーチェの主要著作として喧伝されることになってしまったのです。
これを読み、もしかしたら気づかれた方もおられるかもしれません。
そうです。これはマルクスの『資本論』の第二部、第三部と似ているのです。マルクスも『資本論』を第一巻までしか書いていないのです。

マルクスもニーチェと同じく、思いついたことや書き写したもののメモを膨大に残していました。しかし、それを作品として、「完成された思想」としてまとめることはありませんでした。
しかしエンゲルスがそれらをまとめ上げ『資本論』の第二部以降をマルクスの名で出版しています。
さらには近年、そんなマルクスのメモが体系化され、「マルクスの真の思想を知る手がかり」として登場するようにもなっています。「マルクスの思想は実は発表されていない晩年のメモの中にこそあった。」と述べられるようになっています。
これ以上は申しませんが、「何をもってその人の思想となすのか」というのは非常に難しい問題です。
ただ、この本が述べるにはニーチェは明らかに妹によって改竄されてしまったということでした。しかも皮肉なことに、それによってニーチェが爆発的に広まっていったという結果になったのでした。
ニーチェがいかに受容されていったか、妹によってどのように広められていったかは『ニーチェ その思考の伝記』、『エリーザベト・ニーチェ ニーチェをナチに売り渡した女』、『西尾幹二全集第五巻 光と断崖ー最晩年のニーチェ』に詳しく出ていますので興味のある方はぜひ読んでみてください。
私としてはこうしたニーチェを知り、今まで抱いていた「危険な思想家」というイメージがかなり変わりました。
さらに上に紹介した本と合わせて『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』を読み、ニーチェが何を求め、何に苦悩していたかを知ることになりました。
すると不思議なことに、ニーチェの難解な思想だけでなく、「ニーチェその人」に興味が湧くようになりました。「ニーチェは何を思いながら作品を書いていたのか。それを著作から感じ取れるように読んでみたい」と思うようになったのです。
これはドストエフスキーの時と全く同じです。ドストエフスキーを読み始めた時も、最初は彼の思想や著作にだけ関心を持っていたのがいつしか「ドストエフスキーその人」に興味が湧くようになっていきました。「なぜこの人はこんなことを思うのだろうか」という疑問が浮かんでくるようになったのです。
『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』を読んで感じたように、ニーチェとドストエフスキーはやはり似ているのかもしれません。最近特にそう感じるようになってきました。
最終的な道は違えど、絶対的なものを求めて戦い続けた2人の生涯に私は惹き付けられたのかもしれません。
今となっては私はニーチェを好きとすら言えるかもしれません。
もちろん、彼が「利用されやすい危険な存在」であるという思いは消えていません。しかしニーチェが偉大な哲学者であるという事実は決して変わりませんし、その生涯、人柄は非常に興味深いものがあります。
ドストエフスキーを学ぶ上でも、浄土真宗の開祖親鸞聖人を学ぶ上でもニーチェの存在は新たな視点を授けてくれるのではないかと感じています。
以上、「ニーチェは発狂したから有名になったのか~妹による改竄とニーチェの偶像化」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
ニーチェ: その思考の伝記 (叢書・ウニベルシタス 724)
エリーザベト・ニーチェ ─ ニーチェをナチに売り渡した女 (書物復権)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

ニーチェおすすめ作品、参考書一覧記事はこちらです

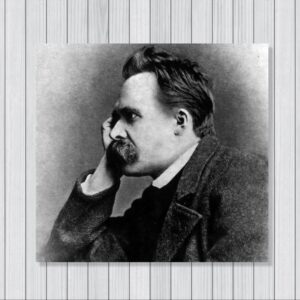
関連記事




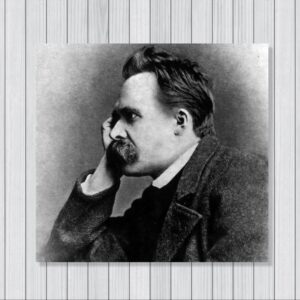









コメント