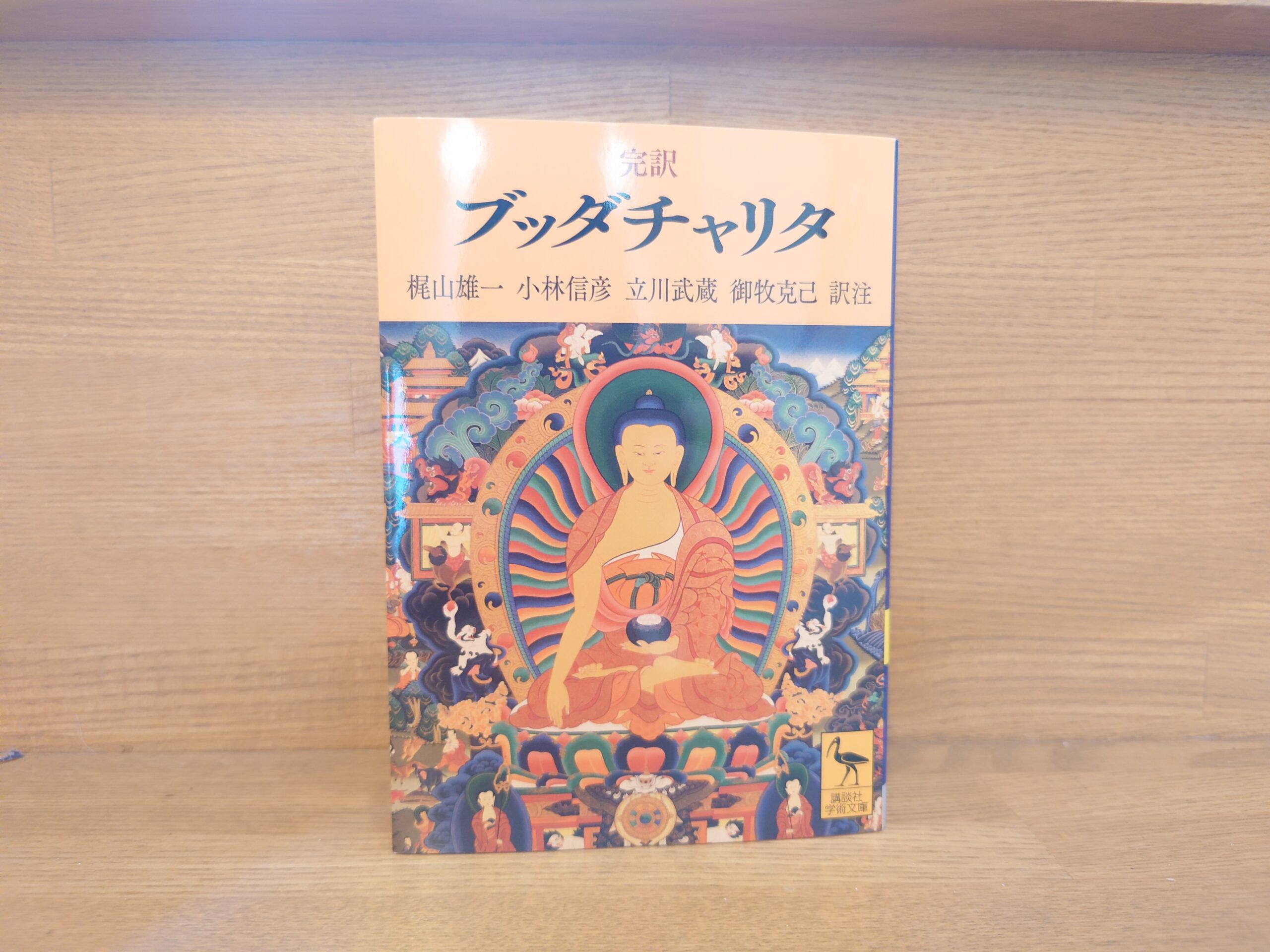アシュヴァゴーシャ『ブッダチャリタ』あらすじと感想~『仏所行讃』としても知られる仏伝の大元!ブッダの生涯を叙事詩化!
今回ご紹介するのは2019年に講談社より発行された梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳の『完訳 ブッダチャリタ』です。
早速この本について見ていきましょう。
誕生からその死、遺骨の分配まで――。ゴータマ・ブッダの全生涯を、仏教詩人・アシュヴァゴーシャが華麗なる美文で綴った、インド文学史の名著『ブッダチャリタ』。
Amazon商品紹介ページより
仏教思想の深い造詣に支えられたその作品は、仏伝資料としての価値も高く、数世紀に亘ってインド仏教界で称えられてきた。しかし、1893年に出版された14章までのサンスクリットテキストはのちに和訳、出版されていたものの、後半14章は長年、欠落したままだった。
その完結をみるべく、4人の仏教学者が完訳に取り組んだのが本書である。チベット訳、漢訳を丹念に補足しながら全28章を、可能な限り原典に忠実に再現。もっとも古く、もっとも美しい、仏教叙事詩の完訳、誕生。

今作『ブッダチャリタ』は1~2世紀頃にインドで活躍した仏教詩人アシュヴァゴーサ(馬鳴)による仏伝です。漢訳では曇無讖によって『仏所行讃』として翻訳されています。空海や最澄、鎌倉仏教の開祖たちもこの仏伝を読んでブッダの生涯を学んでいたのではないでしょうか。
本書『ブッダチャリタ』とアシュヴァゴーサについて巻末の馬場紀寿氏の解説では次のように説かれています。
本書は、インド文学史上の傑作であるアシュヴァゴーシャ作『ブッダチャリタ』の全現代語訳、しかも、近代仏教学史上に燦然と輝く名訳である。(中略)
北西インドを支配したクシャーナ朝で、二世紀頃に活躍したと考えられるアシュヴァゴーシャは、現存資料から知られる限り、仏教史上、個人の名において作品を著した最初の人物である。(中略)
アシュヴァゴーシャは、詩人としてのみならず偉大な仏教者として知られ、その名声はインド仏教世界で数世紀にわたって続いていた。七世紀前半にインドに渡った玄奘は『大唐西域記』巻八で「その知は万物にゆきわたり、仏道の実践は三乗にあまねく」(大正藏五一巻、九一三ぺージ上段二六行目)と称えている。さらに七世紀後半にインドに滞在した義浄は『南寄帰内法伝』巻四で、各世代に一人か二人しか現れない、日月や龍象に喩えられる大人物としてナーガールジュナ(龍猛)やアーリヤデーヴァ(提婆)と共にその名を挙げ(大正藏五四巻、二二九ぺージ中段一五行目)、『ブッダチャリタ』について「五天竺(南アジア)や南海(東南アジア島嶼部)で唱えない者はいなかった」(大正蔵五四巻、ニ二八ぺージ上段一四行目)と証言している。
アシュヴァゴーシャは、『ブッダチャリタ』を作成するに当たって、独自の内容を創作したのではなく、ブッダの伝記にかんする古来の伝承を忠実に継承している。第一章から第二一章は『根本説一切有部律』の「破僧事」に収録される仏伝的記述と、第二二章から第二八章は『涅槃経」と、物語の順序がほぼ対応する。彼に先行する伝承を参照し、それらの内容をまとめて、『ブッダチャリタ』を編纂したのである。
他方、アシュヴァゴーシャは、ゴータマ・ブッダの全生涯を洗練された美文によってうたいあげ、各場面の生き生きとした描写に成功している。若き王子を前にして恋に落ちた若い女性たちのいじらしい態度(第四章)、出家した王子を連れ戻すようにやってきた大臣・宮廷祭官の二人とゴータマとの緊張感に満ちた議論の応酬(第九章)、マガダ国の都、ラージャグリハ(王舎城)に入城する際の出家者ゴータマの気品あふれる姿(第一〇章)、彼をおののかせ修行を断念させようとしてマーラが繰り出す迫力ある化物の軍勢(第一三章)など、本書のいたるところで、アシュヴァゴーシャの詩的表現力は精彩を放っている。
このように、仏教文献であると同時に文学作品でもある『ブッダチャリタ』を翻訳するには、仏典にかんする知識だけでなく、恋愛や戦闘などの主題を扱うインドの美文芸作品(カーヴィヤ)の知識や、アシュヴァゴーシャにより仏教との対決を演出するために盛り込まれた法典やサーンキャ思想の知識が必要となる。訳者にインド文学、インド思想、インド仏教研究の碩学四人を揃え、『ブッダチャリタ』を訳するのに最も望ましい条件を満たすことによって、正確無比な文献理解に基づく卓越した翻訳を実現したのが本書である。
講談社、梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳『完訳 ブッダチャリタ』P499-501
「アシュヴァゴーシャは、ゴータマ・ブッダの全生涯を洗練された美文によってうたいあげ、各場面の生き生きとした描写に成功している」
これはまさにその通りで、読んでみればそのドラマチックかつ華麗な言葉の流れにきっと驚くと思います。
特に上の引用にもありますがブッダを誘惑する女性たちの描写はあまりに生々しく魅惑的で、これが本当に仏教のお話なのかというくらいの語りになっています。せっかくですのでその一部を少しだけ紹介します。
二七 女たちに固まれて王子は森を歩いた。あたかも牡象が牝象の群を連れてヒマーラヤの森を歩くように。
講談社、梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳『完訳 ブッダチャリタ』P43
二八 その麗しい森の中、女たちに侍られて王子は輝いた。あたかも、ヴィブラージャの園で天女アプサラスたちに固まれたヴイヴァスヴァットのように。
二九 若い女たちは、酔いを口実にして硬く丸く豊かで、張り合った美しい両の乳房で、王子に触れた。
三〇 また、ある女はわざとよろけて見せて、なで肩からゆったりと垂れる柔らかな蔓草に似た腕で、王子に力まかせにからみついた。
三一 ある女は唇赤く、酒のにおいのするロで、彼の耳に「私の秘密を聞いて」とささやいた。
三二 ある女は身体に塗った香油がまだ乾いていないまま、王子の手に触れたいと思い、「ここに並んで私を愛して」と、命令するような口調で言った。
三三 他の女は酔いを口実に、しばしば紺色の衣をすべらせて腰紐をちらつかせた。あたかも稲妻を光らせる夜のように。
いかがでしょうか。この後もしばらくはこのような雰囲気、いやさらに露骨にブッダを誘惑するシーンが続きます。
以前当ブログではインド思想を学ぶためにインドにおける性愛の法典『カーマ・スートラ』を紹介しました。
インドのバラモン・ヒンドゥー教世界ではカーマ(性愛)、アルタ(実利、経済)、ダルマ(宗教的な法、真理)という人生において追い求め、享受すべき重要な3つの事柄が重んじられていました。そのカーマ(性愛)についての法典があの有名な『カーマ・スートラ』です。宗教的世界観の重要な位置づけとして性愛の法典があるという時点でインドの個性が現れているように私には思えます。
上の引用箇所でブッダは性的な誘惑を受けるものの、全く動じません。そして最後には嫌悪すら催すようになります。
これは仏教の思想やブッダの生涯を知っている私達からすると何の疑問も持ちませんが、当時のインド社会においては単に性的な問題だけではなくインドにおける宗教観に真っ向から反対するものでもありました。ブッダのこの態度は当時の人々の当たり前とは完全に異なる方向を向いていたのでした。
アシュヴァゴーサは紀元2世紀頃のインド人です。まさにインドの雰囲気を知る人です。だからこそこの誘惑の場面をここまで生々しく書き上げることができたのではないでしょうか。まさにこの誘惑の箇所を読んでいるとたしかに『カーマ・スートラ』の雰囲気が明らかに出ていることが感じられます。
そしてそもそもですが、これだけの誘惑に対して全く動じることのないブッダ自身の内面にも心を向けずにはいられません。正直、よっぽどの悩みや苦悩がなければここまで誘惑を嫌悪せずにはいられないだろうということを感じてしまいました。
元々ブッダは王子で、しかも容姿端麗で頭脳明晰、武芸にも秀でていました。つまり、誰もが憧れるカリスマです。何の苦労もなくモテにモテます。しかも王の指令で女性たちがどんどん誘惑にやってきます。そこに愛はありません。策略のみです。そうなると、ブッダからすると、女性は愛を求めて苦労して仲良くなるものではなく、向こうから勝手にやってくるものになってしまいます。そうなってくるとブッダからすれば女性はそもそも「手の届かないもの、追いかけたいもの」ではなくなってしまったということになるのではないでしょうか。
ブッダはお金も地位も快適な住まいも服も、女性すらすでに当たり前のように享受していました。
だからこそそもそもの初めからそれらに欲望がかき立てられることが少なかった。
これは「持たざる者」にはなかなかわからない精神状況だと思います。ブッダは「欲望をはねつけたものすごい偉人」というイメージを持ってしまいがちですが、私達とは明らかにその出発点が違うということも頭の片隅に置いておく必要があるかもしれません。まあ、そうであるからこそ世界の人々を救う真理を見出せたということで、私達にとってはありがたいことに全く変わりはないでしょう。やはりブッダは特別です。普通の王族であれば自己の快楽を最大化することに喜びを見出して満足するはずです。ん?おぉ、そう考えてみると、王族は下々の人々より得る快楽が大きい分、余計その快楽に縛られるのでは?・・・となるとやはりそれに嫌気がさしたブッダはやはり珍しい人物か・・・あぁ、どんどん思考がぐるぐるしてきました。
何はともあれアシュヴァゴーシャの語りを聴いていると自然にブッダの内面や物語そのものについて様々な思いが浮かんできます。これはやはり彼の素晴らしい筆のなせる業でしょう。
そして最後にもう一点、本書を読んで特に印象に残った箇所があります。以下のブッダの言葉に私はハッとしました。
四〇 惑いの依りどころである王位に、賢い人がどうしてつくことができるでしょうか。王位には恐怖と驕慢と疲労がつきものであり、他人を不当に扱うことによって、正義を滅ぼすことがあります。
四一 王位は楽しいものではありますが、火のついた黄金宮殿のように、毒をもったとびきりのご馳走のように、鰐に満ちた蓮池のように、災いのもとであります。(中略)四九 心の安らぎを楽しむなら、王権はゆらぎます。王権に意を用いると、心の安らぎは崩壊します。心の安らぎと罰の厳しさはいっしょになりません。冷たい水と熱い火が一つにならないように。
講談社、梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳『完訳 ブッダチャリタ』P102-103
これは上の解説でも出てきた「出家した王子を連れ戻すようにやってきた大臣・宮廷祭官の二人とゴータマとの緊張感に満ちた議論の応酬(第九章)」の中のブッダの言葉です。
ブッダはなぜ王位を捨てたのか。ブッダは王位のことをどう思っていたのかがここで端的に示されています。
ブッダの出家の根本的な動機は宗教的な悟りを得るためです。ですが、それはあくまでも究極、根本的な動機であって、ブッダの生活には実際レベルの様々な動機もあるわけです。四門出遊で病人や死人を見たこと、瞑想的な性格だったこと、美しい女性たちの醜い寝姿を見たことなどなど、様々な要因が重なってついに出家へと繋がったわけです。
ですのでこの王位への嫌悪感というのも大きな理由の一つとして見ていく必要があります。
上で紹介した『カーマ・スートラ』もそうでしたが、私は『カウティリヤ実理論』というインドの古典も当ブログで紹介しました。
詳しいことはリンク先の記事を参照して頂きたいのですが、この『カウティリヤ実理論』では王が為すべき権謀術数の数々が説かれています。しかもこれがあのマキャヴェリの『君主論』にも比される相当えげつない帝王学が説かれているのです。
この本を読んでいると王族で生まれることが全く羨ましくありません。どんなに贅沢ができたとしても私は謹んでその権利をお返ししたいと思いました。ブッダももしかしたらそういう気持ちだったのかもしれないと『カウティリヤ実理論』を読んだ時に私は思ったのでありました。
そしてそれから月日が経ち読むことになった『ブッダチャリタ』でまさしくその通りのことが書かれていたではありませんか!これには私も驚きました!
やはりブッダの生涯や思想も当時の時代背景やブッダが置かれた個別の状況あってこそなのだなということを改めて感じることになりました。
現在語られるブッダの生涯の大元となったアシュヴァゴーシャの『ブッダチャリタ』。物語としても非常に面白い作品でした。漢訳の『仏所行讃』は私達日本仏教においても大きな影響を持っていたことでしょう。浄土真宗の開祖親鸞もこの作品を読んでブッダに思いを馳せていたのでしょうか。ロマンがありますね。
ぜひぜひおすすめしたい一冊です。以上、「『完訳 ブッダチャリタ』~アシュヴァゴーシャ(馬鳴)による『仏所行讃』としても知られる仏伝の大元!ブッダの生涯を叙事詩化!」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事