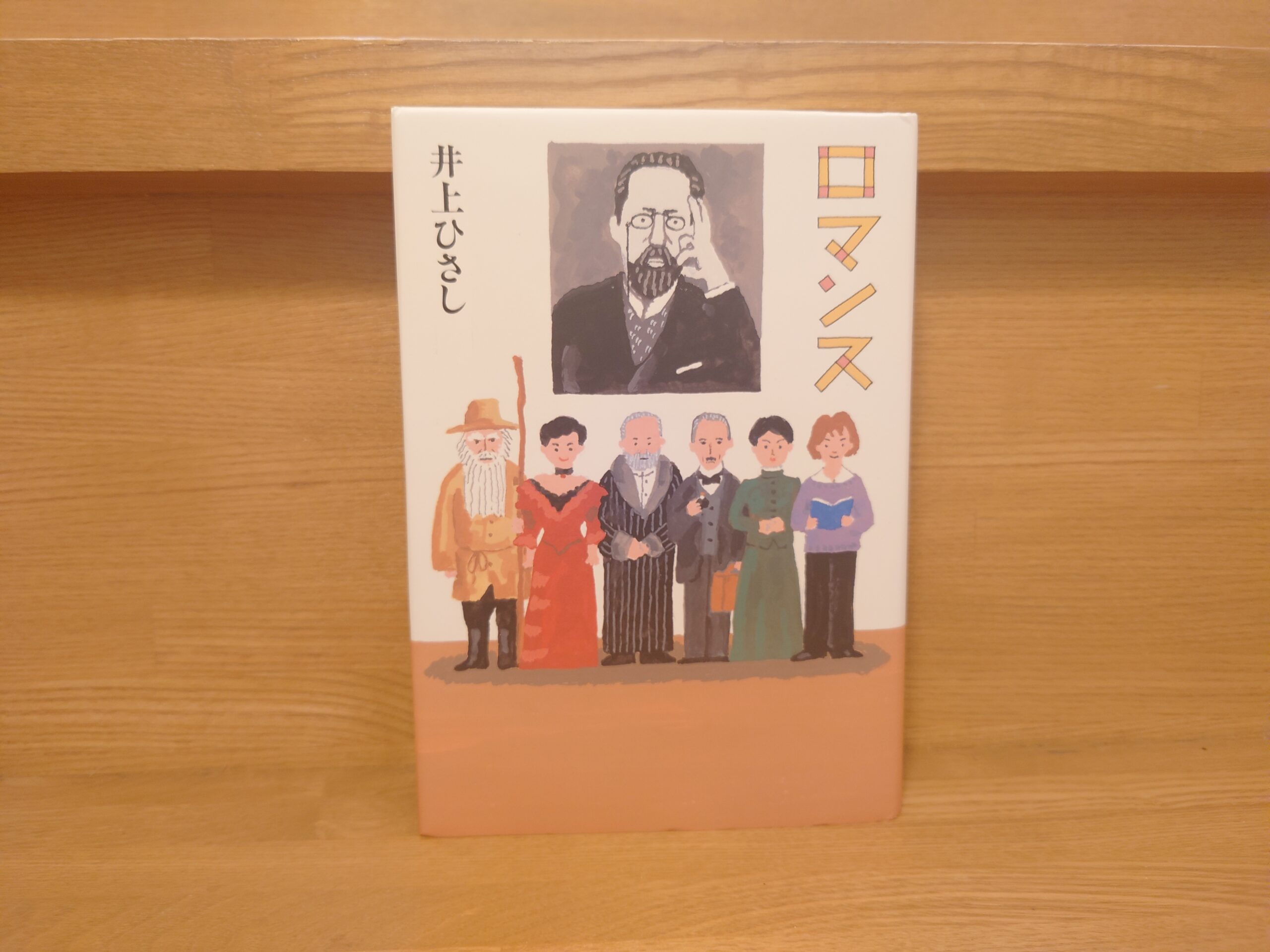井上ひさし『ロマンス』あらすじと感想~チェーホフの生涯を喜劇化した傑作!私はこの作品に嫉妬する…!
今回ご紹介するのは2008年に集英社より発行された井上ひさし著『ロマンス』です。
早速この本について見ていきましょう。
チェーホフの生涯をボードビルとして活写
Amazon商品紹介ページより
ボードビルを、高め、練り上げ、文学にしようとしたチェーホフ。「喜劇だ」「いや、悲劇だ」、いまも世界中で喧しい議論の的となるチェーホフ戯曲の本質を解き明かした傑作、快作、自信作。

この本はロシアの劇作家チェーホフの生涯を喜劇化した作品になります。チェーホフは当ブログでもこれまで何度も紹介してきた私の大好きな作家の一人です。彼は作家であり医者でもあるという異色の経歴の持ち主で、想像を絶するほど波乱万丈の生涯を生きた、まさに大人物であります。
そんなチェーホフの生涯を井上ひさしさんが喜劇化して舞台化したのが本作『ロマンス』になります。
私がこの本を手に取ったのは蜷川幸雄さん演出の舞台『ムサシ』がきっかけでした。
そしてその脚本を手掛けた井上ひさしさんの戯曲『ムサシ』も読みその魅力に驚愕し、私はこの本も手に取ることになったのでした。元々チェーホフが大好きだった私は表紙を見て思わず声を上げてしまい、即決で手に取ったのでありました。
さて、この作品についてですが巻末の扇田昭彦さんの解説があまりに素晴らしかったのでそちらを紹介していきたいと思います。少し長くなりますが井上さんとこの作品のすごさの両方が一発でわかる名解説です。ぜひじっくりと読んでいきたいと思います。
小説家に比べ、劇作家の最盛期はあまり長くないようだ。特に高齢になってから代表作を世に送り出す劇作家は珍しい。日本の現代劇の世界でも、代表作を書いたのは青春時代から、せいぜい中年期までという書き手が多い。
その点、井上ひさしの衰えを知らない劇作活動は注目に値する。井上は今年(ニ〇〇七年)の十一月で七十三歳になるが、この夏、こまつ座とシス・カンパニーの共同制作で上演された井上の新作『ロマンス』(栗山民也演出、宇野誠一郎音楽、石井強司美術)は、チェーホフの生涯を、いかにもこの作家らしい喜劇的視点から描いた見事な音楽劇だった。個性と実力のある俳優六人の演技と歌にも精彩があった。
井上の遅筆ぶりは有名だ。今回も戯曲が書き上がったのは初日の直前で、演出家サイドからは初日延期の案も出たという。こうした執筆遅れに対しては、当然、作者の「甘え」を批判する意見が毎回出るが、『ロマンス』のような秀作を目にしてしまうと、非難の声も小さくなってしまう。
『ロマンス』には、これまでの井上作品になかった新しい趣向がいくつかある。例えば、井上には『表裏源内蛙合戦』『小林一茶』『頭痛肩こり樋口一葉』といった評伝劇が多いが、登場人物が全員、外国人(この作品の場合はロシア人)というのは『ロマンス』が初めてだ。
さらに、主人公のチェーホフを一人の俳優が演じるのではなく、四人の男優(井上芳雄、生瀬勝久、段田安則、木場勝己)がチェーホフの年代に応じて次々に演じ替えていく新しい趣向も面白い。その結果、演劇的多面体としてのチェーホフ像が魅力的に浮かび上がった。女優オリガ役の大竹しのぶと、チェーホフの妹マリヤ役の松たか子も、場面に応じてそれぞれ別の役を演じる。『ロマンス』は、井上が敬愛する作家チェーホフに捧げたオマージュであり、一種の伝記劇でもあるが、同時に、危険な綱渡りにも似た、実にアクロバティックな作品だ。
「チェーホフ劇の本質は喜劇、それも娯楽性に富むボードビルにある」というのが、チェーホフ劇に対する井上の見方だが、ここには明らかに喜劇作家としての井上自身とチェーホフとの意識的で切実な重ね合わせがある。しかも、感心したのは井上がこの劇自体をボードビルのスタイルで書いて見せたことである。つまり、ボードビル風寸劇の連鎖。これは「抱腹絶倒」の喜劇作家として出発した井上ひさしだからこそ出来たことで、しかもその挑戦はかなり成功している。
劇は南ロシアの港町で始まる。少年時代のチェーホフ(井上芳雄)は、未成年者の入場が禁止されていたボードビル、つまり「バカバカしいだけの唄入りのドタバタ芝居」に熱中する。そして、「一生に一本でいい、うんとおもしろいボードビルが書きたい」と願う。
モスクワ大学の医学部を卒業したチェーホフは、滑稽小説の書き手として人気を集めるが、やがて「ブンガクブンガクした小説」で評価を高め、「現代ロシア最高の短篇小説家」と呼ばれるようになる。
だが、諦めかけていたボードビルへの夢を、「舞台で叶える」ように薦めたのは女優オリガ・クニッペル(大竹しのぶ)だった。こうしてチェーホフは「辛味のきいたボードビル」としての傑作『三人姉妹』を書き上げ、オリガと結婚する。
劇中でチェーホフはこう言う。
「ひとはもともと、あらかじめその内側に、苦しみをそなえて生まれ落ちる」。だが、「笑いはちがいます。笑いというものは、ひとの内側に備わってはいない。だから外から……つまりひとが自分の手で自分の外側でつくり出して、たがいに分け合い、持ち合うしかありません。もともとないものをつくるんですから、たいへんです」。
このセリフには、チェーホフの、そして井上ひさしの、「ひとの内側に備わってはいない」笑いを生み出すための「たいへん」な苦闘の体験がたっぷりと込められている。だから劇中で弾ける笑いは幸福感を伴って、深く私たち観客の胸にしみこんでくる。
劇の後半、晩年のチェーホフ(木場勝己)が自作の『三人姉妹』を「上等なボードビル」と呼び、これに対して演出家スタニスラフスキー(井上芳雄)がこの「戯曲の本質そのものは美しい抒情詩」と主張して、激しく対立する場面がある。
激高する二人の間に割って入るのが老作家トルストイ(生瀬勝久)で、「苦しみを和らげるための十二ヵ条」と称して、「指にトゲが刺さったら、『よかった、これが目じゃなくて』とおもうこと」などという珍妙な処世訓を大真面目に延々と語って、客席の爆笑を誘う。シリアスな雰囲気を一気にボードビルに変換してしまう愉快な場面である。
この場面を見ながら思い出したのは、劇団民藝の演出家・俳優だった故・宇野重吉(一九八八年死去)の著書『チェーホフの「桜の園」について』(麦秋社、一九七八年)である。これはチェーホフ最後の戯曲『桜の園』(一九〇四年)を、リアリズム演劇の立場から、ソ連での現地調査も含めて綿密に解釈した著書で、新劇人の「勉強好き」が存分に発揮された本だった。
チェーホフは『桜の園』について「喜劇四幕」と明記している。だが、約三十年前、宇野の本を読んで私が違和感を覚えたのは、宇野が「喜劇」というチェーホフの規定にかなり抵抗していることだった。宇野はまず、ゴーリキーがこの劇を「悲喜劇」と呼んだ例を挙げる。そしてチェーホフは「喜劇」と書き添えることで、「『何故これが喜劇なのか』と、演出者や俳優に疑問をもたせ逆らわせることで戯曲の読み取りを深めさせようとしたのではなかったか」と書く。
これはチェーホフの規定をあえて曲解してみせる不思議な文章だ。『桜の園』=「喜劇」というチェーホフ自身の規定に反し、この戯曲の本質は実は「悲劇」、あるいは「悲喜劇」なのだ、と宇野は示唆しているのだから。
つまり、宇野の立場は、『ロマンス』の中で、『三人姉妹』を「ボードビル」と呼ぶ作者チェーホフに抵抗するスタニスラフスキーの「悲劇」志向の姿勢と基本的に一致している。『桜の園』では名家の没落、男女のすれ違いなどなど、さまざまな出来事が起きるが、それらをあえて冷徹に相対化し、すべては私たちと同じ等身大の「おろか者」たちが引き起こす、おかしな「喜劇」として見るべきだとしたチェーホフの意図(二十世紀の演劇はここから始まった)を、宇野は結局、感受性として理解できなかったのだろう。
劇中では、チャイコフスキー作曲のロマンス集など、多彩な劇中歌が俳優たちにより、ピアノの伴奏(演奏・後藤浩明)で次々に歌われ、舞台を楽しく盛り上げた。最近の井上の音楽劇と同じように、原曲の旋律だけを使い、井上ひさしが新しく歌詞を付けた曲である。しかも、チェーホフとほぼ同時代のチャイコフスキーの曲だけでなく、ガーシュイン作曲のミュージカル『オー、ケイ!』の劇中歌や、リチャード・ロジャース作曲のミュージカル『オン・ユア・トウズ』『シラキュースから来た男たち』の劇中歌を転用するなど、音楽面でも意表をつく趣向がいっぱいだ。チェーホフとガーシュイン、ロジャースの組み合わせなど、井上ひさし以外、だれが考えつくだろうか。ここにもブロードウェイ・ミュージカルに対する井上の並々ならぬ造詣の深さがうかがえる。
芸達者がそろった六人の演技陣はいずれも好演した。中でも女優オリガを魅力的に演じ、さらにチェーホフをペテンにかけるしたたかな老助役をまさにボードビル風に演じた大竹しのぶのうまさに私は惚れ惚れした。持ち前の張りのあるいい声を生かし、大作家トルストイを馬鹿馬鹿しいほどコミカルに演じた生瀬勝久も出色だった。軽妙な鋭さと温かみを合わせ持つ段田安則の演技、渋い味わいと深い人間味を漂わせるベテラン・木場勝己の演技も忘れがたい。兄思いの妹をひたむきに演じた松たか子は歌もよかった。主にミュージカル畑で活躍する気鋭の井上芳雄は初めての井上劇出演だったが、優れた歌唱力を示し、舞台にさわやかな風を吹き込んでいた。
集英社、井上ひさし『ロマンス』P238-243
いかがでしょうか。井上ひさしさんという人がどのような方だったのか、そしてこの作品の特徴や魅力が一発でわかりますよね。こんな素晴らしい解説を書けるようになりたい!そう思ってしまうほど圧倒的な解説。私は例のごとく本編よりも先にこの解説を読んだのですがこの時点でもうこの作品に対する期待感はMAXでした。これは名作でないわけがない!そして井上ひさしさんという人の思いがものすごく反映されている劇なのだということを私は知ったのでした。
また、宇野重吉さんのチェーホフ理解についてのエピソードも非常に興味深かったです。これはまさにソ連的な発想が当時いかに大きな影響を持っていたかということの証左になるのではないでしょうか。ソ連的な思考法というのはこれまで当ブログでも見てきました。
特に上の「レーニンの革命家への道ーチェルヌィシェフスキー『何をなすべきか』に憧れるレーニン 「レーニンに学ぶ」⑷」の記事で見ていきましたがソ連の理論的根拠を作り出したレーニンは強靭な理性とストイックさを前面に押し出した人物でした。
そしてマルクスもそうなのですが、彼らはとにかく人間の制御不能な感情、情念を無視して理論、理屈で進んでいこうという節があります。
理論や理屈を異様なまでに真面目にストイックに押し進めていくソ連的な思考法。そういう流れでチェーホフの戯曲を読めばたしかに宇野重吉さんのような理解になっても不思議ではありません。そもそもチェーホフが存命中でもスタニスラフスキーによって悲劇的に解釈されてしまうのですからソ連的時代風潮になればその流れはより強くなったのではないでしょうか。私は戦前戦後、冷戦時代を生きたわけではないのでこの辺りのことはまだ勉強不足ですがそんな時代背景もこの解説から想像してしまったのでした。
さて、そんな真面目過ぎる悲劇的な考え方を超えて「喜劇を、笑いを!」と奮闘していたチェーホフと井上ひさしさんの思いをストレートに感じられるのがこの作品です。
タイトルに書きましたように、私はこの作品を読みながら「なんて見事な作品だろう・・・!こんな作品を生み出してしまうなんて!」と嫉妬してしまいました。
私はこれまで「親鸞とドストエフスキー」をテーマに世界の文学や歴史、文化を学んできました。もちろんチェーホフもその一人です。
ですがそうした名作たちを読んでも「嫉妬」を感じたことがありませんでした。
歴史の荒波を生き残った名作中の名作に嫉妬して何になるでしょう。私はそれら名作たちにひれ伏し、そこからできる限りのことを学ぼうと懸命になるばかりでした。「世界の偉人に勝負を挑むなんて」でおしまいです。
しかし、井上ひさしさんのこの作品においては違ったのです。私はこの本を読みながら自身に嫉妬の感情が巻き起こっていることをはっきりと感じました。この作品はあまりに素晴らしすぎるのです。私もチェーホフが好きです。ですが井上さんはもっともっとチェーホフを深く理解し、愛している。そして彼の人生、思想をこんなに楽しく、深く表現しているのです。この劇で展開されるひとつひとつのエピソードや舞台展開の美しさ、どれをとっても「やられた!もうだめだ!すごすぎる!」とため息が出てしまうほどでした。どうしてこんなに楽しくも美しい劇を思いつけるのか!
私は今まで読書している最中にこんなにメラメラと嫉妬の炎が燃えるなんてことは経験したことがありませんでした。
ですが、今やその炎をはっきりと認識しています。
きっとそれは今、私が作品を書こうとしている真っ最中だからかもしれません。私も勝負に出ようとしているからこそなのだと思います。
「日本を代表する劇作家井上ひさしさんに嫉妬するなんてなんと不遜な!身の程を知れぇ~い!」
まさにその通りです。
でも、どうせ嫉妬するなら超一流の人に嫉妬していたい。
そんなことを思うわけです。
いやあ素晴らしい作品でした。これを映像ですら観ることができないというのは本当にショックです。演劇という表現媒体の「一回性」というものを強く感じさせられました。その場でないと味わえないものがあるのだと・・・
この本では舞台の写真がシーンごとに掲載されているのでそれはとてもありがたいことでありました。この写真のおかげでまるで舞台を観ているかのごとく読み進めることができます。・・・う~ん、だからこそもっと映像で観たくもなってくる!なんとか映像化の道はないのでしょうか?記録映像は残っていないのでしょうか?狂おしい!
私にとってこの作品は忘れられないものになりました。何度も何度も大切に読み続けていきたいと思います。
本当に素晴らしい作品です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「井上ひさし『ロマンス』あらすじと感想~チェーホフの生涯を喜劇化した傑作!私はこの作品に嫉妬する…!」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事