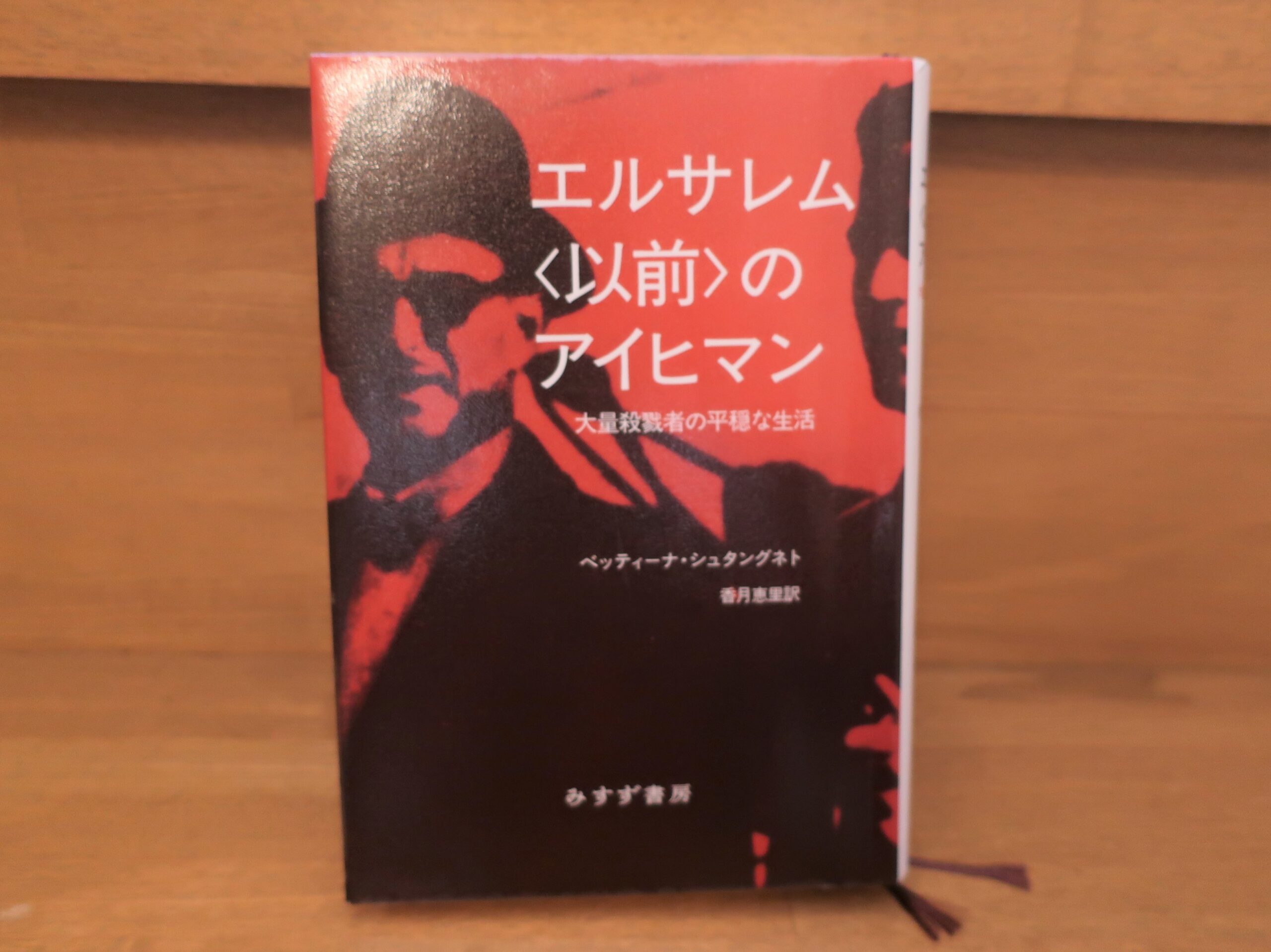「悪の陳腐さ(凡庸さ)」論が覆る!?『エルサレム〈以前〉のアイヒマン 大量殺戮者の平穏な生活』概要と感想
今回ご紹介するのは2021年にみすず書房より発行されたベッティーナ・シュタングネト著、香月恵理訳の『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』です。
早速この本について見ていきましょう。
強制収容所へのユダヤ人移送責任者として絶滅計画の主翼を担ったアドルフ・アイヒマン。このナチ親衛隊中佐については議論が尽くされた感もあるが、じつは肝心な史料の大部分が放置されていた。アイヒマン自身の文章と音声録音である。
戦後アイヒマンが逃亡したアルゼンチンには旧ナチ共同体が築かれていた。アイヒマンはそこで、元武装SS隊員W・サッセン主催の座談会に参加する。サッセンはそれを録音し、テープ巻数にして70以上になる音声のトランスクリプトを作成していた。
アルゼンチンのアイヒマンは大量の独自を記し、エルサレムの囚人となった後も8000枚にわたって自己正当化を書き連ねた。
こうした史料が網羅的に研究されてこなかったのは驚くべきことであるが、それは各所に散在し、分量は膨大で内容は耐え難い、さらに、アルゼンチンでのあけすけな記録を本人が偽と証言したため、史料としての価値を確立する仕事が後の研究者に重くのしかかった。本書は一人の哲学者が成し遂げた気の遠くなるような偉業であり、先駆者ハンナ・アーレントとの対話である。
「エルサレムでのアイヒマンの自己演出が、この犯罪者と、そして彼の殺人者としての成功といかに関係しているかを知りたと願うなら、エルサレム以前のアイヒマンにさかのぼり、また、後の時代に作られたアイヒマン像に基づく解釈の裏に踏み込むことがどうしても必要である」(序章より)
みすず書房、ベッティーナ・シュタングネト、香月恵理訳『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』 裏表紙
まず申し上げましょう。
この本は衝撃的です。
前回の記事「悪の陳腐さとは~アーレント『エルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』」でも見ていきましたが、アーレントはエルサレムで行われたアイヒマン裁判を通して、「悪の陳腐さ」という論を提唱します。
「最終解決」の実行責任者であるアイヒマンは、ユダヤ人に対して強い憎しみを抱いていたはず。凶悪で残忍な人間に違いない―。アイヒマン裁判に注目していた人々は、そのように想像(あるいは期待)していました。しかしアーレントは、実際の彼はまったくそうではなかったと記しています。
そうした姿勢は「悪の陳腐さについての報告」という本書のサブタイトルにも表現されています。陳腐と訳された英語の「banal」は、「どこかで見たような」「ありふれた」「凡庸な」という意味の形容詞。どこにもいそうなごく普通の人間だった、ということです。
若い頃から「あまり将来の見込みのありそうもない」凡人で、自分で道を拓くというよりも「何かの組織に入ることを好む」タイプ。組織内での「自分の昇進にはおそろしく熱心だった」とアーレントは綴っています。
NHK出版、仲正昌樹『悪と全体主義 ハンナ・アーレントから考える』P 165-166
「アイヒマンは悪の化身のような人物ではなく、どこにでもいそうな普通の人間だった。官僚システムの中の単なる歯車の一つに過ぎず、命令に盲目的に従うだけの陳腐な人間に過ぎなかった。そんな人間が大量虐殺を犯していたのだ。」というのがアーレントの論です。
このアーレントの論は世界中で大激論を巻き起こし、彼女の名を一躍知らしめることになりました。そして「悪の陳腐さ」という言葉も世界に定着することになりました。
しかしです。この『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』ではそんなアーレントの理論が覆されかねない衝撃的な事実が語られます。
というのも、この本では近年研究が進んできた資料によってモサドに逮捕される前のナチス時代、そしてドイツ、アルゼンチンでの逃亡期間のアイヒマンの言動が語られます。つまり、文字通り「エルサレムでのアイヒマン裁判」以前のアイヒマンの姿が語られることになります。
そしてそこで明らかにされるアイヒマンは「悪の陳腐さ」とは真逆の姿でした。アーレントはエルサレムで周到に計画されたアイヒマンの罠にかかってしまったことがこの本で語られます。アイヒマンは単なる権力の歯車などではなかったのです。
また、この本では 「自分は決してユダヤ人を憎む者ではなかったし、人間を殺すことを一度も望みはしなかった」 などの証言が大嘘だったことが暴露されます。
アーレントは逮捕以前のアイヒマンを知りませんでした。そして世界中のほとんどの人も彼の実態を知ることなく裁判が続けられたのです。
これによってアーレントの「悪の陳腐さ」という理論がすべて崩壊するわけではありませんが、それをアイヒマンに適用するのはかなり厳しいというのがこの本の述べんとすることです。これはかなり衝撃です。
この本は注も含めれば600ページ以上の大作です。エルサレムでの偽装時代前のアイヒマンは一体どんな人物だったのか。そして彼は周囲からどんな人物として見られていたのか。それをかなり詳しく見ていきます。
上の本紹介にもありますがなぜそんな事実がこれまで見過ごされてしまっていたのかとまず驚きました。その経緯もこの本では詳しく語られます。これも非常に興味深かったです。ホロコーストという未曽有の事件の難しさ、戦後の国際政治の微妙な問題もここで知ることができます。この本自体は2011年に出版されていますので、すでにこの事実が出てきてから10年も経つことになります。「悪の陳腐さ」という概念を揺るがしかねないこのアイヒマンの事実はもっと大々的に報じられてもいいのではないかとも感じたのですが、その辺りの事情は私にもわかりません。
この本で紹介したい箇所が山ほどあるのですが、今回はその中でも特に印象に残った箇所をひとつだけ紹介します。以下はアイヒマンがアルゼンチンでイスラエルの諜報組織モサドに捕らえられた直後の話です。
思いがけず不倶戴天の敵に捕らわれていることを知ると、アイヒマンは、世間に出回っている自分のイメージのうちのどれが己の弁護に最も役立つかをすぐに理解した。用心深い官僚―ただしアルゼンチンで加わった、不利に働くような部分を除いたイメージである。このポーズに二つの要素を加えることで処刑台から守られることを望んだ。自分は無実だということと、ユダヤ人殺害について他人が知らないことを知っていたことである。その上、独自の洞察を付け加える余裕まで持っていた。「私は知っていて、それでもどうすることもできなかったのだ」(「わが逃走」三九頁)。
「ユダヤ人問題」の高名な専門家、絶滅プロジェクトに関する、省庁間の調整担当者、暖炉の傍で上司とコニャックを傾けつつ、大量殺戮実行の進捗をともに祝った人間が、自分は何の権限も持たない、無力な議事録作成人にすぎず、ヴァンゼー会議でも「鉛筆を削りながら、隅の小卓に」座っていただけだと主張した。アルゼンチンでは、どうして自分の名前がすでに戦前から一つの象徴になっていたかを詳しく、誇らしげに解説し、自分に関する新聞記事コレクションの中身をそらんじていた男が、今では「一九四六年まで、私の重要性はほとんどゼロに等しいものでした」と言い張る。目前に迫った裁判は、「全世界から一五年間告発され、誹謗され、迫害されて」きたことで生じた誤解であると。「私もまた、一人の犠牲者なのです」と、彼は法廷での最後の供述で述べる。
こうした仮面舞踏会のために、アイヒマンは、これまでの彼なら発狂したような自己規定さえ厭わなくなる。自分は「了見の狭い」、「役人根性の」「こうるさい」「自分の職分を超えない」人間であると。この最後の嘘を、彼は少し楽しんだかもしれない。(中略)アイヒマンはいつも自分の策略の巧みさを自慢にしていた。そしてこの囚人が策略を使う際、特に生き生きとした様子を見せるのを、尋問官は注意深く観察していた。
彼が自分に貼ったこのようなレッテルは、国民社会主義の敵を表すイメージであり、「官僚」というのは、SS隊員の自己定義と正反対だった。官僚主義というのは、特に官僚主義の価値を信じる者に対しては、武器のように使用することができた。アイヒマンは権力を持っていた頃すでに、堕落した官僚主義的嫌がらせで他の機関や犠牲者を出し抜く術を理解し、権力に具わったこの微妙な道具の使い方を心得ていた。しかしイスラエルの独房では、官僚であるというのはSS隊員であるというよりずっと無害な響きを持っていた。狂信的国民社会主義には無縁の用心深い官僚、学問好きで啓蒙と国際主義を好み、自然を愛する普通の男。一五年前にようやく、煩わしい命令や犯罪的政府と手を切ることができ、本来の自分へと戻ることができた男―これこそ、イスラエルの被告が自分の人生の最後に選んだアイヒマン像だった。役になりきり、完璧に演じる能力のお陰で、アイヒマンはこうしたポーズを取り続け、それに磨きをかけた。嬉々として尋問に応じる囚人、勤勉な歴史家、国際法を重んじる平和主義者に加え、カントとスピノザの助けを借りて、究極の道徳および―今回は「血の声」は抜きにした―存在の問題を極める哲学者までがアイヒマン像に加わった。
みすず書房、ベッティーナ・シュタングネト、香月恵理訳『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』 P500-502
アイヒマンが罪を逃れるためにいかに策略を練っていたかがこの箇所だけでも伝わってきますよね。
ハンナ・アーレントはまさしくこうしたアイヒマンの仮面に騙されてしまったのです。アーレントが提唱した「悪の陳腐さ」は下級官吏などには適用できる理論かもしれませんが、このアイヒマンにおいてはどうなのでしょうか。むしろアイヒマンは「誰しもが意図しなくとも悪を犯しうる。私は歯車に過ぎない。仕方なかったのだ。やりたくてやった犯罪ではない」というイメージを得ることに成功しました。結果的に彼は死刑になりましたが、彼の犯罪を覆い隠すものとして「悪の陳腐さ」という理論が利用されてしまったのです。
私は前々回の記事で、悪の陳腐さは免罪符になるのだろうかということをお話しました。
悪の陳腐さを隠れ蓑にして自分の罪をなかったことにしようとする。あるいは自分は赦されなければならないと自分で判断する。
そうすることで加害者が平然と元の日常生活に戻ろうとする現実があることをこの記事ではお話ししました。
まさしくアイヒマンも、そうした「悪の陳腐さ」を隠れ蓑に自らの所業を覆い隠そうとしたと言えるのではないかとこの本では強く感じました。
アーレントはエルサレムの裁判時のアイヒマンしか知ることができませんでした。ですので数少ない情報の中でしかその理論を構築することができませんでした。
著者はこのことについて非常に興味深い指摘をしています。
彼を厳密に観察することなく、彼の像を手に入れたいという我々の欲望こそが、SS指導者アイヒマンの権力を支えているのだ。この男は、自分の望むものを見たいという人間の願望を巧みに利用した。エルサレムのアイヒマンは、彼を理解したいと願う者に、彼の世界観へ通じる橋があると信じ込ませた。だからこそ、我々は厳しく、そして批判的に「アルゼンチン文書」に見られる倒錯した思想の沼を見つめなくてはならない。さもないと、邪神と戯れるアイヒマンの罠にかかってしまう。
みすず書房、ベッティーナ・シュタングネト、香月恵理訳『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』 P 503-504
アーレントは当時からハイデガーやヤスパースに師事していた著名な哲学者でした。彼女は満を持してエルサレムに飛び、アイヒマン裁判を調査しました。
ハンナ・アーレントは、理解するために自分が学んだ方法を取った。そこで書き、話している男に関わることをくり返し読んだ。理解されたいと願う者だけがものを書き、話すのだと仮定して、そうしたのだ。ほとんど他の誰もしなかったほど徹底的にアーレントは尋問と裁判の調書を読んだ。しかし、まさにそのことによってアーレントは罠にはまってしまった。エルサレムのアイヒマンは仮面以上のものではなかったからだ。それを彼女は認識していなかった。
みすず書房、ベッティーナ・シュタングネト、香月恵理訳『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』 P 13
アーレントは哲学者として、『人間が何かを話したり書き残したりするのは「誰かに理解されたいからだ」』と考えていました。だからこそアイヒマンの裁判調書をひたすらに読み込み、そこからアーレントは自分の理論、すなわち「悪の陳腐さ」という概念を生み出しました。
しかし、著者が述べるように、それこそアイヒマンの罠でした。アイヒマンはアーレントのような、自分を理解しようとする人間の欲望を利用したのです。アーレントは哲学者として極悪人アイヒマンという人物を通して人間の理論を構築し、ホロコーストという理解不能な現象を解明したいという欲求がありました。それ自体は責められることではありませんが、それこそが落とし穴になってしまったのでした。
理解不能な複雑巨大な出来事を理論で以てすっきりと解決する。思想家、哲学者によってこれほど魅力的なことはありません。しかしそうした試みははたして本当に事態を解決することにつながるのか、理解することにつながるのかというと危ういものがあります。
これはアーレントと並んで全体主義に対して強い批判を加えたソ連のワシーリー・グロスマンという作家も提唱していたことです。
全体主義の研究者ティモシー・スナイダーはアーレントとグロスマンについて著書『ブラッドランド ヒトラーとスターリンの大虐殺』で次のように述べています。
アーレントとグロスマンからは、ふたつの明快な考えが導き出される。
そのひとつは、ナチス・ドイツとソ連を正当に比較するには、犯罪について説明するだけではなく、関係したすべての人々ー被害者、加害者、傍観者、指導者ーの人間性についても検証しなければならない、ということだ。
もうひとつは、死ではなく生からはじめるべきだということだ。死は解決ではなく、ひとつのテーマにすぎない。死は不安をもたらすべきものであって、満足を与えるものであってはならない。何より、美辞麗句で物語をすっきりした結末へと導く役目を担わせてはならない。生が死に意味を与えるのであって、死が生に意味を与えるのではない。だから重要な問題は、大量殺人の事実にどのような政治的、知的、文学的、心理的に決着をつけるかということではない。決着はまやかしのハーモニーだ。瀕死の白鳥が歌う美しい歌のように聞こえて、じつは船人をおびき寄せて水底に引きずり込む海の精セイレンの歌なのである。
※適宜改行しました筑摩書房、ティモシー・スナイダー著、布施由紀子訳『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』下巻P245
「美辞麗句で物語をすっきりした結末へと導く役目を担わせてはならない。」
「決着はまやかしのハーモニーだ」
ある出来事を抽象化し、理論化することでその出来事はたしかにわかりやすくなります。
しかし、はたしてそれで終わっていいのかと著者は述べます。巨大な理論の中に一人一人の苦悩の人生が埋没してもいいのかと著者は述べるのです。こうした思いをグロスマンも小説の中で表現しています。
それは彼の代表作『人生と運命』、『万物は流転する』を読んだ時にも強く感じました。
理論ですっきり解決という誘惑に私たちはなかなか抗いがたいのは事実です。
ですが、それで終わってしまっては大切なものが見失われてしまうかもしれません。
『エルサレム〈以前〉のアイヒマン』はまさしく、ティモシー・スナイダーが言うように「関係したすべての人々ー被害者、加害者、傍観者、指導者ーの人間性についても検証」 していく一冊です。
アーレントの「悪の陳腐さ」という言葉はあまりに有名です。
「誰もが悪をしうるのだ」という概念そのものは私も同意しますし、このことを世界中に発信した意義はとてつもなく大きなものだったと思います。
ですが、その理論が生まれるきっかけとなったアイヒマンそのものが「悪の陳腐さ」とは真逆の人間だったというパラドックス・・・
アイヒマンから生まれた理論はアイヒマンには適用できない。
だが人間全体としては「悪の陳腐さ」はいつどこで誰にでも起こりうる理論である。
こうした何とも矛盾した問題を私達は突きつけられることになります。
『「悪の陳腐さ」は免罪符になりうるのか』という問題は今すぐ私に答えを出せるものではありません。ですがスレブレニツァ、ルワンダのジェノサイドを通じてこの問題は私の中でとても大きなものになりました。
今後の課題としてこれからも考えていきたいと思います。
以上、「「悪の陳腐さ(凡庸さ)」論が覆る!?『エルサレム〈以前〉のアイヒマン 大量殺戮者の平穏な生活』」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事