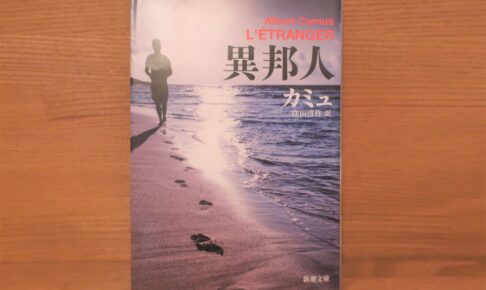目次
パリの伊達男「ダンディー」とは~なぜフランス人男性はモテるのか、時代背景から考える
前回の記事「パリのお針子グリゼットと学生の関係とは~19世紀フランスの若者達の出世コースと恋愛」ではフランス文学者鹿島茂著『職業別 パリ風俗』を参考にパリのグリゼットと学生たちについて見ていきました。
今回の記事ではこの本の中でも特に印象に残ったパリの伊達男「ダンディー」について見ていきたいと思います。
ダンディーが生きるパリの社交界とは
ダンディーそのものを見ていく前に、鹿島氏はパリの社交界についてお話ししています。まずはそこから見ていきましょう。
あたり前のことだが、日本にないものはなかなか具体的なイメージを思い浮かべることができない。その最たるものは社交界だろう。社交界って、いったいなんなんだ?
まず上流階級の男女を成員としていることはだれでも知っている。だが、社交界というのは、政冶や経済といった現実社会を牛耳っている男たちの世界とはまったく別の世界であることも明らかだ。なぜかといえば、その中心にいるのは女性だからである。要するに、社交界とは、権力や実力といった「力」を支配原理とする男の表社会とは価値体系を異にするもう一つの社会であり、その中心は常に女性たちである。そしてこの女性たちに気に入られた男だけが社交界に入れるのだ。
では、この二つの世界は、全然関係なく存在しているのかといえば、そんなことはない。少なくともバルザックの描いた十九世紀のフランスでは、表世界と社交界は、さながら温泉地の男湯と女湯のように、入口は別だが、奥ではあいまいに結びついていて、この二つが相互に補完しあって初めて「上流社会」が存在するような構造になっている。
したがって、上昇意欲に燃えた青年が、社交界の入口から人って、表世界のほうへ抜けることも決して不可能ではないのだ。表世界の入口からまともに入った場合は、なによりも時間と忍耐が必要である。しかし、社交界で貴婦人の寵愛を得られさえすれば、表世界の高位高官を努力なしで手に入れることもできる。これぞ、十九世紀の若者を鼓舞したフレンチ・ドリームにほかならない。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P65-66
19世紀のパリの社交界は私たちが想像する社交界とはだいぶ違った構造のものでした。
そこでは女性が中心で、彼女たちに寵愛を受けるかどうかで社交界での位置が決まるという仕組みでした。婦人に好かれれば階級の階段を一気に駆け上がれる。これは野心ある青年たちにとってのフレンチ・ドリームだったのでした。
ですがここで素朴な疑問が浮かびます。そもそもどうやって社交界に入ることができるのでしょうか。そこに入るための資格などはあるのでしょうか。鹿島は次のように述べます。
では、社交界に入るには、いったいどのような資格があればいいかといえば、これがどうもよくわからないのである。大学卒というような資格が明記されているわけではない。もちろん貴族の称号や財産は必要条件ではあるが、十分条件ではなさそうだ。つまり、社交界に入る資格というのは表社会の場合とちがってかなり漠然としているのである。
そして、この「曖昧さ」が、じつは、《人間喜劇》のフランス版ビルドゥングス・ロマンを先に進ませる駆動力の一つとなっているのである。なぜかといえば、この「曖昧さ」があるおかげで、多種多様な出自をもつ青年を主人公に据えることができるし、また「曖昧さ」それ自体がドラマとなりうるからだ。そうした「曖昧さ」にもがく主人公を通して、広範囲の読者を出世物語に参加させることが可能になるからである。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P66
これは驚きですよね。19世紀のパリ社交界はそこで成功できるかは別にして一応は誰にでも門戸は開かれていたのです。
だからこそ美貌と才気があれば誰でものし上がれるというフレンチ・ドリームがあったのですね。
ダンディーを目指す青年の典型、『ゴリオ爺さん』の主人公ラスティニャック

ここから社交界のダンディーを目指す青年の姿を見ていきます。
社交界の入口を選んだ主人公の代表的な例、それはいうまでもなく『ぺール・ゴリオ』のラスティニャックである。アングレームの子沢山の貧乏貴族の長男であるラスティニャックは、パリに上った初めこそ表世界の入口を目指すが、すぐに、こちらには見切りをつける。
「初めこそ、一心不乱に勉強にうちこもうと思ったが、すぐに、やはり縁故は必要だと思い返し、社会生活に女性たちがどれほど重大な影響を及ぼすかに気づくと、突然のように考えを変え、後ろ盾となってくれる貴婦人を見つけるために社交界にうってでようと決心した」(拙訳)
なぜ、このように突然考えを変えたかといえば、故郷に戻ったとき、家族の窮迫ぶりを目の当たりにして、てっとり早く社交界で出世しなければ埒があかないと悟ったからである。じつは、ラスティ二ャックは、心ひそかに自分には社交界に入るための資格が備わっているのではないかと自負していたのだ。
「情熱と才気に富み、しかもその情熱と才気が、上品な身のこなしと女心をいともたやすくとらえる凛々しい美貌によって裏打ちされている青年なら、社交界の女たちが放っておくわけはない」(同書)
なるほど、社交界に入るための資格の第一は、まず社交界の中心である貴婦人に気に入られることが先決条件であるから、美貌とエレガントな身のこなし、それに情熱と才気、二つに絞れば美貌と才気というわけだ。これは、『フランス人の自画像』の「ダンディー Le Fat」の項目を担当したウージェニー・フォア夫人の言葉とぴたり一致する。
「本物のダンディーはバラエティが少ない。私の知る限り二つだけ、美貌のダンディーと才気のダンディーである」
そうか、美貌と才気の両方があればそれに越したことはないが、どちらか一つでもいいのだ。ラスティニャックは、バルザックが「ある種の力強い美貌」という曖昧な表現を使っているところからもあきらかなように、とびきりの美男子というわけではなく、どちらかといえば男っぽいごついタイプの男なのだが、それを補ってあまりある才気と情熱がある。つまり、ラスティニャックは「才気のダンディー」に分類されるタイプである。ただし、才気だけでまるっきりの醜男というのではだめらしく、やはり、「才気のダンディー」でも、ある程度の美貌は必要なようである。その反対もまた同じで、美貌でも才気がなければ社交界では通用しない。つまり、美貌と才気は社交界における最低の必要条件なのである。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P67-68
『ペール・ゴリオ(ゴリオ爺さん)』はまさしくパリの社交界に打って出ようとする青年ラスティニャックの物語です。
この作品はタイトルこそ『ゴリオ爺さん』という「読みたい欲」をあまりそそらない無骨なものですが、実際はパリの青年たちの成り上がりの過程を描いたものすごく刺激的な作品となっています。
主人公のラスティニャックは表の世界の出世の道を辿ることを早々に諦めます。家が貧しく、そんな余裕はなかったのです。そこで彼が目指したのが貴婦人に気に入られ、社会の階級を一気に駆け上るダンディーへの道だったのです。
では、そんなダンディーの中でも目指すべきトップダンディーとはいかなる存在なのでしょうか。
鹿島氏はバルザックの小説群《人間喜劇》から次のように述べています。
では《人間喜劇》で、だれがこの「本物のダンディー」に相当するのかといえば、それはいうまでもなく《人間喜劇》最多登場記録を誇るアンリ・ド・マルセーである。
「一八一五年の四月の中旬、一人の若者が、みずからの力を知り尽くして、悠然と歩を進める猛獣のように、チュイルリ公園の遊歩道を屈託なげに歩いていた。ブルジョワ女たちは若者を見ようとあけすけに振り返った。いっぽう、貴婦人たちは、さすがに振り返りこそしないものの、彼が引き返してくるのを待ち、あとで思い出して楽しむために、このうっとりするほどの美貌を記憶にしっかりと刻みつけようとした。というのも、その美男たるや、貴婦人たちの中でもっとも美しい女の体にその顔をすげ替えてもすこしもおかしくないほどの美貌だったからである」(バルザック『金色の眼の娘』)
バルザックは「猛獣」という言葉を使っているが、アンリ・ド・マルセーはたしかに、ライオンやトラのような猛獣の持つ自信としなやかさをそなえている。いや、アンリ・ド・マルセーだけではなく、バルザックの時代の本物のダンディーたちは皆この猛獣のような特徴をもっていたのだろう。だからこそ彼らは、現実に「ライオン」とか「トラ」と呼ばれていたのだ。
たとえば、アンリ・ド・マルセーに次いで《人間喜劇》に数多く登場するダンディー、マクシム・ド・トラーユもこの「ライオン」や「トラ」の仲間である。『ペール・ゴリオ』の最初で、ラスティニャックはその事実をいやというほど見せつけられる。
「ラスティニャックはこの若者に激しい憎しみを感じた。まず、きれいにカールされたマクシムのブロンドの髪が自分の髪型がいかにみっともないかを教えてくれた。次に、マクシムのブーツは汚れひとつなくピカピカに磨かれているのに、自分のブーツは、あれほど注意して歩いたにもかかわらず、かすかに泥がついていた。そして、最後に、マクシムの着ているフロックコートは粋な感じに胴を締め、ほとんど美しい女の体のように見せていたのに対し、ウージェーヌはといえば、昼の二時半だというのに黒の燕尾服を着ていた。シャラント県出身の才児は、すでに衣服と着こなしで、このダンディーに負けたことを認めぬわけにはいかなかった」
ラスティニャックは、のちに「才気のダンディー」として社交界の一員となるのだが、まだこの段階では、本物のダンディーにあこがれ、なんとか「ダンディーに見せようとしている男」にすぎない。美貌はさておいても、装いのエレガンスの面で彼我の差がありすぎるからである。いくら才気があっても、装いのエレガンスという第一の必要条件をクリアしていなければ、本物のダンディーにはなれない。
フォア夫人は、本物のダンディーと、ダンディー志願者のちがいをこう説明している。
「ダンディー志願者と本物のダンディーとの関係は、パロディーと芸術の関係に等しい。前者は後者のあとを一歩一歩追いかける。だが、滑稽は崇高と紙一重でも、ついぞ追いつくことはない。本物のダンディーはダンディーの称号を守ろうとするのに対し、ダンディー志願者はそれを獲得し、称号にふさわしいものになろうと努め、自分がそうであることを証明しようと懸命になる。それは絶えざる研究であり、瞬時として休まることのない思考である」
ようするに、ダンディー志願者と本物のダンディーは漸近線にも似て、志願者はいくら研究にいそしんでも永遠に本物には追いつけないというわけだ。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P70-71
ダンディーたるには凄まじいまでの努力と研究が必要なのがここからもわかると思います。しかも真のダンディーたるにはただ見た目がいいだけではまだまだ不合格です。ここからさらに才気も必要となってきます。引き続き鹿島氏の言葉を聞いていきましょう。
しかも、それは、単に装いのエレガンスだけではなく、当意即妙の言葉のやりとり、つまり才気についても言える。着こなしがだめなら、才気で勝負と考えても、現実は甘くない。アングレームから、いきなりダンディーたちの牙城であるパリのオぺラ座の桟敷に飛び込んでしまったリュシアン・ド・リュバンプレは自他を隔てるこの才気のバリアーにぶつかって驚く。
「リュシアンはこの男たちが返事をかえすさいの巧みな言い回し、ツボを押さえた才気に驚き、いわゆるきらめくような機知や警句に腰を抜かした。とりわけ会話の屈託のなさと態度の気安さは彼を呆然とさせた。午前中には、商品の贅沢さに恐れをなしたが、今度はその同じ贅沢さを思想のうちに見いだしたというわけである。いったい、これらの男たちはどんな秘法によって、あのような辛辣な考察や当意即妙の返答を瞬時に見つけるのだろう。自分など、よほど長いあいだ考え抜いたあとでしか思いつかないものばかりだ」(『幻滅』生島遼一訳)
出世の階段を駆け上がるのに、社交界の入口から入ろうと決意した志願者たちをまごつかせる「曖昧さ」というのがこの「秘法」なのである。それは秘法だからマニュアルによって学ぶことはできない。忍術のように、良き先生を選び、常住坐臥その一挙手一投足を観察して極意を盗みとるほかない。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P72
瞬時に当意即妙の言葉のやりとりができること。ツボを押さえた才気。きらめくような機知や警句。そして会話の屈託のなさと態度の気安さ。
フランス人らしいといえばフランス人らしい「言葉に対する意識」。
これを人間関係、社交界において極めていたのが彼らダンディーだったのです。これはちょっとやそっとで会得できるようなものではありません。
だからこそ、ダンディーたらんとする者は先輩ダンディーにくっつき、その一挙手一投足を観察し、極意を盗み取ろうとしていたのでした。
「ダンディー」の中で、フォア夫人は、本物のダンディーであるアルべールと偶然知り合って以来、アルべールを模倣しようと努める裕福な商人の息子アシルをこんなふうに描いている。
「その日からというもの、アシルには、いっときの休息も、一瞬の停止も許されなくなった。アルべールはアシルにとって、モデルであり神であり理想であった。アシルは服の着こなしも、靴の履き方も、帽子の被り方も、アルべールそっくりにし、馬車も同じようなものをあつらえて、同じように自分の競走馬を買ってレースに出場させた」(中略)
いっぽう、こうしたダンディー志願者につきまとわれる本物のダンディーはどう考えているのかというと、案外、この種の「生徒」の効用を認めていたりする。つまり、自分の「本物ぶり」を際立たせるために、隣に「志願者」をはべらしておくのである。バルザックはこの二種類のダンディーの共生関係をこんな風に描いてみせる。
「アンリ・ド・マルセーはこのポール・ド・マネルヴィルという若者を友達として扱っていたが、それは、大胆な投機家が腹心の株式仲買人を使うように、社交界で彼を引き立て役として使おうと考えていたからである。いっぽう、ポール・ド・マネルヴィルにとっては、ド・マルセーの友情が偽物であろうと本物であろうと、それは社会的な問題であり、彼は彼で、この親友を自分なりに利用しているつもりになっていた」(『金色の眼の娘』)
なるほど、これでわかった。《人間喜劇》に登場するダンディーたちが、常に「つるんで」行動しているののは、不良少年と同じように、相互に相手を利用するためだったのである。ただ、ブールヴァールやオぺラ座の回廊を歩き回る第一段階で「つるんで」行動することができたとしても、社交界の貴婦人の愛人におさまるという最終局面では、さすがに一緒に行動することはできない。なぜなら、本物のダンディーとダンディー志願者では、同じ社交界でも相手にできる女性の「格」がちがうからである。だが、結局のところ、ここでも後者は前者の真似をしようと虎視眈眈と狙っている。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P73-74
この箇所はもはや痛快ですらありますよね。ダンディー達はつるんでいつつも互いに利用し合っているだけなのでした。これは19世紀パリに関わらず、どこの時代や世界にもありうる人間の相ですよね。
そして最後にもう一つ、ダンディー達の生態を知る上で重要なことがあります。
何度もいうように、アンリ・ド・マルセーのような最高のダンディーはライオンやトラのような猛獣である。であるがゆえに、それが狙う獲物、すなわち社交界の貴婦人は、最高に「いい獲物」でなければならない。つまり、たんに社交界の名花であるばかりか、若くとびきりの美人で、しかも金づるとして利用できるという獲物の条件をクリアーしている必要がある。
さらに、もうひとつ重要な条件がある。その貴婦人の夫である。夫が嫉妬という感情とは無縁のさばけた人間で、妻が愛人をもつことを黙認するばかりか、その愛人を「友人」として、フリーパスで家庭に迎え入れてくれるようでなければならないが、こうした夫というのは、社交界の一番上か一番下に位置していることが多い。前者は老齢でほとんど夫人の相手を務めることができず、後者は社交界で成り上がろうという野心に燃えているから、妻をその手段に使うことぐらい朝飯前だからである。
鹿島茂著『職業別 パリ風俗』P74-75
なぜ青年たちはダンディーになろうとしたのか。それが自分の出世になるからです。そしてその獲物こそ社交界の婦人です。その中でも「最もいい獲物」をいかにして陥落させるか、そのために青年たちはモテるための技術を競い合っているのです。
そして上の解説にありますように、そうしたことができるのも、愛人が公然と認められているような時代風潮があったからです。一応当時においても不貞は世間的にも非難を受けますし、罰せられます。しかし、要はそれを公にしなければいいだけなのです。こうした愛人を用いていかにのし上がっていくかも当時の男たちの戦いの一つだったようです。
フランスの青年たちにとってはこれは単に恋愛だけの問題ではなく、自分の地位と生存をかけての戦いだったのです。まともに勉強して働いても生活は上向かないし、階級の上昇も望めない。仮にできたとしてもものすごく手間と時間がかかる。そんな余裕などどこにもない。ならば手っ取り早く大逆転を狙うしかない。ダンディーになって社交界に入れば、道は開けるかもしれない。
こう考えてみればどれだけ「モテること」が切実な問題だったかがわかると思います。もともと開放的で言葉巧みに話すことが得意なフランス人がそこからさらにしのぎを削っていかにモテるかを究極にまで高めたのです。これはとてつもないことになりますよね。
私には当時の人たちのことはわかりませんが、打算だらけの世界です。しかも男性側だけでなく女性の側でも社交界でのし上がるための熾烈な戦いが行われています。互いの恋愛テクはもはやすさまじい域に達していたと思われます。
結局、フランス文学を読んでいると、もうとっかえひっかえの様子で用済みになればポイで次の相手に向かいます。家庭環境などはなから破綻しています(文学の世界だからかもしれませんが)。
恋を追い求めてもいつかは冷めてその熱は薄れます。それでもなお一緒に生活していくとしたらやはりそこに愛があるから、あるいは生活上一緒に生きていく必要があるからでしょう。しかし彼らにはそういうものがはたして存在するのかというのはよくよく考えなければならないことです。
そもそもが自分の出世のためにこうした社交界の世界に飛び込んだのです。家庭の安定なんてことは全く考慮されません。こうしたことも「個」を重んじるフランスらしいのかもしれません。日本のような「家」の論理とは全く異なります。
何はともあれ、パリのダンディーがいかに凄まじい存在かはなんとなくは伝わったのではないでしょうか。
フランス人男性がモテるイメージがありますが、ここまで読んできた皆さんもお分かりのように、そりゃモテますよね。こんな歴史的、文化的背景があるのですから。
「不器用ですから」の一言で象徴される日本人男性じゃそりゃ敵いません。
ですが、こうした日本人男性のメンタリティもフランスと同じく歴史的、文化的な背景があって形成されたきたものです。
ですからどっちがよくてどっちが悪いというものではありません。
テレビや映画などを通してヨーロッパの輝かしい面ばかりを見ている私たちは彼らを優れているかのように思ってしまいがちですが、彼らも私達日本人と同じようにいい面もあれば悪い面もあるのです。歴史的な背景があってそうなっているのです。彼らをバラ色の色眼鏡で理想視して「これだから日本人はだめなんだ」と自虐しすぎても苦しくなるだけです。ほどほどにしましょう。どっちもどっちなのです。その上でできることをするしかないのです。
さて、少し話は逸れましたがこうしたダンディーについてはバルザックの『ゴリオ爺さん』や『幻滅』、スタンダールの『赤と黒』が彼らの生態をものすごくわかりやすく描写しています。
また、ゾラの『獲物の分け前』や『ごった煮』、『ボヌール・デ・ダム百貨店』などでもこうした男女のやり取りが詳しく書かれていますのでとてもおすすめです。
鹿島氏の『職業別 パリ風俗』は他にも社交界の貴婦人や弁護士、医者、教師、警察、女優などさまざまな人間がまだまだたくさん出てきます。ものすごく興味深い事実がわんさか出てきますのでぜひ読んで頂きたい本だなと思います。
次の記事ではまさしく社交界に打って出ようとする人間がどのような道筋を通っていくのかを描いた鹿島茂著『馬車が買いたい!』を紹介します。この本もものすごく面白いのでぜひ引き続きお付き合い頂ければと思います。
以上、「なぜフランス人男性はモテるのかーパリの伊達男「ダンディー」の存在から考えてみた」でした。
※2023年1月17日追記
この記事ではパリのダンディーについて見ていきましたが、そもそもダンディーという存在そのものはいつどこから始まったのかということを以下の記事でお話ししています。ぜひこちらもご参照ください。読めばきっとびっくりすると思います。私も度肝を抜かれました。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事