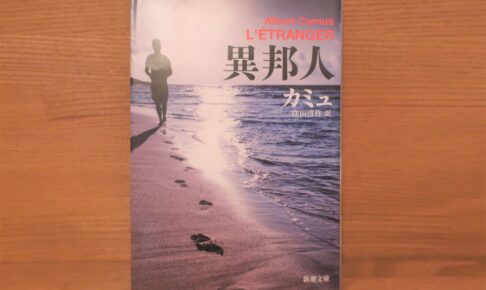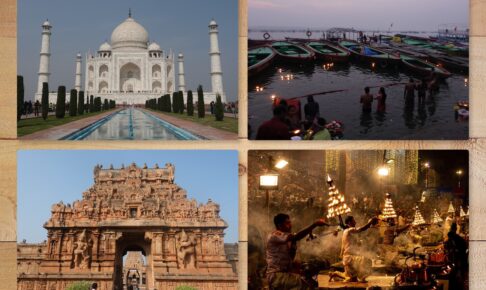はじめに
前回の記事「ジャヴェールこそレミゼのもう一人の主人公である!愛すべき悪役ジャヴェールを考える」ではジャヴェール(ジャベール)こそ『レ・ミゼラブル』のもう一人の主人公であるということをお話ししました。
そして今回の記事ではそのジャヴェールがなぜ自ら死を選んだのかということを、レミゼの原作にたずねていきたいと思います。
※今回の内容はネタバレを含みますので、ご注意ください。
ジャヴェールはなぜ死んだのか。『レ・ミゼラブル』原作からその真相を探る。
映画やミュージカルをご覧になった方にはもうお馴染みのジャヴェール。
物語の後半、バリケードで彼はジャン・ヴァルジャンに命を救われます。
そのショックで、もはや彼はジャン・ヴァルジャンを無意識に「きみ」と呼びかけるようになっていました。
彼の心に何かとてつもない衝撃が与えられていたのです。
そして瀕死のマリユスを担いで地下水道から脱出したジャン・ヴァルジャンを待ち構えていたジャヴェール。
映画ではここでの会話の後、すぐに絶望し、苦悩の歌を歌い、川に身を投じます。
しかし原作ではジャン・ヴァルジャンの願いを聞き入れ、まず馬車を呼び、マリユスを家まで送り届けます。
かつての彼なら問答無用でひっ捕らえ、ジャン・ヴァルジャンを警察に突き出していたことでしょう。
しかし彼はあろうことか犯罪人のジャン・ヴァルジャンを馬車に乗せ、彼の願いを聞き入れマリユスを送り届けたのです。
さらにジャン・ヴァルジャンの家まで彼を送り、ここで待っていると言っておきながら、彼はそっと姿を消します。
ジャン・ヴァルジャン自身も捕まることを受け入れていた中、これには彼も驚きます。
あの厳格なジャヴェールが、罪人を許し、解放してしまったのです。
そしてこの後に、善悪に引き裂かれたジャヴェールはそれこそ死ぬほど葛藤し、自身の存在意義、これまでの人生、これからの人生について苦しむのです。
この苦しみの描写は鬼気迫るものがあります。文庫版にして20ページ、それが延々とつづられます。ここにこそジャヴェールの死の真相があるのです。
その一部をここで抜粋してもきっとそれは不十分で断片的なものにしかなりません。やはり20ページにもわたる彼の葛藤を知らなければその真の理由はわかりません。
『レ・ミゼラブル』の原文を20ページもなんて読めないよとお思いのあなた。
ここは騙されたと思ってまず試しに読んでみてください。
レミゼは文庫でおよそ2500ページ超の大作です。そのうちのたった20ページだけと思ったら、なんかいけるような気がしてきませんか?
しかもこのシーンは第5巻の後半にあるシーンです。普通に読んでたら1巻からは遠い遠い道のりです。
全部読むのはきついなぁと足踏みされていた方にはこのシーンはきっと永遠に出会うことがない場面かもしれません。
そういう意味でもここでジャヴェールの最大の見せ場であるこのシーンを読んでみる価値は十分あると思います。
読んでみれば意外と読みやすいことにきっと驚くと思います。古典だから難しいという先入観もきっと壊れるのではないでしょうか。
では、早速読んでいきましょう。
『レ・ミゼラブル』第五部 第四章 脱線したジャヴェール
ジャヴェールはゆっくりした足どりで、ロマルメ通りを去って行った。
生れて初めて頭を垂れ、これも生れて初めて手をうしろに組んで、歩いて行った。
この日までジャヴェールは、ナポレオンの二つの姿勢のうち、決断をあらわす方、つまり腕を胸で組む姿勢しかしたことがなかった。不安をあらわす、腕をうしろに組む姿勢は、知らなかった。いま一つの変化が起きていた。全身が、にぶく、沈鬱で、苦悩の色がしるされていた。
彼はひっそりした通りばかり歩いて行った。それでも一つの方角をたどっていた。セーヌ河に向って、いちばんの近道をとり、オルム河岸に出て、河岸伝いにグレーヴをすぎると、シャトレー広場の派出所から少し離れた、ノートル・ダム橋の角で立ち止った。セーヌ河はそこで、一方はノートル・ダム橋とポン・トー・シャンジュ橋、他方はメジスリー河岸とフルール河岸にはさまれて、急流が横切る四角な湖みたいになっていた。
セーヌ河のこの辺は、水夫たちに恐れられている。当時、この急流は、今は取りこわされたが、橋の水車の杭でせばめられ、沸き立っていて、これほど危険なものはなかった。二つの橋が近すぎることが、その危険を大きくする。流れは橋の下で恐ろしく早くなる。水がすさまじい大波を立てて流れ、そこに集まって盛り上がり、波は橋桁を太い水の綱で引抜いてしまいそうになる。人がそこへ落ちたら二度と浮び上がらない。どんなに泳ぎが上手でも、溺れてしまう。
ジャヴェールは両腕を欄干につき、顎を両手で支えて、機械的に濃い頬髯を爪先でいじりながら、物思いにふけった。
ある新しいこと、ある革命、ある破局が、彼の心の奥に訪れ、みずから検討すべきことがあったのだ。ジャヴェールは恐ろしく苦しんでいた。数時間前から、ジャヴェールは単純ではなくなってしまった。彼は混乱していた。盲目にされても澄みきっていたその頭脳が、透明さを失い、水晶に曇りがかかった。ジャヴェールは義務が二分されるのを心に感じ、そのことを自分に隠すことができなかった。セーヌ河の水ぎわであんなに思いがけなくジャン・ヴァルジャンに出会ったとき、彼のうちには、逃げた獲物をまた捕まえた狼のようなものと、見失った主人にめぐり会えた犬のようなものとがあった。
行く手に道が二筋見えた、どちらも同じようにまっすぐだが、たしかに二筋の道が見えた。そのことが、生涯に一本の直線しか知らなかった彼を、脅かした。しかも、ひどく心を苦しめることには、二筋の道は相容れないものだった。二本の直線の一方が他方を退けていた。どちらが本当の道なのか?彼の立場は言い表わしようのないものだった。
悪人に命を救われ、その負債をみとめて、返済し、心ならずも前科者と対等になり、奉仕に奉仕をして報いること、「行け」と言われて、こちらからも「自由にしろ」と言ってやること、個人的な動機から、義務を、つまり一般的な責務を犠牲にし、しかもその個人的動機の中に、同じく一般的な、おそらくより高いものを感じること、良心に従うために、社会を裏切ること、このような不条理なことがすべて実現し、彼の上に積み重なってきたのだ。彼はそれにすっかり打ちのめされてしまった。
あることが彼をびっくりさせた。ジャン・ヴァルジャンが彼を許したことであった。またあることが彼を茫然自失させた。ジャヴェールがジャン・ヴァルジャンを許したことであった。
自分はどういう立場にあるのか?彼は自分を捜したが、見つからなかった。
これからどうすればいいのか?ジャン・ヴァルジャンを引渡す、それはいけないことだ。ジャン・ヴァルジャンを自由にしておく、それもいけないことだ。前の場合は、その筋の者が徒刑囚以下になりさがることになり、あとの場合は、徒刑囚が法律以上に高くのぼって、法律をふみにじることになる。どちらにしても、彼ジャヴェールにとって、不名誉なことだった。どう決心してみても、そこには堕落があった。運命には、不可能の上に切り立っていて、その向う側には人生がまさしく深淵となるような断崖が幾つかある。ジャヴェールはそうした絶望の一つに面していた。
彼の苦悩の一つは、考えなければならないことだった。これらすべての矛盾し合う感動の激しさが、彼に考えることを強いた。考えるということは、彼の習慣にはないことであり、とてもつらいことだった。考えるということには、必ずいくらか内的な反逆が含まれるもので、彼は自分の心に反逆をいだくことでいらだった。
考えることは、それがどんなことであろうと、彼の職務というせまい範囲外の問題についてなら、彼にとっては、どんなときでも、無駄なことであり、骨折り損だったろう。しかし、過ぎ去った今日の一日について考えることは、拷問であった。それでも、あんなショックのあとでは、自分の良心をのぞきこんで、自分で自分を納得させる必要があった。
自分が今してきたことが、彼を戦慄させた。ジャヴェールは、警察の全規則に反して、社会と司法の全組織に反して、法典全体に反して、ある釈放を決定してもよいと考えたのであり、そうすることが彼には妥当だったのであり、私事を公事にすりかえたのであった。なんとも言語道断ではないか?自分の犯したこの不都合な行為に面と向うたびに、彼は頭から足先までふるえた。どう決心したらいいのか?残された手段はただ一つ、急いでロマルメ通りに戻って、ジャン・ヴァルジャンを投獄することだった。たしかにそれこそ彼のしなければならないことだった。彼にはそれができかった。
何かが、その道をふさいだ。何かとは?なんだ?法廷と執行命令と警察と権力以外のものが、この世に何かあるのか?ジャヴェールの心はかき乱れた。
神聖な懲役人!法で追及できない徒刑囚!しかもジャヴェールにとっては、それが事実なのだ!
ジャヴェールとジャン・ヴァルジャン、法に仕える人間と法に裁かれる人間、どちらも法の下にいる二人の人間が、二人ながら法を超えるところまで来てしまったとは、恐ろしいことではないか?
なんていうことだ!こんな途方もないことが起っていいのか、誰にも罰せられなくていいのか!ジャン・ヴァルジャンが、社会秩序の全体よりも強力になり、自由の身となっても、ジャヴェールが政府のパンを食べつづけていてもいいのか!
『レ・ミゼラブル』佐藤朔訳 新潮社平成二四年四四刷 P264-268
~ここまでで文庫5ページ分。4分の1です。
彼の夢想は、次第に恐ろしさを増した。
この夢想の間にも、フィーユ・デュ・カルヴェール通りに連れ戻された暴徒について、少しは自責の念にかられてもよさそうなのに、彼はそのことは考えなかった。小さなあやまちは大きなあやまちの中に、消えてしまっていた。それに、あの暴徒は明らかに死んでいた。だから、法律上、死は追及を中止させる。
ジャン・ヴァルジャンこそ、彼の精神にのしかかる重荷だった。
ジャン・ヴァルジャンは彼を面くらわせた。一生の支えであった公理が、この男の前ではすべてくずれ去った。彼ジャヴェールにたいするジャン・ヴァルジャンの寛大さが、彼を圧倒した。他の諸事実を今思い出してみると、かつては嘘か狂気の沙汰と思っていた事実が、今や現実となって戻ってきた。マドレーヌ氏がジャン・ヴァルジャンの陰に再びあらわれ、二人の姿が重なり合って、ただ一つの、尊敬すべき姿になった。ジャヴェールは何か恐ろしいもの、徒刑囚にたいする称讃の念に、魂を貫かれるのを感じた。懲役人にたいする尊敬、そんなことがありえようか?彼はふるえた。その考えからのがれられなかった。もがいても無駄だった。良心の法廷では、あのみじめな男の崇高さをみとめないではいられなかった。それはたまらないことだった。
善行を施す悪人、憐れみ深い、優しい、人助けをする、心の広い、悪に善を報いる、憎しみに許しを報いる、復讐より憐れみを好む、敵を滅ぼすより自分が滅びることを喜ぶ、襲いかかる者を救う、徳の高みにひざまずき、人間より天使に近い徒刑因!ジャヴェールは、こんな怪物が実在することを、みとめないわけにいかなかった。こんなことかいつまでもつづくはずがなかった。
無論、断わっておくが、彼を驚かし、彼を怒らせたともいえるこの怪物に、このいやらしい天使に、このみにくい英雄に、彼が無抵抗に降参したわけではなかった。馬車の中でジャン・ヴァルジャンと向い合っていたとき、法律の虎が彼の内部で、何度も、吠えたてた。何度も、ジャン・ヴァルジャンに襲いかかり、つかんで食ってしまいたい、つまり逮捕したい気持にかられた。実際、それほど簡単なことがあっただろうか?どこでも派出所の前を通りかかったら、「ほら、住居指定令違反の前科者だぞ!」と叫び、憲兵を呼んで、「この男は君たちに任した!」と言って、立ち去り、罪人をそこに残して、あとのことはかまわず、自分は一切関係しない。あの男は永遠に法の囚人となり、法が好きなようにする。これほど正当なことがあるだろうか?ジャヴェールはそうしたことを全部自分に言いきかせてみた。強行しよう、行動に移ろう、あの男を逮捕しようと思ったのだが、そのときも、今と同じことで、できなかった。彼の手は、ジャン・ヴァルジャンの襟首めがけて、痙攣するようにあげられるたびに、大変な重みをかけられたみたいに、さがってしまった。そして心の底に、一つの声、不思議な声が叫ぶのを聞いた。「よし、救い主を引渡せ。それから、ポンテオ・ピラト(訳注 キリストを十字架にかけたユダヤ人)の盥を取寄せて、爪を洗え」
そして、彼の考えは彼自身の上に戻って、偉大になったジャン・ヴァルジャンと並んで、堕落した彼ジャヴェールを見るのだった。一人の徒刑囚が恩人なのだ!
それにしても、なぜあの男に命を助けてもらったのか?バリケードで彼は殺される権利があった。その権利を行使すべきだった。ジャン・ヴァルジャンに反対して、他の暴徒に頼んで、無理に銃殺してもらう、その方がよかったのだ。
彼の最大の苦悩は、確信を失ったことだった。根を引抜かれてしまったように感じた。法典は彼の手中で木切れになって残っているだけだ。今まで知らなかった疑惑と取組まなければならなかった。心のうちに、これまで彼の唯一の尺度であった法律的な確信とは全く別な、一つの感情的な啓示が生れた。以前の実直さにとどまるだけでは、もう満足できなくなってきた。一連の意外な事実が起って、彼を圧倒した。新しい世界が、彼の魂の前に出現した。つまり、受けて返す善行、献身、慈悲、寛大、情けにほだされて威厳をくずすこと、個人を重んじること、決定的に人を裁くことも、罰することもできないこと、法の目にも涙がありうること、神の正義とでもいえる何かが人間の正義とあべこべになっていること。彼は、暗闇の中に未知の道徳の恐ろしい日の出を見て、おびえ、目がくらんだ。鷲の目を持つことを強いられたフクロウ。
彼は考えた、これは真実なのだ、例外ということがあり、権威も動揺することがあり、規則もある事実の前では行きづまることがあり、すべてが法典の枠にはまるわけではなく、予測できないことは服従するより仕方がない、徒刑囚の徳が役人の徳に罠をかけることもあり、怪物みたいなものが神でもありうるし、運命はこのような伏兵を隠しているものだ。そして、彼自身は一つの不意打ちを避けられなかったのだと、絶望しながら考えた。
彼は親切が存在することをみとめざるをえなかった。あの徒刑囚は親切だった。また彼自身も、かつてなかったことだが、親切だった。してみると、自分は性質が変ったのだ。彼は自分を卑怯だと思った。わが身がおぞましかった。
ジャヴェールにとって、理想とは、人間的になることでも、偉大になることでも、気高くなることでもなかった。非の打ちどころがなくなることであった。ところが、今はあやまちを犯してしまったのだ。
どうしてそんなことが起ったのか?どうしてそういうことになったのか?自分にもわからなかった。頭を手でかかえてみても駄目だった。説明がつかなかった。
たしかに彼は、いつでも、ジャン・ヴァルジャンを法の手に返すつもりだった。ジャン・ヴァルジャンは法の虜であり、ジャヴェールは法の奴隷であった。ジャン・ヴァルジャンを捕まえていた間は、彼のうちには、逃がしてやる気など、一瞬もみとめられなかった。いわば無意識に手がひらいて、放してしまったのだった。
あらゆる種類の謎めいた新事実が、眼前に見えてきた。彼はいろいろ自問自答してみたが、自分の答えにおびえた。彼は自分に尋ねた。「俺が迫害するまでに追及したあの徒刑囚は、あの絶望した男は、俺を足下に踏まえ、復讐できる立場になり、怨恨からも保身のためにも復讐するのが当然なのに、俺の命を助け、許すことで、いったい何をしたのだ?彼の義務。いや、義務以上の何かだ。また俺の方でも彼を許すことで、何をしたのだ?俺の義務。いや、義務以上の何かだ。では義務以上の何かが存在するのか?」。ここで彼はおびえた、彼の秤ははずれてしまった。皿の一方は深淵に落ち、一方は天にのぼった。そしてジャヴェールは、上にあがった方にも、下に落ちた方にも恐怖を感じた。彼は、ヴォルテール主義者とか哲学者とか不信心者と呼ばれる人間からははるかに遠く、逆に、本能から、確立されたカトリック教会を敬っていたのだが、それも社会全体の威厳のある断片としてみとめるだけで、秩序こそ彼の教義であり、それで満足していた。成年になり、役人になってからは、言葉のほとんどすべてを警察の中におき、こんな言葉を使うのも皮肉ではなく、真面目な意味で言うのだが、すでに言ったように、人が司祭であるように、彼はスパイであった。彼には上官としてゴスケ氏があり、今日まで、いま一人の上官である神のことは、ほとんど考えたこともなかった。
彼は、この神という新しい長官を、思いがけずも感じて、動揺しているのであった。
この予期しない存在に当惑した。この上官をどう扱ったらいいのか、わからなかった。部下はいつでも腰をかがめているものであり、服従しなかったり、非難したり、反論したりすべきではなく、あまり無法な上官にたいしては辞表を出すより手はない、ということを知らないわけではなかったが。だが、神に辞表を出すには、一体どうしたらいいのか?
『レ・ミゼラブル』佐藤朔訳 新潮社平成二四年四四刷 P268-274
ここでちょうど半分!10ページです。
それはともかく、彼がいつもそこに引戻され、彼のすべてを支配していたことは、彼が恐ろしい違法を犯したということだった。彼は、住居指定令違反の再犯者にたいして目をつぶった。懲役人を釈放した。法に属する男を法から奪い取った。そういうことをしでかしたのだ。もう自分で自分がわからなかった。自分自身に確信が持てなかった。そんなことをした理由が、自分でもわからず、ただめまいを感じるだけだった。これまでは、暗い実直さを生む盲目的な信念によって生きてきた。その信念が逃げ出し、実直さが失われかけていた。信じていたことが、すべて消滅しかけていた。彼の望まない真実が、無慈悲に彼につきまとった。これからは別の人間になるしかなかった。いきなり白内障を手術された良心の奇妙な痛みに、彼は苦しんだ。見たくないものが見えるようになったのだ。自分がうつろで、無益で、過去の生活から切り放され、免職になり、抹消されるのを感じた。権威は彼のうちで死滅した。もはや存在理由がなくなった。恐ろしい立場!揺り動かされるということは。
花崗岩でできていながら、疑惑を持つ!すっかり法の鋳型の中で鋳造された懲罰の像でありながら、その青銅の胸の下に、突然、何か不条理なもの、不従順なもの、心臓に似たものをみとめる!善に善を報いてしまう。今日まで、そんな善は悪だと言いきかせてきたくせに!番犬でありながら、賊の手をなめる!氷である自分が、溶ける!釘抜きであるものが、手となる!ふと指がひらくのを感じる!手を放す、恐ろしいことだ!進路を見失ってたじろぐ弾丸のような人間!
次のことをみとめざるをえないのだ。誤りのないものが、必ずしもあやまちがないのではない、教義にも誤りがありうる、法が語っていることですべてが言いつくされはしない、社会は完璧ではない、権威には動揺が伴う、不動なものがぐらつくこともありうる、裁判官も人間である、法がまちがうこともある、法廷が勘違いすることもある!大空の無限な青ガラスにも、ひびが見える!
ジャヴェールのうちで起っていること、それは直線的な良心のファンプー(訳注 脱線事故のあった現場)であり、魂の脱線であり、不可抗力で一直線に突進して、神に衝突して砕けた、実直さの粉砕であった。たしかに、これは異常なことだ。秩序の火夫、権威の機関士が、軌道を走る盲目の鉄の馬に乗っていたのに、光の一撃を受けて落馬するとは!移動できないもの、直線的なもの、正確なもの、幾何学的なもの、受動的なもの、完璧なものが、屈曲するとは!機関車にもダマスクス(訳注 聖パウロはダマスクスへの途上で改宗した)への道があるとは!
常に人間の内部にあって、真の良心となって、偽の良心に抵抗する神、火花が消えるのを防ぐもの、光線に太陽を思い出せと指令するもの、真の絶対を、それと接する偽の絶対から見わけよ、と魂に命じるもの、滅びることのない人間性、失われることのない人間的感情、この輝かしい現象、人間内部の奇蹟のうちでおそらく最も美しい奇蹟、ジャヴェールはそれを理解しかけていたのか?それを見抜きかけていたのか?それを納得しかけていたのだろうか?明らかにそうではなかった。しかしこの不可解だが、否認しえないものの圧力のもとで、彼は自分の頭がいくらかひらけるのを感じていた。
彼はこの奇蹟によって変化したというより、その犠牲になった。憤激しながら、それに耐えた。これらすべての中に、生きることの無限な困難しか見なかった。これからは永遠に、息が苦しくなりそうに思われた。頭上に未知のものをいただくこと、彼はそういうことに慣れていなかった。
これまで彼が頭上にいただいてきたものは、彼の目には、明白で単純で澄んだ表面だった。そこには知らないもの、不分明なものは何もなかった。限定されない、整理されない、脈絡のない、簡明でない、正確でない、限界のない、制限のない、閉ざされていないものは、何もなかった。すべてが予想されていた。権威とは平坦なもので、その中にはどんな失墜もなく、その前ではどんなめまいもなかった。ジャヴェールは下の方にしか未知なものを見たことがなかった。不規則なもの、思いがけないもの、混沌への乱雑な入口、すべり落ちるかも知れない絶壁、それは下層地帯のもの、謀反人や悪人やみじめな人のものだった。それが今やジャヴェールは仰向きに倒れて、思いがけない出現に、つまり上にある深淵に、いきなり脅かされたのだ。なんということだ!上から下まで防備を解かれてしまった!完全に面くらってしまった!何に頼ったらいいのか?信じていたものがくずれるのだった!
なんということだ!社会の鎧の欠点が、心の広い、みじめな人間によって見つけられるとは!なんということだ!正直な法の僕が、突然、二つの罪、一人の人間を逃がす罪と、彼を逮捕する罪の間で、板ばさみになるとは!官吏が国から与えられる命令も、すべてが確実とはかぎらないのか!義務にも行き止りがあるのか!一体なんということだ!こんなことがすべて現実なのか!刑罰の下にひしがれていたもと強盗が、身を起し、結局、彼の方が正しいなどということが、事実だろうか?そんなことが信じられようか?それでは、法律も、形の変った犯罪の前で、言いわけをつぶやきながら、引き下がらねばならない場合があるというのか!
そうだ、そうなのだ!ジャヴェールはそれを見たのだ!それに触れたのだ!それを否定できないばかりか、自分もそれに加わっていたのだ。これが現実なのだ。現実の事実がこれほど奇形になろうとは、呪わしいことだ。
事実が本分を守るかぎり、事実は法の証明であるにとどまろう。事実とは神がつかわすものだ。それでは、無秩序が天から降ってくるのか?
こうして、―増大する苦悩の中に、仰天させられた視力による幻覚の中に、彼の印象を抑制し矯正してくれるものはすべて消滅し、社会も人類も宇宙も、以後彼の目には、単純で醜悪な輪郭にすぎなくなり、―こうして、刑法、判決、法に基づく力、上級裁判所の判例、司法官、政府、拘留と懲罰、公務の思慮、法の無謬、権威の原則、政治的、個人的保安の基盤となるすべての教義、主権、正義、法典に基づく論理、社会的絶対、公的真理などのすべてが、残骸となり、屑の山となり、混沌となった。そして、秩序の監視人であり、警察に仕える廉潔そのものであり、社会の番犬であるジャヴェール自身も、征服され、打ち倒されてしまい、それらすべての廃墟の上に、一人の男が、頭に緑の帽子、額に光輪をいただいて立つというのが、彼のおちいった混乱であり、彼が魂の中にいだいた恐ろしい幻影であった。
これが耐えられることか。耐えられなかった。
これまでになかったひどい状態。そこから抜け出るには、ニつの方法しかなかった。一つは、断然ジャン・ヴァルジャンのもとに行って、あの徒刑囚を監獄に送り返すこと。いま一つは……
ジャヴェールは欄干を離れ、今度は顔をあげて、しっかりした足どりで、シャトレー広場の片隅の、角灯でそれとわかる派出所に向って行った。
そこに着いて、ガラス戸越しに巡査が一人いるのを見つけて、中に入った。警察の人間は、ドアのあけ方一つで、仲間を見わけるものである。ジャヴェールは名のり、身分証明書を巡査に見せると、蝋燭が燃えている事務机の前に坐った。机の上には一本のペンと鉛のインク壷と紙が、不時の調書や夜間巡察の申送り用においてあった。
『レ・ミゼラブル』佐藤朔訳 新潮社平成二四年四四刷 P274-279
ここで15ページです。あと5ページ!もう少しです!
こうした机は、きまって藁椅子つきで、規格品、つまり、どこの派出所にもあるもので、きまって鋸屑のつまった黄楊の台皿と、赤い固形封蝋のつまったボール箱がそなえつけられ、役所式のうちでの下級品ということになっていた。国家の文学がはじまるのは、この机からである。
ジャヴェールはぺンと一枚の紙を取って、書きだした。それは以下のようなことである。
職務上の意見書
一、総監閣下が一読されたい。
二、予審から帰った留置人は、身体検査中、靴を脱いで、跣で敷石の上に立っている。何人かは監房に戻ってから、咳をする。これでは医務室の出費を増すことになる。
三、尾行は、距離をおいて立てた警官のリレーで行うのがよいが、重大な場合には、少なくとも二人の警官が互いに見失わぬようにして、なんらかの理由で一人が任務を怠ることがあっても、他の一人がそれを監視し、代理ができるようにすべきであろう。
四、マドロネット監獄には代金を払っても、囚人に椅子を持つことを禁じる特別規定があるが、納得できない。
五、マドロネット監獄の酒保には、格子が二本しかなく、酒保係の女は留置人に手を握らせることができる。
六、呼出し人と言われる、他の留置人を面会所に呼出す役の留置人は、名前をはっきり呼ぶ代金として二フラン取るが、これは盗みである。
七、織物工場の囚人は、糸を一本はずすごとに賃金を十スー減らされるが、そのために織布の質が落ちるわけではないから、これは請負人の越権である。
八、フォルス監獄の面会人が、サント・マリ・レジプシエーヌ面会所へ行くのに、子供たちの中庭を通るのは、好ましくない。
九、刑事被告人にたいする司法官の訊問について、毎日、憲兵たちが、警視庁の中庭で噂をしているのが他人に聞かれていることは、たしかである。神聖なるべき憲兵が、予審廷で耳にしたことを、もらすのは、重大な秩序紊乱である。
十、アンリ夫人は正直者で、その酒保はきわめて清潔であるが、一女性が独房の出人口を一手に握るのはよくない。これは大文明国の裁判所付属監獄にふさわしくない。
ジャヴェールはこの数行を、このうえなく冷静で正確な筆跡で、句読点一つ落すことなく、紙の上にしっかりしたぺンの音を走らせながら書いた。最後の行の下に署名した。
一等警部
ジャヴェールシャトレー広場の派出所にて
一八三二年六月七日、午前一時ごろ。ジャヴェールは紙の上の新しいインクを乾かし、手紙のように折って、封をすると、裏に「管理上の覚え書」としたためて、机におき、派出所を出た。ガラスのついた格戸が、うしろでしまった。
彼はまたシャトレー広場を斜めにつっ切って、河岸に出ると、自動的な正確さで、十五分前に離れた地点に戻った。彼はそこで肱をつき、欄干の同じ敷石の上で同じ姿勢をとった。前からそこを動かなかったみたいだった。
真っ暗闇だった。真夜中すぎた墓地のような時間だった。雲の天井が星を隠していた。空は不気味に垂れこめていた。中の島の家々には一条の明りもなく、人ひとり通らず、街路も河岸も見渡すかぎり寂寞としていた。ノートル・ダム寺院と裁判所の塔が夜の輪郭のように見えた。街灯が一つ河べりを赤く染めていた。幾つもの橋の影が霧でぼやけて、重なり合っていた。雨で河の水かさが増していた。
ジャヴェールが肱をついていた場所は、読者も覚えているように、セーヌ河の急流の真上にあたり、足もとで恐ろしい渦が、無限の螺旋のように解けては結ぶところだった。
ジャヴェールは顔をかしげて、のぞきこんだ。真っ暗だった。何も見えなかった。泡立つ音は聞えるが、河は見えなかった。ときどき、目もくらみそうな深みに、薄明りがあらわれて、ぼんやりとうねった。水は、真の暗夜の中でも、どこからともわからない光をおびて、それを蛇に変える力を持っている。光が消えると、何も見えなくなった。無限がそこに口をあけているようだった。足もとにあるのは、水ではなくて、深淵だった。切り立った岸壁が、ほのかに見えたかと思うと、靄にまじって、たちまち消え、無限への断崖といった感じだった。
何も見えないのだが、水の敵意を含んだ冷たさと、ぬれた石の気の抜けた臭いが感じられた。荒々しい息吹きが、この深淵から立ちのぼってきた。水かさの増したことが、見えるというよりも想像される河、波の陰気なささやき、橋のアーチの陰惨な巨大さ、この暗い底なしに墜落するという想像、この闇のすべてが恐怖にみちていた。
ジャヴェールはしばらくじっと立ったまま、この暗黒の入口を見つめていた。見えないものを凝視するみたいに、じっとながめていた。水はざわめいていた。不意に彼は、帽子をとって岸辺においた。一瞬後、高く黒い人影、遅くなった通行人が、遠くから見たら幽霊と見まちがえそうな人影が、欄干の上に立っている姿を見せ、一度セーヌ河をのぞきこんでまた直立してから、暗闇に落ちて行った。にぶい水音がしたが、暗闇だけが、この水中に消えた黒い影の痙攣の秘密を知っていた。
『レ・ミゼラブル』佐藤朔訳 新潮社平成二四年四四刷 P280-284
ジャヴェールの死の真相
長い文章でしたが、みなさんいかがだったでしょうか?
たしかに長いですが意外とすらすら読めた気がしませんでしたか?
『レ・ミゼラブル』は大作でしかも難しいというイメージが先行していますが、実はそれほど厄介な言い回しもなく、むしろ情景描写や心理描写もはっきりしていて、ストーリーの展開も臨場感があって読みやすいものとなっています。
ノリやすいリズム感と言いますか、テンポよく読み進めることができるのがレミゼのいいところです。
さて、ジャヴェールがなぜ自ら命を絶ったのか、この長々とした彼の心理的葛藤を読めば皆さんもなんとなくその全貌を掴めたのではないでしょうか。
思っていたよりその死の原因が複雑で混沌としていることに気付かれたかと思います。
そして彼がなぜこれまでジャン・ヴァルジャンを執拗に追いかけていたのか、これまで彼がどんな人生観のもと生きてきたのかも見えてくるかと思います。
ジャン・ヴァルジャンは物語のはじめに、ミリエル司教と出会ったことで新たな人生が始まり、生まれ変わりました。
ですがジャヴェールはジャン・ヴァルジャンという圧倒的な男に出会ったものの、新たな人生を始めることはできませんでした。
それはきっとジャヴェールはすでに自分がとてつもない悪を犯し続けてきたことや、哀れな人びとを法の名の下に苦しめ続けてきたこと、そして警察という仕事柄、悲惨な悪人たちをあまりにたくさん見続けていたことなどもその背景にあったのかもしれません。
もはや彼がやり直しをするには、あまりに重たいものを背負いすぎていたのかもしれません。
ですが最後の最後に監獄の囚人たちの待遇を改善する案を書き残して提出します。これはそれまでのジャヴェールでは考えられないことだったのではないでしょうか。この嘆願書の意味はとてつもなく大きいものであるように私には思えました。
人生のこれまでとこれからの全てが崩壊したジャヴェール。
彼が深淵に身を投じたシーンはレミゼの中でも屈指の名シーンであると私は思います。
今回、長々とジャヴェールのシーンを読んできましたが、原作は基本的にこのような感じで進んで行きます。一人一人の心の内をとことんまで掘り下げます。ですので小説が長くなってしまうのは仕方がないのです。
ですがここまで読んできてお察しの通り、実はひとつひとつの文章はそこまで難解ではありません。むしろ、楽しく読めたのではないでしょうか。
原作は手が出せないと二の足を踏んでいるそこのあなた!
大丈夫です!読めます!怖がらずにこの機会にぜひ読んでみてください。
もっとレミゼが好きになること請け合いです。
以上、「ジャヴェールはなぜ死んだのか。『レ・ミゼラブル』原作からその真相を探る。」でした。
※2021年7月28日追記
以下のリンク先では『レ・ミゼラブル』をもっともっと楽しむためのお役立ち情報が満載です。ぜひご覧ください。
関連記事