ユゴー『死刑囚最後の日』あらすじと感想~ユゴーの死刑反対への思いが託された渾身の小説

ユゴー『死刑囚最後の日』あらすじ解説、感想~―死刑反対への思いが託されたユゴー渾身の小説

ヴィクトル・ユゴー(1802-1885)Wikipediaより
ユゴーの『死刑囚最後の日』は1829年に出版された作品です。
私が読んだのは潮出版社の小潟昭夫訳の『死刑囚最後の日』です。
巻末の解説ではこの作品について次のように書かれています。
死刑廃止について、世界ではまだコンセンサスをもつにいたっていない。犯罪者に対して、被害者やその遺族が殺してやりたいと思うのは、心情として理解できるだろう。人を殺したのだから、死刑に処せられて当然だという風潮は消えることはないように思われる。他方、世界のいくつかの国々では、死刑廃止を決めて、施行している。
一九八一年十月、フランスのミッテラン政権は、ついに死刑廃止を決定した。そして現在施行されているのである。あのとき、十九世紀において、生涯、死刑廃止を唱えつづけたヴィクトル・ユゴーのことを想ったフランス人は少なくなかったにちがいない。なぜならば、ユゴーは生涯、死刑廃止を、小説や詩であれ、政治的なパンフレットであれ、議会発言であれ、あるいは素描であれ、あらゆる機会を利用して、唱えつづけたからである。
なぜユゴーは、死刑廃止を生涯唱えつづけたのだろうか?本書にその理由が見出せるにちがいない。
潮出版社 小潟昭夫訳『死刑囚最後の日』P375
ユゴーは生涯、死刑に反対し続けていました。
そんな彼の思いを死刑執行の瞬間を待つ死刑囚の手記という形を取って作品にしたのがこの小説です。
彼の死刑反対への思いは幼少期の体験にまでさかのぼることができます。
死刑囚に対する恐怖や関心は、彼自身の幼児体験にさかのぼることができる。五歳のヴィクトルが、アヴェルリーノ知事になった父レオポルの赴任地イタリアへの道中で、木に吊るされたゲリラの死体を見たり、十歳のときスぺインで将軍になった父のもとへ赴いた、その帰り路、ブルゴスの広場の絞首台で処刑されようとしている情景に立ち会ったりしている。また母の恋人で、ナポレオンのおたずねものだったラオリー将軍も、銃殺されている。
十六歳のときに、裁判所の前で、盗みで真っ赤な焼きごての烙印を押された若い女性の拷問に立ち会ったことを、後に思い出している。そしてユゴーは、何年も経った後も、犠牲となった女性の恐ろしい叫び声が耳について離れなかったという。
潮出版社 小潟昭夫訳『死刑囚最後の日』P375ー376
ユゴーにとって死刑執行は恐怖以外の何物でもなかったのでしょう。
興味深いことにロシアの文豪トルストイも死刑執行に対して非常に嫌悪を抱いた人物です。彼もパリで見た死刑執行に激しい怒りを感じたと言われています。
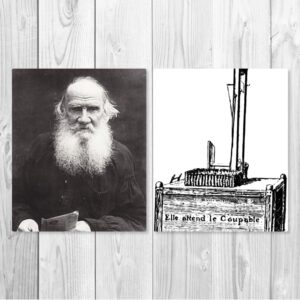
当時の死刑執行は民衆の見世物になっていました。多くの人間がそれを見ることを娯楽として楽しんでいたのです。
そんな中でユゴーとトルストイは民衆とはまったく異なる目でそれを見つめていたのでしょう。
作中では死刑囚が自らの最後の時間を手記に書き続けていきます。ユゴーは彼に次のように語らせています。
私がこのように書くことはおそらく無駄にはなるまい。私の苦しみが綴られるこの日記は、一時間ごとに、一分ごとに、激しい苦痛のたびに、肉体的につづけることが不可能になるときまで、この日記を継続すれば、それが意義深い教訓を担っていないだろうか。死を目前にした思考の調書のなかに、つねに増大する苦悩の展開なかに、囚人の一種の知的な解剖のなかに、断罪する人びとにとって多くの教訓があるのではないだろうか。いつの日か、考えるひとつの頭を、正義の秤と呼ばれるもののなかに投げ込む場合に、この一文を読むならば、彼らの手はもっと重味を増すだろうか。おそらくあの不幸な罰を課す人びとは、死刑判決という手っ取り早い方式に、拷問のゆっくりとした時間の連続が含まれることをかつて考えたことがあっただろうか。彼らが排除する人間に、ひとつの知性があるという胸をえぐるような考えに一度だって目を留めたことがあるのだろうか。生命を頼りにしているひとつの知性があり、死に対してはまったく予期していないひとつの魂があるのだ。彼らはこうしたことすべてのなかに落下する三角の刃しか見ていないし、おそらく断罪された者にとっては、以前も、以後も何もないと、考えているのだ。
この一文は彼らの過ちを悟らせるだろう。おそらくいつか出版されて、人の苦悩にしばし彼らの精神を向けさせるだろう。なぜならば、人の苦悩こそ彼らには思いも浮かばぬことなのだから。彼らは肉体をほとんど苦しめないで殺すことができると勝ち誇っている。おやおや!問題なのはそんなことか!精神の苦痛に比べれば肉体の苦痛など、いったいどれほどのことか!恐怖と哀れみだ、このように作られた法律は!いつかやってくるだろう、そしておそらくみじめな男の最後の告白である、この回想録が貢献するだろう……。
潮出版社 小潟昭夫訳『死刑囚最後の日』P15
この小説ではこのような、死刑囚の痛切な心の内を聴き続けることになります。この死刑囚は決して野蛮な殺戮者ではなくどこか知的な印象すら与えます。ユゴーはこの人物の罪状は意図的に明かしていませんが、わかりやすい残酷な悪人ではないことは確かです。
そんな人物による恐怖と苦悩の吐露がこの作品では語られるのです。
感想―ドストエフスキー的見地から
ユゴーの『死刑囚最後の日』も『ノートル=ダム・ド・パリ』と同じく若き日のドストエフスキーが親しんだ作品です。
この作品は死刑囚が処刑される直前までのシーンを描いた作品でありましたが、ドストエフスキー自身もまさか同じ体験を後にするとはその時は思っていなかったことでしょう。
ドストエフスキーも禁止されていた社会主義サークルに出入りしていたという罪で1849年に逮捕され死刑を宣告されています。

そして銃殺刑に処されるほんの直前に、皇帝からの恩赦が宣告され、そのままシベリアに流刑となったのです。
ドストエフスキーはまさしくこの作品の主人公と同じように、死の寸前まで行った男なのです。あと5分で自分は死ぬ!そういう極限状況にいたのです!
ドストエフスキーは後に、彼の傑作小説『白痴』で主人公のムイシュキン侯爵にその時の体験を語らせています。
その中に、先ほどユゴーの文章にあった「彼らは肉体をほとんど苦しめないで殺すことができると勝ち誇っている。おやおや!問題なのはそんなことか!精神の苦痛に比べれば肉体の苦痛など、いったいどれほどのことか!」という言葉に応答するような箇所も出てきます。
『死刑囚最後の日』の影響はドストエフスキーが自身の体験を文学に昇華させるひとつのきっかけになったのではないでしょうか。
死刑によって「確実にあと数分で死ぬ」という極限の状況に置かれた人間が何を思うのか。これは非常に重いテーマでありますが、私たちに大切なことを考えさせてくれる作品であります。
作品自体もそこまで長いものではないので手に取りやすいものとなっています。
死刑問題に関心のある方にとっても重要な書物となるのではないでしょうか。
以上、「ユゴー『死刑囚最後の日』あらすじ解説と感想~ユゴーの死刑反対への思いが託された渾身の小説」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら
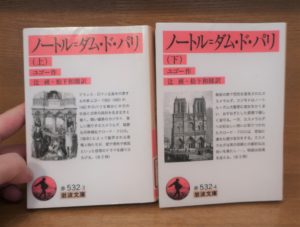
関連記事















コメント