ツルゲーネフとヴィアルドー夫人の宿命の恋~ツルゲーネフの運命を決めたオペラ女優の存在

生涯独身を貫いたツルゲーネフの運命の人―オペラ女優ポーリーヌ・ヴィアルドー
ツルゲーネフは大地主の御曹司でしかも容姿端麗。文壇のスターとして活躍し、さらに社交界では軽妙洒脱な話術や抜群の知性で伊達男として通っていました。これはモテないわけがありません。これはドストエフスキーと比べても興味深いです。彼とは真逆のモテっぷりです。ツルゲーネフは若い頃から恋多き男でした。
しかし、そんな彼でしたが生涯結婚することはありませんでした。
彼には生涯にわたって愛し続けた一人の女性がいたのです。
それがポーリーヌ・ヴィアルドーというオペラの歌姫だったのです。

一八四三年はツルゲーネフにとって、むしろ、イスパニア生まれの歌姫ポリーナ・ヴィアルドーとの出会いということによって、記憶さるべきであった。
ヴィアルドー夫人と知り合ったことは、ツルゲーネフのその後の個人的運命を大きく左右することになる。ツルゲーネフとヴィアルドー夫人との関係の真相は永遠の謎であるが、ツルゲーネフが一生を独身で通したのは、ヴィアルドー夫人への愛のためであろうと言われている。
ツルゲーネフは結婚こそしなかったが、彼には、青年時代に母親のお針女に生ませたポリーナ(ポーリンあるいはポーリネットと呼ばれた)という娘が一人いた。
彼女が七歳になったとき父親は娘の養育をパリ在住のヴィアルドー夫人に託した。ポーリネットは夫人のもとで成長するが、年ごろになるにつれて父親と父の愛人との三角関係が奇妙なものとなっていったであろうことは、想像に難くない。
とにかくツルゲーネフは、ヴィアルドー夫人の行くところ、その後を追って、生涯の大半を国外で過ごすことになるのである。
講談社『世界文学大系―38 ツルゲーネフ』P376
※一部改行しました
彼がポーリーヌ・ヴィアルドーと初めて出会ったのは1843年。舞台上の彼女に一目惚れしたのがきっかけでした。
ですが皆さんもこの解説を読んでお気づきのように、彼女は人妻です。
普通ならそこで終わりのところですがツルゲーネフはおかまいなしに彼女との交流を深めていくことになります。
当時、特にフランスでは不倫は暗黙の内によく行われていたようです。そもそも恋愛結婚よりも経済目的の結婚が多くを占めたので男女関係は割り切っている夫婦が多かったというのが実情のようです。フランスの文豪バルザックやエミール・ゾラの小説では頻繁にそうしたことが描かれます。ヨーロッパにどっぷり浸っているツルゲーネフもそうした感覚を持っていたのかもしれません。
数年後に晴れて彼女と結ばれることになるのですが、伝記によると基本的に彼女とは燃えるような恋をしつつもプラトニックな関係である方が全体としては多かったようです。
そのおかげもあるのか、驚くべきことにヴィアルドー夫人のご主人とは生涯にわたっての親友となってしまいます。ご主人も夫人とツルゲーネフとの関係には薄々気づいているのですがそれでも深い友情関係が保たれていたようです。
ツルゲーネフとヴィアルドー家は家族ぐるみの付き合いになり、彼はヴィアルドー夫人を追って生涯の大半を国外で過ごすことになります。
さらに驚くべきことに彼はドイツのバーデン・バーデンのヴィアルドー家の隣に家を建ててしまいます。それほどまでにヴィアルドー夫人を愛していたのです。
では、そのヴィアルドー夫人とはどのような人だったのか、その人となりとツルゲーネフがなぜ彼女をそこまで愛したのかを見ていきましょう。
この不思議な女性ポーリーヌ・ヴィアルドーの魔力に、ツルゲーネフは一生つなぎとめられることになる。
賢くて、底知れぬ魅力とマクべス夫人的魔力を持つその女性は、実母ヴァルヴァーラ亡きあと彼を支配した唯一の女性であった。
人々はそのひとのことを不美人だと言った。端正で上品なロシヤ貴族、すでにいくつかの詩を活字にし、一部から有望視されていたロシヤ文学の未来の星が、選りに選って、なんであのような素性の定かでない異国の不美人に有頂天になるのか、人々は解しかねることとして彼の燃える恋を見守った。
しかも相手は人妻なのだ。その熱中を気違い沙汰だと言っていさめる者もあった。誰よりも彼の母が、生前すでに反対だった。しかし、その母も、こっそり彼女の出る劇場に行って、その声を聞き、その姿を見て、言いようのない強い印象を受けて帰って来るのである。
猫背で、口が大きく、しかもその口はやや前に出ており、眼もいくらかとび出ていて、顔の線もいくらかきついスペイン生れのその歌姫の素顔を、美しいと言った回想は少ない。(中略)
だが、女の美とはいったい何なのか。人々はただその外貌ばかりを見て、一個の生きた全人間としての彼女を見ていない。外側からばかりでなく、内側からも当然見ねばならないのに。
「でも、美は人間の個性の中ほど力強く輝くところはありません。そこでは美は何よりも多く理知に語りかけます。ですから私について言うなら、私はいつも不完全な声で表現される偉大な音楽の力のほうを、美しくはあってもその美が単に物質的なものにすぎないような愚かしい声より好きです。」(一八五〇年九月九日、ヴィアルドー夫人宛)
これはツルゲーネフ自身の言葉である。女性の美をも含めて美一般を云々する者は、彼のこの言葉をまず読まねばなるまい。「美しくはあっても、その美が単に物質的なものにすぎない愚かしい」美は、彼の心を打たなかったのである。(中略)
ツルゲーネフが彼女を見染めたのは一八四三年の秋で、初めは舞台の上の芸の人としての彼女に惚れたのである。
後年、エミール・ゾラの中に自分とは異質なざらざらしたものを感じ取り、素朴さと善良さを持つフローべールに身近なものを感じたように、芸と人とが一体になったヴィアルドーの中に芸術の本質を見てとり、一つの完璧を見出したと思ったのである。
彼の愛したのはヴィアルドーという女であったのか、それとも芸術であったのか、おそらくはその渾然一体の現前そのものであったのだろう。
筑摩書房、佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P50-52
※一部改行しました
どこまでも芸術家であるツルゲーネフらしい恋のエピソードです。
こうして彼は生涯にわたってヴィアルドー夫人と生活を共にしていたのです。
とは言え、ツルゲーネフも純粋一途にこの女性とだけ関係を持っていたわけではありません。
ヴィアルドー夫人がいつつも多くのロマンスを演じています。
ヴィアルドーは肉体的な恋の理想というより精神的な、全人間的な理想であり、そして良き理解者として彼の中にあったようです。(もちろん肉体的にも惹かれている面もありますが)
ツルゲーネフの女性遍歴は彼の小説にもものすごく反映されています。
彼の代表作『初恋』は若き日の彼の恋が自伝的に書かれていますし、『片恋』や『ルーヂン』などの小説に出てくる主人公たちはツルゲーネフ的な男性像が多いとされています。
一つその例を挙げますと、女性と割と簡単に恋に落ちるのですが、男は最後の最後で踏ん切りがつかず、「ぼくには無理だ。仕方がない。私も苦しんでいるのだよ。許してくれ」と言って女を泣かし去っていくパターンです。彼の小説には自分に不利な状況があるとすぐに委縮し、仕方がないと逃げてしまう弱い性格が描かれがちです。恋する相手のために逆境をもはねつけて戦おうという強い意志がないのです。
これは読んでいて非常にやきもきします。
彼の伝記にもそうした恋がいくつも出てきます。
特にアンリ・トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』では彼のそうした「性格の弱さ」が余すことなく描かれています。
トロワイヤからするとこれがツルゲーネフ作品を理解する上で重要な点であると感じたのでしょう。
この辺りもドストエフスキーと比べてみるととても面白いです。
ドストエフスキーは彼とは真逆でまずモテるタイプではありません。
陰気で癇癪持ちで自意識過剰で自尊心は人一倍強く、人付き合いも苦手。地位もお金もありません。
ですが恋をするときは異常なほどの熱を傾け、もはや狂気のごとくのめり込んでいきます。
彼の最初の妻マリアとの恋も、不倫相手のスースロワとの恋もまさしく狂気の恋です。ドストエフスキーは激情と煩悶に苦しめられます。
ただ、そんな狂気の恋も妻の死と、そしてその後に再婚したアンナ夫人との生活によって変化を迎えます。
彼の生来の気質は相変わらずでしたが、アンナ夫人のおかげで彼の性格が少しずつ大らかになり、晩年は子供たちと共に穏やかな生活を送ることができました。
もちろん彼女との結婚生活、特に初期の頃はあまりに波乱万丈でしたが、最後にはドストエフスキーは妻との愛や家庭の幸せを感じて暮らすことができたのです。
このこともドストエフスキーの晩年の作品、特に『作家の日記』や『カラマーゾフの兄弟』に大きな影響を与えていると思われます。
モテ男ツルゲーネフは生涯独身を貫き、全くモテない狂気の男ドストエフスキーは穏やかな家庭を築いた。
どちらがよくてどちらが悪いというわけではありませんが、この違いは非常に興味深いものだと私は感じています。
ライバルツルゲーネフと比べてみて改めてドストエフスキーという人物により愛着といいますか、興味が湧いてきました。
アンリ・トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』ではツルゲーネフの人となりが余すことなく描かれていてとても面白いです。ぜひ彼の作品と合わせて読んでみて頂ければと思います。
以上、「ツルゲーネフとヴィアルドー夫人の宿命の恋~ツルゲーネフの運命を決めたオペラ女優の存在」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら

関連記事


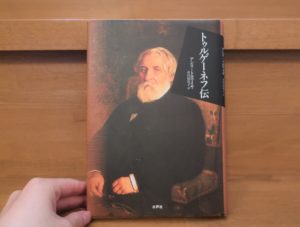
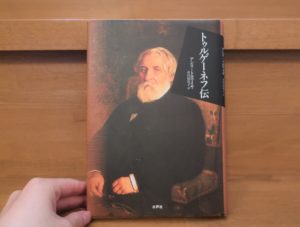
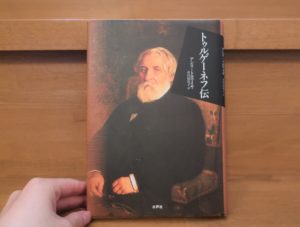








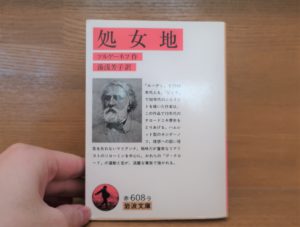



コメント