ツルゲーネフ側から見たプーシキン講演~ドストエフスキーとの最終決戦の結末はいかに!?

ツルゲーネフ側から見たプーシキン講演―ドストエフスキーの最終決戦
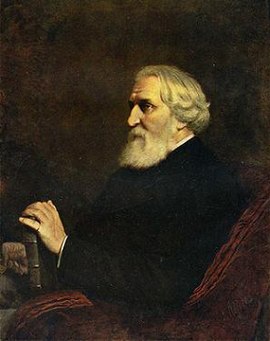
ツルゲーネフ(1818-1883)Wikipediaより
1880年、ツルゲーネフはモスクワでプーシキン像除幕式の記念講演に招待されます。この講演会はドストエフスキーも招待されていて、最晩年の2人が直接その文学論を戦わせた歴史的な一日として有名です。
以前当ブログでも「プーシキンをこよなく愛したドストエフスキー。伝説のプーシキン講演とは」の記事でもこの講演のことは紹介させて頂きました。

ドストエフスキーはプーシキンを最も尊敬していましたが、ツルゲーネフも同じようにプーシキンを師と仰いでいたのです。
ドストエフスキー伝記や参考書ではこのプーシキン講演がドストエフスキーの名声の絶頂として描かれることが多く、ツルゲーネフはその引き立て役、あるいは敵役として描かれがちです。
そのためドストエフスキー側からツルゲーネフを見るとどうしても偏ったものになってしまいます。
というわけで今回はツルゲーネフ側から見たプーシキン講演を見ていきたいと思います。
ツルゲーネフの『プーシュキン論』
ドストエフスキーのプーシキン講演の原稿が残されているように、ツルゲーネフもその時の原稿が残され、今も読むことができます。
私が読んだのは岩波書店、『ハムレットとドン キホーテ』所収、柴田治三郎訳の『プーシュキン論』です。
この本の巻末に当時のツルゲーネフが置かれていた状況や、この講演会の様子などがわかりやすく書かれていましたので引用します。
ツルゲーネフは一八五六年からほとんどフランスとドイツ、殊にパリに住んでいて、ロシヤにはめったに帰らなかった。
恋人ヴィアルドー夫人から離れ難かったためでもあるが、ツルゲーネフが『ソヴレメンニク』同人と決裂した一八六〇年頃からようやく政治的意識の強くなったロシヤの読者、殊に青年層が、必ずしも直接に社会にはたらきかけることを目的とはしない芸術家ツルゲーネフを理解せず、ツルゲーネフをロシヤの現實を知らないものとして攻撃しつづけたからある。
しかし晩年になってツルゲーネフは、自分に対するロシヤの読者の共感が次第に盛り返して来たのを感取した。
そして一八七九年二月、ツルゲーネフは「ロシヤの読者及び青年と仲直りしよう」と冗談を言いながら、故国に帰った。
するとそこでツルゲーネフは夢にも思わなかっほどの熱狂的な歓迎を読者、殊に若い世代から受けた。
モスクヴァでは十二年ぶりで「ロシヤ文学友の会」に出席し、ぺテルブルクでは高座に上って『猟人日記』の一節を朗読し、割れるような喝采を浴びた。
老作家と読者の間の永年に亘る誤解と不和が完全に氷解したように見えた。
実は、永いあいだの批評家の意識的な攻撃にもかかわらず、読者の胸の中に温められていたこの作家に対する敬慕の情がことに爆発したのだと思う。
翌八〇年六月五日から三日間に亘ってモスクヴァで行なわれた「プーシュキンの日」に出席するため、ツルゲーネフは再びパリから故国を訪れた。
するとこの度は前回にもまさる民衆の熱烈な歓迎ぶりだった。ツルゲーネフの通る道の両側には群集が殺到して帽子を投じて歓呼する。大学生の一団が途中に待ち伏せして、ツルゲーネフの身柄を自分たちの馬車に移して会場へ送りとどける、という有様であった。
次々に行なわれる演説の中に少しでもツルゲーネフに感謝の意を表するところがあれば嵐のような拍手が起こった。さながらこの会がプーシュキンのためではなくて、ツルゲーネフのために催されたような観を呈した。
数多い演説の中でドストイェーフスキーとツルゲーネフの演説が白眉だった。とりわけツルゲーネフのそれが感動的な印象を与えた。―ツルゲーネフの『プーシュキン論』はそのような状況のもとに発表されたものである。
ツルゲーネフの故国訪問はそれが最後となり、一八八三年八月パリ郊外の別荘で死んだ。
岩波書店、『ハムレットとドン キホーテ』所収、柴田治三郎訳の『プーシュキン論』P125-126
※一部改行し、旧字体は新字体に改めました。
ツルゲーネフは『猟人日記』や『貴族の巣』など一八六〇年代が始まるまではロシアで絶大な人気を誇っていました。
しかし1860年代以降に発表された『父と子』や『煙』、『処女地』などは文壇から激しい非難を受けることになります。
というのも上の引用にもありましたように、ツルゲーネフは政治意識が少ない作家だったからなのです。1860年代からのロシアはテロの恐怖が現実になるほど政治的に過激な状況になっていました。彼は極端な過激思想を嫌います。彼はあくまで中道的に時代を観察し芸術を生み出すことを目指していたのです。
そのため「芸術家」ツルゲーネフの作品はどっちつかずで傍観者的なものだと過激派から避難されることになってしまったのです。
しかし時代を経てツルゲーネフの作品は確実に読者に浸透していきました。文学は過激派だけではなく一般の読者にも必ず届いていきます。ゆっくりとではありますが多くの人に確実に彼の文学の素晴らしさが浸透していったのです。(もちろん、政治情勢も変わったという面もありますが)
その結果が彼を驚かせたロシアでの大歓迎だったのです。
プーシキン講演会ではツルゲーネフは熱狂的に迎えられています。ですが面白いことにこの大歓迎についてドストエフスキー側の本では「ツルゲーネフは熱狂的に迎えられていたがサクラも多く混じっていた。」と皮肉を交えて語られることが多い印象がありました。
この辺にも立場の違いが見えて興味深かったです。
さて、引用を続けます。ここからはツルゲーネフのプーシキン論についてお話ししていきます。
プーシュキンはその詩においてほしいままに自由を歌ったため当時の官憲に壓迫され、二度も僻地に追放され、その葬儀まで官憲の干渉によって物淋しく行なわれたほどだったが、プーシュキン自身は文学を政治の婢にして社会に直接にはたらきかけようとする意志は少しもなかった。
プーシュキンの求めた自由は内心の自由だった。美を美として歌う自由だった。
プーシュキンの功績は、創作用語としてのロシヤ語を完成し、ロシヤ固有の詩(文学)を創建したことにあった。
プーシュキンはロシヤ文学史上、詩の固有価値を宣揚した最初の詩人である。しかし、ようやく目覚めかけたロシヤの社会には、より痛切な問題がありすぎたので、プーシュキンの「芸術のため芸術」に対して、プーシュキンの生前すでに読者は冷淡になり始めた。
死後その名はますます読者の念頭から遠のいた。六十年代のいわゆる政治と労働の時代は言うもおろかである。ツルゲーネフの比喩をもって言えば、プーシュキンを祭司とする詩の聖堂から人々は騒然たる市場へ―そこでは何よりも箒を必要とする市場へ―出て行ったのである。
しかしやがて青年たちが再びプーシュキンを読むようになった。一八八〇年にはモスクヴァにプーシュキンの美しい銅像が建てられた。
ロシヤの読者は「詩に復った」のである。―ツルゲーネフはプーシュキンの意義とプーシュキンと読者の関係の歴史をこのように述べた。
ツルゲーネフはいつもみずからプーシュキンの弟子と称していた。
ツルゲーネフの作品はその溢れる人間性の故におのずから社会的に作用を及ぼし、そのため官憲はつまらぬ口実を設けてツルゲーネフを投獄禁錮さえしたこともあるが、ツルゲーネフ自身は文学を政治の具にする気は毛頭なかった。
そのため六十年代の若い世代はツルゲーネフの敵だった。八十年頃になってようやく読者との「仲直り」が実現したことは前にも述べたとおりである。
このように見て来ると、ツルゲーネフがこの講演で述べたプーシュキンと読者との関係の歴史には、ツルゲーネフ自身の読者との関係が二重写しになって見えるではないか。
ツルゲーネフはプーシュキンの運命を語りながら、自分自身の運命をも語っていることに気づいてどんなに感慨が深かったであろう。
ただ両者の違うところは、プーシュキンには不幸にも読者との「仲直り」が死後四十年を過ぎて初めて行なわれたが、ツルゲーネフは辛うじて生前のうちに凱旋将軍のように読者に迎えられたということである。
岩波書店、『ハムレットとドン キホーテ』所収、柴田治三郎訳の『プーシュキン論』P126-128
※一部改行し、旧字体は新字体に改めました。
ツルゲーネフが自らをプーシキンの弟子と言っていたということはあまり知られていないことかもしれません。「ツルゲーネフが若い頃に憧れの人プーシキンを見て興奮した」というのは読んだことがありましたが、「芸術における師」としてプーシキンをそこまで尊敬しているということは私も初めて知りました。
そしてここで述べられるように「芸術のための芸術」であったプーシキン作品が多くの人に読まれなくなってしまっていたというのも意外でした。
もしそうだとすれば、それでもなおプーシキンを愛し続けていたツルゲーネフとドストエフスキーというのはロシア文学界の中でも異質な存在だったのかもしれません。
ですが結局この二人がロシア文学界を牽引していくことになったのですからこれも世の中の不思議だなと思います。
さて、この本ではツルゲーネフに対してかなり好意的に解説がなされていますが、少し違った視点からも意見を聞いてみたいと思います。
佐藤清郎の『ツルゲーネフの生涯』でもこのプーシキン講演についてドストエフスキーと比較しながら述べている箇所がありますのでこちらも見ていきます。
ツルゲーネフがあくまで知識人の、人道的西欧人の立場で物を言っているのに対して、ドストエフスキーはロシヤ的即全人的という立場から発言している。傾向としてはスラヴ派に近いドストエフスキーの講演に、西欧派の人たちも拍手したのだが、それは自分たちの主張、たとえば前日のツルゲーネフの講演中の次の言葉、「芸術はその十分な表現に達するときには、学問以上に全人類の財産となる」に呼応するものがあったからだ。
この日のドストエフスキーの講演の成功は、聴衆への呼びかけの熱っぽさ、自説の強烈な説教、その内容のメシヤ的深遠さによるのである。ツルゲーネフは冷静で、人々を自説の中に巻きこもうとする熱っぽさはなかった。事実の凝視があるだけだ。病的に感じる者とあくまでクールに物を観る者の姿勢がここにも見られる。相対主義という安全弁を底に持っていて物を言うツルゲーネフの「賢者ぶり」には、われも人も捲きこまずにはいられないドストエフスキーの激情は、我慢ができなかったのである。この日、お互いに接触点を見出して、熱い握手を交したものの、両者の間の異質性はあまりにも大きいものがあった。
筑摩書房、佐藤清郎『ツルゲーネフの生涯』P237-238
ツルゲーネフとドストエフスキーの違いが一発でわかります。
病的に感じ、人を巻き込まずにいられない激情家ドストエフスキー。
どこまでもクールな観察者、賢者ツルゲーネフ。
二人の間にはこうした違いがあるのですね。たしかに作品を読んでみればこれは大いに納得できます。
ドストエフスキーの伝記ではこのプーシキン講演でのツルゲーネフについて以下のように述べています。これはドストエフスキーの講演が終わった直後のお話です。
三十分ものあいだアンコールの声がつづいた。聴衆は熱狂していた。ある学生が涙を浮かべて駆け寄って来たが、失神して彼の足もとに倒れてしまった。ツルゲーネフは、感動のあまり、旧敵を抱擁した。会は一時間中断された。
モチューリスキー『評伝ドストエフスキー』松下裕・松下恭子訳P704
クールな観察者であり賢者、芸術家であるツルゲーネフですら感動してしまうほどの熱弁をドストエフスキーは繰り出したのです。旧敵同士が和解し抱き合うというのは何とも感動的な場面です。もしかしたらプーシキンを愛し続けてきた2人だからこそ通じ合う何かがここにあったのかもしれません。
ですがやはりツルゲーネフはツルゲーネフ。ドストエフスキーの黒魔術的な熱狂から醒めるとその異質性にまた元の宿敵に戻ったそうです。この辺も2人の関係性を示す興味深いエピソードだなと感じます。
ここまでツルゲーネフ側から見たプーシキン講演をお話ししてきましたが、やはりある出来事を片側だけではく両方の立場から見てみるというのは非常に面白いことだなと思いました。
そうすることでよりドストエフスキーについて知ることができたなと思います。
以上、「ツルゲーネフ側から見たプーシキン講演―ドストエフスキーとの最終決戦」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら

関連記事





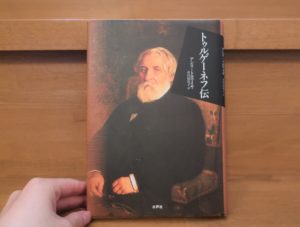
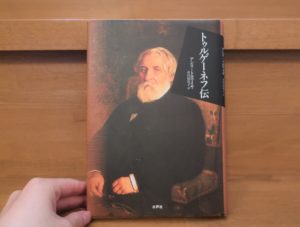




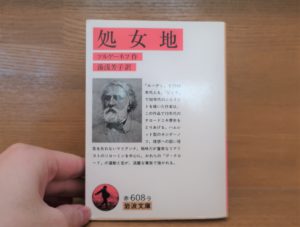



コメント