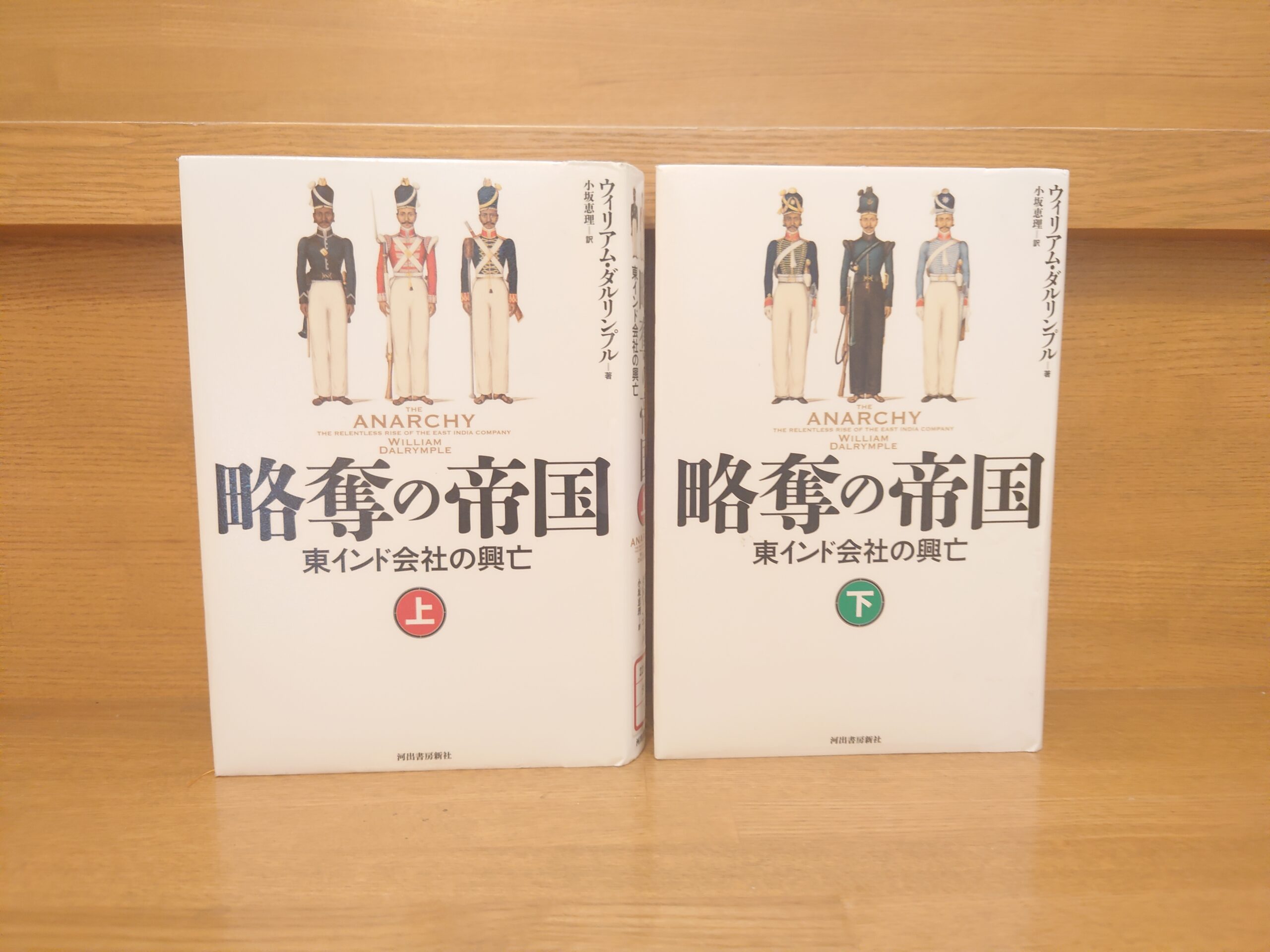W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』概要と感想~現代への警告!大国インドはなぜイギリスの植民地になってしまったのか
今回ご紹介するのは2022年に河出書房新社より発行されたウィリアム・ダルリンプル著、小坂恵理訳の『略奪の帝国 東インド会社の興亡』です。
早速この本について見ていきましょう。
18世紀、インドを征服した一企業による歴史的な組織暴力と、インドの悲劇を描いた、近年の歴史書最大の話題作、待望の邦訳!
Amazon商品紹介ページより

この本では巨像インドがイギリスの東インド会社に支配されていく流れを詳しく見ていく作品です。
はじめに言わせて言わせて頂きますが、この本はあまりに衝撃的です。読んでいて恐怖すら感じました。圧倒的な繁栄を誇っていたムガル帝国がなぜこうもあっさりとイギリスの貿易会社に屈することになってしまったのか。この本で語られることは現代日本に生きる私たちにも全く無関係ではありません。この本はまさに私達現代人への警告の書とも言えるでしょう。
この本について訳者あとがきでは次のように述べられています。
インド亜大陸は、かつては独立した大陸で南半球に位置していた。しかしプレートの動きと共に北上を続け、五〇〇〇万年前頃にユーラシア大陸と衝突したという。そして今日のインドは面積が世界第七位にランクされる。およそ一三億の人口は、世界で二番目に多い。これに対して日本の国土の面積は、インドの約一〇パーセント程度しかない。そんな広大な地域に様々な民族や宗教や言語が入り混じっているのだから、コンパクトにまとまっている日本とはまったく違う国である。日本でもかつて国が統一されるまでには時間がかかり、各地の実力者による覇権争いが続いたが、本書『略奪の帝国―東インド会社の興亡』で描かれるインドの混乱状態は桁外れである。
本書は、インドのかなりの部分を支配下に収めたムガル帝国が衰退し、国土が分裂状態に陥った一八世紀が舞台である。インドの莫大な富を目当てにはるばる海を越えてやってきたイギリス東インド会社は、一介の商社だったにもかかわらず、混乱に乗じて巧妙に立ち回り、何と自分たちで大規模な軍隊を所有するまでになり、ついに広大なインドの全域を征服した。どうしてそんなことが可能だったのだろう。成功するためにはどんな要素が必要か、逆に失敗するのはどんな要素のせいなのか、あるいは何が足りなかったからか、本書は貴重な教訓を与えてくれる。
河出書房新社、ウィリアム・ダルリンプル、小坂恵理訳『略奪の帝国 東インド会社の興亡』下巻P235
この本を読んでまず驚いたのはインドの自滅とも言える分裂ぶりでした。ムガル帝国の力が弱まりインド国内が混乱状態になり、一致団結してイギリス東インド会社に立ち向かおうという空気に全くならなかったという点にインドの悲劇がありました。インド国内におけるそうした分断を利用して各個撃破していった東インド会社です。もちろん、インド人同士連合を組んで戦うこともありましたがいつ裏切るかわからない状況であったり、イギリス側の賄賂や懐柔策によって実際に裏切りや離反が相次ぎました。結局、インド国内でインド人同士が争い続け、弱体化したところを狙われたというのが実際のところでした。
当時は現代のような「インド人」という概念もなかったでしょうし、「インド人が団結して」という発想にならなかったのも仕方ありませんが、それにしても国を分断させて一致団結させないという東インド会社の狡猾さを感じることになりました。そう考えると、日本の幕末から明治にかけて内戦が大きくならずに明治維新ができたというのはとてつもなく大きな意味があったのではないかと思います。もし徳川慶喜が徹底抗戦の意志を持って戦おうとしていたら日本中焼け野原で悲惨なことになっていたことでしょう。優秀な人材も多く失われていたことでしょう。国の分断を避け、それらを維持したまま新政府に移行して西欧諸国と向き合おうとした徳川慶喜の判断はまさに国を救った究極の判断だったのかもしれません。
この徳川慶喜の判断については鹿島茂著『渋沢栄一』でも説かれていました。
渋沢栄一は徳川慶喜と深いつながりがあった人物です。徳川慶喜は君主として、渋沢栄一は経済人として国の行く末を心から案じ戦い抜きました。そのことにも思いを馳せることになった『略奪の帝国 東インド会社の興亡』でした。
また、これも意外だったのですがイギリス本土も東インド会社に対して強い批判を加えていたという点です。
私はてっきりイギリス本土の植民地政策の一環として東インド会社があるものだと思っていたのですが、実はそんなに単純な話ではなかったのです。東インド会社はインド社会を破壊し、さらにはイギリス本土の経済まで破壊しかねない爆弾と化していたのです。しかも経済面だけでなく、人道面でもあまりに残虐すぎるという批判がなされていたのです。ひとつの会社が軍隊まで持ちすべて思うがままに支配する体制に対してイギリス本土が強い批判を加えていたというのは私には驚きでした。(もちろん、そうは言っても利益をもたらす以上、金の成る木を手放せないのは言うまでもありませんが・・・)
このことについても「訳者あとがき」で次のように説かれています。
イギリス東インド会社は、今日の巨大企業の走りである。いまでも、巨大企業が破綻の瀬戸際に立たされたとき、「大きすぎて潰せない」( too big to fail)という表現が使われることがあるが、イギリス東インド会社もそれを理由に救いの手を差し伸べられた。それには、会社の株に多くの議員が投資しているという事情もあった。現地の悲惨な状況を把握していなかったとはいえ、一企業の活動がここまで許されるのは行きすぎだ。これに対して今日の企業は、いくら大きくても軍隊を持つことはない。ただし露骨な行動こそ目立たないが、世界各地に巧妙に支配網を張り巡らせ、自己利益の追求に余念がない点は同じだ。それが世界の秩序に歪みをもたらし、戦争のような不測の事態を引き起こす恐れはないだろうか。いったん戦争がはじまると、罪のない一般市民が犠牲になることは、ウクライナ問題からもわかる。そして戦場では残虐行為が当たり前のように繰り返されることは、本書の生々しい描写からもわかる。
本書では、会社成長の立役者であるロバート・クライブとウォーレン・ヘースティングスが、イギリスに帰国してから無実の罪を着せられて激しく非難される場面も印象に残った。偽情報でも、それが繰り返し報道されると、さも真実のような印象を与え、とんでもない事態に発展してしまった。いまは当時とは比べものにならないほど情報が氾濫しているのだから、同じような恐ろしい展開になる可能性は格段に高くなった。膨大な情報の正しさを見分けるのは本当に難しいが、せめて疑ってかかる姿勢だけは身に着けておくべきだろう。
現在の世界はコロナ禍やウクライナ問題に振り回されているが、そんななか、インドは非同盟・全方位外交の姿勢を崩さない。それが八方美人的だと非難されるときがあるのは事実だ。ただし国土の広い多民族国家には、かつて混乱状態に付け込まれ、最終的に植民地として支配された苦い歴史がある。なるべく敵を作らず、どの国とも手を組める可能性を残しておく姿勢には、そんな歴史の影響があるのだろう。本書を読むと、インドという国のしたたかさにも十分納得できる。
河出書房新社、ウィリアム・ダルリンプル、小坂恵理訳『略奪の帝国 東インド会社の興亡』下巻P238-239
この本はまさに現代社会への警告書です。私はこの本を読んでつくづく今の日本が怖くなりました。
今、日本も分断が進められているのではないか。過激な主張やレッテル貼り、ヘイトがどんどん増えてはいないだろうか。
そして共同体意識がどんどん失われ、「個」の成功、「自分さえよければそれでいい」、「世の中をうまく立ち回れ、出し抜け」と喧伝する社会になってはいないだろうか。ぱっと見ればこれは「個人の考え方の問題」で社会とは無縁なものにしか見えないかもしれませんが、こうして他者との共同体意識はどんどん薄れて分断へと突き進むことになるのではないでしょうか。
分断し、一致団結できない状況まで追い込んでから各個撃破する。これが敵を切り崩す最も確実な方法だとこの本を読めばよくわかります。
東インド会社は虎視眈々と数十年、百年スパンでこれを実行し、ついには巨大なインドそのものを支配下に置きました。これは他人ごとではありません。
私はこの本を読んで心底恐くなりました。繁栄を誇っていた国もあっという間に崩れ落ちるのです。日本もかつては繁栄していたかもしれませんが今や完全に右肩下がりの状況です。そして今の混乱。
現代の警告書としてこの本は非常に大きな意味があると思います。
もちろん、インドの歴史やイギリス史に興味のある方にもとてもおすすめです。私もこれまで学んできたこととこの本が繋がり、非常に刺激的でした。まさかアメリカの独立戦争やあのナポレオンまでこの出来事と繋がってくるのかと仰天しました。
世界は繋がっているんだということも知れる名著です。これはぜひおすすめしたい一冊です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』~現代への警告!大国インドはなぜイギリスの植民地になってしまったのか」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事