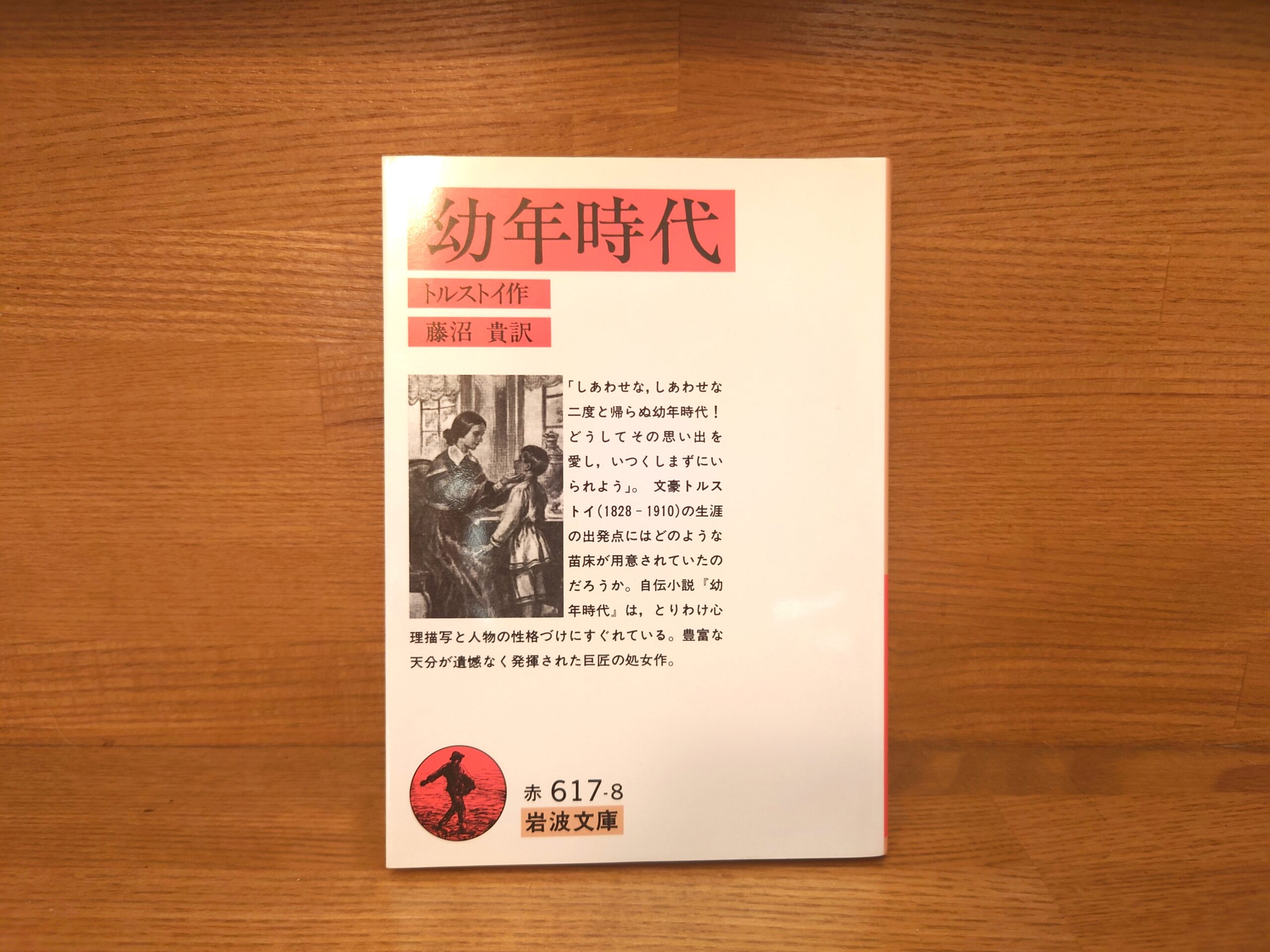トルストイ『幼年時代』あらすじと感想~ロシア文壇を驚かせたトルストイのデビュー作!
今回ご紹介するのは1852年にトルストイによって発表された『幼年時代』です。私が読んだのは岩波書店、藤沼貴訳の2018年第17刷版です。
早速この本について見ていきましょう。
「しあわせな,しあわせな二度とかえらぬ幼年時代! どうしてその思い出を愛し,いつくしまずにいられよう」.文豪トルストイの生涯の出発点にはどのような苗床が用意されていたのだろうか.自伝小説『幼年時代』は,とりわけ心理描写と人物の性格づけにすぐれている.豊富な天分が遺憾なく発揮された巨匠の処女作.
Amazon商品紹介ページより
この作品はトルストイのデビュー作です。1852年、トルストイ24歳の年です。
24歳にしてすでに「自伝的小説」を書き発表したというのはすでに大物感が出ていますよね。この小説はトルストイ自身の実体験とフィクションが巧みに融合された作品となっています。
そしてこの作品が発表されるとロシア文壇は「この新人は何者か」と騒然となったそうです。
では、この作品がそこまで評価されるポイントとは一体何だったのでしょうか。
トルストイは『幼年時代』決定版完成の前に『私の幼年時代の物語』というタイトルでこの作品を書いていました。これらを比べてみることで『幼年時代』の特徴が浮き上がってきます。藤沼貴著『トルストイ』ではその要因のひとつを次のように解説しています。少し長くなりますが、トルストイ文学全体を貫く重要なポイントですのでじっくり読んでいきます。
トルストイは大学中退・領地経営挫折後の迷走と模索の時期にいろいろなことをためしてみた。一二五~一二六ぺージで述べたように、小説を書いたのもその数多い試みの一つにすぎなかった。だが、失敗つづきだったそれまでの試みと違って、小説という方法が意外にうまくいきそうな感じがした。トルストイはこの方法を、最近数年自分を悩ませてきた問題―自分とはいったい何か?そもそも人間とは何か?という問題に適用してみる気になった。こうして「私の幼年時代の物語」が書きはじめられた。それはトルストイの多くの作品と同じように写実的な(リアリズムの)方法で書かれた。リアリズムといってもいろいろな性格のものがあって、一概に定義することはむつかしいが、いちばん単純なリアリズムは「さまざまな出来事、事物、情景、人間の言動、感情、心の動き、あるいはそういうもののイメージを、自分から距離をおいて、外側から見ながら、現実と等身大に写生風に描写したもの」と言えるだろう。
「私の幼年時代の物語」もはじめはそのような素朴なリアリズムの作品だった。その最初の草稿はある人が友人に自分の子供時代のことを書いた手記を送るという形式になっていた。冒頭に「まえがき」として、作者が友人にあてた手紙が一ぺージほどあり、それから小説の本文がはじまる。だが、その冒頭では、プライバシーをさらけ出すことについての作者の一般論が展開され、それからようやく小説らしい部分がはじまる。その書き出しは次のようになっていた。「あなたは私の母とその経歴を知らなかった。かの女は結婚前までB公爵令嬢で、イワン・アンドレイチ・B公爵の娘だった……」。このように、事物や、人間の即物的な描写ではなく、主人公のバックグラウンドの説明が延々と五ぺージつづいた後で、ようやく主人公ニコーレンカが朝早く、住み込みのドイツ人家庭教師イワン・カルロヴィチに起こされる場面、つまり、世間に発表された『幼年時代』の第一ぺージに当たる部分が出てくる。だが、その書き出しは次のようなものだった。
「一八三三年八月十三日。いい日だった。イワン・カルロヴィチがいつもの通り七時半にわれわれを起した。二階の子供部屋は、手すりに囲まれた空間でニつの部分に分けられており、削ってはあるが、色は塗っていないその手すりには、われわれのシャツとズボンとシャツの胸あてが三組、それぞれ別に小高く積み上げられていた……」※1
これは普通の小説によくある描写だから、このまま書きつづけても一つの幼年時代の物語はできあがっただろう。しかし、この素朴な写実的、伝達的な書き方では、当時流行していた数多い自伝形式の小説と大同小異で、今われわれが読んでいる『幼年時代』のように、群小の作品から抜け出て、新鮮な印象を読者に与える作品にはならなかったに違いない。それに、もっと重要なことは、この方法では自分自身や人間を描くことはできても、トルストイが目ざしていた、人間の本質を追究することはできなかっただろう。人間を知るためには写実だけでなく、人間の内面をとらえ、表現しなければならない。トルストイ自身もそれを感じとっていた。
この時すでにトルストイは自分に写実の才能があることに気づいていたが、それよりむつかしい人間の内面の把握・表現には自信がなかったらしい。実は、人間心理の把握・表現にこそ、他の作家の追随を許さないトルストイの特徴があったのだが、若いトルストイは自分の未熟さを意識して、もっと勉強しなければならないと思った。五一年三月二十四日の日記に「記憶と文体を向上させるために、何か外国語からロシア語に翻訳しなければならない」と書いたのは、その意味である。この時点のロシアでは、ツルゲーネフもドストエフスキーもまだ大作を書いていなかったので、人間心理のとらえ方や表現の方法を勉強するには、西欧文学をお手本にするのが当然だった。この勉強のための翻訳はすぐには行われなかったが、その意図は一時の思いつきではなく、ロシアからカフカースまでもつづけられた。
第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P157-160
こうしてトルストイは外国作品の翻訳を通してさらなる作家修行を始めます。
若きドストエフスキーもバルザックなどの作品を翻訳して研鑽を積んでいたことを考えると、作家活動の王道としてやはり翻訳は重要なのだなと感じさせられます。
トルストイが修行の題材に選んだのは十八世紀のイギリスの作家スターンの『センチメンタル・ジャーニー』でした。藤沼貴著『トルストイ』ではこの作品とのつながりも詳しく語られるのですが、ここでは長くなってしまうので割愛しますが、トルストイはこの作品の翻訳修行を通して『幼年時代』を完成させていきます。解説を引き続き見ていきましょう。
トルストイの『センチメンタル・ジャーニー』の翻訳は第一章だけで終わり、それ以上は進まなかった。例の怠け癖が出てほうり出したのではない。このごろ(五二年五月)トルストイはすでにスターン的手法をかなりマスターしてしまっていて、もう学ぶ必要がなかったのだ。かれはその一年以上前の五一年三月、「何か外国語から翻訳しなければならない」と書いた翌日に、勉強を飛び越して、人間の内面をとらえるための習作にとりかかっていた。そして、かれは「生活の奥に秘められた部分をとらえようとして」、「きょうのこと」(のちに「きのうのこと」と改題)という題名で、一日のことを大小もらさず、時間と事象が流れるままに書いてみた。その手法はスターンと同じはずだったのに、若いトルストイのもとではうまく流れずメモ的な記述の集積になってしまった。そこで、かれは習作の内容を変え、二人の女性の偶然的で、これといった意味のない日常会話を流れるままに書いてみることにしたが、それもうまくいかなかった。このほかにトルストイが勉強のために書いた習作は今では残っておらず、その勉強の過程を具体的に跡づけることはできないが、かれが「奥に秘められたもの」を表現しようと努力をつづけ、短期間で急速に進化したことは間違いない。五二年六月に完成し、九月に世に出された(現代のわれわれも読んでいる)『幼年時代』の決定版の冒頭を見てみよう。
「一八……年八月十二日。私が十歳になって、実にすてきな数々の贈り物をもらってからちょうど三日目のこと、朝の七時に、カルル・イワーヌイチが私の頭の上ではえたたきをふるって―それは棒に砂糖の包み紙をとりつけたものだった―はえを打ち、私の目をさましてしまった。……《かりに》と私は思った。《ぼくが小さいからといって、何のためにぼくの気にさわるようなことをするんだ?……》」
これを一五九ぺージで引用した「私の幼年時代の物語」の相応の部分(※先の引用箇所の※1の箇所)と比較すると、その差は歴然としている。決定版の『幼年時代』のほうがはるかに生き生きしていて、読者はその場に居合わせるような気分になる。その感じだけで十分だが、あえて二つだけ理屈を言うことにしよう。
その理屈の一つは次のようなことである。「私の幼年時代の物語」に比べると、『幼年時代』では対象を見る目が複合的になり、そのために表現が立体的になっている。「私の幼年時代の物語」では、作者(トルストイ自身)は「まえがき」の部分が終わると引っこんでしまい、視点は成長した私(主人公)一つだけになる。一方、『幼年時代』では私(主人公)の視点が一つではなく、成長した今の私の視点と、幼年時代の視点と二つあり、さらに、それを整理統一する作者の視点がある。しかも、主人公は写実的に対象を見ると同時に、意識の流れに身をおいており、一人で二重の機能をはたしている。これらが組み合わされて、叙述の構成は四重になっている。それが生き生きとして厚みのある感じを読者に与えるばかりでなく、奥底にあるものを引き出してくれる。
もう一つ理屈がある。このように作品が進化したことは、視点がふえたといった量的なことだけではなく、それより重要な質的な変化が起こった結果である。若き作者トルストイは写実的に情景や人物の言動を描写・伝達するという意識の次元で進化しただけでなく、意識の流れに入りこむことで、意識下、無意識の次元でとらえがたいものをとらえるのに成功した。これはまさに革命的な進化であり、駆け出しの作家が一年ほどで、素朴なリアリズムからこのような文学的次元に駆けのぼったのはおどろくにあたいする。凡人ならほかの作家のものをたくさん読んで勉強したり、同人誌仲間にいじめられたり、出版社に原稿を提出して十五も年下の編集部員に乱暴に突っ返されたり、バーでご勉強中の先生の代作を数年かかっても到達できない次元である。トルストイがそれをあっという間に通過したのは、もちろん、非凡な文学的才能によるものだ。しかし、人間を知りたいという思いが人並みはずれて熾烈だったことも、急速な文学開眼につながったのだと思われる。
第三文明社、藤沼貴『トルストイ』P161-163
いかがでしょうか。この解説を読むと、トルストイのデビュー作『幼年時代』がいかにすさまじい作品であるかに驚くと思います。
この作品はトルストイ文学の原点であり、こうしたトルストイの文学的手法は後の作品にも貫かれています。
この小説はトルストイ作品の特徴を知るのに最もおすすめな入門書と言えるかもしれません。
また、主人公の「ぼく」を通した世界の描写。これも素晴らしいです。私たち大人は当たり前のように目の前の世界を認識していますが、子供から見た世界は私たちとは違って見えています。
世界は一つであるけれどもその状況によって見え方が全く異なる。そしてその意味するところも・・・
私たちが見ている世界を、子供という「私たちの当たり前とは違った」視点から描くことの新鮮さ、巧みさもこの作品では光っています。この作品を読めばトルストイの驚くほどの感受性、繊細さを感じることになるでしょう。
分量的にも文庫本で200ページ弱と、かなりコンパクトな作品です。文豪トルストイというと難解なイメージがあるかもしれませんが、この作品の語り口はとても読みやすいものになっています。
トルストイの特徴がどこにあるのかを知るにはこの作品は格好の入り口になります。
ぜひぜひおすすめしたい作品です。
以上、「トルストイ『幼年時代』あらすじと感想~ロシア文壇を驚かせたトルストイのデビュー作!」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事