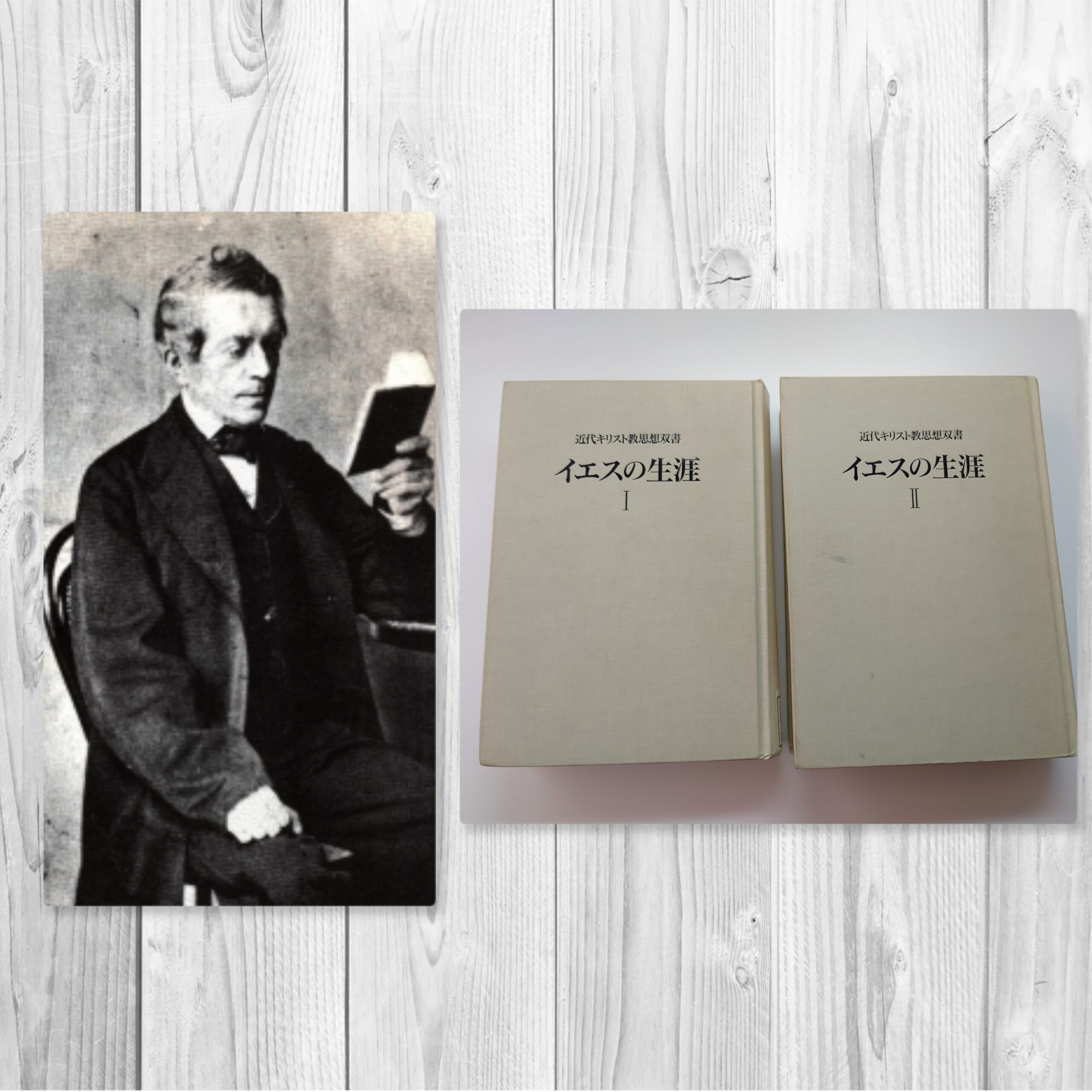目次
無神論者のバイブル、シュトラウス『イエスの生涯』概要と感想~青年たちのキリスト教否定と無神論へのの流れとは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ』(7)
上の記事ではマルクス・エンゲルスの生涯をざっくりと年表でご紹介しましたが、このシリーズでは「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」というテーマでより詳しく2人の生涯と思想を見ていきます。
これから参考にしていくのはトリストラム・ハント著『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』というエンゲルスの伝記です。
この本が優れているのは、エンゲルスがどのような思想に影響を受け、そこからどのように彼の著作が生み出されていったかがわかりやすく解説されている点です。
当時の時代背景や流行していた思想などと一緒に学ぶことができるので、歴史の流れが非常にわかりやすいです。エンゲルスとマルクスの思想がいかにして出来上がっていったのかがよくわかります。この本のおかげで次に何を読めばもっとマルクスとエンゲルスのことを知れるかという道筋もつけてもらえます。これはありがたかったです。
そしてこの本を読んだことでいかにエンゲルスがマルクスの著作に影響を与えていたかがわかりました。かなり驚きの内容です。
この本はエンゲルスの伝記ではありますが、マルクスのことも詳しく書かれています。マルクスの伝記や解説書を読むより、この本を読んだ方がよりマルクスのことを知ることができるのではないかと思ってしまうほど素晴らしい伝記でした。
一部マルクスの生涯や興味深いエピソードなどを補うために他のマルクス伝記も用いることもありますが、基本的にはこの本を中心にマルクスとエンゲルスの生涯についてじっくりと見ていきたいと思います。
その他参考書については以下の記事「マルクス伝記おすすめ12作品一覧~マルクス・エンゲルスの生涯・思想をより知るために」でまとめていますのでこちらもぜひご参照ください。
では、早速始めていきましょう。
信仰の危機
前回の記事「エンゲルス『ヴッパータールだより』~工場の劣悪な環境を18歳のジャーナリスト、エンゲルスが告発「マルクス・エンゲルスの生涯と思想背景に学ぶ」(6)」でお話ししましたように、エンゲルスは1839年、彼が18歳の時に『テレグラフ』誌に「フリードリヒ・オスヴァルト」というペンネームで『ヴッパータールだより』を投稿します。
この記事は彼の生地ヴッパータールの労働環境を痛烈に批判したものです。
この記事を投稿した直後のエンゲルスの手紙から今回のお話は始まります。
「ハハハ!『テレグラフ』の記事を誰が書いたか知っているかい?執筆者はこの文章の書き手だよ。でも、これについて他言はしないよう忠告する。とんでもなく厄介な目に僕が巻き込まれかねないからね」。エンゲルスの「ヴッパータールだより」はヴッパータール沿いで大いに歓迎され、世論の嵐を巻き起こした。クルマッハーへの詳細にわたる個人的批判は、敬虔主義と貧困とが結びついていることとあいまって強烈なものになった。
そして「フリードリヒ・オスヴァルト」は、この論争に有頂天になりつつも、まだバルメンの主要な息子たちの一人であることを暴露するだけの心の準備はできていなかった。そこで彼は安全なブレーメンから、ヴッパータールの一部の友人たちと仲間内でほくそ笑み、楽しむことで満足していた。
彼の文通相手は昔の同級生であるフリードリヒとヴィルへルム・グレーバー兄弟だった。彼らは正統派教会の牧師の息子たちで、自分たちも牧師になる訓練を受けていた。一八三九年から一八四一年までにエンゲルスが二人に書いた彼らしい率直な一連の手紙から、ブレーメンで暮らした年月のあいだにエンゲルスの知性面に生じた最も重要な変化を読みとることができる。信仰の喪失である。
社会主義への道が世俗主義によって開かれたというのは、十九世紀の精神史を扱う歴史学の決まり文句となっている。ロバート・オーエンからべアトリス・ウェブ、アニー・べサントにいたるまで、精神的な旅が新しい人類宗教となって頂点に達した人びとにとって、キリスト教の否定はお馴染みの通過儀礼となっていた。
しかし、キリスト教が見え透いたものになったからと言って、その真理に説得カがなくなるわけではない。「まあ、僕は一度も敬虔主義であったことはない。一時は神秘主義だったが、それは過去のことだ。いまでは正直者になって、ほかの連中とくらべればリべラルで、超自然主義だ」というのが、一八三九年四月にエンゲルスがグレーバー兄弟に信仰面における自分の気質を説明したものだった。
彼は長年、ヴッパータールの敬虔主義が奉じる偏狭な精神主義には不満を感じていたが、十九歳の時点では、キリスト教の中心的教義を否定するまでには、まだとうていいたっていなかった。ブレーメンの暮らしの知的リべラリズムのなかで、エンゲルスは自分の教会には予定説と地獄落ち以上のものを求めたいと感じるようになっていた。
原罪の考えに彼はますます悩まされるようになり、キリスト教から受け継いだものを、〈青年ドイツ〉から吸収した進歩的で合理的な考え方と、どうにか結びつけたいと願っていた。「率直に言おう。僕はいまでは理性の試練に耐える教えだけを、神聖なものとして見なすようになっている」と、彼はフリードリヒ・グレーバーに告げてから、聖書のなかの多くの矛盾を指摘し、神の慈悲について疑問を呈し、近年のクルマッハーの説教で語られた一連の天文学上の間違いを露呈させることに、とりわけ喜びを見出していた。
筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P58-59
※一部改行しました
この引用の後半部分は特に重要です。エンゲルスは簡単に信仰を捨てたわけではありません。
彼の地元や家庭の宗教事情については上の記事で見ていきました。
エンゲルスはそのような宗教には我慢ならなかったようですが、キリスト教そのものを捨てるのはまた別問題です。
「原罪の考えに彼はますます悩まされるようになり、キリスト教から受け継いだものを、〈青年ドイツ〉から吸収した進歩的で合理的な考え方と、どうにか結びつけたいと願っていた。「率直に言おう。僕はいまでは理性の試練に耐える教えだけを、神聖なものとして見なすようになっている」
エンゲルスのこうしたキリスト教との葛藤は非常に重要なものだと思います。後に宗教を厳しく批判するエンゲルスですが、その彼でさえ葛藤があったということ、そのことは彼を知るためにもポイントになると思われます。
では、そんなエンゲルスを無神論へと向かわせた決定的な契機とは何だったのでしょうか。それが次の箇所で語られます。ここは非常に重要です。当時の急進的な青年たちに絶大な影響を与え、無神論へと導いた書物があったのです。
シュトラウス『イエスの生涯』~実証的に聖書を研究し、奇跡を排除したイエス伝
一八三九年の夏には、信仰上の危機にたいする受け入れ可能な妥協案を、フリードリヒ・シュライアマハーの教えに見出したかもしれないと彼は考えた。シュライアマハーの説く贖罪の神学は、近代の理性の要求とも相容れる直感的な心の宗教に重きを置くもので、「偽善者の住む僕らの谷」の業火と池獄落ちとはまるで異なった信仰のように思われた。
エンゲルスにとって、シュライアマハーは「〈青年ドイツ〉の意味するところのキリストの言葉を教える」人だと言われていた。しかし、それすらエンゲルスが十九世紀初頭ヨーロッパの神学上の爆弾に出合ったのちは、色あせて見えた。
ダーフイト・フリードリヒ・シュトラウスの『批判的に検証されたイエスの生涯』は一八三五年から三六年に刊行され、多くの若者にとって恐ろしいほどの非宗教的な啓示となった。「この本が人におよぼした魔力は、筆舌に尽くしがたい」と、リべラルな哲学者ルドルフ・ハイムはそれについて語った。「いままでこれほど楽しく、徹底して本を読んだことはなかった……目から鱗が落ち、自分の道に一条の太い光が射し込んだかのようだ」
シュトラウスの書は聖書が文字どおり真実かどうかに、じかに疑問を投げかけたものだった。福音書は絶対に確かな聖なる書ではなく、むしろそれぞれの時代に歴史的および文化的に生みだされた偶然の産物なのだと彼は見なした。福音書はユダヤ人の神話、または人間の発展におけるどこか特定の段階を想像のなかで表現しており、したがっていまの時代には当てはまらないものとして接することが望ましい、と彼は断言した。
同様に、人物としてのキリストは、「人類」という概念の表現として最もよく理解されていた。『イエスの生涯』の影響は、聖書を知的探究および聖書研究のより厳密なプロセスにかけたことであり、エンゲルスは意気込んでその先頭に立った。
「僕はいま哲学と批判的神学で非常に忙しい。十八歳にもなって、シュトラウスを知るようになれば……何も考えずにすべてを読むか、あるいはヴッパータールの信仰を疑い始めるしかない」と、彼はグレーバー兄弟に気取って告げた。それから数カ月のあいだ、エンゲルスは何度も聖書の矛盾の話題に戻りつづけた。キリスト教の年表に新しい地質学的な発見が与えた衝撃や、原罪にたいする疑問などである。しかし、フリードリヒ・グレーバーへの手紙のなかで彼が語っているように、生まれたときから教化されてきたことを捨て去るのは、容易でもなければ、快いプロセスでもなかった。
僕は毎日、というよりむしろ、ほぼ一日中、真理を求めて祈っている。疑問をもち始めてからずっとそうしてきたが、まだ君と同じ信仰に戻ることはできない……こう書いているいま、僕の目は涙であふれている……確かに、君は温かいべッドにいるように、信仰のなかに気持ちよく横になっている。そして、神が神であるのかないのか、僕ら人間が決めなければならないときに、くぐり抜けなければならない争いのことは何も知らない。最初に疑問をいだいたときに感じる荷の重さも、昔の信仰の重荷も知らない。それに賛成するのか反対するのか、それを奉じつづけるのか、捨て去るのか決断しなければならないときに。
一八三九年十月には、疑念はなくなった。エンゲルスにはもう秋を思わせる「ドーヴァー海岸」〔マシュー・アーノルドがのちに信仰の危機を綴った詩〕の引き潮の憂鬱は感じられなかった。いったん決断が下されると、彼はその新しい精神的状態を楽しむようになった。「僕はもうシュトラウス主義者になった」と、彼はヴィルヘルム・グレーバーに淡々と告げた。「惨めなへボ詩人である僕は、天才ダーフィト・フリードリヒ・シュトラウスの翼の下に潜り込んだのだ……信仰よ、サラバ!信仰など海綿のように穴だらけなのだ」。
エンゲルスはのちにみずから述べたように、伝統的なキリスト教の見地から、「完全にすっかり逸脱」していた。そして、これまでどおり、彼は新たに選んだ立場をゆるぎない確信をもって支持し、フリードリヒ・グレーバーを「シュトラウス〔駝鳥を意味する〕主義者を狙う大狩人」だと揶揄した。
筑摩書房、トリストラム・ハント、東郷えりか訳『エンゲルス マルクスに将軍と呼ばれた男』P59-61
※一部改行しました

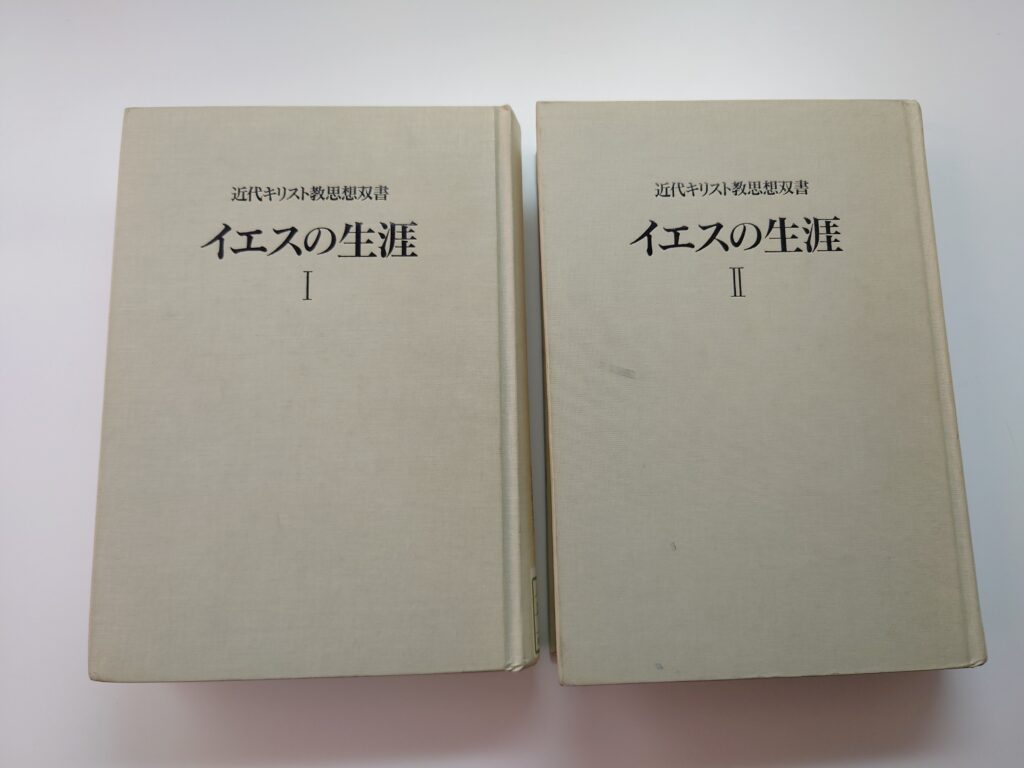
こちらがシュトラウスの『イエスの生涯』です。写真ではわかりにくいですが、かなり分厚い本です。
この作品は徹底的に奇跡を排して実証的にイエスの生涯を分析しています。有名なラザロの復活のシーンも、そもそもラザロは死んでいなく、仮死状態だったラザロをイエスが生き返らせたように見せただけだと述べます。数々の病気治癒も奇跡ではなく、実証的にそれはありうると考察していきます。
イエスは奇跡を操る超人間的な存在ではなく、あくまで我々と同じ人間であるという立場で書かれています。これはキリスト教の教義に真っ向から反論する立場です。
一九世紀半ばには科学技術の発展もあり、科学的に証明できなければ事実として認めないという流れができ始めていました。シュトラウスも、まさしくそうした立場からイエスの生涯を考察していったのでした。
この本については後に改めて紹介しますが、エンゲルスがこの本から受けた衝撃は上で見た通りです。彼が後に『空想より科学へ』という本を出すのもこうした「科学的」な思想に影響を受けたからと思われます。
エンゲルスにとってこの本がどれだけ衝撃的だったかがうかがわれます。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事