カルロ・コッローディ『ピノッキオの冒険』あらすじと感想~『ピノキオ』の原作は想像以上に残酷?ディズニー映画の見事な改変について考えてみた
さて、今回ご紹介するのは1883年にイタリアの作家カルロ・コッローディによって発表された『ピノッキオの冒険』です。私が読んだのは2003年に角川書店より発行された大岡玲訳版です。
今回この本を紹介しようと思ったのはディズニー映画の『ピノキオ』がきっかけでした。ここ最近私はディズニー関連の本を読んでいたのですがその流れでほぼ20年ぶりに映画の『ピノキオ』を観ることになりました。
改めてこの映画を観て驚いたのは『ピノキオ』がものすごく教育的な内容だったということです。あの遊園地の乱痴気騒ぎからのロバへの変身は今も昔も変わらず子供たちを恐怖のどん底に突き落としてきたことでしょう。
そして数々の愛すべきツッコミどころも忘れられません。
まず、ゼペット爺さんについて。
誕生したその翌日にピノキオを学校に送り出すという鬼のようなスパルタっぷりには笑わずにはいられません。そしてピノキオが遊園地から何とか帰り着いたら当のゼペット爺さんが海に出ていたという超展開。ゼペット爺さんの無邪気なぶっ飛びぶりは最高にエキサイティングです。
そして私も大好きな正直ジョンとギデオンのコンビですが、なぜこの2人(2匹?)は動物なのにごく当たり前のように人間世界に溶け込んでいるのでしょうか。映画を観ているとごく自然に彼らの存在を受け入れてしまいますが、よくよく考えてみると不思議ですよね。あ、でもジミニー・クリケットも喋っているではないか!ですが彼はあくまでピノキオの良心としての存在です。もしかすると人間世界において彼は認識されていないのかもしれません。そう考えてみるとやはり正直ジョンとギデオンの存在は不思議です。ですがそんな疑問も吹き飛ばすくらい彼らは魅力的です。彼らのやりとりには思わずクスっとせずにはいられません。特に彼らがピノキオを診察して病気に仕立ててしまうシーンは最高です。この2人は『ピーターパン』のフック船長とスミーに匹敵する名コンビですね。大好きです。
そして先ほども申しましたが悪童たちがロバに変身するあの恐怖の遊園地でありますが、これもよくよく考えると子供たちが不憫でなりません。なぜなら、彼らは「ここで何でも好きなことをしてもよい」という許可をもらった上であの乱痴気騒ぎをしたのですから・・・。彼らはたしかに元々悪童たちではあります。ですが、遊園地での狼藉は大人の許可をもらった上での行動です。これではもう子供たちの意思云々の話ではありません。あの遊園地に入ってしまった時点でゲームオーバーです。自分で悪いことをしたならまだしも、「やってもいいよ、好きにしちゃいないよ」と言っておきながら、その後で「お前たちは悪いことをしたからロバになるんだ」では如何せん厳しすぎます。まあ、日々の行いこそ大切なのだと言われてしまえばそこまでですが・・・
いずれにせよ、大人になって改めて観た『ピノキオ』に私はすっかり夢中になり、数あるディズニー映画の中でも上位に来るお気に入り作品となりました。
さて、そんな『ピノキオ』でありましたが、この作品について有馬哲夫著『ディズニーとライバルたち アメリカのカートゥーン・メディア史』で次のような解説がなされており、これがきっかけで私は原作を読もうと思い立ったのです。
『ピノキオ』の原作となったのは、イタリアの作家コッローディの同名の童話で、ウォルトはこれを、一九三〇年代の後半にたまたま行った書店で見つけている。これをベースにして面白い作品が作れると思ったウォルトは、すぐにスタッフに作品化に取りかかるよう命じた。原作はかなり長いもので、しかも、かなり残酷で荒々しい内容だった。
原作では、悪いことをした少年たちは単にロバになるだけでなく、皮をはがれて太鼓の皮にされるという目に遭っている。また、主人公に説教をするコオロギも、主人公をばかにしたということで、木槌で叩き殺されている。それをウォルトは、親たちが子供に安心して見せられる、教訓に満ちたストーリーに変えた。
フィルムアート社、有馬哲夫『ディズニーとライバルたち アメリカのカートゥーン・メディア史』P206-207
私はこの解説を読んで衝撃を受けました。コオロギが木槌で叩き殺されただって!?
『白雪姫』でもそうでしたがやはり原作はバイオレンスで残酷です。
そしてそんな残酷な物語を親子で安心して見られる映画に改変したウォルト・ディズニー。
私たちはウォルトが制作した完成品の『ピノキオ』を当たり前のように受け取っていますが、原作から映画まではものすごく遠い道のりがあります・・・!この変化をたどればディズニー映画の特徴がよりはっきりするだろう。そう思い私は『ピノキオ』の原作に強い関心を持ったのでありました。
では、ディズニー映画の原作『ピノッキオの冒険』について見ていきましょう。
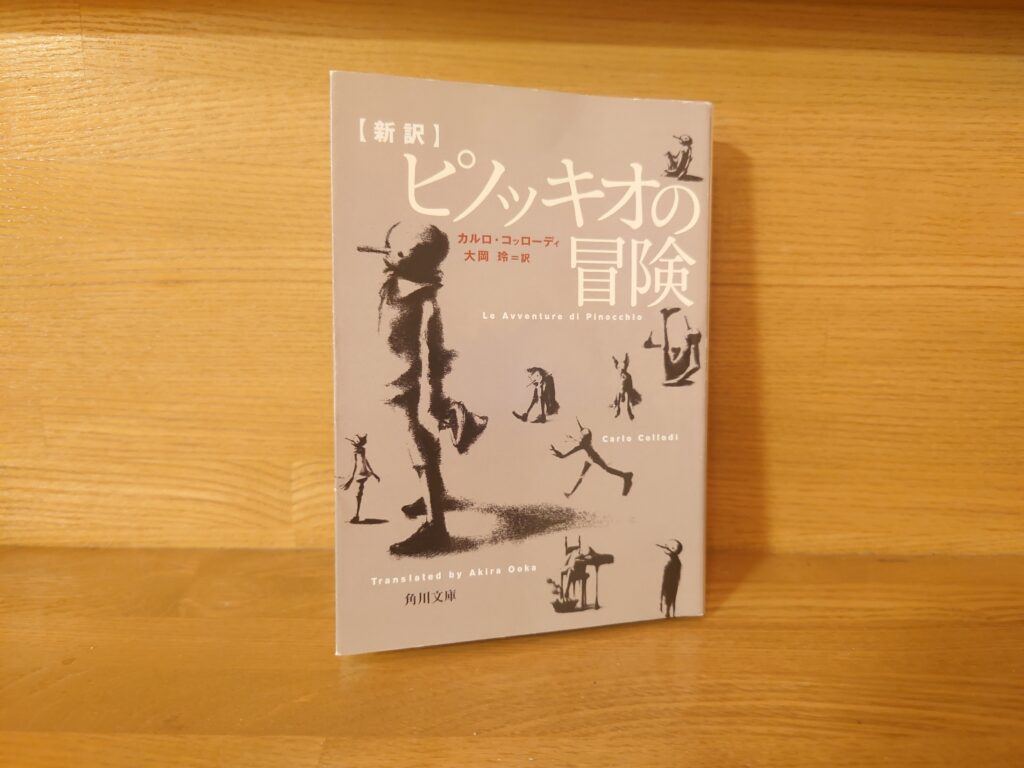
「ぼくだって、いつか人間になりたいよ…」イタリアで生まれ、世界中の子供たちから愛され読みつがれてきた、あやつり人形の物語。なにもかもが木で出来ているから、考える事もとんちんかん。自分を作ってくれた、かわいそうなおじいさんを想いながらも、いたずらを繰り返し、あれこれ事件を巻き起こす。あと一歩で幸せになれるというところで、いつも失敗してしまい―。芥川賞作家・大岡玲の新鮮な訳により、現代に蘇ったピノッキオ。生きることへの深く、鋭い洞察に満ちていることに、あらためて驚かされる、永遠の名作。
Amazon商品紹介ページより

『ピノキオ』の原作はイタリアの作家カルロ・コッローディによって1883年に発表されました。
上の解説にもありましたように本書はディズニー映画とはかなりの違いがあります。
まずその始まりからして強烈です。
なんと、ピノキオは最初ただの棒切れだったのです。大工のさくらんぼ親方の工房にあった棒切れが突然喋り始め、それに肝を冷やした親方が人形職人のゼペット爺さんに棒切れを譲ったのがきっかけだったのでした。
ディズニー映画のようなロマンチックな始まりとはえらい違いです。
そしてゼペット爺さんにはネコのフィガロも金魚のクレオもいません。彼らはディズニーの創作でした。
そして何と言ってもコオロギの殺害です。上の解説を読んで衝撃を受けましたが、私も心してその箇所を読みました。せっかくですのでその殺害シーンをここで見ていくことにしましょう。
「クリッ、クリッ、クリッ」
「だれだ、ぼくを呼ぶのは?」。ピノッキオはふるえあがっていった。
「わたしさ」
ピノッキオがふりむくと、まるまる太ったコオロギが目に入った。ゆっくりゆっくり、かべをはい登っている。
「なんだ、コオロギか。おまえはだれなんだ?」
「わたしは、ものをいうコオロギだよ。もう百年以上、この部屋に住んでるのさ」
「でも、今日から、ここはぼくの部屋なんだ」と、あやつり人形はいい放った。「ぼくをいい気分のままにしておきたいなら、さっさとでていくんだな。ふリかえったりせずにね」
「でてってもいいが」と、コオロギは答えた。「その前に、おまえさんに物事の大切な道理を教えてやらにゃならんのさ」
「とっとといえよ」
「親にさからって、勝手気ままに家を飛びだしたりする子は、気をつけたほうがいい。そんな子供は、決してしあわせにはなれないんだから。おそかれはやかれ、にがい後悔を味わうことになる」
「ふん、コオロギ野郎め、勝手なことを好きなだけほざいてろ。ぼくは、明日ここからでていくつもりさ。だって、いつまでもここでグズグズしてたら、ほかの子供たちとおんなじ目にあわされるからね。学校に行かされ、甘いことをいわれたりおどされたりしながら、むりやり勉強させられるんだ。はっきりいって、ぼくは勉強なんてだいっきらいなのさ。チョウを追いかけて走りまわったり、木のぼりして鳥の巣からヒナをとってきたりするほうが、ずっと楽しいからね」
「かわいそうに、おまえはバカなんだね。そんなことをしていたら、いずれ折り紙つきの大パカとして、みんなの笑い者になれるだろうよ」
「だまれ!このくそったれのでぶコオロギ!」と、ピノッキオはさけんだ。
しかし、がまん強く考えぶかいコオロギは、相手の失礼ないいぐさにも腹をたてず、同じおだやかな声でさとし続けた。
「学校が好きじゃないなら、なにか手に職をつければいいだろうに。そうすれば、パンのひときれくらいにはありつける」
「じゃあ教えてやるよ」と、だんだん頭に血がのぼってきたピノッキオが答えた。「この世でたったひとつ、ぼくのお気に入りの仕事がある」
「それはなんだね?」
「食べて、飲んで、寝て、遊びほうけて、朝から晩までのらくら過ごす生活さ」
「おまえさんのやり方にしたがって」と、決して変わらない静かな口調でコオロギはいった。「そういう仕事にはげんだら、末はまちがいなく慈善病院か牢屋行きだろうね」
「気をつけてモノをいえ、このくそったれのでぶコオロギ!……ぼくをあんまり怒らすと、ひどい目にあうぞ」
「哀れなピノッキオ!おまえさんがふびんでならないよ」
「どうしてふびんなんだ」
「なぜかって?そりゃ、おまえさんは木の人形で、おまけに脳みそまで木でできてるからよ」
この最後の言葉を聞くと、ピノッキオはカンカンになって飛びあがり、台の上にあった木づちをとって、ものをいうコオロギに投げつけた。
たぶん、ピノッキオだって、本気でぶつけるつもりはなかったはずだ。だが、まずいことに、木づちはコオロギの頭にまともにあたってしまった。気の毒にコオロギは、かすかにクリッ、クリッ、クリッと息もたえだえに鳴くと、壁にはりついたまま死んでしまった。
角川書店、カルロ・コッローディ、大岡玲訳『ピノッキオの冒険』P24-27
いかがでしょうか。ピノキオの悪童ぶりに驚いた方もおられるかもしれません。私もその一人です。ディズニー映画ではピノキオは無垢で世界を知らないお人よしだからこそ誘惑に負けてしまいますが、この原作では明らかに悪に傾いた存在として語られることになります。
そしてコオロギの死ですね・・・。
まさかこんなにあっけなく死んでしまうとは・・・しかもピノキオの手によって殺されるというのが何とも・・・。
実はこのコオロギ、ウォルト・ディズニーの当初の計画では映画に登場しない予定だったそうです。
こうした無残な死を迎えたキャラクターをわざわざ映画に出してもということだったのでしょう。しかしピノキオをより人間的に描く必要からこのキャラクターに登場を願うことになったのでした。ストーリーの構成上、無垢なピノキオを導く道徳的な存在が必要だったのです。
そしてその狙いは大成功。ジミニー・クリケットという名前を与えられ、見た目も小さな紳士の姿に変身させ、映画『ピノキオ』に欠かせぬキャラクターになりました。さすがウォルト。あっさり殺されてしまうコオロギを物語のキーパーソンに成長させたのでありました。
原作ではピノキオはこれから様々な出来事に巻き込まれることになります。誘惑されたとはいえそのほとんどが自業自得、ピノキオ自身が選び取ったものでありました。そこで毎回ひどい目に遭い、その度に「もう悪いことはしない。いい子になる」と反省するのですが、すぐにまた悪い方向へ行ってしまうのです。
正直ジョンとギデオンのコンビの原型となるキツネとネコのコンビも何度も登場します。ジミニー・クリケットもそうでしたが、原作では基本的に動物には名前がありません。ただその動物の名前だけが与えられています。見た目も動物そのままです。こうしてみると、ディズニーの特徴がここにも見えてきます。ディズニーは「擬人化」という伝家の宝刀を駆使しています。単なるずる賢いキツネとネコを個性的な正直ジョンとギデオンという名コンビに押し上げたのはこの絶妙な擬人化、コメディタッチにあります。残酷で暗い原作の雰囲気をこうして家族向けの明るいムードに変換させたのでした。
そして映画で一際印象に残るあの遊園地も原作に登場します。映画ではあっという間にロバ化が進みますが、原作ではなんとピノキオたちはそこで5カ月も遊び呆けて暮らしていました。そこでロバになってしまったあの友人も悲劇的な最期を遂げることになります。映画ではロバになっておしまいでしたが、原作では売り飛ばされ、こき使われて衰弱死という描写がはっきり出てきます。
最後に、映画でも最大の山場となる怪物クジラですね。なんと原作ではクジラではなく巨大サメということになっています。しかもその脱出方法もかなり地味です。油断したサメが口を開けている隙にそっと抜け出すという、なんとも映画監督泣かせの展開です。そう考えるとここもウォルト・ディズニーの才能が遺憾なく発揮されたシーンと言えるでしょう。あのクジラからの逃走は物語のラストにふさわしい劇的なシーンでした。
こうして原作を読んでみると、いかにウォルト・ディズニーが物語に手を加えているかがよくわかります。そして映画の『ピノキオ』を支えたのはウォルトのシナリオ改変だけではなく圧倒的なクオリティーと素晴らしい音楽の力もありました。ウォルトは1937年に公開され大ヒットした『白雪姫』の収益を利用し、260万ドルという当時としては前代未聞の予算をかけてこの作品を制作しました。この映画の素晴らしさについてクリストファー・フィンチ著『ディズニーの芸術』では次のように解説されています。
『白雪姫』の公開は、ディズニー・スタジオにとって驚異的な創作の時代の幕開けとなった。1940年2月から’42年8月までの間に、さらに四つのアニメ映画が公開された。なかでも最高傑作は『ピノキオ』(Pinocchio,1940)であるといわれている。
この映画は観る者が思わず息をのむような効果的なシーンで始まる。カメラは白い大きな光を放つ一つの星からぐんぐん手前に移動して、静まり返る夜の村の屋根の連なりを越え、やがてゼぺットじいさんの家の明かりのともった窓へと近づいていく。それは一瞬で消え失せる、派手なだけの見世物ではなかった。一言のせりふも始まらないうちに、観客を物語の世界に引き入れてしまう魔術であった。その瞬間から、映画は想像の世界の中で観客の心をつかんで離さなかったのである。(中略)
ピノキオの画面のレイアウトはことさらに独創的であったし、背景画も類を見ないまでにすばらしい。『白雪姫』に見られたように、アルバート・ハ一ターの影響がこの映画の中でも随所に感じられる。音楽が非常に効果的であったことも見逃せない。斬新さという点では『白雪姫』に一歩ゆずるかもしれないが、その出来は見事で、「困った時には口笛を」(Give a Little whistle)や「星に願いを」(When You Wish Upon a Star)などは圧巻である。どちらも作曲はリー・ハーライン、作詞はネッド・ワシントンである。
『ピノキオ』は巧みな物語の構成とアニメーターの優れた技術が相まってできあがった力作である。しかし批評家たちが絶賛したにもかかわらず、観客数の伸びは今一つであった。この映画の公開が第二次世界大戦勃発後5か月足らずのときで、民衆はこの種のおとぎ話など観る気分ではなかったのだろう。だが『ピノキオ』はただ面白おかしいだけの映画ではない。ハッピーエンドではあったがディズニーの作品の中でも特に、暗く悲しい面をもった最高傑作である。
講談社、クリストファー・フィンチ、前田三恵子訳『ディズニーの芸術』P59-61
「『ピノキオ』はただ面白おかしいだけの映画ではない。ハッピーエンドではあったがディズニーの作品の中でも特に、暗く悲しい面をもった最高傑作である。」
私もまさにそう思います。『ピノキオ』は単なる子供向けの映画でくくることのできない芸術作品です。
この作品には大人になった今だからこそ感じる素晴らしさがあります。
原作は原作で風刺的で教訓的な見事な作品であることも間違いありませんが、それをこれだけの映像作品に変身させたウォルト・ディズニーにはやはり脱帽です。ディズニーのすごさを感じるのに『ピノキオ』はピカイチです。ぜひ原作と映画をセットで堪能することをおすすめします。私もかなり衝撃を受けました。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「『ピノキオ』の原作は残酷?ジミニーを殺すピノキオ…ディズニー映画の見事な改変について考えてみた」でした。
本作『ピノッキオの冒険』のAmazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事





































