能登路雅子『ディズニーランドという聖地』あらすじと感想~信仰・巡礼の聖地としてのディズニーという刺激的な視点が魅力のおすすめ本!

能登路雅子『ディズニーランドという聖地』概要と感想~信仰・巡礼の聖地としてのディズニーという刺激的な視点が魅力のおすすめ本!
今回ご紹介するのは1990年に岩波書店より発行された能登路雅子著『ディズニーランドという聖地』です。
早速この本について見ていきましょう。
カリフォルニアの「魔法の王国」ディズニーランドとは、いったい何なのか。「ディズニーの国」との深いかかわりを通してその表と裏を知り尽くした著者が、絶大な人気の秘密を考察し、そこに満ちるアメリカの過去と未来、ファンタジーと超リアリズムを鋭く解剖する。「ディズニーの国」の東京・パリ進出にも説き及ぶ新鮮なアメリカ文化論。
Amazon商品紹介ページより

本書は1955年にアメリカ・カリフォルニア・アナハイムで開業したディズニーランドを中心に「ディズニーとは何なのか」を考察していく作品です。
そして本書タイトルにもありますように、本作は「聖地」「信仰」「文化」という側面からディズニーを見ていく点にその特色があります。僧侶である私にとってこれは非常に興味深いテーマであります。
著者の能登路雅子氏はアメリカ文化の研究者で、1980‐83年にウォルト・ディズニー・プロダクションズおよびオリエンタルランド社嘱託として東京ディズニーランド・プロジェクトに参加していたという、ディズニーの現場のスペシャリストです。
本書について著者は「序」で次のように述べています。
自分がそれまで何気なく見聞きしていた世界が研究上きわめて重要であることに気づいた私は、ディズニーに関する手に入る限りの文献を読み、その作業はハリウッド文化史を皮切りに、象徴、神話の領域へと徐々に広がっていった。ディズニーランドという対象は、奥を探れば探るほど得体の知れない怪物のような存在であり、しかもそれはアメリカ人の心のあり方や世界観と深いところで関わりあっていた。私にとって興味がつきないのは、遊戯やレジャー空間とのディズニーランドの姿であるよりは、アメリカ国民の多くがこの場所に寄せる特殊な、信仰にも似た想いであり、また、そのような民族色の強い文化遺産が、一方で世界に広がっているという現象である。
この場所については、すでに多くの人がさまざまな視点から多くを語っている。特にこの一〇年間、アメリカにおいては、社会評論家、建築家、文化人類学者、アメリカ研究者などによるディズニーランド論が活発に展開されている。また日本国内では、東京ディズニーランドに関する著書も多数出版されている。私はこの本で、ひとりの日本人として、ディズニーが創り出したテーマパークがどのような文化的意味をもつかを、その草創期に立ちかえって解き明かしてみたいと思う。
岩波書店、能登路雅子『ディズニーランドという聖地』P14-15
「私にとって興味がつきないのは、遊戯やレジャー空間とのディズニーランドの姿であるよりは、アメリカ国民の多くがこの場所に寄せる特殊な、信仰にも似た想いであり、また、そのような民族色の強い文化遺産が、一方で世界に広がっているという現象である。」
本書はまさにこのことについて文化人類学的、社会学的に深く掘り下げていきます。はっきり申しましょう。「この本はものすごく面白いです・・・!」
私が印象に残っている箇所をいくつか抜粋します。前後の脈絡まではここでお伝え出来ないので少しわかりにくいかもしれませんが、以下の引用を読んで頂ければこの本の雰囲気を感じられると思います。
三次元の演劇空間としてのディズニーランド
ディズニーランドとは、一体、誰のために何の目的でできたものなのか—。それは、もともと、子供を相手に作られた遊園地ではなかった。ウォルト・ディズニーが対象として頭に描いていたのは、第一に、すべての人間のなかに潜む「子供性」ともいうべき部分であった。アメリカの大衆文化には、子供というものを年齢を超えた普遍的存在とみる伝統がある。この国の愛唱歌には、たとえば有名な「クリスマス・ソング」のように、「一歳から九二歳の子供たち」といった表現がよく出てくるし、アメリカが生んだ大サーカス団「リング・リング・サーカス」のショーは、「紳士淑女の皆さん。あらゆる年齢のお子さん方」という歓迎の決まり文句で始まる。
ディズニーが「哲学」と呼ぶべきものをもっていたとしたら、その根底には、人はいくつになっても子供の無垢な心と好奇心を失わないという、きわめて素朴な人間観が流れていた。
岩波書店、能登路雅子『ディズニーランドという聖地』P30-31
ディズニーランドという場所そのものの本質を理解するうえで忘れてならないのは、その発案者ウォルト・ディズニーの本職が映画のプロデューサーであったという事実である。デイズニーランドは、彼が三〇年間の映画作りで学んだ手法のすべてを土台とし、さらにそれを発展させた「作品」であった。ディズニーランドをひとつの立体スクリーンと見立てたディズニーは、自分が語る物語の世界に人々を誘いこみ、ひとつのシーンから次のシーンへと移動させていくことを考えていた。
アメリカのSF作家レイ・ブラッドベリは、ディズニーランドが映画と演劇の世界を融合させた新しい娯楽形態であると指摘している。(中略)
なるほど、ディズニーランドという場所は二次元のスクリーンではなく、三次元の舞台であり、生きた人間がさまざまな役柄を演じるという点では、演劇の世界に通ずるものがある。園内の客の眼に触れる部分が「オン・ステージ」、それ以外の部分が「バック・ステージ」と呼ばれているのも、ディズニーランドのそうした劇場性を物語る。しかしながら、演劇のもつ偶然性は完璧主義者であるウォルト・ディズニーにとっては回避すべき深刻なリスクであり、彼の関心は生ま身の出演者に毎回いかにして同じ完璧な演技をさせるかに向けられた。当初、計画されていたジャングルの野生動物が機械仕掛けの動物に変更され、また園内のアトラクションが次第にロボットを主役とするエレクトロニクス空間に様変わりしていったのも、完璧な演技と正確な反復性に対するディズニーのこうした傾斜を反映している。ディズニーランドは、それゆえ、映画というメディアがもつ統制力を三次元空間に応用した一大実験であったと考える方が妥当と思われる。
岩波書店、能登路雅子『ディズニーランドという聖地』P33-34
ここに出てきたSF作家レイ・ブラッドベリはあの『華氏451度』の作者です。

大衆文化の危険性を本書で指摘したブラッドベリその人がディズニーの大ファンを公言し、さらには上のような分析をしていたというのは非常に興味深いです。
また、「ディズニーランドという場所は二次元のスクリーンではなく、三次元の舞台であり、生きた人間がさまざまな役柄を演じるという点では、演劇の世界に通ずるものがある」という指摘も重要です。私はこの解説を読みバチカンのサン・ピエトロ大聖堂を連想してしまいました。

バチカンのサン・ピエトロ大聖堂といえば誰もが知る美の殿堂として名高いローマカトリックの総本山でありますが、実はこの建築もまさに巡礼者を取り込む演劇空間を意識した構造だったのです。その三次元空間を構想したのが17世紀に活躍したベルニーニという建築家でした。

なんと、彼もウォルト・ディズニーと同じように、単なる建築家ではなくまさにプロデューサー的な資質を持った人物だったのです。彼は幼い頃から彫刻家としてミケランジェロ級の才能を発揮し、デッサンも超一流、演劇の脚本を書いては自ら演じ、さらには多数の人員を指揮して前代未聞の大プロジェクトを実行していくというまさにウォルト的な才能を持った人物でありました。
彼がいなければ今のサン・ピエトロ大聖堂やローマの景観はありえなかったと言っても過言ではありません。彼はまさにローマを演劇的空間に作り替えてしまったのです。
私はこうしたベルニーニの宗教的空間作りに感銘を受け、2022年にローマを実際に旅しました。そして私が数年来研究を続けてきたドストエフスキーと重ね合わせて考察したのが以下の記事です。

ここでは話がそれてしまうのでこれ以上はお話しできませんが、私にとってウォルトが作ったディズニーランドはベルニーニのサン・ピエトロ大聖堂と重なるものを感じてしまうのでした。そういう意味でも本書『ディズニーランドという聖地』は非常に示唆に富む作品でした。
ディズニーランドの自然観
引き続き本書を読んでいきましょう。少し長くなりますがディズニーの自然観についての非常に興味深い指摘ですのでじっくり読んでいきます。
自然に対して幾世代にもわたって培われた独特の姿勢や感じ方は、たとえ自然自体や人間生活が変わってもかなりの慣性をたもちつづけるものである。(中略)ここで重要なのは、ウォルト・ディズニーが少年時代を過ごしたころの中西部の大平原では、人々が現実に砂嵐や泥と格闘していたということである。ウォルトの兄ロイは、ちなみに前述のメニンジャーと同じ一八九三年の生まれである。
広大なアメリカ大陸の真ん中の、まさに恐怖空間ともいえる生活環境に暮らす人間たちが、自然の脅威の存在しない安全で清潔で快適な世界に強烈な憧れを抱いたであろうことは、想像に難くない。そのような人間のひとりであったウォルト・ディズニーに初めて成功をもたらした漫画の主人公が清潔で楽天的なネズミであったことは、これまでもたびたび指摘されてきたように、きわめて象徴的である。
周知のように、ミッキーマウスはネズミらしからぬネズミである。彼は汚らしい現実のネズミ族とはちがって、赤い半ズボンに黄色い靴をはき、四本指の手には真っ白の手袋をはめている。ミッキーマウス映画、それも特に初期のものは、農場や田園を舞台にしたものが多いが、それらは例外なく緑豊かで平和な牧歌的風景である。登場する動物キャラクターたちも、美しい彩色とともにピカピカに磨きあげられ、いつも愉快な珍騒動を繰りひろげる。人間の言葉を話す彼らは、ほとんど動物性をとどめていない。雄と雌のちがいも、ズボンとスカート、長いつけまつげやリボンといった記号に集約され、これらの衣装を剥ぎとれば、それらはいずれも無性である。ディズニーの作品世界の大きな特色は、自然の徹底的な否定と狂信的とさえいえる衛生思想なのである。
「ディズニーの国」が「塵ひとつない清潔そのものの世界」として人々の称賛を浴びてきたことは、こうした精神のもたらした結果のひとつといえる。そこには、泥や埃と戦いつづけた中西部農民の執念が反映されている。ディズニーランドの入口から向かって左手にある「フロンティアランド」は、ミシシッピ河流域地方の開拓時代をテーマとしているが、その地面は砂塵の舞う赤茶けた土ではなく、赤茶色に着色したアスファルトであり、砂も埃も入りこむすきがない。園内の川も海も湖もコンクリートで塗り固めたもので、水が泥で汚れることはない。
こうした例に限らず、ディズニーランドは地面も山も川も含め、全体がコンクリートやアスファルトで覆われた反自然的世界に仕上がっている。ここが昔、一六〇エーカーのオレンジ畑であり、造成工事の第一歩が何万本ものオレンジの木をすべて根こそぎ取り除く作業であったことの意味は、きわめて重要である。自然の地形や植物を十二分にとりいれた日本の伝統的な造園とは根本的に異質な精神が、そこでは底流をなしているのである。オープン以来すでに三五年を経たカリフォルニアのディズニーランドでは、オレンジにかわって植え込まれた大量の樹木がかなり成長しているために、一見したところ、その人工的な本質があまり感じられない。しかし、それはより新しいフロリダのウォルト・ディズニー・ワールド、あるいは東京ディズニーランドに明確に見てとれる。
樹木や草花はディズニーランドの美しさを演出する重要な要素であるが、これとても自然のままの勝手な成長は許されない。それは置かれた場所のテーマや目的が何であるかによって、形や大きさを整えられ、ディズニー・ショーの小道具として大事な役割を負わされている。このことは、自然の木でも人工の木でも変わりはない。(中略)
すべての要素がつねにベスト・コンディションに保たれているディズニーランドにおいて、枯葉やしおれた花はタブーである。樹木はほとんどすべて落葉しない常緑樹であり、花は毎日のように満開状態のものに植えかえられる。「ディズニーの国」の植物の運命は、ミッキーマウスの笑顔に形づくられた正面ゲートの巨大な花壇に集約されている。
動物のあり方は、植物のそれよりさらに自然から遠い。「ディズニーの国」においてはネズミも象もライオンも恐竜もすべて安全で愉快な人間の味方である。「アドベンチャーランド」のなかでも最も冒険的な「ジャングル・クルーズ」で人々が遭遇する猛獣たちも人畜無害な機械人形であるし、密林のなかには蠅も蚊もいない。そしてジャングルの裏手のトイレも、水洗で清潔そのものだ。危険な動物もばい菌も悪臭も、ここでは文明人の快適と娯楽のため、徹底的に飼いならされ、無菌化、無臭化されている。
このような世界は、ウォルト・ディズニーが三〇年にわたってアニメーション映画で追求してきたものの延長線上にあるが、その淵源をさらにたどれば、大平原を切りひらいたアメリカの開拓者たちの生活意識に行きつく。自然を恐れ、敵視した彼らの世界観からすれば、自然状態が存在しないディズニーランドは、まさに天国と映るにちがいない。ディズニーという人物の不気味さは、そうした現実には到底ありえない場所を、巨大資本を投じて出現させ、それを「地上で一番幸せな国」と信じて疑わなかったことにある。
岩波書店、能登路雅子『ディズニーランドという聖地』P77-81
「ディズニーの作品世界の大きな特色は、自然の徹底的な否定と狂信的とさえいえる衛生思想なのである。」
これは興味深いですよね。私達日本人は自然と共存していく文化を持っていますがまさにその逆の発想です。そしてこの引用の直後にも指摘されていましたが、今やその日本もこうした反自然というディズニー化が進んでいるとのことでした。たしかにそうですよね。私達は今やあまりに無菌化を望み過ぎているように感じます。ディズニーランドといえばゴミ一つない清潔空間というイメージがありますが、この清潔信仰の裏にあるものを知れるのも本書の魅力です。
民間信仰としてのディズニー。永遠の子供という夢。老いと死を否定する世界観
そして最後にもうひとつ。これも見逃せない重要な指摘です。
「ファンタジーランド」のアトラクションの大半は、こうした勧善懲悪の昔話や童話を題材にとっており、善が悪の追跡から逃れて安全な世界に戻るという基本的な筋立てになっている。ここで悪を代表するのは、魔女、トランプの女王、海賊船の片足の船長、サーカスの団長といった魔法や権力、邪心をもった醜い大人であり、一方の善は美しく純真な子供である。これらのアトラクションを体験する老若男女の客たちは、入念に仕掛けられたディズニーの魔術によって「あらゆる年齢の子供」に変身し、全員が一緒になって邪悪な大人に追われる子供の役割を演じる。どの物語においても、子供の味方となるのは、妖精やこびと、森の小動物、昆虫といった空想上の小さな生き物で、それらの助けを借りて子供たちは最終的な勝利をおさめる。同工異曲ともいえるこのようなアトラクションの反復体験は、知らず知らずのうちに、訪問者たちにいくつかの魅力的なメッセージを伝えている。
「どんなに恐ろしいものでも、我々を滅ぼすことはない。」
「我々の肉体は老いも衰弱も死も超えて、永遠に若く美しい。」すでにみたように、ディズニーランドは人間の意のままにならない自然の力を敷地から放逐した理想的な人工世界である。人間についても、これとまったく同じことが行われている。つまり、ここは現実の人間が成長とともに知る汚れ、老醜、そして死という生物学的法則を頭から否定した超自然世界なのである。生者必衰の運命を背負った人間が太古の昔から追い求めてきた不老長寿、起死回生の奇跡といったすこぶる重大な主題が、陽気なこびとや妖精の助けによって、このように無邪気に、このように単純明快に語られる世界が、人々の心をとらえるのは当然である。
映画もテーマパークも含めてディズニーの作品を観客大衆が「理屈ぬきに楽しい」と喝采し、批評家たちの多くがディズニーに脱帽してきたのは、ディズニーが通常の批評能力の到底およばないお伽話の世界という大鉱脈を掘りあて、自らの錬金術にひたすら磨きをかけつづけたからにほかならない。(中略)
ディズニーの錬金術はこうして大衆の心も知識人の分析能力をも、まさにメロメロに溶かしてきた。
波書店、能登路雅子『ディズニーランドという聖地』P115-118
「ここは現実の人間が成長とともに知る汚れ、老醜、そして死という生物学的法則を頭から否定した超自然世界なのである」
これぞまさにディズニーランドの本質を言い表しているのではないかと私も思います。
そしてこのことがなぜ重要かというと、まさにこの「老いと死の否定、永遠の生」こそ人類が求め続けてきた究極の願望であり、あるいは苦しみの原因であり、さらには宗教の説く教義の根本に据えられるものだからです。
これぞディズニーランドの究極の魅力であり、だからこそ「大衆の心も知識人の分析能力をも、まさにメロメロに溶かしてきた」のでありました。その究極の例として挙げられるのがあの三島由紀夫です。

彼も1960年にカリフォルニアのディズニーランドを訪ね、メロメロに溶かされた一人なのでありました。三島自身、老いと衰えを強く嫌悪し、若さを賛美していました。そして45歳で自刃し、その命を終えています。私はまさにこの三島由紀夫とディズニーについての関係を学ぶためにディズニー関連書籍を読み始めたのでした。いずれこのことについては改めて記事にしたいと思いますが三島を知りたい私にとって大いなる示唆を与えてくれたのが本書でした。
※2024年8月追記
三島由紀夫とディズニーについての関係についてまとめたのが以下の記事になります。ぜひご参照ください。
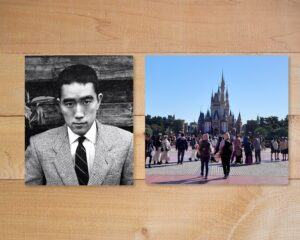
他にもご紹介したい箇所が山ほどあるのですが、記事の分量上それもかないません。興味の湧いた方はぜひ本書を手に取って頂ければと思います。新書でこれだけのことがまとめられているというのはかなり奇跡です。これほどの本にはなかなかお目にかかれません。ディズニーファンだけではなく、文化や宗教に関心のある方にもぜひおすすめしたいです。
以上、「能登路雅子『ディズニーランドという聖地』~信仰・巡礼の聖地としてのディズニーという刺激的な視点が魅力のおすすめ本!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事
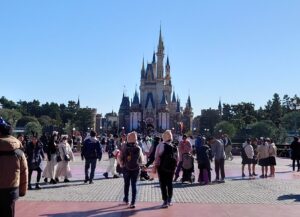












コメント
コメント一覧 (2件)
上田様
まずは、ご挨拶させてください。
東京にて中国の伝統芸能京劇を学び、芸能娯楽と宗教の領域を軸に、文化のチカラで自分のための生きやすい避難所(テーマパーク)を社会に作ろうと妄想している、とある会社の平社員です。たまたま教育関係の記事から『ディズニーランドという聖地』と言うタイトルを知り、ググったところ、上田様のページに初めて流れ着くことができました。
上田さまの記事のおかげで、劇場都市ローマなど個人的に初見の視点に出会えて楽しく学ばせていただきました。
おわりに、コメント欄をちゃんと用意してくださる、読手心情へのそのご配慮に深く感じ入りました。篤く御礼申し上げます
カトウ様
コメントありがとうございます。
嬉しいお言葉ありがとうございます。とても励みになります。
私自身、ディズニーの歴史を調べていて驚くことばかりでした。
今後ともよろしくお願いします。