O・ファイジズ『ナターシャの踊り ロシア文化史』あらすじと感想~ロシアの文化・精神性の成り立ちに迫るおすすめ参考書!

O・ファイジズ『ナターシャの踊り ロシア文化史』概要と感想~ロシアの文化・精神性の成り立ちに迫るおすすめ参考書!
今回ご紹介するのは2021年に白水社より発行されたオーランドー・ファイジズ著、鳥山祐介、巽由樹子、中野幸男訳の『ナターシャの踊り ロシア文化史』です。
早速この本について見ていきましょう。
ロシア文化を主人公とした一大叙事詩
「ロシアは頭ではわからない」――「ロシア」をめぐるイメージ=神話の典型のひとつだ。本書では、そうした「ロシア」という「神話」が生み出してきた豊饒たるロシア文化の歴史が、国家や社会を主体とするマクロな歴史を縦糸、個人の生に関わるミクロな歴史を横糸として織りなされる。文学、音楽、美術、演劇、バレエといった大文字の文化のみならず、宮廷の様子や農村の習慣、食や入浴文化、フォークロアまで、ロシア史のさまざまな局面における日常生活を垣間見られるのも本書の魅力だ。
Amazon商品紹介ページより
本書が射程に入れるのは、1703年のピョートル大帝による新都建設から、1962年のストラヴィンスキーの亡命先からの一時帰還という250年を超える時間であり、さらに亡命ロシア人社会にもその筆は及んでいるため、膨大な時空間にわたる「ロシア文化」を読者は旅することになる。「ロシア文化」において「ロシア」という「神話」がいかに大きな問題として底流にあったのか、また逆に「ロシア」という「神話」を支えるのにいかに「文化」が重要な役割を担ったのかを、本書で描かれる人物たちを追体験しながら感得することになるだろう。
まずはじめに述べさせて頂きます。
「この本は素晴らしいです!びっくりするほど面白いです!」
この本は間違いなく名著です。これだけの本にお目にかかれるのはめったにありません。
ロシアの文化、ロシアの精神性を学ぶのに最高の本です。
私個人としては、この本を読んで特に印象に残ったのはオプチナ修道院についての記述です。

以前当ブログでもオプチナ修道院のことは紹介しましたが、この修道院は晩年のドストエフスキーが訪れた、ロシアのとても名高い修道院で、あの偉大なる文豪トルストイも何度も足を運んでいます。
今作の『ナターシャの踊り』ではチェトヴェーリコフの本よりもさらに俯瞰的にオプチナ修道院のことが解説され、この修道院がいかにロシア人のメンタリティーに影響を与えたのかが語られます。
単にオプチナ修道院の歴史だけを見ていくのではなく、ゴーゴリ、ドストエフスキー、トルストイらとの繋がりからロシア人のメンタリティーを探っていくというのが非常に興味深かったです。これはドストエフスキーのキリスト教理解を学ぶ上でも非常に重要な視点を与えてくれると思います。
他にもこの本では興味深い内容がどんどん出てきます。正直、この記事では紹介しきれません!この本はすごすぎます!
最後に、この本の特徴について書かれた訳者解説を紹介します。少し長くなりますがこの本の長所がわかりやすく説かれていますのでじっくりと見ていきましょう。
本書の特徴としてまず挙げられるのは、その活き活きとした語りである。
著者ファイジズはプロの歴史研究者だが、本書は学術書ではなくあくまで一般の読者に向けた啓蒙書として書かれており、読み物としての面白さが強く意識されている。
本書を通読する読者は、さまざまな人物の波乱万丈のエピソードに次から次へと惹きつけられ、あたかも大河小説を読んだかのような読後感を得るだろう。
一方でそれらの物語は、ピョートル改革、ナポレオン戦争、デカブリストの乱、農奴解放、ロシア革命、独ソ戦など、登場人物たちを翻弄する歴史上の大事件とも緊密に結びついている。
国家や社会を主体とするマクロな歴史を縦糸、個人の生に関わるミクロな歴史を横糸とした織物のようなこの構成は、『囁きと密告』などファイジズの他の著作とも共通する特徴である。
しかしながら、本書の独自性は、ロシアの文化や歴史についての既に知られたストーリーをそのように面白く語り直した点に尽きるわけではない。本書がロシア文化史を扱う本としてユニークな存在であるのは、一般読者向けに書かれていながら、「ロシア文化」という概念そのものの自明性を問い直し、その概念が作られてきたメカニズムに意識的に焦点を当てているからである。
白水社、オーランドー・ファイジズ、鳥山祐介、巽由樹子、中野幸男訳『ナターシャの踊り ロシア文化史』下巻P419-420
※一部改行しました
さらに訳者は続けます。
「ナターシャの踊り」が意味するもの
「ナターシャの踊り」という、想像をかき立てる本書の標題は、序章で明らかにされるようにトルストイの小説『戦争と平和』の有名な一場面に由来している。
小説の主人公の一人、貴族ロストフ家の令嬢ナターシャが、猟のあとで森の中にある「おじさん」の丸太小屋を訪れる。バラライカの音色や民謡の調べを耳にした彼女は、「おじさん」に促されると農民のような身のこなしで踊り出す。むろん、伯爵家に生まれ育った彼女がそんな踊りを習い覚える機会など、それまでにあったはずがない。
では「どうしてナターシャは踊りのリズムをこれほど直感的にわがものとすることができたのか?どうして彼女は社会階層によっても教育によっても自分から隔たっている農村文化に、これほどたやすく入り込むこができたのか?ロシアのような国は生まれながらの感性という目に見えない糸でひとつにまとまっているのかもしれないと考えるべきなのか?」(本書一七頁)
本書の冒頭でこのエピソードが紹介されるのは、ファイジズがそこに本全体のコンセプトと共鳴する象徴的な光景を見ているためである。
十八世紀初頭のピョートル改革をきっかけとして、ロシアではヨーロッパ化したエリートと従来の生活習慣の中にとどまる民衆との文化的な隔絶が決定的となった。トルストイの描く上記の場面で前提とされているのもその点である。
一方、そこで問題となるのは、ロシアの社会がそのように分裂を抱えていたのであれば、彼らの文化をまとめて「ロシア文化」と称することがどうして可能なのか、そもそも「ロシア文化」とは誰によって担われていたのか、といった点である。
実際、『戦争と平和』が描いた時代の、ヨーロッパ式の教育を受けフランス語を日常語とした首都の上流貴族にとって、自分の領地の農民よりも遠い西欧のエリートの方が文化的に近い存在と感じられても不思議ではなかっただろう。
ファイジズは本書を通じてそんな根源的な問題に読者の注意を促している。本書が前提とするのは、「ロシア性」というものが決して時代を超えて普遍的に存在する実体ではなく、歴史上の諸局面で人びとの意識の内に「作られてきた」概念である、という認識である。もっとも、著者の狙いはこの概念を虚構に過ぎないとして退けることではない。むしろこの虚構がいかに豊かな文化を生み出してきたか、また逆にこの概念が作られ伝達されるプロセスにおいて文化がいかに重要な役割を担ってきたか。この観点から二五〇年にわたるロシア文化史を描いたのが、本書『ナターシャの踊り』なのである。
従って、ここにはロシア文化史を彩る多くの固有名詞が登場するが、その主眼はあくまでロシア文化の「ロシア性」を形作っている要素を浮き彫りにすることにある。著者も序章で述べているように本書の目的は包括的な歴史記述ではなく、そのため重要な文化人にそれに見合った紙面が割かれていないことも多い(チャイコフスキーの扱いがムソルグスキーやストラヴィンスキーなどに比して小さいことなどはその一例であろう)。本書の最大の主人公は「ロシア文化」という概念そのものなのである。
白水社、オーランドー・ファイジズ、鳥山祐介、巽由樹子、中野幸男訳『ナターシャの踊り ロシア文化史』下巻P420ー421
※一部改行しました
いかがでしょうか。この解説を読むだけでワクワクしてきますよね。ものすごく刺激的な内容です。文化はいかにして生まれてくるのか。それは自然発生的なものなのか、人為的なものなのか、はたまた相互作用的なものなのか・・・
こうしたことを幅広い視点からじっくりと考えていくのがこの本の最大の特徴です。ものすごく面白いです。
ロシアの文化、精神性を学ぶのに最高の1冊です!2021年、素晴らしい作品が登場しました!これはぜひぜひおすすめしたい作品です!
以上、「O・ファイジズ『ナターシャの踊り ロシア文化史』ロシアの文化・精神性の成り立ちに迫るおすすめ参考書!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事





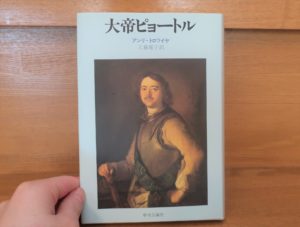






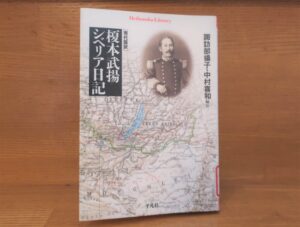



コメント