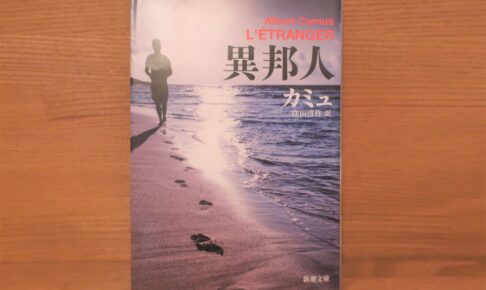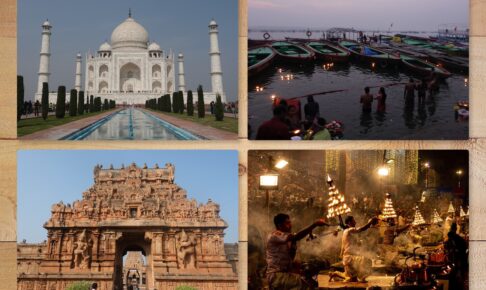目次
トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑷
今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。
私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。
スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。
こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。
異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。
そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。
ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。
この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。
では早速始めていきましょう。
拷問の効果ー人々に恐怖を植え付け、全体主義主義政治を行いやすくなる
異端審問官による拷問の実際の効果は、いくつもの裁判に見ることができる。コロンビアのカルタヘナでは一六三五年、アントニオ・ロドリゲス・フェレリンがポトロ(※拷問台 ブログ筆者注)に寝かされた。彼は「ロープが縛られ、脚のロープが一団締め上げられると途端に気絶して冷や汗を流し、何も言わなくなった。ロープがきつくなっても、不平も言わなければ返事もせず、拷問は延期せざるをえなくなった」。
一六三九年にぺルーのリマでは、マヌエル・バウティスタ・ぺレスの裁判中、フアン・デ・アセべードが泣きじゃくりながら異端審問官に近づき、「私は拷問に耐える勇気も体力もなく、そのため拷問室でいくつも嘘をつきました。(中略)もし拷問室に戻されたら、弱さと絶望から、嘘を重ねてしまいます」と訴えている。
アセべードやフェレリンの事例から分かるように、異端審問官の行動は宗教の世界をはるかに超えて、集合的恐怖の領域にまで入ってきていた。実際、拷問で集められた「証言」には重大な欠陥があったが、そんなことは当局にとってはどうでもよく、むしろ、このような恐怖を作り出すことのほうが重要だった。一七世紀後半でさえ、異端審問による拷問件数は実際には大幅に落ちていたのに、人々は誰もそう思っていなかった。詳しくは後述するが、恐怖のため言いなりになる態度は、この時期までに人々の心にしっかりと植えつけられていた。
そして恐怖は、改めて言うまでもなく、全体主義的傾向を強める国家にとっては権力を強化するのに好都合な道具である。なぜなら、いったんしっかりと植えつけてしまえば、いつでも好きなときに恐怖を煽り、その矛先を、政治や経済面で頭痛の種となっている存在に、勧善懲悪の闘いという名目で向けることができるからである。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P119
※一部改行しました
拷問による証言が真実がどうかはもはや関係なく、重要なのは国民に恐怖を植え付けることでありました。
スペイン王朝はそれによって権力の維持を図っていたのです。
疑わしきは罰せよ

プラド美術館所蔵、ベルゲーテ『異端審問』Wikipediaより
やがて異端審問所も気づくことだが、敵を作り出すこと自体はそれほど難しくない。その後に生じる問題のほうが、実は解決不可能なのだ。それまで真面目なカトリック信者だった人間が、異端審問に投獄されたのをきっかけに教会の敵になる―その好例が、一五九四年エヴォラの異端審問所に逮捕されたイザべル・ロぺスだ。
彼女は司祭マヌエル・ルイスに、次のように言っている。「夫と私は無実です。ユダヤ教徒だったことは一度もありませんが、拷問を受け、このままだと死んでしまうのではと恐れて、そう自白したのです。(中略)この牢獄に来たときはキリスト教徒なのに、出ていくときはユダヤ教徒になった人もいますが、それはすべて異端審問官が強制する嘘と拷問のせいなのです」。
異端審問制度は、目指すものとはまったく逆の結果を生んでいた。背教者を教会と和解させるのではなく、真面目なカトリック信者を背教者に変えていたのだ。国家に忠実な市民を、政府転覆を企む反乱者に変えるものがあったとすれば、それは迫害機関である異端審問所の審問手続きにあった。なぜなら、この制度では真実よりも偏見と権力が重視されていたからである。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P120
この部分もなかなか衝撃的な部分です。特に最後の部分ですね。異端審問は結局、背教者を増やし政府転覆を企む反乱者さえ作り出すことになってしまったのです。
実はこれ、ソ連成立の立役者レーニンも同じでした。
レーニンは裕福な貴族出身でした。普通に考えればそんな家からロシア王朝を転覆させる革命家が生まれてくるのは想像できません。
しかしレーニン17歳の頃、彼の兄が国家の秘密警察に逮捕され、処刑されてしまいました。実際にテロを計画した容疑での逮捕でしたので冤罪ではありませんでしたが、悲惨な国を救おうと蜂起した兄が無残にも国そのものから抹殺された。そのことにレーニンは激しい怒りを抱くのでした。レーニンが革命家となったのはこの事件がきっかけだったと言われています。
秘密主義と密告の横行による社会不信
疑心暗鬼の雰囲気を作り出した原因は、匿名による告発を認めたことにあった。(中略)
とりわけ彼らが驚いたのは、子供が親の罪を償い、被告は誰が自分を告発したのか知りもしなければ教えられもせず、告発者が被告と直接対峙することはなく、証人の名前は決して公表されないという点だ。それまで他の裁判では、これとはまったく逆のことが行なわれていたからである」。
ここで重ねて指摘しておくが、異端審問の残虐さは、当時の人々から見ても、少なくとも最初のうちは、当たり前でもなければ、容認できるものでもなかった。新しい異端審問の裁判手続きは通常の訴訟手続きから大きく逸脱していると、当初は見なされていたのだ。しかし、マリアーナのように異端審問を擁護する人々は、時代の求めに応じて社会が変わらなくてはならないと主張した。人々は、自分たちが敵に囲まれていると信じるようになった途端、常軌を逸した尋問方法に黙って従うようになったのである。
匿名証言は、嫉妬や復讐心を発散させる絶好の隠れ蓑となった。また、証人に匿名を認めるということは、異端審問に、その活動の妥当性について責任を負う義務を持たせることができないということでもある。そのため当然ながら、この秘密主義は徹底的に守られ、違反する者は極刑に処された。たとえば一五六三年のムルシアで、グレゴリオ・アルディードは異端審問の秘密主義を破ったかどで、ガレー船での六年の漕役刑と鞭打ち一〇〇回の罰を言い渡されたし、クリストバル・デ・アルネードも、同じ罪で鞭打ちニ〇〇回を受けた後にガレー船へ送られ八年間の漕役刑に服している。(中略)
秘密主義は社会にさまざまな影響を与えたが、その中で最も有害だったのは、マリアーナも指摘しているとおり、警戒心と隠蔽体質を醸成したことだ。秘密主義のせいで社会全体に不信感が広がり、拷問を避けるため誰もが作り話をするようになった。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P122-123
いかがでしょうか。これが最初は単に「異端を裁くだけのシステム」と思われていたものが、社会全体の病気となっていく過程です。
最初は疑わしきものを罰するだけでした。
しかしそれがどんどんエスカレートし、もはや誰が誰に密告されるなどわからない疑心暗鬼の世界に変わっていきます。こんな世界で人と人との温かい交流などありえるでしょうか。私たちがこれまで当たり前のように交わしていた楽しいつながりはありえるでしょうか。
ここまで監視と密告が定着してしまえば、人間同士の信頼関係は崩壊です。
こうなってしまえばひとりひとりの国民にはほとんどなす術がありません。スペインは徐々に活力を失っていくのでありました・・・
続く
次の記事はこちら
前の記事はこちら
「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む記事一覧はこちら
関連記事