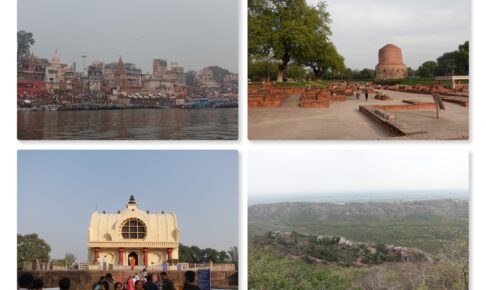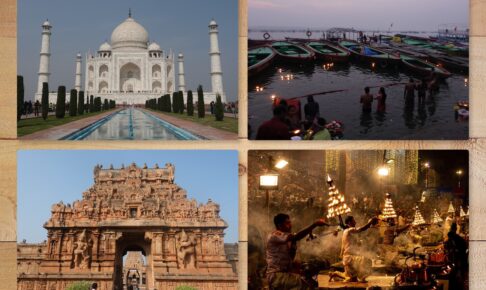(2)ドストエフスキーとアンナ夫人との出会い~絶望的な状況で始められた『賭博者』の口述筆記
前回の記事「妻アンナ夫人と出会うまでのドストエフスキー(1821~1866年「誕生から『罪と罰』頃まで)をざっくりとご紹介」でドストエフスキーの波乱万丈の前半生をお話しした。
ドストエフスキーがいかに壮絶な人生を送ってきたか、そして『罪と罰』執筆時にどれほど危機的な状況に陥っていたかが伝わったのではないだろうか。
そして今回の記事ではいよいよ今回の物語の主人公であるドストエフスキーとその妻アンナ夫人の出会いについてお話ししていく。
二人が出会ったのは1866年の10月のこと。ドストエフスキー45歳、アンナはなんと20歳の年だった。この時彼女は速記の講義に通う学生だったのである。
なぜこうも年の差ある二人が出会うことになったのか。まずはアンナ夫人の声を聞いていくことにしよう。
ドストエフスキーとアンナ夫人の出会いのきっかけ
一八六六年十月三日、夕方七時ごろ、わたしはいつものように、オリヒン先生が速記の講義をされる第六男子中学校に行った。講義はまだ始まっていなくて、みなは遅れてくる人たちを待っていた。いつもの席について、ノートをひろげようとしたとき、オリヒン先生がつかつかとやって来て、となりの席に腰をおろすとこう言った。
「アンナ・グリゴーリエヴナ、仕事をするつもりはありませんか。速記者をひとり探してくれと言われているのですが、あなたなら引きうけてくれると思ったものですからね」
「ぜひさせてください」とわたしは答えた。「ずっとまえから働けるようになるのが夢だったのです。でも、責任ある仕事が引きうけられるほど速記の力があるかどうか心配ですが」
オリヒン先生は、心配しないようにと言ってくれた。先生の考えでは、その仕事は、わたしが追いつけないほどの速さは必要ないだろうとのことだった。
「で、どなたのところの仕事なのでしょうか」と、わたしは好奇心をそそられて言った。
「作家のドストエフスキーです。彼はいま新しい小説にかかっていて、速記者の助けを借りて仕上げたいと思っているのです。小説は大判の印刷紙で七枚くらい(一印刷紙は十六ページ分)になるらしく、その仕事全体で五十ルーブル払うということです」
わたしは急いで承諾した。ドストエフスキーの名は、わたしには子どものころから親しいものだった。彼はわたしの父の好きな作家だったから。わたし自身もその作品に夢中になって、『死の家の記録』に涙を流したものだった。すぐれた作家と知合いになれるばかりか、その仕事まで手伝うことになると思うと、すっかり興奮して、うれしくてならなかった。
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P29-30
アンナ夫人は口述筆記という、当時最先端の筆記術を学んでいた学生だった。その中でも彼女は優秀な学生としてオリヒン先生に信頼されていた。そのオリヒン先生を介して紹介されたのがなんと、ドストエフスキーだったのである。
ではなぜドストエフスキーはオリヒン先生に口述筆記者を依頼したのだろうか。これまで通り自分で作品を書けばいいではないか。
実はここに前回の記事の後半でお話しした悪徳業者の契約と繋がってくるのである。
再びアンナ夫人の言葉を引用していく。アンナ夫人はドストエフスキーから聞いたその契約を『回想のドストエフスキー』に記している。少し長くなるがアンナ夫人がなぜ速記者として依頼を受けたかがここで明らかになる。
くわしいことをたずねると、彼は、じつに恐るべきわなにかかっていることを語ってきかせてくれた。
彼は、兄のミハイルが亡くなってから、兄が出していた雑誌『時代』(エポーハ)でできた負債をすべて引きうけたのだ。借金は手形になっていて、債権者たちはフョードル・ミハイロヴイチ(※ブログ筆者注、ドストエフスキーのこと)をしきりに責め、差し押えるだの、債務監獄に入れるだのといっておどした。そのころはそういうことができたのだった。
どうしても引きのばせない負債は、三千ルーブルほどあった。彼は八方手をつくしたが、金策はうまく行かなかった。債権者にのばしてもらうすべての試みがむだだとわかって絶望の極にたっしたとき、ひょっこり出版社主のステルロフスキーが現われて、三千ルーブルで彼の三巻全集の版権を買いたいと申し出た。その金額には、あらたに小説を一篇書き足すことも義務づけられていた。
フョードル・ミハイロヴィチは非常な苦境に立たされていたので、自由を奪われずにすみさえすればと、契約のすべての条件をのんだ。
一八六五年(夏)に契約は結ばれて、ステルロフスキーは金を公証人に払った。その金は翌日にはもう債権者たちに支払われてしまい、フョードル・ミハイロヴィチの手には一文もわたらなかった。そしてなにより腹が立ったことは、数日後にこの金がそっくりまたステルロフスキーの手にもどったことだった。彼はフョードル・ミハイロヴィチの手形を捨値で買いあさり、ふたりの手下をつかって取立てをはかっていたことがわかった。ステルロフスキーは、わが国の文学者や音楽家(ピーセムスキー、クレストフスキー、グリンカ)からもしぼり取った悪がしこい、抜け目のない男だった。彼は、人が苦しんでいるところをねらっては網でとらえるやり方を心得ていた。三千ルーブルなどは、ドストエフスキーの小説を手に入れるうまみにくらべては、まったくのはした金だった。とりわけ最も苛酷な条件は、一八六六年十一月一日までに新しい小説を書いてわたさなければならないことだった。期限までに果たせない場合には、フョードル・ミハイロヴィチは莫大な違約金を払わなければならない。十二月一日(※ブログ筆者注、本文誤植か。正しくは十一月)までに小説が仕上らぬとすると、ドストエフスキーの著作権はすっかりその手をはなれて、永久にステルロフスキーのものになってしまう。むろんこの強欲な人間は、このことは十分計算ずみだった。
フョードル・ミハイロヴィチは一八六六年には『罪と罰』にかかりっきりで、それの仕上げに骨折っていたときだった。病身の彼に、新しい小説をさらに多くの枚数を書きあげる余裕などあったろうか。
彼は秋にモスクワから帰ってきて、一カ月半やニカ月かでその契約をはたせないことがわかって、絶望的になっていた。アポロン・マーイコフ、ミリュコフ、ドルゴモスチェフそのほかの彼の友人たちは、窮状を見かねて、こう申し出た。ドストエフスキーが小説の筋を立て、自分たちが各部分を受けもって、三、四人がかりで期限までに間に合うように仕上げよう、彼は原稿をまとめて、どうしても直さなければならないところだけを手直しすればいいというのだった。けれども彼はこの申し出を辞退した。他人の書いた作品に自分の名を冠するくらいなら、違約金を払うか、著作権を失うかするほうがまだましだと思ったのだ。そこで友人たちは、速記者の手を借りるようにすすめた。ミリュコフがオリヒン先生を知っていることを思い出し、彼をたずねて速記者をよこすようにたのんでくれた。フョードル・ミハイロヴィチは、こういう仕事がはたしてうまく行くかどうかと強い疑念をもったが、期日がさしせまっているので、速記者の助けを借りることになったのだ。
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P43-45
ドストエフスキーとアンナ夫人が出会ったのは10月3日。つまり契約の締め切りまであと1か月を切っていた。この短い時間にドストエフスキーは長編小説を一本書かなければならない。自分で構成、清書をする時間など到底ありえなかった。だからこそ速記者の助けが必要となったのだ。
つまり、悪魔的な契約の存在が結果的にアンナ夫人と出会うきっかけとなったのである。人生とは本当に不思議なものだ。地獄のような人生を送ってきたドストエフスキーが、まさにその地獄で自分を救ってくれる存在と出会ったのである。何たる奇跡だろう。・・・だが、先を急ぐのは慎もう。この時はまだ二人ともそんなことなど露にも想像していなかったのだから。
では、ここでドストエフスキーとアンナ夫人の初対面の様子を見ていくことにしよう。
ぎこちない初対面と共同作業の始まり
アンナ夫人は指定された10月4日の11時半きっかりにドストエフスキーの家を訪れた。ドストエフスキーは時間に厳格だったようで「それよりも早くも遅くもなく」が口癖だったそう。神経質な彼の性格がまさに伝わってくるようだ。
そして部屋に通されたアンナ夫人はいよいよドストエフスキーと対面することになる。
「速記をはじめてもうだいぶになりますか」
「まだ半年です」
「先生にはたくさんお弟子さんがいますか」
「はじめのうちは百五十人以上もいましたが、いまでは二十五人くらいしかいません」
「どうしてそんなに少なくなったのです」
「だれでも速記なんてごくやさしいと思って来るのですが、何日かたってもろくにできないので、やめてしまうのです」
「新しいことはなんでもそういうものですよ。意気ごんで始めても、たちまち熱がさめて投げ出してしまうのです。苦労しなければならぬのはわかっていても、いまどき誰がすすんで苦労しようとするでしょう」
ちょっと見たところドストエフスキーはかなりの年に見えたが、話しはじめると、すぐに若々しくなって、三十五から、せいぜい三十七だろうかと思った。中くらいの背丈で、非常に姿勢がよかった。やや赤みがかった明るい栗いろの髪に、うんとポマードをつけて、念入りになでつけてある。おどろいたのはその目だった。それは不ぞろいで、一方は茶いろ、もう一方はひとみが目いっぱいにひろがって、虹彩が見えなくなっていた。そのちぐはぐなことが、ドストエフスキーのまなざしに何か謎のような表情をつけくわえていた。ドストエフスキーの顔は、青白く、病的で、わたしにはもうすっかりなじみのような気がした。まえに写真を何度も見たことがあったからにちがいない。かなり着古した青いラシャの上着を着ていたが、シャツ(襟と袖口)は雪のように白かった。
*ドストエフスキーはてんかんの発作でたおれたとき、とがったものにぶつかり、右の目をひどく痛めたのだった。ユンゲ教授にかかって、アトロピンの点滴をはじめたところだったので、ひとみがひどくひろがっていたのだ。
五分ほどして、女中が非常に濃い、ほとんど黒いくらいのお茶を二つ持って来た。盆には小さな白パンがニつのっていた。わたしはコップをとりあげた。お茶はほしくもなく、おまけに部屋が暑かったが、ただ失礼なような気がしたので飲みはじめた。わたしは壁ぎわの小さなテーブルのまえに掛けていた。ドストエフスキーは、仕事机のまえに掛けたり、部屋を行き来しながらタバコを吸ったりして、しょっちゅう消してはまた新しいのにつけた。わたしもすすめられたが、ことわった。
「遠慮なさっているのじゃありませんか」と彼は言った。
わたしは、自分は吸わないどころか、女の人が吸うのは見るのもいやなのだとあわてて答えた。
話はとりとめがなく、そのうえドストエフスキーはたえず新しい話題にうつっていった。彼は疲れはてて、病人のようだった。ロを開くなり、自分はてんかん持ちで、何日かまえにも発作におそわれたと言いだしたので、そのあけっぴろげなことにはとてもおどろかされた。今度の仕事のことになると、ドストエフスキーは、なぜかはっきりしなかった。
「どうやったらいいか、ふたりで考えてみましょう。とにかくためして、できるかどうか見てみましょう」
わたしは、この共同の仕事はうまくいかないのではないかと思いはじめた。ドストエフスキーは、こんな仕事の仕方がはたして成り立つのか、便利なことかどうかと疑って、断ろうとしているのではないかと考えたほどだ。それで決心をうながすように、わたしは言った。
「ええ、やってみましょう。でも、お手伝いするのがぐあいわるいようでしたら遠慮なくおっしゃってください。うまくいかなくても、わたしのほうはちっともかまいませんから」
ドストエフスキーは、『ロシア通報』の一節を読みあげるから、速記して、普通の文字になおすようにと言った。そして非常な速さで読みはじめたが、わたしはそれをさえぎって、普通の話の速度にしてもらった。
それからわたしは速記をかなりはやく起こしはじめたが、それでも彼はひっきりなしにせきたてて、ずいぶん時間がかかると驚いたようすだった。
「それでは、書きなおす仕事はここではせず、家でしてくることにしましょう。そうすればどれほど時間がかかっても、ご迷惑はおかけしませんから」とわたしはなだめるように言った。
彼は写しをしらべてみて、終止符をひとつ抜かしたのと、硬音符をはっきり書かなかったのを見つけて、きつい調子で注意した。彼はいらいらして、考えをまとめることができそうにもなかった。わたしの名をたずねてはすぐ忘れたり、わたしがいることなど頭にないかのように、部屋をながいあいだ行ったり来たりした。考えにふけっているじゃまをしないように、わたしは身じろぎもしないでいた。
とうとうドストエフスキーは、口述するのは今はどうしてもむりだ、もう一度今晩八時ごろ来てくれないだろうかと言った。そのときには小説の口述ができそうだというのだった。二度もやって来るのはとてもぐあいわるかったが、仕事をのばしたくなかったので、わたしは承知した。
ドストエフスキーはわたしを送りだしながら、「オリヒン氏が、男でなく娘さんの速記者をよこそうかといったとき、うれしかったが、なぜだかわかりますか」と言った。
「なぜでしょう」
「それはですね、男ならうんと飲むでしょうが、あなたなら飲まないでしょうから」
わたしはおかしくてしょうがなかったが、笑いをこらえて、まじめにこう言った。
「ええ、わたしは確かに飲みませんから、それは安心なさってけっこうですわ」
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P34-37
これがドストエフスキーとアンナ夫人の初対面だった。
出会ってすぐに恋に落ちるというロマンス溢れる初対面とはどうやらいかなかったようだ。そう簡単に『ロミオとジュリエット』のようにはいかないものである。後にどんなに強い愛で結ばれようと、最初の出会いは案外このようなものなのかもしれない。むしろこうであってくれた方が私たちにとっては救いがあるのではないか。
だがこのぎこちない初対面とは打って変わり、この後2人は急速に接近していく。
次の記事ではそんな2人の様子を見ていくことにしよう。
続く
次の記事はこちら
前の記事はこちら
ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら
「おすすめドストエフスキー伝記一覧」
「おすすめドストエフスキー解説書一覧」
「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」
関連記事