(26)ドストエフスキー夫妻の4年ぶりの帰国!旅を経てすっかり丸くなったドストエフスキーとアンナ夫人の成長とは

【ドイツ旅行記】(26)ドストエフスキー夫妻の4年ぶりの帰国!旅を経てすっかり丸くなったドストエフスキーとアンナ夫人の成長とは
前回の記事「(25)カジノの街ヴィースバーデンでドストエフスキーのギャンブル中毒が消滅!!旅の終盤、彼の身に起こった奇跡とは!」ではドストエフスキーの身に起きた奇跡についてお話しした。

そして今回の記事では彼らの旅の終わりについてお話ししていきたい。4年にわたる西欧旅行もいよいよ終わりを迎えるのだ。
1871年7月、念願の帰国
一八七一年六月の下旬に、『ロシア通報』の編集部から小説の稿料を送ってきたので、その日のうちに、生活にけりをつけ(もっとはっきり言えば、質草を請けだして、借金を払い)、荷造りに取りかかった。
出発の二日まえに、夫はわたしを呼んで、ぎっしり書きこみのある大判の部厚い紙たばを渡し、焼きすてるようにと言った。
ふたりで前からこのことを話しあってはいたが、わたしは原稿を焼いてしまうのがいかにも惜しくなって、自分に持って帰らせてほしいとしきりに頼んだ。けれども彼は、ロシアの国境ではきっと捜索され、原稿類は没収され、一八四九年に逮捕されたときと同じように失われてしまうにちがいないと言った。原稿類の検閲がおわるまでわたしたちがヴェルジボロヴォ駅に足止めされることも考えられ、出産という大事をひかえているためにそれは危険だった。
この原稿を手ばなすのがどれほど残念ではあっても、夫がつよく主張する理屈には従わざるをえなかった。わたしたちは暖炉をたいて、原稿をくべてしまった。こうして「白痴」と「永遠の夫」の原稿は失われた。とりわけ惜しかったのは、「悪霊」の一部がなくなったことで、それはこの傾向的な作品のまったく別のヴァリアントだった。
わたしにできたことといえば、わずかにこの小説のノート類をとりのけて、おくれて秋の末に帰国するはずの母にあずけることだった。母はトランクいっぱいの原稿を引きうけることは承知しなかった。こんなにたくさんの原稿はきっと疑われて没収されるにちがいなかったから。
とうとうわたしたちは、べルリンでロシア行きの汽車に乗りかえることにして、七月五日の夕方、ドレスデンをあとにすることができた。
やっと一年十カ月にしかならないいたずら盛りのリューボチカをかかえて、道中いろいろな厄介があった。子守りは連れていなかったし、身重の体だったので、途中ずっと(六十八時間も)彼女の世話をすることになったのは夫のほうだった。プラットフォームを手をひいて散歩させたり、牛乳や食事をあたえたり、退屈しないように相手をしてやったり—ほんとうに気のきく乳母のようにふるまってくれたので、ながい道中、まったく助かった。
はたして、国境で、トランクや包みを何もかもかきまわされ、原稿や本の束は横にとりのけられてしまった。
ほかの人たちはみなもう検査室から出て行ってしまったのに、わたしたち三人だけが残された。
そしてまだ何人も役人たちがテーブルのまわりにむらがって、取りあげた本やわずかな原稿の包みをこまかくしらべていた。わたしたちはペテルブルグ行きの列車に乗りおくれはしないかと気が気でなかった。その時だった、リューボチカがその場を救ってくれたのは……かわいそうにちいさな娘は、すっかりおなかをすかせて、こんなふうに叫んだのだ。「ママ、パンをちょうだい」。せつく声がうるさくなった役人たちは、とうとう本も原稿もそれ以上は見ないで、なんのとがめもなしに放してくれた。
それからもまだ一晩は列車のなかで苦しんだが、もうロシアの大地を走っていて、まわりはみな同じロシア人なのだと思うとすっかり安らかな気もちになり、旅のつらさも大方わすれてしまうほどだった。夫もわたしも上機嫌で幸せでならず、とうとうロシアにかえってきたが、夢ではあるまいかと語りあった。長い長い念願がかなったことが、なんだかうそのように思えるほどだったのだ。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P217-219
四年前、ベルリンから始まった二人の旅。
新婚早々のドレスデン、バーデン・バーデンの悪夢、ジュネーブでの天国と地獄、フィレンツェでの日々、そしてホームシックのドレスデン。色んなことがあった。ありすぎた。想像を絶する日々を夫妻は二人三脚で乗り越えてきた。
旅に出た当初の二人はもういない。
ドストエフスキーは自身の闇や狂気に打ち克ち、作家として一回り大きくなって帰って来た。そしてアンナ夫人はドストエフスキーを支える名マネージャーとしてこれから抜群の活躍を見せることになる。
この四年間はドストエフスキーにとってまさに運命を変えた旅だったのだ。
アンナ夫人、この旅を振り返る
アンナ夫人はこの旅を振り返り、『回想』で次のように述べている。せっかくなので全て読んでいこう。
外国生活時代のことを結ぶにあたって、わたしは運命にふかい感謝をもって思いかえさずにはいられない。
たしかに、四年あまりの放浪の期間、わたしたちは幾度もつらい試練にみまわれた。
長女の死、夫の病気、たえまない貧乏と仕事の保証のなさ、ルーレットにたいする夫の不幸な熱中、帰国の障害などだったが、それでもこれらの試練は結局わたしたちに利益をもたらした。
わたしたち夫婦はそのためにいっそうしっかりと結びついた。よりよく理解しあい、たがいを尊重するようになり、また、夫婦生活を幸福なものにした互いの愛情を育てることになった。
わたし自身にとっても、この数年間の思い出は、かがやかしく美しい一枚の絵となっている。
わたしたちはたくさんの美しい街や名所(ドレスデン、バーデン・バーデン、ジュネーヴ、ミラノ、フィレンツェ、ヴェネツィア、プラハ)に住んだり訪れたりした。それまで見たこともなかったいろいろな世界が目のまえにひらけてわたしを夢中にさせた。旺盛な好奇心は、数々の寺院や博物館、美術館をおとずれることですっかり満足させられたが、とりわけ愛する人といっしょにそれらを見ることになったので、ふたりで交わした話はみな、芸術や人生について何かしら新しいものをひらいてみせた。
フョードル・ミハイロヴィチにとっては、これらの土地はみな少しも新しいものではなかったが、たいへん進んだ芸術的趣味の持主だったので、ドレスデンやフィレンツェの美術館にはいかにもたのしげに足をはこんだし、何時間もヴェネツィアのサン・マルコ寺院や宮殿などを見て飽きなかった。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P219
辛いこともあったこの西欧旅行ではあったが、結果として二人の愛を育み強い絆を得ることができたとアンナ夫人は振り返っている。そしてさらに続ける。
たしかに、外国でわたしたちは、偶然に、行きずりに会った人たちのほか、友人らしい友人をひとりも持たなかった。
だが最初の二年間、彼は、かえってまったくつきあいのないことを喜んでいたくらいだった。兄のミハイルが死んでから、彼は自分自身の失敗と不幸とたたかうことに疲れすぎてもいたし、文壇の人々からつらく当たられすぎてもいた。そればかりか彼は、思想家というものは、たえず心をかきたてられる日々の事件から遠ざかって、孤独のうちに生活し、思索と夢想にふけることが時にはきわめて大切だと考えていた。
のちにペテルブルグのあわただしい生活にもどってから、夫は、外国生活では、小説のプランを立てたり、歓喜と感動にひたりきってゆっくりと好きな本を読んだりするまったく自由な時間にめぐまれていて、なんとよかったことだろうとたえず思い出しては語っていた。
外国生活のあいだには、めずらしいものを見聞きするたのしみのほかに、数々の輝かしい深いよろこびを感じることができた。
フョードル・ミハイロヴィチのたえず夢みてきた子どもたちに恵まれ、家庭が形づくられて、ふたりの生活をにぎやかに、明るくしてくれた。わたしは運命に感謝しながら、こう言わずにはいられない。「このすぐれた、高い精神性をもった人とほとんど二人きりで外国生活をおくることができたすばらしい数年間は何と幸せだったことだろう!」
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P220
ここで「彼は自分自身の失敗と不幸とたたかうことに疲れすぎてもいたし、文壇の人々からつらく当たられすぎてもいた。」とさらっと書かれているが、実はここにドストエフスキーの深い苦労が見え隠れする。
当時のロシア文壇では文学そのものの評価より、政治的な立場からの批評が非常に多かったのだ。文壇内は党派ごと陣営に分かれて批判や中傷に明け暮れていたという面があった。スラブ派と西欧派の対立はその典型だ。

当時のロシア文学は純粋な娯楽や芸術としてだけではなく、国や人間のあり方について激論を交わす場として存在していた。国家による検閲が厳しく、政治的主張を制限されていた彼らにとって、文学とは自分の生き方、そして世の中のあり方を問う人生を賭けた勝負の場だったのだ。
だからこそ作品をフラットに見てその芸術性や面白さを評価することなく喧々諤々とやり合うということも多かった。個人的な人間関係もその批評に大きく影響することもある。ドストエフスキーはただでさえ神経質で人付き合いが苦手なタイプだ。若い頃には文壇でいじめられた過去もある。(「(1)妻アンナ夫人と出会うまでのドストエフスキー(1821~1866年「誕生から『罪と罰』頃まで)をざっくりとご紹介」の記事参照)
そんながやがやした文壇から離れて自分の世界に籠ることができたのはある意味貴重な時間だったのだ。
そして籠りに籠った4年間の蓄積が帰国後に烈火のごとくはじけ出す!何か言わずにはいられない!そのマグマの噴出が『作家の日記』というジャーナリスティックな作品へと結実する。そしてもちろんそれは『カラマーゾフの兄弟』にも繋がっていくのだ。そうした面でもこの旅の隔離生活はドストエフスキーにとって大きな意味があったのである。
そしてアンナ夫人はこの旅を通して変化したドストエフスキーについてこう語る。
四年あまりの外国滞在中の生活の紹介をおえるにあたり、あんなにも長かった孤独なわたしたちの生活の精神的な重要さについて語っておきたい。
数かぎりない心配ごと、たえまのない貧乏、時折りおそう恐ろしいさびしさにもかかわらず、あれほど長い孤独な生活は、つねに夫のなかにあったキリスト教的な思考と感情をきわだたせ、はぐくむのに有益な影響をあたえることになった。
帰国して迎えてくれた友だちや知合いはだれもが、フョードル・ミハイロヴィチは見ちがえるようになったと言った。
それほど彼の性格はいいほうに変化し、かどがとれて、やさしく、人にたいして寛大になっていた。彼につきまとっていた片意地なところや気短かなところは、ほとんど影をひそめていた。(中略)
夫は、ずっと後年になってからも、この外国生活を感謝の気もちをもって思い出した。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P220-221
「彼の性格はいいほうに変化し、かどがとれて、やさしく、人にたいして寛大になっていた。彼につきまとっていた片意地なところや気短かなところは、ほとんど影をひそめていた。」
つまり、とてつもなく丸くなったのである。
あの気難しくて癇癪持ちでいつも神経質だったあのドストエフスキーがすっかり穏やかになってしまったのである。
これはとてつもない変化だ。かつての彼を知る人は皆ハッとしたことだろう。
人間そんなに変わるのだろうか。
まあ、変わるでしょう!これだけの旅をして、アンナ夫人という心強いパートナーができたのだから!
だがもちろん、癇癪持ちは相変わらずであったし、てんかんの発作後のうつ症状も残っている。猛烈なやきもち焼きも変わっていない。まるっきり別の人間になったとまではいかないが、周囲が驚くほど彼は丸くなって帰って来たのであった。それだけでもものすごいことではないか。あの破天荒人間がすっかり落ち着いて微笑みすら浮かべるようになったのだから。
アンナ夫人は最後に自身の変化について次のように述べ、この西欧旅行を締めくくっている。
親戚や知合いの人たちは、わたしにもやはり大きな変化を認めた。
わたしは、かつての小心で内気な小娘から、確固とした性格をもった一人の女になっていた。
そしてもはやどれほどの生活の不如意ともたたかうことを恐れなかった。
もっとはっきり言えば、ぺテルブルグに帰りついたときには、借金は二万五千ルーブルにもたっしていた。明るい性格と生活をたのしむ気もちはそこなわれずにあったが、それは家庭のなかでだけ、身内のものや友だちとのあいだでだけだった。知らない人たち、とくに男の人たちのまえでは、わたしは極度に自制して、そっけない態度をとるようにつとめ、自分の考えを言うよりは黙って人の話を傾聴するほうにまわることが多かった。
女友だちはみな、この四年間にわたしがひどく老けたといって、服装にも髪型にもかまわなくなったのをとがめた。そのとおりにちがいなかったが、それでもわたしはそれをあらためようとは思わなかった。
フョードル・ミハイロヴィチがわたしを愛してくれてるのは、ただ外見からだけではなく、知恵と気だてのよさのためだったし、彼自身も言ったように、ふたりは外国生活のあいだで「魂で結びついた」のだとかたく信じていたからだ。流行おくれの身なりと、はっきり男の人たちを避けるようにした暮しぶりとは、なんの根拠もなく嫉妬する夫のわるい性格が出ないようにするために、夫にいい影響だけをあたえたのである。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P221-222
「わたしは、かつての小心で内気な小娘から、確固とした性格をもった一人の女になっていた。」
ドストエフスキーの変化も目覚ましいものがあったが、やはり何と言ってもアンナ夫人の成長ぶりには驚くしかない。この旅行記でも何度も述べてきたが、アンナ夫人はドストエフスキーとの強烈な旅を通して精神的な成熟を見せた。今やドストエフスキーは彼女なしでは生きられない。
「ぺテルブルグに帰りついたときには、借金は二万五千ルーブルにもたっしていた。」とアンナ夫人は述べるが、帰国後、ドストエフスキーは彼女の活躍で借金を完済することになる。しかもドストエフスキーはスターラヤ・ルッサという町に別荘を買うこともできた。そこでの生活は夫妻の幸福な思い出となった。そして何より、このスターラヤ・ルッサこそ『カラマーゾフの兄弟』の舞台のモデルとなったのである。
ただ、上のアンナ夫人の言葉でドストエフスキーの嫉妬について書かれていたのは少し注意が必要だ。
結婚当初からドストフスキーのやきもち焼きはとてつもないものがあったが、アンナ夫人への愛が深まるにつれ嫉妬心も大きくなっていったのである。ほんのちょっとでも他の男と楽しそうに話すともうだめなのである。ドストエフスキーは制御不能の激情に狂ってしまう。ドストエフスキーはアンナ夫人をそれこそ溺愛した。その愛の強さに比例して嫉妬の激情も燃え上がる。何事も極端なところまで行かずにはいられないドストエフスキーらしさはやはり健在なのである。愛と嫉妬の関係は興味深い。その姿はまるでオセローだ。
それを分かった上で自分自身の振る舞いを制御するアンナ夫人はやはりスケールが違う。
次の記事ではそんなアンナ夫人の帰国後の無双ぶりをお話ししていこう。この旅を通してどれほどアンナ夫人が強くなったのか、そして彼女の有能ぶりも見ていくことにする。
ドストエフスキーとアンナ夫人の関係性もそこから見えてくる。ドストエフスキーがどれほどアンナ夫人を信頼しているかが一発でわかる。ドストエフスキーがアンナ夫人を「私の守護天使」と呼ぶのもむべなるかなである。
続く
主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら
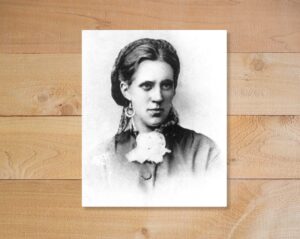
前の記事はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら
「おすすめドストエフスキー伝記一覧」
「おすすめドストエフスキー解説書一覧」
「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」
関連記事















コメント