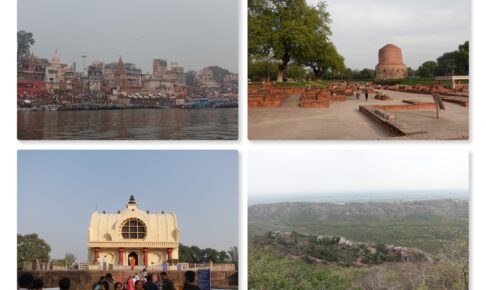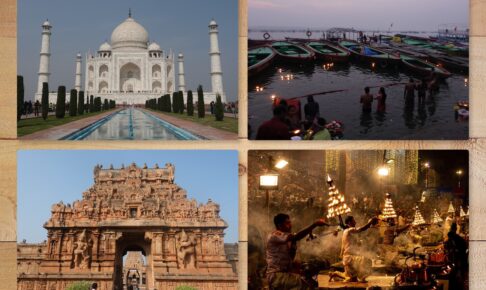金子晴勇『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』概要と感想~マルクスの歴史観にもつながるキリスト教教父の思想とは
今回ご紹介するのは2019年に教文館から発行された金子晴勇著『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』です。
早速この本について見ていきましょう。
二つの愛が二つの国を造った
古代教会最大の思想家アウグスティヌスの畢生の大作であり、その後のヨーロッパ思想の歴史観・国家観に多大な影響を及ぼした『神の国』。
教文館商品紹介ページより
アウグスティヌス研究の第一人者である著者が、『神の国』が執筆された時代背景、全体構想、そして基本思想を分かりやすく解説した入門書。
この本はキリスト教思想に巨大な影響を与えた思想家アウグスティヌスの『神の国』の入門書になります。

アウグスティヌスはキリスト教がローマ帝国に国教化された頃に活躍した大哲学者です。
今回ご紹介する『神の国』ですがかなりの大作で時間の都合上これを読むことができなかったのでこちらの参考書を紹介させて頂くことになりました。
ですが、この『神の国』はアウグスティヌスにとって、いや、キリスト教にとって非常に重要な作品でした。この作品がなぜ執筆されたかという理由が非常に興味深かったのでまずはそちらを紹介します。
四一〇年にアラリクスに率いられた西ゴート族が、「永遠の都」ローマを攻略した。この事件はわずか三日間にわたったものであったが、ローマ帝国の住民には未曾有の大惨事となる衝撃を与えた。事実、ケルト人のローマ帝国への侵入があってから八〇〇年間は、このような事件はかつて起こったことがなかった。
この時代にキリスト教はすでに帝国の宗教として公認され、三八〇年には国教と見なされ、三九二年には伝統的なローマの神々の祭儀が禁じられ、それに背く者には実刑が科せられると定められた。こうして世界はキリスト教時代を迎えるようになっていた。
だが、そうはいっても異教の勢力は依然として維持されており、元老院議員や政府の高官はなお続けて異教徒のままであった。彼らはこの機に乗じて、キリスト教への攻撃を激化させていった。
異教徒たちは、伝統的な神々を廃止し、キリスト教を国教としたがゆえに、ローマの攻略を許したのだ、と主張した。このような非難を受けてアウグスティヌスは『神の国』(De civitate Dei,413-26)を一三年の歳月を費やして執筆し、キリスト教の立場からその批判に対する反論を展開した。
教文館、金子晴勇著『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』P47
※一部改行しました
ローマ帝国の崩壊のきっかけとなる蛮族の侵入とアウグスティヌスの『神の国』が関係しているというのはとても驚きでした。なぜこの本が書かれねばならなかったのかという背景を知ると、この本で述べられることのリアルさ、緊張感が伝わってくるような気がしました。
さて、前回、前々回と「ユートピア思想の源泉」を辿るためにプラトンの著作を紹介しましたが、今回紹介する『神の国』もその流れでぜひ取り上げたい作品です。
というのも、ロバート・スキデルスキー、エドワード・スキデルスキー著『じゅうぶん豊かで、貧しい社会 理念なき資本主義の末路』ではアウグスティヌスについて次のように説かれていたからです。
近代以前のこれらのユートピア(※ブログ筆者注 トマス・モアやプラトンのユートピア)には、共通する特徴がある。どれも歴史の外にしか存在しないことだ。これらはすべて一種の神話であり(エデンの園、「金の時代」)、地上のどこかに一時的にせよ出現したことはない。プラトンの国家は純粋に理論上の存在で、現実の世界のはるか上を浮遊している。
モアのユートピアは、そのギリシャ語の語源である″ou-topia″が示すとおり「どこにもない場所」だ。(中略)
残念ながら、当時歴史と呼ばれていたものの中には、ユートピアへの道はどこにも見当たらない。歴史においては、何か一つの流れが徐々に勢いを増し続けるのではなく、あたかも季節のように、時折何かが誕生しては花開き、やがて朽ち果てるということが繰り返される。成長と繁栄のあとには贅沢と退廃が訪れ、この循環が無限に続く。(中略)
これとは異なる歴史観を最初に打ち出したのは、ユダヤの予言者たち、中でもイザヤだった。善と悪が戦い最後に善が勝つという歴史観である。預言者の語る歴史は循環的ではなく方向性があり、倫理的であって悲劇的ではない。(中略)
こうした歴史観は初期のキリスト教徒に受け継がれ、「キリストの再臨」と今日呼ばれるものでクライマックスを迎えるとされている。詩と狂気に満ちた黙示録には、「新しい天と新しい地」の到来が告げられている。そこでは「もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない」。
この千年至福説はキリスト教的歴史観に深く根を下ろしており、苦難や混乱の時代が来るたびに新たに力強く息を吹き返す。ただしキリスト教の主流的思想は、この説から用心深く距離を置いてきた。かつてはプラトン学派だったアウグスティヌスは、「神の国」は歴史の終着点ではなく時の流れの外にあるとし、「人の国」は循環的な運命に委ねた。こうして聖なるものの歴史は、世俗の歴史から切り離された。
とはいえ、両者が混ざり合う可能性はつねに存在した。たとえば一二世紀の神秘主義者フィオーレのヨアキムは、三位一体論に基づく独創的な人間的歴史観を打ち立てた。父なる神の時代はキリストの誕生をもって終わりを告げ、子の時代も終末に近づいている。そして精霊の時代が迫っている。その時代にはキリスト教徒はもはや法律に縛られることなく、精神の新たな王国に集うことができるというのだ。言うまでもなく、そのときが来ても何も起こらず、ヨアキムの教えは異端と宣告された。
だがこの教えが残した目に見えない影響は長いこと消えず、へーゲルやマルクスにまでおよんでいる。
※一部改行しました
筑摩書房、ロバート・スキデルスキー、エドワード・スキデルスキー、村井章子訳『じゅうぶん豊かで、貧しい社会 理念なき資本主義の末路』 P68-69
少し長くなりましたが、ここで重要なのは、アウグスティヌスをはじめとしたキリスト教思想では循環的な歴史観ではなく、直線的な歴史観を打ち出したという点です。時間は円のように繰り返すのではなく、最後の時に向かって徐々に進んでいくという考え方です。これがヘーゲルやマルクスにも影響を与えているとここで述べられています。
そして『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』を読んでみると、たしかにそのことが書かれていました。
人間の歴史は、神の永遠の計画が実現される歩みであって、最初の人間たちから生まれた兄弟殺しのカインに始まる。彼は自らの意志で神に背き、死をその罰として負い、楽園から追放された悲惨な生活を送ったが、神はそのような人類の中から、ある者を恩恵によって神の国の民として永遠の生命へと救い出し、残りの者を地の国の者として永遠の罰へと至らせる、とアウグスティヌスは説いた。
教文館、金子晴勇著『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』P86
アウグスティヌスが歴史を「神の永遠の計画が実現される歩み」であるとしている点は非常に重要です。これはまさしくヘーゲルの歴史観とつながってくるところです。マルクスも神ではありませんがそうした歴史観に非常に影響を受けています。そしてもう一つ、非常に重要な箇所を紹介します。
アウグスティヌスは『神の国』で「あらゆる時間の創造者にして秩序者」なる永遠の神が「永遠不変な計画」をもって歴史を導いていることを一貫して力説する。(中略)
この時間の秩序は、ギリシア人が考えた時代の循環説の空想を打破し、円環的時間から直線的時間を打ち立て、神の言の受肉によって神の救済史が段階的に構成されるように導いた。一般に救済史というと創造・堕罪・救済・完成の図式をとっている。
またパウロによると律法以前・律法の下・恩恵の下という三段階が立てられるのであるが、アウグスティヌスの救済史の構成方法は、個人の救済よりも、全人類史的視野に立ち、神の救済計画の歴史における実現をエポックメイキングな「時代の区分」(articulus temporis)によって行われたものと見なし、第一のアダムより第二のアダムであるキリストまでの歴史を聖書の記事に従って全体として六時代に分け、その最終段階にキリストの来臨と歴史の決定的転換を見ており、ここから生じる必然的な帰結として歴史の終局を捉える。
教文館、金子晴勇著『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』P189
※一部改行しました
まず最初に神という「絶対の真理」が歴史を導いているという考え方。歴史は真理・理念によって動かされているという発想はヘーゲルを連想させます。
また後半の 「個人の救済よりも、全人類史的視野に立ち、神の救済計画の歴史における実現」 という箇所は非常に重要です。「救済という神の計画」を個人レベルではなく全人類にまで拡張して理解していくあり方、これはヘーゲル、マルクスを考えていく上でも非常に重大なつながりであると思われます。
ヘーゲルもマルクスも、個人レベルの救済というよりも、社会そのものの変化に全力を注ぎます。ここであまり詳しくはお話しできませんが。「個から全体へ」、そして「全体の救いの内に含まれていく存在としての個」というのは注目すべき点ではないかと私は考えます。最後にもう一つこの本から引用します。
神の国と地の国との歴史上の対立は、天上の国と悪魔の国の対立が歴史の舞台で激しく闘争する姿として描かれてきたのであるが、こういう対決的な構図は「時間の秩序」と「秩序の静謐」によって創造と歴史を通して終局的な解決へと、否、対立を絶えず和解させて超克する秩序の思想へと導かれる。
神の秩序は歴史と社会を導き、かつ、それらを支え、神の国を悪の力に決して屈することなく終局の勝利に向かわしめる。こうして神の国と地の国の対立は、絶対的に相容れない対立の現実がそのリアルな姿を少しも割り引かれることなく、終局的な理解にまで到達する。
だからこそアウグスティヌスは歴史を人類が演じる壮大なドラマとして生き生きと描くことができたのである。
※一部改行しました
教文館、金子晴勇著『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』P 197
この箇所は読んでいて度肝を抜かれました。
・天上の国と悪魔の国の対立が歴史の舞台で激しく闘争する姿として描かれてきた
・対立を絶えず和解させて超克する秩序の思想
・神の秩序は歴史と社会を導き、かつ、それらを支え、神の国を悪の力に決して屈することなく終局の勝利に向かわしめる
・絶対的に相容れない対立の現実がそのリアルな姿を少しも割り引かれることなく、終局的な理解にまで到達する
・アウグスティヌスは歴史を人類が演じる壮大なドラマとして生き生きと描くことができた
こうした言葉はヘーゲルやマルクスを学べば必ずといっていいほど目にする表現です。
「対立を絶えず和解させて超克する」という表現はあの有名な「弁証法」という言葉をそのまま連想させますよね。
ヨーロッパの思想に絶大な影響を与えたアウグスティヌスの代表作『神の国』にはこうしたことが書かれていたのかとこの解説書を読んで驚くばかりでした。本当は『神の国』そのものに当たるべきだったのでしょうが、時間の都合上それもできませんでした。ですがマルクスを学ぶ上でこれは非常に参考になった読書になりました。
この本はキリスト教の知識が全くないという方には少し厳しいかと思いますが、ある程度知識があり、アウグスティヌスについて学んでみたいという方には最高の解説書になると思います。キリスト教の哲学、特にアウグスティヌスというと難解なイメージがありましたが、この本はとても読みやすく、わかりやすかったです。
これはぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「『アウグスティヌス『神の国』を読む―その構想と神学』~マルクスの歴史観にもつながるキリスト教教父の思想とは」でした。
次の記事はこちら
前の記事はこちら
関連記事