プラトン『国家』あらすじと感想~エリートによる国家運営の原型。ここからすでに管理社会は始まっていた

プラトン『国家』あらすじと感想~エリートによる国家運営の原型。ここからすでに管理社会は始まっていた
今回ご紹介するのは紀元前375年頃に書かれたとされるプラトンの『国家』です。

プラトンは「無知の知」で有名なソクラテスの弟子であり、後にはアリストテレスの師ともなりました。
ソクラテス→プラトン→アリストテレスという流れは学校の授業で習った記憶がありますよね。ただ、そこから彼らの著作を読むとなるとなかなか機会がないというのが実際のところだと思います。
私もそうでした。私も彼らのことをできるだけ避けていました。学生の頃何度か挑戦したのですがどうしても苦手でその都度挫折してしまっていたのです。
そんな私がなぜ今プラトンを読んだのかというと、ヨーロッパ的なユートピア思想の源泉がすでにしてこの作品で現れているということを知ったからでした。
このことについては後に改めて見ていきますが、プラトンの『国家』にはユートピアを知る上で非常に興味深い内容が書かれています。
では、遅くなりましたがこの本の要約を見ていきましょう。
ソクラテスは国家の名において処刑された。それを契機としてプラトン(前427‐前347)は、師が説きつづけた正義の徳の実現には人間の魂の在り方だけではなく国家そのものを原理的に問わねばならぬと考えるに至る。この課題の追求の末に提示されるのが、本書の中心テーゼをなす哲人統治の思想に他ならなかった。プラトン対話篇中の最高峰。(上巻)
ソクラテスの口を通じて語られた理想国における哲人統治の主張にひきつづき対話は更に展開する。では、その任に当る哲学者は何を学ぶべきか。この問いに対して善のイデアとそこに至る哲学的認識の在り方があの名高い「太陽」「線分」「洞窟」の比喩によって説かれ、終極のところ正義こそが人間を幸福にするのだと結論される。(下巻)
Amazon商品紹介ページより
ここで解説されているように『国家』が書かれた背景には尊敬する師ソクラテスの処刑がありました。
巻末の解説でも次のように述べられています。
プラトンをつよく動かしたのは、そのようにソクラテスが教えた意味での(魂において)最もすぐれた人間でさえ、彼が住む国家社会がすぐれたものでなければ、その卓越性を全うすることができないというきびしい認識(cf.VⅠ.497A~C)であった。
すでに、「同時代の人々のなかで最もすぐれた人、知恵と正義において比類なき人(『パイドン』118A)とみなされたソクラテスその人が、国家の名において死刑にされているのであって、プラトンはこの出来事をめぐり、ソクラテスのような生き方をした人間にとって国家や国法とは何であったかを、『クリトン』いう対話篇を書くことによって深刻に考えている。
ソクラテスが体現していた正義の徳が充分に生かされるためには、人間ひとりひとりにおける魂への配慮とともに、さらに現実の国家そのものの変革こそが志向されなければならず、そのために国家体制のあり方について徹底的に行なうことが、以後プラトンにとって、生涯の最後まで執拗に追求される課題となった。
岩波書店、プラトン、藤沢令夫『プラトン』(下)P472
※一部改行しました
尊敬する師が不当にも処刑されねばならなかった。そのショックたるや計り知れないものがあったのではないでしょうか。
ここで解説されるように、プラトンは、いくら徳高く知恵豊かな立派な人物であっても、悪意ある人間たちの横暴や国家システムの不備には太刀打ちできないことを悟ります。
だからこそあるべき理想の国家像をこの本で提示し、正義とは何か、善とは何かを徹底的に追求していくことになります。
有名な「イデア論」や「洞窟の喩え」もこの本で登場します。後のヨーロッパ思想に絶大な影響を与えることになるこれらの考え方もじっくり観ることができます。これも非常に興味深いことでした。
ですが、やはり今私がこの本を読みたいと思った最大の理由は彼の国家観がユートピア思想の先駆けともいえるものだったという点にあります。これはどういうことかと言いますと、次のようになります。
以下ロバート・スキデルスキー、エドワード・スキデルスキーの『じゅうぶん豊かで、貧しい社会 理念なき資本主義の末路』の解説です。

民衆の信じた愉快で素朴なユートピアには、惰眠と安楽への人間の永遠の憧れがよく表れている。
これに対して、哲学者の考える都市型のユートピアはそれほど親しみやすいとは言えない。そこでは、欲求はひたすら満たされるのではなく、合理的な政府によって抑制される。その原型となったのは、プラトンの『国家』である。そこに描かれた理想の都市国家は、英才教育を受けた選ばれしエリートである。彼らはすべてを、そう、財産や妻まで共有する。そうやって国家のために定期的に子供を産ませるのだ。
トーマス・モアが一五一六年に発表した『ユートピア』は、このジャンルの文学の名付け親となった作品だが、そこに描かれているのもやはり不気味な国である。モアのユートピアでは、支配階級のみならずすべての階級が財産を共有する。労働時間は一日六時間と短い。それが可能なのは、技術が進歩したからではなく、欲求が厳格に抑制されているからだ。「人生のささやかな楽しみ」は厳重に禁じられている。飲酒は禁止で、住民はみな同じ地味な服を着る。余暇はあるけれども、消費に費やすわけではない(そもそも消費するものがあまりない)。人々は余暇を「楽しく学び、議論し、読書し、朗読し、書いたり、散歩したり、心と体を鍛える」ことに費やす(同じく消費財の欠乏から、旧ソ連では余暇活動としてチェスが奨励された)。
次のような記述を読むと、人々を常時監視するビッグブラザーが連想される。「誰もがあなたを見ているので、あなたは熱心に働くこと、余暇を適切に活用することを強いられる」。女性は男性に従属し、二度姦通をすれば死刑に処される。
筑摩書房、ロバート・スキデルスキー、エドワード・スキデルスキー著、村井章子訳 『じゅうぶん豊かで、貧しい社会 理念なき資本主義の末路』 P67-68
彼いわく、ユートピア思想の始まりにはプラトンの『国家』が影響を与えているとのことでした。しかもトマス・モアの『ユートピア』の段階ですでにオーウェル的な監視社会がすでに連想されるというのです。

ならばぜひとも確かめてみたい!私はそう思い『国家』を読んでみたのでした。
するとやはりこの解説通りのことがたしかに書かれていました。今回はその一部を紹介したいと思います。
女たちのすべては、これらの男たちすべての共有であり、誰か一人の女が一人の男と私的に同棲することは、いかなる者もこれをしてはならないこと。さらに子供たちもまた共有されるべきであり、親が自分の子を知ることも、子が親を知ることも許されない
岩波書店、プラトン、藤沢令夫『プラトン』(上)P 261
「これらの男たち」とは国を指導するエリート層のことです。人々を導く優秀な人間は、優秀な子孫を残すためにできるかぎり多く生殖の機会を持たねばならないとのことでした。現代でもこれは到底受け入れられない考え方でしょうが、これには少し既視感があります。
というのも19世紀のニヒリストたち、社会主義者たちも特定の相手と交際するのではなく、男女それぞれが自由に相手を共有しようとしていたというのを私は読んだことがあります。
当時のニヒリスト、社会主義者たちはインテリばかりです。彼らの多くは知識を身につけています。この本を読んでつくづく感じるのはプラトンが理性を非常に重んじていたことです。人間の理性によって世界を統治していく、変革していくという思考パターンはこういう所から脈々とヨーロッパに根付いていたということが感じられます。
さて、他にも見ていきましょう。
また若者たちのなかで、戦争その他の機会にすぐれた働きを示す者たちには、他のさまざまの恩典や褒賞とともに、とくに婦人たちと共寝する許しを、他の者よりも多く与えなければならない。同時にまたそのことにかこつけて、できるだけたくさんの子種がそのような人々からつくられるようにするためにもね(中略)
そしてその都度生まれてくる子供たちは、そのために任命されている役職の者に引き渡されて―この任に当るのは男たちでも女たちでも、あるいはその両方であってもよい。役職もまた、女と男に共通に分けもたれるはずだからね(中略)
で、ぼくの思うには、すぐれた人々の子供は、その役職の者たちがこれを受け取って囲い(保育所)へ運び、国の一隅に隔離されて住んでいる保母たちの手に委ねるだろう。他方、劣った者たちの子供や、また他方の者たちの子で欠陥児が生まれた場合には、これをしかるべき仕方で秘密のうちにかくし去ってしまうだろう」
岩波書店、プラトン、藤沢令夫『プラトン』(上)P 368-369
いかがでしょうか。これはなかなかに恐ろしい発想ですよね。子供たちは生まれた瞬間に隔離され、「しかるべき教育」を施され、次世代のエリートとして育てられる。そして劣った子は秘密のうちにかくし去る、つまり社会的に(もしくは物理的に)抹殺する国家をプラトンは想定しているのです。
これには驚きました。こうした発想はオルダス・ハクスリーの『すばらしき世界』を連想させます。

この世界も生殖と子供の教育を完全にコントロールした世界です。まさしくこの小説で語られた不気味な世界をすでにプラトンは想像していたのでしょうか。
プラトンはこの本で師のソクラテスと同じように相手に質問をし、そこからそれをどんどん問い詰めることで最後には論破するという形式で自説を語っていきます。(プラトンはこの本のメインの語り手である主人公にソクラテスを設定しています。つまり、師の姿を借りてこの本で自説を述べています)
特に『国家』の前半はそんなソクラテス式問答法が次から次へと炸裂します。こんな人は絶対に敵に回したくないなと正直思ってしまいました。
ソクラテス、プラトンの恐るべき知性をこの本で目の当たりにすることになります。
理性を極限まで突き詰めていくとこういうことになるのかと感じてしまいました。
特にプラトンは尊敬する師を失った悲しみ、憤りからこの本を書いています。そんな彼が理想の国家を極限の理性を用いて創造した結果、私たちから見ればディストピアのような世界になってしまったというのは、まさしく小説の闇堕ちみたいな話ではないでしょうか。これは何とも言えない重い気持ちになってしまいます・・・
もちろん、当時の時代背景、時代精神というものも当然ありますので、現代を生きる私たちのものさしで考えるのはナンセンスです。ですが、このプラトンの『国家』がヨーロッパ人の精神に多大な影響を与え、後のトマス・モアの『ユートピア』につながり、そこからさらに空想的社会主義者たちやマルクス、レーニン、スターリンの世界にも繋がっていくというのは非常に興味深いものがありました。
これは読んでよかったです。
かつては挫折したこの本ですが、やはり「今読まねばならぬ」という目的意識があると全然違ってきますね。読んでて面白さすら感じてしまいました。
「目的があること」は読書における良いスパイスであることを実感した読書になりました。
以上、「プラトン『国家』あらすじと感想~エリートによる国家運営の原型。ここからすでに管理社会は始まっていた」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事



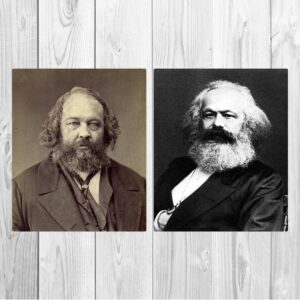

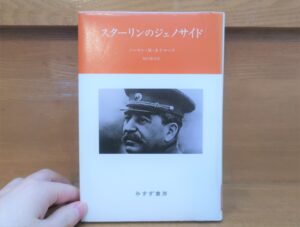












コメント