ツルゲーネフ『煙』あらすじと感想~ドイツの保養地バーデン・バーデンが舞台!文学における芸術を知るならこの本がおすすめ!

ツルゲーネフ『煙』あらすじ解説―文学における芸術を知るならこの本がおすすめ!
『煙』は1867年にツルゲーネフによって発表された長編小説です。
私が読んだのは河出書房新社『世界文学全集9 プーシキン ツルゲーネフ』所収の神西清訳の『けむり』です。
では早速あらすじを見ていきましょう。少し長いですがアンリ・トロワイヤの『トゥルゲーネフ伝』が非常にわかりやすかったのでそちらを引用していきます。
『堙』の恋愛の筋立ては、『貴族の巣』と同じ着想に基づいて展開している。この新しい小説の主人公リトヴィーノフもまた、決断力を欠いた苦悩するハムレットの一人である。
彼はバーデン=バーデンで静養しており、婚約者である優しいタチヤーナと、その叔母カピトリーナ・シェストワと一緒である。
その彼が情熱的で浮気な、若く美しい女性イレーネと邂逅する。かつて彼が恋をし、結婚しようとまで思いつめた女性だった。しかし社交界に出て成功をおさめたイレーネは、もっと華々しい運命を求めて彼を捨てたのだった。
彼女はバーデン=バーデンで、愛想よく優雅で恰幅のいい将軍の夫とともに、街の小さなロシア人社会に君臨していた。
リトヴィーノフと再会した彼女には、もはや一つの考えしか浮かばない。すなわちふたたび彼の心を取り戻すことである。ほどなく彼はそれに屈した。
気まぐれなイレーネのような浮かれ女をまた愛せば、待っているのは破滅だと知りながら、リトヴィーノフは婚約者と別れ、イレーネに駆け落ちしてほしい、と申し出た。
彼女は土壇場になって、二度までもリトヴィーノフの人生を打ち壊しておきながらその恋を捨て、夫の元にとどまる決心をする。
主人公はロシアに戻ってゆく列車の中で、苦痛のあまり「ぐったりと」しながら、汽車の煙が風によって、駅のプラットホームに流れ込んでゆくのを眺めている。
「その車両には彼一人しかいなかった」とトゥルゲーネフは書く。「誰ひとり邪魔する者はいなかった。『煙だ、煙だ』と、彼は何度も繰り返した。と突然、彼にはすべてが煙だと思えてきた。自分の人生も、ロシアでの生活も、人間に関わることすべて、とりわけロシア的なるものすべてがである。すべては煙、蒸気にすぎないと彼は考えた。すべては絶え間なく変化し、到るところ新しい像、新しい現象があらわれては古いものにとって代わっているが、しかし実際はすべてが変わらぬままである。すべてが知られざる目的に向かって急ぎ、突き進み、そしてすべては何を達成することもなく、あとかたもなく消えてゆく。」
数年たって心も落ち着き、後悔の気持ちをかかえたリトヴィーノフは、もとの婚約者タチヤーナと再会し、穏やかな結婚生活に入る。イレーネの方は、社交界での成功を目指す。お金があって、人にちやほやされながらも、残念ながらその社会的立場のせいで、きわめて高位の人々からは疑わしげな目を向けられる。そしてその「とげとげしい気性」にあてられて、若い青年たちさえ彼女の元を去っていくのである。
水声社 アンリ・トロワイヤ 市川裕見子訳『トゥルゲーネフ伝』P139-140
主人公リトヴィーノフは彼を深く愛する優しく誠実な婚約者と落ち合うためにドイツの保養地バーデン=バーデンへとやって来ます。

彼の目の前には彼女との穏やかで幸せな生活が待っているはずでした。
・・・あの女と再会するまでは。
リトヴィーノフは再会したイレーネにダメだとわかっているのに惹き付けられてしまいます。
このイレーネという女は非常に狡猾な魔性の女です。こういう女性に目をつけられたリトヴィーノフは不運としか言いようがありません。
とはいえリトヴィーノフはリトヴィーノフで煮えきらないというか、妙に悩み過ぎたりと言いますか自分から破滅に向かいたがっているかのようにも見えます。彼自身にも破滅の原因があったのです。
この物語はそんな二人を軸に展開されていきます。
感想―ドストエフスキー的見地から
この作品はドストエフスキーにもゆかりがあります。
以前の記事「ロシア文学史に残るドイツでのドストエフスキーとツルゲーネフの大喧嘩」でもお話ししましたが、1867年この作品が発表された時、ツルゲーネフとドストエフスキーはドイツのバーデン・バーデンで大喧嘩をしたのです。

その時ドストエフスキーはツルゲーネフをやっつけるためにこの小説をやり玉に挙げ彼をカンカンに怒らせます。
実際、この『煙』という作品はロシアで非常に評判が悪かったのです。
1860年頃からの『その前夜』、『父と子』あたりの作品からツルゲーネフはロシアの文壇から激しい非難を浴びることになります。
この小説もそれらの作品の流れを受けたものでやはりロシアの実態を風刺したものと捉えられ、ロシア人から怒りのこもった非難を浴びることになりました。
当時のロシアの文学界は政治的、思想的な強い主張がないと評価されない風潮がありました。しかしツルゲーネフはそのような強い主張をすることを避け、ひたすら社会を観察し、それを芸術に昇華することを目指していました。そんなツルゲーネフの姿勢がロシアの過激な文壇からは弱腰な時代遅れなものと映ったのです。
このことについては以前の記事「ツルゲーネフ『その前夜』あらすじ解説―農奴解放直前のロシアを描いた長編小説」でお話ししましたのでそちらをご参照ください。
さて、当時のロシア文壇からは不評だったこの作品ではありましたが現代日本に生きる私が読んでみたらどうだったのかと言いますと・・・
正直、面白くはなかったです。
リトヴィーノフとイレーネのどうしようもない恋、そしてそれを取り巻く小者な男たち。彼らのやりとりを延々と見せられるのはかなり厳しかったです。ストーリー展開もそれほどなく、ただただリトヴィーノフが振り回され、婚約者への不実をぐにぐに悩み悔やみ続けます。
では、この小説は読むに値しないものなのか。
いや、それが違うんです。
実は私にとってこの『煙』という小説は、ツルゲーネフ作品の中でもトップクラスに印象に残った作品となったのです。
面白くはないはずのこの作品がなぜ私の中でこんなにも印象に残ったのか、そのことを説明するのにズバリな解説が文学全集の巻末解説にありましたのでそちらを紹介します。
長編小説『けむり』の終章で、女と別れた主人公リトヴィーノフが、汽車の窓を流れる白い蒸気を眺めながら、人間世界のいっさいは「みんな煙なんだ、蒸気なんだ」とつぶやくくだりは、なんとも文学的である。鑑識の必要がないだけに、いっそう文学的でさえある。
数百ぺージにおよぶこの長編を、作者はこの一節を書かんがために我慢して進めてきたのではないかという、錯覚に陥るほどである。
人生は煙なんだ―なんという美しい言葉だろう。虚無的な、諦観的な匂いのする言葉である。わかりきった哲理であるか。わかりきった哲理を美しく表現するのが文学というものだ。文学は思想ではない。思想は文学になり得るが、文学は思想にならぬのである。
河出書房新社『世界文学全集9 プーシキン ツルゲーネフ』P453
※一部改行しました
これです。まさにこれなんです!
この小説の最後の最後に、すべてを失ったリトヴィーノフが汽車の車窓から眺める景色。
そしてその煙を眺めながら「煙だ、煙だ。」とつぶやくリトヴィーノフ。
この場面はまるで目の前にその情景が現れてくるかのような感覚を受けました。
まるで映画の一場面を見ているかのような気分になったのです。そしてその場面のなんと美しいことか!
解説で「数百ぺージにおよぶこの長編を、作者はこの一節を書かんがために我慢して進めてきたのではないかという、錯覚に陥るほどである。」と言われるのが本当にわかります。本当にそう思ってしまうのです。
たしかにこの小説は面白くはないです。
しかし、最後の最後、この煙のシーンまで来ると「あぁ・・・!」となります。
このためにこの小説を書いたんだと一発でわかります。
するとそれまでの面白くなさが一気に吹き飛びます。
これぞ芸術!これが文学における芸術なんだと驚かされました。
なんて詩的で美しいシーンなんだろうと開いた口が塞がりませんでした。
この作品はたしかにロシア文壇で不評でした。
しかしそれは政治的、思想的な意味においてであります。
今現在、日本を生きる私たちにはそのような制約はありません。
この作品の最も素晴らしい点、車窓から見る煙の一場面の圧倒的美しさをダイレクトに感じることができます。
当時のロシア文壇はあまりに感情的に怒り過ぎていたのでこの芸術に目を向けませんでした。ドストエフスキーですらこの作品をこてんぱんにこき下ろしています。
たしかにこの作品は面白くはないです。思想的にもドストエフスキーが怒るのも十分わかります。ですが、ツルゲーネフの芸術、文学における芸術ということを知るにはうってつけの作品のように思います。
個人的にはとてもおすすめな作品です。私はこの作品がツルゲーネフの中でも特に強いインパクトを残した作品となりました。
以上、「ツルゲーネフ『煙』あらすじ解説―文学における芸術を知るならこの本がおすすめ!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
世界文学全集〈第9〉プーシキン,ツルゲーネフ スペードの女王 猟人日記 けむり 他(1962年)
次の記事はこちら
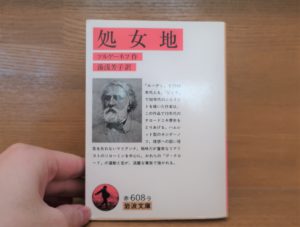
前の記事はこちら

ツルゲーネフのおすすめ作品一覧はこちら

関連記事













コメント