(5)結婚初期のドストエフスキーの危機的な経済状況~なぜ彼はいつまでも貧乏なままだったのか

(5)結婚初期のドストエフスキーの危機的な経済状況~なぜ彼はいつまでも貧乏なままだったのか
前回の記事「(4)文豪ドストエフスキーの一風変わったプロポーズ!アンナ夫人に小説仕立ての愛を告白したドストエフスキーの大勝負!」ではドストエフスキーとアンナ夫人がめでたく結ばれたところまでをお話しした。
今回の記事ではその二人が新生活を始めるにあたりまず考えなくてはならなかった経済問題について見ていきたい。
「(2)ドストエフスキーとアンナ夫人との出会い~絶望的な状況で始められた『賭博者』の口述筆記」の記事でもお話ししたがドストエフスキーは兄ミハイルの急死とそれに伴う会社倒産で莫大な借金を背負うことになった。しかしその後『罪と罰』という大ヒット作を世に送るもなぜか彼の貧乏は相変わらずだった。なぜ彼は貧乏のままだったのか。彼には浪費癖でもあったのだろうか。・・・実は違うのである。この貧乏暮らしには訳があったのだ。
では例のごとくアンナ夫人の声を聞いていくことにしよう。
ふたりにとって、主な、最も重要な話題は、もちろん将来の結婚生活のことだった。
結婚したら決して別れたりせず、夫の仕事を助け、健康を見守り、しつこく悩ませる人々から夫を守ろうと思い、そういうことが間もなくみんな実現するのだと考えると、うれしさのあまり思わず涙がこぼれそうになることがあった。(中略)
フョードル・ミハイロヴィチは、心配ごとをたえず知らせるようにしてくれた。なにごともかくしだてしようとしなかったが、それはたぶん貧しさがつきまとって離れないにちがいない将来のふたりの生活が、わたしに不意の重荷にならないようにするためだったろう。その率直さをわたしはとても有難く思い、とりわけ彼を苦しめている負債をへらすためのさまざまな方法を頭にえがくのだった。
まもなくわかったことだが、いまの仕事の状態では、負債を払いきってしまうことはできなかった。めぐまれた家庭で何不自由なく暮して、生活の実際をろくに知らなかったわたしでも、結婚までの三カ月に、まったくとまどうような或る事実に気づかないわけにはいかなかった。
彼に金ができるとたちまち、弟、兄嫁、義理の息子、甥たちの身寄り全部が、予想外の、だが差しせまった金の無心にやってくる。
「罪と罰」でモスクワから三、四百ルーブルもらっても、翌日には手もとに三、四十ルーブルしか残らず、手形の支払いにまわすどころか、利息をはらうのが精一杯だった。こうして、彼はふたたび、どうして利子をはらい、生活をまかない、たくさんの身内の頼みをかなえるための金をつくるか心配しなければならなかった。
こんなようすを見て、わたしは真剣に心配しはじめた。結婚したら、家計は自分の手でして、親戚たちには各自年いくらと決めて生活費を出すことにしようと考えては自分をなぐさめた。兄嫁のエミリヤ・フョードロヴナには、もう十分たよりになる大きな息子たちがいた。弟のニコライ・ミハイロヴィチは、才能のある建築家で、その気になりさえすれば働くことができた。義理の息子は二十一にもなっていて、病身で多く借財を背負った義父をあてにせずに、何かまじめな仕事につくべき年になっていた。
フョードル・ミハイロヴィチがしょっちゅう金策に走らねばならず、そのために精神状態をわるくし、健康もそこなっているのを見るにつけ、わたしはこののらくら連中みんなに腹が立った。彼はたえず不快な気分でいたので、神経をひどくやられ、てんかんの発作にしばしばおそわれた。彼の生活にわたしが姿を現わすまでは、ずっとこんなぐあいだった。だがわたしは、将来の共同生活で、彼がすっかり健康を取りもどし、快活で楽しい気分がつづくようになってくれることを夢みたものだ。
おまけに負債に苦しんでいた彼は、作品をあちこちの雑誌に、持ちこまぬわけにはいかなかったが、当然その結果、原稿料は、ツルゲーネフやゴンチャロフのような生活にこまらぬ作家たちよりはるかに少なくなった。たとえばフョードル・ミハイロヴィチは、「罪と罰」で、印刷紙一枚あたり百五十ルーブルだったが、ツルゲーネフは同じ『ロシア通報』の小説で、一枚五百ルーブル受けとっていた。
なにより残念なことは、いつまでたってもなくならない借金のために、仕事に追われどおしのことだった。時間の余裕がなく、十分作品に手を入れられないことが、彼にとっては大きな悲しみだった。
批評家はよく、彼の小説は形式で失敗している、ひとつの小説のなかにいくつもの話がからみあっている、事件が互いに重なりあって尻切れとんぼが多いなどといって非難した。
こういうやかましい批評家たちは、彼がどんな条件のもとで仕事をしなければならなかったか、ろくに知らなかったのだろう。たとえば、長篇の最初の三章は印刷がおわり、第四章は組版中、第五章は郵送したばかり、第六章は執筆中で、残りは筋も立てていないというようなことがよくあった。その後、何度わたしは、彼が不意に、「あれほど大事にしていたイデーが台なしになってしまった、取りかえしがつかないと言って、深い絶望にとらわれるのを見たことだろう。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P100-103
これを読んで驚かれた方も多いのではないだろうか。ドストエフスキーはお金を稼いだ瞬間に身内にそのほとんどを持って行かれていたのである。これでは借金を返すどころの話ではない。
だが、これは現代でもよくあるパターンかもしれない。特に南米のサッカー選手がヨーロッパで成功すると一族皆を養うというのはよく聞く話だ。一族の中で誰かが出世頭になれば、その人が一族の面倒を見る。ドストエフスキーもそのように一族の面倒を見ようとしていたのだ。(借金を返してもらえない債権者からすれば迷惑極まりない話であるが)
このドストエフスキーの家族・経済観念について『回想のドストエフスキー』の松下裕氏による巻末解説では次のように述べられている。
ドストエフスキーの生涯でもう一つ目立つことは、その強い肉親愛である。
はやく亡くなった母への愛慕、兄との格別つよい結びつき、弟妹たちにたいするきょうだい愛、この回想の著者である二番目の妻との夫婦愛、晩年になって出来た子どもたちへの溺愛にちかい親子の情ほか、彼の愛情は、肉親たちにほとんど例外なしに向けられている。
なかでも一つちがいの兄にたいしては、彼は特別の感情をいだいていた。彼らは力をあわせて文学の世界に出て行こうとし、それはある程度成功した。彼ら兄弟にはどちらにも一種の事業欲というべきものがあったが、それはのちに雑誌の創刊によって実現し、兄が文学企業家となり弟が創作家となって相たすけ、たがいを支えたのだった。
ドストエフスキーが失意のなかで兄にかけた迷惑と甘えの感情は度はずれたものだった。この兄は、シべリア時代の不幸な弟に、自身も人生の苦闘中だったにもかかわらず、力以上のことをしてやっている。ドストエフスキーはのちに、兄の急死後、その遺族の全生活をみることでこの負目をかえした。彼がこの過大な負担をどこまでも引きうけようとしたことは、昔のことに関係のない二番目の妻にはどうしても理解できないことだったが。ドストエフスキーの甘えの本質は、才能への自負からだけではなく、自分の善意と同じものを他人に求めようとするところから生れたものではなかったろうか。
たしかに彼は人間としてのよさを持っていた、といっていい。この回想記には、著者にとって「わが生涯の太陽」だったというドストエフスキーが理想化されてえがかれているが、それはまったく根拠のないことではなかった。彼には人にたいする思いやりがあり、きちょうめんな一面があった。
対人関係の最もするどくあらわれる金銭観では、ドストエフスキーはどうみても近代的ではなかった。彼は、金のある者が貧しい者の窮状を救うのは当然だと考え、必要ならば持てる者からどんなにしてでも取るという態度だった。雑誌や自分の作品集を出そうとするときに、金持ちの親類たちから金を引きだそうとしたのはそのあらわれだったろう。
他方、彼は人が困っているときに、なければ借りてでも助けようとしてそれを実行したことは、この回想記に著者が何度も書いている。彼にはキリスト教の愛の精神があり、施しということが大切な意味をもっていた。けれども、兄の遺族の面倒をどこまでもみたことなどには、この彼の金銭観が裏づけになっている、とわたしは思う。したがってまた彼の強い肉親愛は、貧しさと結びついていた。肉親愛は、貧乏生活とそのなかでの相互扶助の精神が動機となっていた。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー2』P273-274
ドストエフスキーが身内の者から普請をどうしても断れなかったのはこうした事情があったからなのだ。
優しさと言えば優しさなのかもしれないがやはり度を越している。ドストエフスキーは若い頃からお金の管理が壊滅的に下手だった。自分がいくら持っているのか、どれくらいあれば生活を続けることができるのかという計算が全くダメなのである。そんな彼に次々と普請が来る。となれば計算もせずに言われるがままに彼は与えてしまうのだ。
しかもさらに残念なことに彼は借金取りにまで同じようなことをしてしまっていたのである。それが積もり積もってにっちもさっちも行かなくなる。その結果がアンナ夫人と出会うきっかけにもなったあの奴隷契約だったのである。アンナ夫人がここで現れていなかったらそれこそ彼は破滅だったことだろう。
そしてアンナ夫人の言葉にもあったように、彼はツルゲーネフやゴンチャロフらの半分以下の値段で小説を買い叩かれる。トルストイもそうだ。彼ら大貴族が悠々と作品制作に没頭している間、借金取りの恐怖に怯えて狂ったように小説を書いていたのがドストエフスキーなのである。
ある意味、この常に追い立てられていた環境が彼の黒魔術的な小説に大きな影響を与えていたとも言えるかもしれない。
もし彼が金銭的に余裕があってゆっくりと作品を書いていたら・・・
それはそれで興味深いものがあるが、もしかしたら歴史に残る傑作を残せていなかった可能性も大いにある。私はドストエフスキー小説の最大の魅力の一つは、あの「読む者を引きずり込む混沌」にあると思っている。いつの間にか感情の大渦に巻き込まれていくかのようなあの独特な疾走感。緻密に構成されたというより、一気呵成に書きなぐられたかのような狂気の流れ。これをドストエフスキーが維持できたのかと言われれば何とも難しいところである。
さて、これが結婚当初のドストエフスキーの経済状況である。
アンナ夫人との新婚生活はまずこの経済問題が最大の壁として立ちはだかる。
そしてアンナ夫人には辛いことに、まだまだ障壁はいくつもあった。次の記事ではドストエフスキーを生涯苦しめた持病、てんかんについてお話ししていく。
続く
主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら
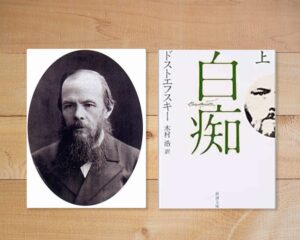
前の記事はこちら

ドストエフスキー年表はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら
「おすすめドストエフスキー伝記一覧」
「おすすめドストエフスキー解説書一覧」
「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」
関連記事




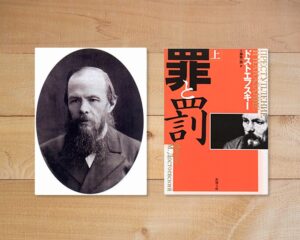



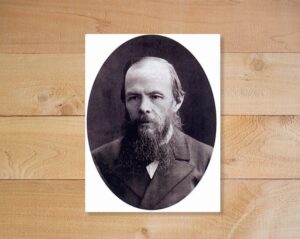





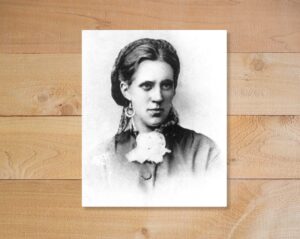

コメント