生きる意味とは?絶望の時代にどう生きる―ショーペンハウアーを読んで感じたこと
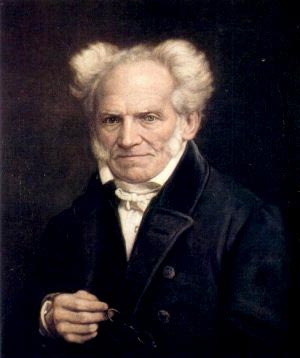
時代精神を掴んだショーペンハウアー
これまで6回にわたってショーペンハウアーについて記事を書いてきました。
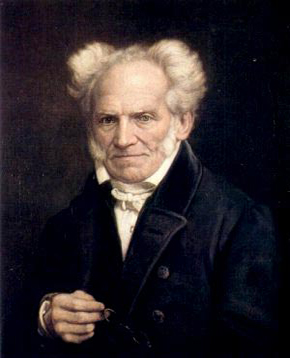
悲観思想、厭世思想の大家として世界中に大きな影響を与えた大思想家ショーペンハウアー。
厭世思想(ペシミズム)の大家ショーペンハウアーとドストエフスキーの記事でお話ししましたように、彼はこの世を「最悪の世界である」と考え、そこから「芸術的静観と仏教的涅槃」によって解脱するべきだと述べます。
ショーペンハウアーはこの世を最悪なものと見ます。
このブログでも紹介してきましたように、彼は『幸福について―人生論―』や『読書について』でこの社会の俗悪ぶりを鋭く批判します。金儲けや地位や名誉のために粗悪なものを大量に作り出し、愚かな大衆はそれを喜んで買い求め、俗悪な人間がますます儲ける。この社会においては真にいいものが全く無視されていると彼は批判するのです。
たしかに『幸福について―人生論―』と『読書について』ではかなり辛辣な意見が述べられています。もし彼の言うことが世の中に全面的に適用されるとしたら、あらゆるものがその活動を停止せざるを得なくなるでしょう。
彼の言葉を聞いていると、そのうち本当に世の中が嫌になってきてどんどん絶望的な気持ちになってきます。
彼の思想は世界中に多大な影響を及ぼしました。
今の私と同じように、世の中が嫌になり絶望的な気持ちになった人間がどれだけいたか測り知れません。
「死んだら無」「どうせこの世なんて」と虚無感を抱えた人がどれだけいたことでしょう。
ただ、これは何もショーペンハウアーのせいというわけではありません。彼がそういうことを言ったからそうなったのではないと私は思っています。
ショーペンハウアーは時代の風潮、時代精神を掴み、それを言葉や哲学にして人々に掲示したということではないかと私は思うのです。
世の中が嫌になり絶望的な気分に落ち込みやすい社会状況がすでにこの世界にあった。しかし個々の人間は苦しみながらもその感情が一体何なのかははっきりとはわからない。何か漠然とした苦悩や怒りが人々の内にあった。
その言葉や形に表せない何とも漠然とした感情をショーペンハウアーは時代から掴み、絶妙に言い表したのだと思います。そしてその言葉に多くの人が共鳴したのではないでしょうか。
ショーペンハウアーの思想が流行したのは19世紀中頃からです。フランス革命からナポレオン戦争を経てヨーロッパ中がまだまだ混乱していた時代です。これまでの秩序が失われ、何が良くて何が悪いのかがあっという間に入れ替わり、何を信じていいのかわからない混沌とした世界でした。
そして新興資本家が次々と現れ、格差が一気に広がった時代です。金があれば何でもできる。金のためには何が何でも勝ち抜かなければならない。そして一度負のループに落ち込んでしまえばもう抜け出すことはできない。金のある人間の横暴、そして無いものの貧困や堕落が世の中を覆っていた時代です。
いくら勉強して知識を蓄えても、そこに自分の場所はない。夢や希望を持って学んだはずの知識や哲学も所詮世の中に出れば役に立たない。学問しても働き口もないのです。もし働くとしてもそれまで嫌悪していた新興資本家と同じことをしなければならない。もしそうなれたとしたらまだ抜群にいい方で、大抵は労働者として搾取されて終わりです。
実はあのツルゲーネフも学生時代に大学教授を志していました。しかしロシアの社会状況によってその道は閉ざされてしまったのです。ツルゲーネフが文学の道に進んだのも大学教授の道が閉ざされたことも大きな影響があったのです。
当時のヨーロッパ、特にロシアでは時代の閉塞感が私たちの想像を絶するものでした。秘密警察が暗躍し検閲も厳しく、密告やスパイが横行していました。そういう時代だからこそドストエフスキーも政治犯としてシベリア送りにされてしまったのです。
そんな人々に「この世は最悪だ」「死ねば無だ」「世の中には俗物が溢れていて真にいいものが捨てられている」という言葉はどのように響くでしょうか。
ここが当時の時代背景を考える上で非常に重要ではないかと私は思うのです。
ドストエフスキーもツルゲーネフもトルストイもこうした絶望の時代に生きていた。そしてそんな中で自分の思想を文学作品に託して世界にぶつけていた。
それは迫力が違うのは当然だと思いました。絶望の中どう生きていくのか、どう打破していくのか、世の中は最悪だとしてそれでもなお生きる意味はどこにあるのか、それを問うのが彼らの文学だった。そう考えると彼らの作品に込められたものがまた違って見えてくるような気がします。
ショーペンハウアーの悲観思想は毒かワクチンか・・・
さて、最後にもうひとつ。上の副タイトルにもありますようにショーペンハウアー思想は毒なのかワクチンなのか・・・このことは非常に重要な点だと私は感じています。
というのも、ショーペンハウアーは後のニーチェと同じく、世俗的なもの、俗物的な商業世界を激しく非難します。
ざっくりと言い換えるなら、
「この世界はわかってない人間ばかりで低俗極まりない。愚かな大衆は金儲けや名誉欲に駆られた俗物たちにいいように騙されている。しかし大衆はそれに気付かない。いや、自ら進んでそれを幸せだと信じている。人間における真の価値をわかっている人間はあまりに少ない。なんて嘆かわしい世の中なのだ」
ということになります。そしてわかっている人間はわかってない人間に不当に扱われ、受難の憂き目に遭うだろうと予言します。
たしかに世の中そういう面もあるかもしれません。資本主義の世界、いや世界そのものはきれいごとだけでは済みません。
しかしショーペンハウアー思想の危険なところはこの「わかっている人間」と「わかってない人間」を二分するところにあるような気がするのです。
どういうことかと言いますと、ショーペンハウアー思想に傾倒すると次のようなことが起こりえます。
「私は世の中を知っている。世界は低俗だ。周りの人間は何もわかっちゃいない。だが、私は真に正しいものを知っているし、行いも正しい。周りの人間はあまりにひどい。こんな人間たちとなど一緒にいたくもない。あぁ、なんて憎たらしいのだ。なんでこんな奴らと私は・・・あぁ!私は不当に扱われている!なぜ正しいはずの私がこんな目に遭うのだ!なぜ私のような人間がこんな惨めな思いをしなければならないのだ!憎い・・・!この世界が憎い・・・!」
自分はわかっている人間であり、周りはわかってない人間だと二分することで、相手が敵になっていってしまうのです。
たしかにショーペンハウアーの言うように、そういう仕組みによって世界が悪い方向へと向かって行ってしまうのは確かかもしれません。しかし、「自分はわかっていて正しいが、他の人間は低俗だ」と決めつけてしまうのは、ただただ攻撃性を増してしまうのみになってしまうのではないでしょうか。
これはありがちですが非常に危険なことだと思います。
世の中そんな単純ではありません。簡単に善悪で割り切れるはずもなく、どれだけ多くのグレーゾーンがあるかは私たち自身が一番感じている部分ではないでしょうか。
「自分はわかっている」、「自分は正しい」、「なぜ自分はこんな目に遭わなければならないのだ。おかしいのは奴らだ」
こうした精神状態は一歩間違えばかなり危険な状態へと向かいます。悲劇はこういうところに起こります。ロシアではそれがやがてテロリズムと結びつき、皇帝の暗殺やテロが相次ぐ時代になりました。日本でも悲惨な事件が今でも起きていますよね。
ショーペンハウアーの思想をこう受け取ってしまうとそれは毒にもなってしまうでしょう。
世の中にはおかしいことがたくさんあります。批判しなければならないことも当然たくさんあります。ですが「自分は正しい」と独善的になり過ぎてしまうとそこにもまた思わぬ罠があるのです。
そして「世の中は最悪だ、死んだら無なのだからどう生きようが関係ないではないか」という虚無主義の絶望へと落ち込んでいきます。
ショーペンハウアーを読むと気分が重くなります。正直、彼の記事を更新している期間、たしかに気が沈んでしまいました。
ですが、ショーペンハウアーは何も世の人々に絶望を運ぶために思想を説いたわけではありません。
彼の主著『意志と表象としての世界』の解説でも次のように書かれていました。
厭世主義、非合理主義、自殺の哲学、女性の敵、反動主義、性愛の哲学、頽廃の哲学―ショーぺンハウアー哲学にはさまざまなレッテルが貼られ、それらが一人歩きすることによって、無数の顔をもった妖怪のような姿で読者を幻惑する。そうした一般評価がほんとうに的を射たものであるかどうかは、読者諸賢が本書を直接読むことによって確認してくださるであろう。
中央公論新社、西尾幹二訳『意志と表象としての世界Ⅰ』P1
ショーペンハウアーは難解過ぎて誤解されがちなのです。
ですので彼の思想が完全に理解される前に、その悲観的な思考が読者を圧倒してしまうのです。
そしてそれに飲み込まれてしまうと、先ほど申しましたように毒となってしまうのです。
ですが、もしそうしたショーペンハウアーの思想を摂取し、それに耐えることができたならそれは厳しい世の中に対するワクチンともなります。
ショーペンハウアーは世のあり方に厳しいメスを入れ、私たちが気付かない、あるいは見ようとしない世界の姿をはっきりと私達に突き付けます。
もしそれに対する免疫を持っていなかったら、私たちはそれに対して全く無防備ということになり、パニックを起こしてしまうことでしょう。
しかし、「世界とは、人生とは、幸福とは」とショーペンハウアーの思想を摂取することでそれに対する免疫を持つことができます。
そして彼の悲観主義、厭世思想を知った上で、「ではどうやってそれを乗り越えていくのか、最悪の世界だとして、それでも私はなぜ生きるのか」と私たちは考え始めるのです。
悲観主義に沈むのはあっという間です。現実の辛い環境に置かれればどんな強い精神を持っていたとしても押しつぶされてしまっても全くおかしくありません。
しかしそれでもなお考え続け、生きていく。そのもがきこそショーペンハウアーとの戦いになるのです。
ツルゲーネフもトルストイもドストエフスキーもなぜ生きるのかということにストレートにぶつかっていきます。
フランスの文豪エミール・ゾラもショーペンハウアーの悲観思想と戦っています。
そして今私が読んでいるロシアの偉大な劇作家チェーホフもまさしくショーペンハウアーと真向かいになっています。特に彼の代表作『六号病棟』、『退屈な話』、『ともしび』ではまさしくショーペンハウアー思想が物語として語られていきます。この作品におけるチェーホフの筆は鬼気迫るものがあります。彼がどれほどショーペンハウアーと真向かいになっていたかが感じられます。
このタイミングでショーペンハウアーを読むことができて本当によかったなと思います。
彼の本を読み、考え、記事にするのはなかなかに厳しい時間でした。普段の数倍疲労感がたまり、気持ちも落ち込みました。
しかしだからこそショーペンハウアーの悲観主義を乗り超えねばならぬとも感じました。ドストエフスキーやトルストイはその偉大なる先達なのだと改めて感じたのでありました。あの時代の文豪たちがなぜあそこまで本気で「生きること」について思索し続けていたのかが少しわかったような気がしました。
絶望の時代だったからこそ彼らは「生きること」に真剣になっていたのだと。そしてその葛藤を文学にぶつけていたのだと。
ショーペンハウアーは答えを与えてくれません。
「思索せよ。言われたことを鵜呑みにしてはならない。じっくりと自分の頭で考えるのだ。」
ショーペンハウアーは改めて私に大きな課題を与えてくれたように思えます。
絶望の時代にどう生きるのか。
これは今まさしく私たちが直面している問題です。
コロナ禍において「世の中何かおかしい。これでいいのか。自分は何をすべきなのか」と多くの方が考えられたと思います。そして同時に「何をしても事態は変わらず、何をしても無駄。何を信じていいかわからない」というという無力感、絶望感を感じた方も多いのではないでしょうか。
私はそのどちらも感じました。いや、今も感じています。
絶望の中でどう生きるのか。なぜ私たちはこの世を生きねばならないのか。
ショーペンハウアーを読んでそのことを改めて強く意識しました。
このタイミングでショーペンハウアーを読めて本当によかったなと思います。
次の記事ではドストエフスキー亡き後のロシアで活躍したチェーホフについてお話しします。
先程述べましたようにチェーホフはショーペンハウアー思想に強い影響を受けています。
チェーホフを読むとショーペンハウアー思想が世の中にどう受け入れられていたかが非常にわかりやすいです。
ぜひ引き続きお付き合い頂けましたら嬉しく思います。
以上、「生きる意味とは?絶望の時代にどう生きる?―ショーペンハウアーを読んで感じたこと」でした。
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事
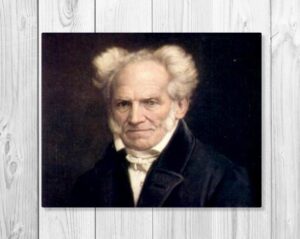











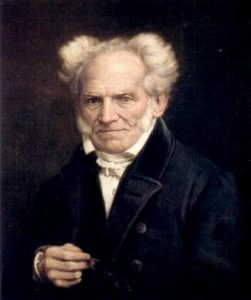
コメント