チェーホフ『退屈な話』あらすじと感想~トルストイも絶賛!退屈どころではないとてつもない名作
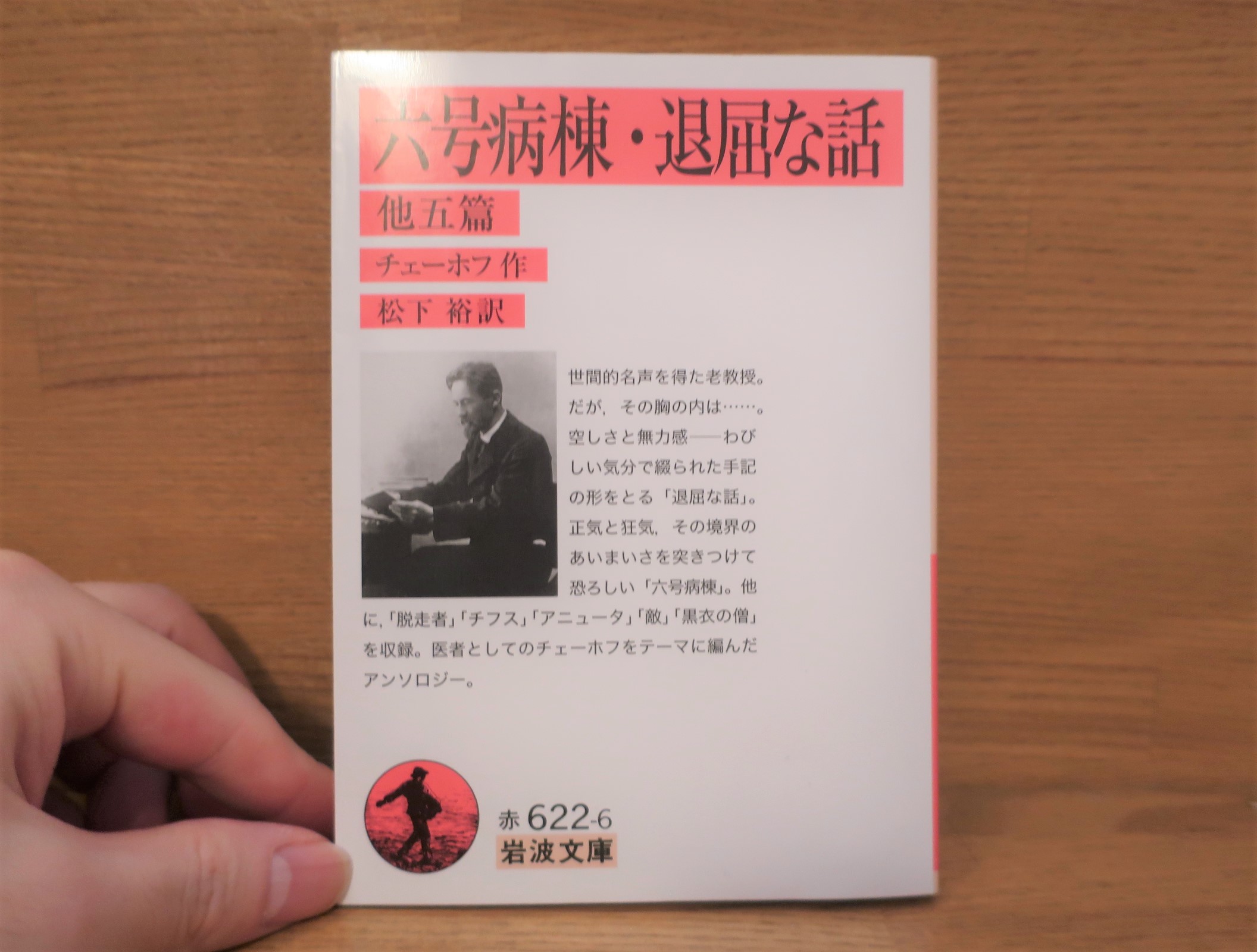
チェーホフ『退屈な話』あらすじ解説―トーマス・マン、トルストイも絶賛した名作短編

『退屈な話』は1889年にチェーホフによって発表された短編小説です。
私が読んだのは岩波文庫、松下裕訳『六号病棟・退屈な話』所収の『退屈な話』です。
この作品の主人公はニコライ・ステパーノヴィチという老教授で、この教授の手記という形で物語は進んで行きます。
この物語についてチェーホフ研究者佐藤清郎氏は次のように解説します。
『退屈な話』は、チェーホフをサハリンに駆り立てた動機を探る鍵の一つを秘める作品である。まさに「人は何のために生きるのか」という熱い問いかけで全篇が貫かれていると言っていい。のちの実存主義の先駆的作品のおもむきさえある。
この時期の彼がしばしば口にしていたように、文学は「問題解決」を目指すべきものではなくて、「問題提起」を目指すべきだという、まさにその「問題提起」を一つの極限状態において提示してみせた作品である。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P145
チェーホフはこの作品を書いた翌年の1890年、サハリン島へと調査旅行に赴きます。この旅行が後の作家人生に大きな影響を与えることになります。
なぜ彼はわざわざ命の危険をも顧みず旅に出たのか、その謎を解く鍵のひとつがこの『退屈な話』と言われています。
主人公ニコライ・ステパノヴィチ教授は今年六十五歳(プロトタイプはモスクワ大学教授ア・イ・バブーヒンだと言われている)、病気のため、あと半歳の生命であることをみずから知っているという設定になっている。
世間的には功成り名を遂げたと言っていい境遇だが、ある日、突然、これまでの生涯がまったく空虚であったことに気づくのである。
「生きた人間の神」(世界観)がないからだと言う。「普遍的理念」を持たないことに気づいたからだと言う。それも、「ある日、突然」にそのことに気づくのである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P145ー146
これまで学者として成功するために必死に学び、実際に国内外に知られる教授となったニコライ・ステパノヴィチ。世間的には成功者として晩年を迎えています。
しかし死を目前にしてその世間的名声、成功がまったく空虚なものにしか見えなくなってしまった。自分はこれまで一体何をしてきたというのか、このまま空虚なまま死を迎えるだけなのかと彼は悩み始めるのです。
突然、この世の一切が別の眼で見えてくる。突然の覚醒は家族の誰にも起らず、この勅任教授にだけ起る。なぜ彼だけに起るのか。
「わからない。もしかしたら、すべての不幸は、妻や娘には私のような力が神から与えられていないためであろう」と彼は解釈する。
妻子には与えられていない覚醒の「力」が彼のみに与えられており、「ある日、突然」目覚めることからすべては始まるのである。
「あなたの眼が開いただけよ。それだけよ。あなたは以前なぜか気づきたくなかったことが見えてきただけよ」と友人の娘カーチャは言う。おそらく、そのとおりであろう。人には、「気づきたくない」ものがあるものだから。(中略)
作品構成の上では、チェホンテ時代の手慣れた手法が使われている。つまり、初め虚を実と思いこんでいた者が、ある日、突然、それが虚であることに気づくという構図である。(中略)
もしこの、「覚醒」が訪れなければ、安らかな晩年がこの老教授を待っていたであろう。満ち足りた安らぎの中に、日々過していられたであろう。世の多くの「成功者」たちがそうであるように。作者は非情にも、ぬるま湯の幸福から主人公を引っぱり出して、生きる意味の総括を求める。この覚醒は自足的幸福から自覚的苦悩へ主人公を導く。凪いでいる水面に、なんで波を起させる必要があるのか。
それが「真実」の要求なら仕方がない、と作者は言いたげである。
「退屈な話」執筆の翌年、作者自身も「真実」を求めて苦行の旅に出発するのである。諸事実の底にひそむ真実を自分の眼で確かめるために。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P146-147
ぬるま湯の幸福から自覚的苦悩への目覚め。
これは後のチェーホフ作品でも語られ続けるテーマです。
そして佐藤氏は次のように指摘します。
この作品の原題が「名声と私」であったことも、見落していいことではない。
新進作家チェーホフの名はすでにかなり広く知れわたっていて、文学の新しいスターとしての地位は固まりつつあつた。そのため、家族までが特別視される。「あれがチェーホフの、あの作家の妹よ」とささやかれたことを妹マリヤが伝えている。
一個の人間としてでなく、「名声」という余計なレッテルつきで見られるようになっていたのである。チェーホフはそのたびに顔をしかめる。人間が消えて、「名声」のみがひとり歩きをするからだ。
しかも、その名声にふさわしい内容はまだ彼にはなかった。それをいちばんよく知っているのは彼自身なのだ。いまのところは、「まだ」ないと言っていられる。しかし、いつまでも「まだ」と言っていられるのか。
年老いて、虚名の果てに、「空虚」が待っているとしたら恐ろしいことだ。虚名のなかでむなしく消光する気はさらさらなかった。では、内容のある人生とはいったいどういうものなのか。生き甲斐とは何か。手遅れにならないうちに、生き甲斐のある生き方をしなくてはならない。
『退屈な話』はいわばその自戒の書なのである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P147
この作品はチェーホフ自身の「名声」に対する葛藤が表現されていた作品だったのです。この時チェーホフはまだ29歳。この歳にしてすでにそこまで行く末を考えていたとは、恐るべしチェーホフです。
感想
この作品のタイトルは『退屈な話』ですが、読んでみると退屈どころではありません。とてつもない作品です。
地位や名誉を手に入れた老教授の悲しい老境が淡々と手記の形で綴られていきます。
どんなに光り輝く栄誉や名声、地位があろうと、死を目の前にすればそれらは虚しく散り去る。
今まで自分を支えてきたと思っていたものがすべて意味を失ってしまい、自分が死を待つ丸裸の人間のように思えるようになってくる。
それが自分だけのことならまだいい。しかし問題なのは周りのものすべてが俗悪に見えてくるということ。
愛していたはずの妻や娘ですらそう見えてしまう。かつてはあんなに愛していたはずなのに、今やこんなに惨めな女になってしまった。もはや見る影もない・・・(これは何も見た目の問題ということではありません。あくまで精神的なものです)
そんな老教授にチェーホフは最後の最後まで人生とは何かの答えをあげません。
チェーホフはこの小説で「問題解決」ではなく、「問題提起」をしようとしました。チェーホフ自身がまだその解決を見出せていなかったのもありますが、その解決はあくまで読者自身で考えてほしいとチェーホフは考えたのです。
チェーホフは、こういうふうに死を目前に控えて生涯「共通理念」を持とうとしなかったことを自覚した人間として主人公を描いた。この人間は、経済的に不如意な若い時分から、人生の真の自由を築くような生き方をしてこなかった。家庭からの疎外感と、学問的名声が人生のどんづまりに来てなんの役にも立たない惨めさとが、その生き方にたいする応報だった。(中略)
チェーホフはそれを今後の課題として残し、「退屈な話」では問題提起にとどめ、老主人公の口を借りてかずかずの的確な社会批判をしたのだった。そこにこそこの小説の、作者の危惧した、しかし決して省くことのできない「退屈な話で、非芸術的な論議」(一八八九年九月二十四日付け『北方通報』編集部宛の手紙)のおもしろさがあり、それがトーマス・マンの言う、「『退屈な』とみずから名乗りながら読む者を圧倒し去る物語」(「チェーホフ試論」)となった理由である。(中略)
この作品を知人に朗読してもらったレフ・トルストイは、その間、チェーホフの知力に驚嘆しつづけたという
岩波文庫、松下裕訳『六号病棟・退屈な話』P390
『ヴェニスに死す』や『魔の山』で有名なドイツの文豪トーマス・マンが「『退屈な』とみずから名乗りながら読む者を圧倒し去る物語」とこの作品を評したのはあまりに絶妙であるなと思います。まさしくその通りです。この作品は読む者を圧倒します。
そしてトルストイもこの作品の持つ力に驚嘆しています。
それほどこの作品の持つパワーは計り知れないということが言えるのではないでしょうか。
チェーホフ中期の傑作『退屈な話』、これは非常におすすめです。
以上「チェーホフ『退屈な話』あらすじと感想~トルストイも絶賛!退屈どころではないとてつもない名作」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事









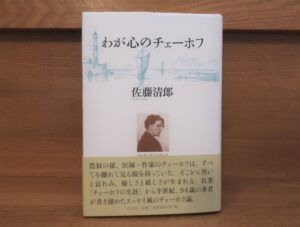



コメント