サハリン体験を経たチェーホフの人間観の変化とは~理想主義と決別し、トルストイを超えんとしたチェーホフ

チェーホフ『決闘』あらすじ解説⑶-サハリン体験を経たチェーホフの覚醒
前々回の記事では『決闘』のあらすじと「ロシアの余計者」について、そして前回はチェーホフとトルストイの関係についてお話ししました。
チェーホフは余計者ラエーフスキーに様々な試練を与え、最後に決闘を経て彼を新たな人生へと旅立たせます。
『決闘』は「ロシアの余計者」という大きなテーマがありますが、チェーホフ研究者の佐藤清郎氏によれば、この作品はチェーホフの思想そのものを知る上でも非常に重要であるとしています。
今回の記事でもその佐藤清郎氏の『チェーホフ芸術の世界』を参考にその意味するところを見ていきましょう。
『決闘』という作品のテーマは、自分の中に真の自分を見出すための精神の旅である。ラエフスキーとフォン・コーレンの間の現実の決闘に先立って、主人公ラエフスキーの心の中で、仮の自分と真の自分との間に熾烈な決闘がたたかわれていたのだ。自己一体性を求めての闘いが。それは、主人公だけの闘いではない。この時期のチェーホフ自身の心の中でも闘われたものなのだ。そして、その闘いは、これから、さらに五、六年はつづくのである。
ひとは多くの場合、「仮の自分」の中に埋没して、「真の自分」を求めようとせず、安易な惰性に身をまかせつつ日日を送っている。自分自身に嘘をつきながら。この作品を読んだスヴォーリンが、「嘘」という題にしたらいいと言ったところ、チェーホフはこう答えた。
「無意識の嘘は、嘘ではなくて、過ちです」
過ちは許されねばならないのである。
人物たちの多くは、それぞれ心の「仮面」をかぶって出てくる。主人公の愛人ナジェージダは、進歩的女性の仮面をかぶり、読みもしないスぺンサーを口にする。
決闘の相手フォン・コーレンは、モラリストぶり、借り物の社会ダーウィン主義で仮装する。主人公自身も「余計者」ぶることで、仮面をかぶり仮装して出てくる。
仮面をとって素顔を見せるためには、この人たちには「情事」や「決闘」が必要だったのだ。だが、仮面をかぶり仮装をまとっている者は、作中の人物たちばかりであろうか。われわれも、ぶってはいないか。醒めた眼で顧みれば、この世は仮面舞踏に似てはいないか。
だが、仮面を取って素顔になることで、人は仕合せになれるか。
その保証は実はどこにもない。むしろ世俗的な意味では不幸になることだって稀ではない。中期以後のチェーホフはしばしば「幸福否定論」を説くようになるが、その幸福はあくまで物質的・世俗的幸福を指すのであって、心の幸福ではない。
チェーホフはあくまで執拗に心の幸福を求めつづけた作家である。心の幸福は素顔になるときから始まる。自分の中に、「純粋」を見出すときから始まるのである。そのときから、すがすがしい涼気が心の中をよぎるようになるのだ。
チェーホフ文学とは、仮面を取らせるための、仮装を脱がせるための努力にほかならない。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P168-169
私たちは仮面をかぶって生きている。そしてこの世はまるで仮面舞踏会のようではないか。
佐藤氏はそう述べます。この考え方はチェーホフが作家としてデビューしてから一貫して彼の中にあったものでした。それは以前紹介した初期の短編『仮装した人びと』でも語られていました。
チェーホフは「虚」の底にひそむ「実」を見抜く。虚と実の対置は、二十三歳のおりの『仮装の人々』に始まり、『退屈な話』『六号室』『黒衣の僧』から晩年の『小犬を連れた奥さん』に至るまで、プロット構築の大切な骨組となっている。虚と実の対置こそ覚醒へ通じる近道であるとチェーホフは考えている。覚醒へのいざないこそ、チェーホフ文学の変ることのないテーマなのである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P169
そしてその仮装によって隠されていた真実の姿に目覚めること、これこそがチェーホフ文学のテーマなのだと佐藤氏は述べるのです。
今回の作品ではそのためにラエーフスキーは様々な危機に遭い、そして決闘で死の恐怖を味わうことになります。彼にとってはそれが「覚醒」のために必要なものだったのです。
象徴的なシーンがあります。
決闘の前夜、「明日にも自分は殺されるだろう」と怯えるラエーフスキー。経済的にも行き詰まり、嘘ももうつけない。万策尽きた。そんな絶望のさ中、とぼとぼ自分の家へ帰っていきます。家に帰ると恋人のナジェージダが寝床で横になっていました。ナジェージダは彼に気づき、寝床に座ります。
そしてそんな彼女を見て彼は次のような行動を取るのです。
彼はやにわに彼女を抱きしめて、その膝や手に接吻の雨を降らせた。それから彼女がなにか彼に呟いて、思い出にわなわなと戦くと、彼は女の髪を撫でてじっとその顔に見入りながら、この不幸な罪の女こそ自分の唯一の隣人、親身の、かけがえのない人間であることを覚った。
外へ出て馬車に乗ったとき、彼は生きて帰りたいとしみじみ思った。
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 8」P459-460
それまで顔を見るのも嫌で、不貞すらしていた恋人に対して彼は「この不幸な罪の女こそ自分の唯一の隣人、親身の、かけがえのない人間であることを覚った」のです。
自分もこれまで彼女に対して罪を犯していた。そして彼女も罪を犯していたがそれを悔い、こうして自分を待っていてくれた。間もなく死んでしまうであろうという気持ちでいた彼が、この時になってようやく彼女を真に愛し、そして「生きていたい」と思った。
「余計者」の系譜にいた人物の中でこれほど誠実な心を持った人間はいませんでした。人生に投げやりだったはずの彼が「生きていたい」と思うようになった。これは驚きの展開です。ここにチェーホフらしい人間観が込められています。
そして決闘は行われ、ぎりぎりのところで彼は命拾いし、両者は和解することとなりました。
そして月日は経ち、彼は正式に彼女と結婚をし、地道に借金を返そうと別人のように勤勉になりました。その姿は宿敵フォン・コーレンですら驚嘆するほどでした。
この物語はフォン・コーレンが船で旅に出るのを皆で見送るシーンで終わります。
ボートは素早く埠頭を廻って、沖へ乗り出した。波間に隠れるかと思うと、すぐまた谷の底から高い丘へせり上がって、人影から橈まで見分けられる。ボートは三間ほど出ては、二間ほど投げ戻される。
「手紙をくれよお」とサモイレンコは彼に叫ぶ、「悪魔めが、とんだ天気に君を引っ張りだしたなあ。」
『そうだ、誰もまことの真実を知るものはない……』とラエーフスキイは、悲痛な眸を荒れ騒ぐ暗い海に注ぎながら思う。
『ボートは投げ戻される』と彼は思う、『二歩出ては一歩さがる。けれど橈子は頑強だ。たゆまず橈を働かせて、高い波も怖れない。ボートはだんだん前へ出る。ああもう見えなくなった。半時間もすれば橈子の眼に、はっきりと船の燈が見えだすだろう。一時間もすればもう船のタラップに着くだろう。人生もこれと同じだ。……真実を求めて人は、二歩前へ出ては一歩さがる。悩みや過失や生の倦怠が、彼らをうしろへ投げもどす。真実への熱望と不撓の意志とが、前へ前へと駆り立てる。そして誰が知ろう、おそらく彼らはまことの真実に泳ぎつくかもしれないのだ……」
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 8」P478
この結末について佐藤氏は次のように述べています。
『決闘』の末尾の感慨が、三十二歳の時点でのチェーホフのたどりついた思想である。
「人間は真実を求めて二歩前進し、一歩後退する。苦悩や過ち、退屈が、人間を後ろに投げ返すが、真実の渇きと不屈の意志は、前へ前へと駆り立てる。そして、誰が知ろう?ひょっとしたら、真実にまでこぎつけるかもしれないということを……」
試行錯誤の是認であり、回答の猶予である。不可知論的絶望ではない。人間の可能性を信じるオプチミズムが底にある。この姿勢は、基本的には、これから生涯にわたって変ることがないのである。
かくて、人物たちはそれぞれ借り物の衣装を脱ぎ捨て生地で生きようとする。そして、それぞれ違った「人生の旅路」に出発し、余計者やスペンサーのパロディたちの覚醒劇は一応ここで幕を閉じるのである。
物語の終りは新しい生活の門出となる。いざ生きめやも、である。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P180
人間の可能性を信じるオプチミズム。
「人間は真実を求めて二歩前進し、一歩後退する。苦悩や過ち、退屈が、人間を後ろに投げ返すが、真実の渇きと不屈の意志は、前へ前へと駆り立てる」という人生観がチェーホフにはあるのです。
地獄の島サハリン島を経て書かれた『決闘』はチェーホフの思想を知る上でも非常に重要な作品となっています。
以上、「サハリン体験を経たチェーホフの人間観の変化とは~理想主義と決別し、トルストイを超えんとしたチェーホフ」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事
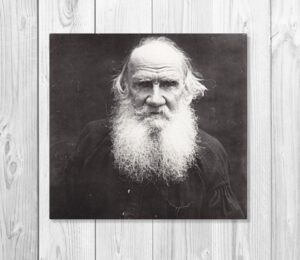










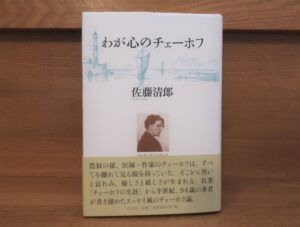



コメント