P・マクフィー『フランス革命史 自由か死か』あらすじと感想~フランス革命の背景を大きな視点で捉えるおすすめ解説書
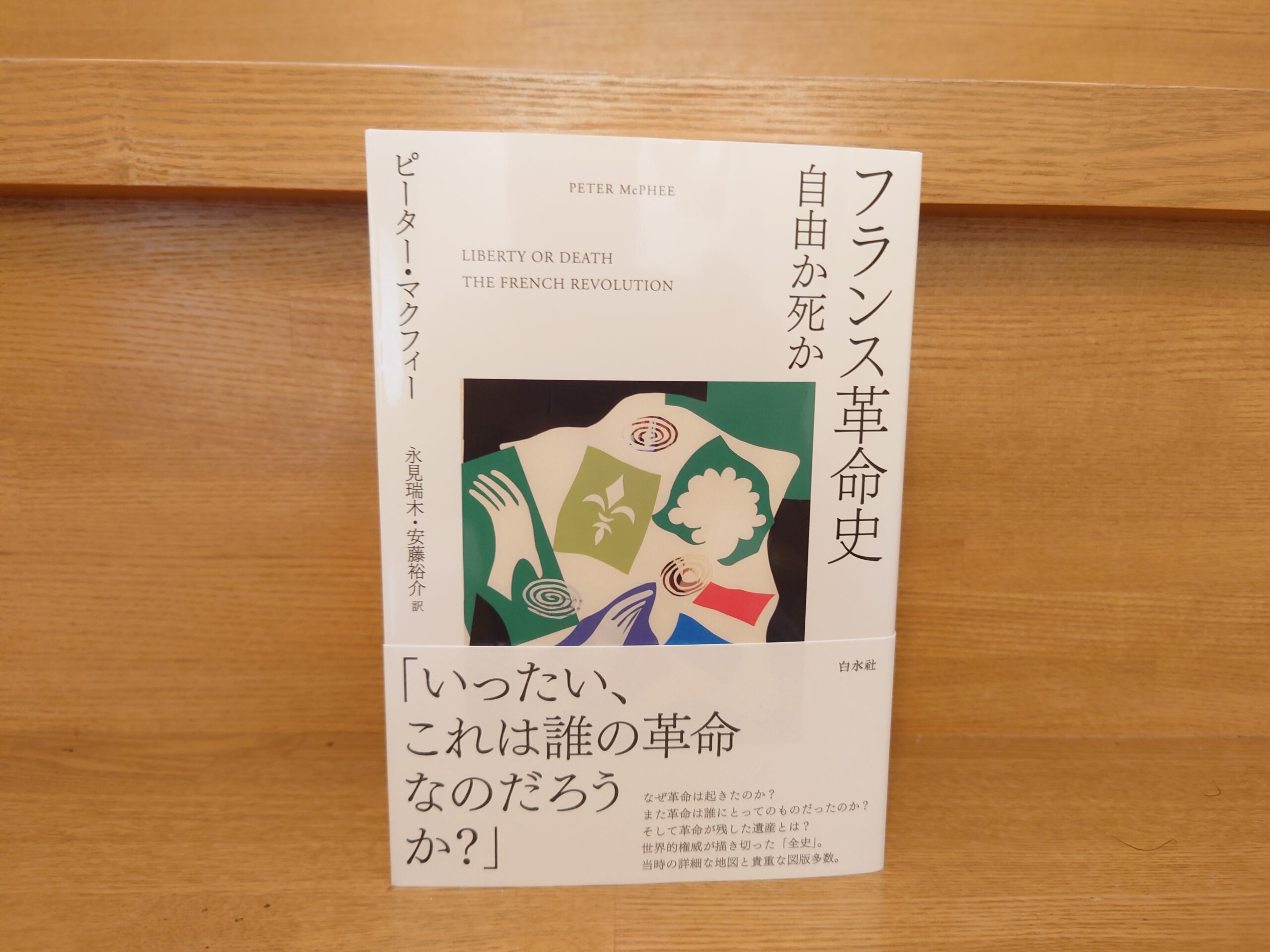
P・マクフィー『フランス革命史 自由か死か』概要と感想~フランス革命の背景を大きな視点で捉えるおすすめ解説書
今回ご紹介するのは2022年に白水社より発行されたピーター・マクフィー著、永見端木、安藤裕介訳の『フランス革命史 自由か死か』です。
早速この本について見ていきましょう。
革命は終わったのか?
1789年以降、フランスの革命家たちは人民主権、国民統合、そして市民的平等の諸原理に基づいて自分たちの世界を再建しようと努めた。それは、絶対王政と身分特権、地方特権に彩られた王国において、途轍もない挑戦だった。
Amazon商品紹介ページより
本書は、なぜ革命が起きたのか? また革命は誰にとってのものだったのか? そして革命が残した遺産はなにか? 世界的権威が描き切った「全史」である。
これまでの革命史は、革命は純粋にパリのものであり、それに反抗し、敵対心を募らせる農村に押し付けられたものであるかのように描かれてきた。パリが革命を起こし、地方がそれに反応した、というわけだ。
本書は、対照的に、パリ対地方という図式を超えて、人々の主体的選択という側面を重視している。革命は嵐のように人々を翻弄したのではなく、一人ひとりが自ら選び取った出来事だったのだ。
「革命は終わった」――。1789年以降、何度もこう繰り返されてきた。ナポレオンもフランソワ・フュレもそう宣言してきた。しかし本書によれば、革命は「決して終わらない」。世界史の転換点と一人ひとりの決断に寄り添った革命史の決定版!

フランス革命といえば1789年7月14日のバスティーユ監獄の襲撃が有名ですが、本書はこうしたパリでの出来事だけではなくフランス全土にわたって革命の流れを追っていきます。
私達はフランス革命というとパリをすぐに思い浮かべてしまいます。ですがこの革命はパリだけに起こったわけではありません。パリと地方、相互の関係性によってこの革命は動いていたのでした。
著者のピーター・マクフィーは序章でこのことについて次のように述べています。
フランス革命の一般的な歴史の大半は、あたかも革命が純粋にパリのものであり、それに反抗し、敵対心を暮らせる農村に対して押し付けられたものであるかのように書かれてきた。パリが革命を起こし、地方がそれに反応した、というわけである。これとは対照的に、本書の基底となるアプローチは、フランス革命はパリの政府と国全体に広がる人々、すなわち都市や町、村の人々との間の交渉と対決の過程として最もよく理解し得るというものである。そのため本書の読者は、パリでの政治抗争の歴史と同じくらい、いかにして都市と農村の普通の人々が革命的変化を引き起こし、それに対抗し、それを経験したのかについて、多くを知ることになるだろう。
白水社、ピーター・マクフィー、永見端木、安藤裕介訳『フランス革命史 自由か死か』P13-14
フランス革命はミラボー、アベ・シェイエス、ロベスピエール、ダントンなど、有名人がどんどん出てきます。
フランス革命といえば首都パリを舞台に政治家たちと国王側が繰り広げた闘いがフォーカスされがちですが、事はそんなに単純な話ではありませんでした。
この作品はフランス革命の複雑さにスポットを当てています。訳者あとがきではこのことについて次のように述べられています。
マクフィーは叙述にあたり、敵か味方かといった二項対立や分かりやすい単純な図式を退け、あえて物事の複雑さや多面性、多様性に着目し、時には矛盾や緊張関係を孕んだ社会の姿をありのままに捉えようとする。
貴族や聖職者の内部にも分断は存在するし、マルクス主義的な「革命的ブルジョワジー」などは想定されない。何よりも、本書を通じて読者は改めて、革命の舞台となる当時のフランス社会がいかに多様性の宝庫であったかを知ることになるだろう。
フランスという国土が抱える多様な自然環境や居住環境からはじまり、各地方の農業実践、商業や交易、産品、言語や文化に至るまで、実に様々である。あるいは政治活動に積極的な女性やユダヤ人、プロテスタント、エスニック・マイノリティの存在も度々フォーカスされる。
人々はフランス人となる以前にブルトン人、バスク人、カタルーニャ人でもあり、フランス語よりもそれぞれの地域言語を日常では使用していた。国境付近では、侵攻してくる敵方の話す言葉を理解するものの、同じフランス人同士互いの言葉が通じないことすらあった。また都市と農村の文化的隔たりに加えて、宗教への関与の度合いにおいても地域ごとに顕著な違いが見られた。
こうした多様性はまさに、長い年月をかけて伝統や慣習、種々の特権が重層的に積み上がってできたフランス社会の歴史に由来するものでもあり、そうした社会に人民主権や国民統合、市民の平等といった原理を打ち立てることがいかに困難を極めた企てであったかが強調される。
そしてこのような多様な条件を踏まえれば、革命の経験もまた人それぞれ異なるものとなるのは不思議なことではない。革命が未来の可能性を開き、希望をもたらした人々がいる一方で、革命によって一切を失った人々がいたのであり、そうした経験は革命のイメージ、個人や家族、共同体の記憶、さらには政治的イデオロギーという形で長く受け継がれることになる。
白水社、ピーター・マクフィー、永見端木、安藤裕介訳『フランス革命史 自由か死か』P492
※一部改行しました
「マクフィーは叙述にあたり、敵か味方かといった二項対立や分かりやすい単純な図式を退け、あえて物事の複雑さや多面性、多様性に着目し、時には矛盾や緊張関係を孕んだ社会の姿をありのままに捉えようとする。
貴族や聖職者の内部にも分断は存在するし、マルクス主義的な「革命的ブルジョワジー」などは想定されない。何よりも、本書を通じて読者は改めて、革命の舞台となる当時のフランス社会がいかに多様性の宝庫であったかを知ることになるだろう。」
ここは非常に重要なポイントです。
フランス革命はとにかく複雑です。ですがそれをわかりやすくするために単純化してしまえば大切なことまで失われてしまうことになります。
この作品はこれでもかというくらいフランス社会の多様性を見ていくことになります。
同じ政治家でも人によって立場や思いも違いますし、地方の村ひとつとってもそこにはひとりひとり全く異なる生活があります。
そんな多種多様な人々がごった返す中でフランス革命はいかにして進んでいったのか、これは非常に興味深いものがありました。
この本を読んで特に感じたのは革命のカオスぶりです。
あまりに多様な人々をどうひとつにまとめていくのか、何かひとつのことをする度に、必ず不利益を被る人が出てくる。そしてその人達は政府の反対者となり、革命の歩みは難しくなる。ではどうするのか?ギロチンか・・・
こうした問題にどうしてもぶつかってしまうのが革命なのかという事を考えさせられました。
また、こうしたことを考えているとどうしても連想してしまうのがレーニンによるロシア革命でした。
ロシア革命勃発後の内戦と粛清も凄まじいものがありました。そのことについてはS.P.メリグーノフ『ソヴィエト=ロシアにおける赤色テロル(1918~1923)レーニン時代の弾圧システム』やヴィクター・セベスチェン『レーニン 権力と愛』で詳しく語られていますが、フランス革命とロシア革命を比べながら考えるのも大切なことなのではないかと思ったのでありました。


さて、ここまでピーター・マクフィー著『フランス革命史 自由か死か』を見てきましたが、この本はかなり骨太な本です。世界のあまりの複雑さに頭がくらくらするほどです。ですが読みにくいとかそういうわけではありませんのでご安心ください。
ただ、フランス革命の入門書としては正直厳しいと思います。ですのでこれまで当ブログでもフランス革命の入門書として紹介した神野正史著『世界史劇場 フランス革命の激流』やルフェーヴルの『1789年―フランス革命序論』などを先に読んでからこの本に取り掛かることをおすすめします。
フランス革命の複雑さ、革命とは何なのかを考えることができるこの本は素晴らしいものがあると思います。
ぜひおすすめしたい作品です。
以上、「P・マクフィー『フランス革命史 自由か死か』フランス革命の背景を大きな視点で捉えるおすすめ解説書」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
前の記事はこちら

関連記事
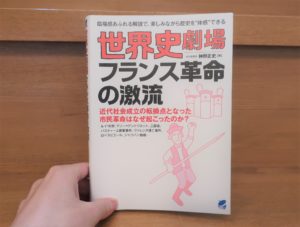












コメント