(2)1932年ウクライナの悲惨な飢饉をもたらしたレーニンボリシェビズムと宗教の関係とは

(2)1932年ウクライナの悲惨な飢饉をもたらしたレーニンボリシェビズムと宗教の関係とは

ヨシフ・スターリン(1878-1953)Wikipediaより
前回に引き続きサイモン・セバーグ・モンテフィオーリ著『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』の中から印象に残った箇所を紹介していきます。
大事なことは会議室で決まるのではない。休暇で決まるのだ。
一九三一年末、飢餓が深刻化して大規模な飢饉が発生しつつある頃、スターリンとナージャの夫婦を始めとしてほとんどの党幹部がすでに休暇に入っていた。
ボリシェビキの幹部たちは休暇をきわめて真面目に考えていた。実際、大飢饉が最悪期を迎えた時期でさえ、スターリンの宮廷内でやり取りされた手紙の少なくとも一〇パーセントは、休暇に関するものだった(二〇パーセントは健康問題に関する手紙だった)。
休暇に関する情報交換のネットワークこそスターリンと懇意になるための最善の方法だった。雪に閉ざされたクレムリンの城壁の中よりも、休暇先の陽光降り注ぐ別荘のべランダで人事問題が話し合われ、陰謀が計画されることの方が多かったのである。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P144
※一部改行しました
政治は会議室だけで決まるのではない。会議と会議の合間の廊下やそれこそ休暇中に重大なことが決まってしまう。
これは政治に限らずあらゆる事柄がそうかもしれませんね。
世の中はなんと難しいことか・・・
1932年ウクライナの「でたらめな」飢饉
政治局の最高幹部たちは、何が起こっているのかを正確に知っていた。彼らの手紙には、幹部用の豪華列車の窓から目撃した恐るべき光景が描かれている。
プジョンヌイは休暇先のソチからスターリンに報告している。「列車の窓から見える人々は、ぼろを身にまとい、疲れきった様子をしている。馬も、骨と皮ばかりだ……」。
しかし、スターリンの気休め役になりさがっていた「村の長老」カリーニン大統領は、「『飢えに苦しむ』ウクライナへの支援」を求める「政治的ぺテン師ども」をせせら笑った。「そういうひねくれた連中を生み出せるのは、堕落し、崩壊した階級だけだ」。
しかし、六月十八日になると、スターリンはカガノーヴィチに対して、いわゆるウクライナの「大飢饉」という「明らかなでたらめ」には実態があることを認めている。
この「でたらめな」飢饉は、そもそも銑鉄の精錬所を建設したり、トラクターを製造したりするための強引な資金調達を行なわなければ、発生しなかった悲劇である。
この悲劇の犠牲となった死者の数は少なくとも四〇〇万人から五〇〇万人、最大で一〇〇〇万人と推定されている。ナチスの虐殺と毛沢東のテロルを別とすれば、人類史上に類例のない悲劇だった。
ボリシェビキにとって、農民は常に敵だった。レーニン自身、「農民はいつも多少飢えさせておかなければならない」と言っていた。
コーぺレフは認めている。「私を含めて、同世代の人間は皆、目的が手段を正当化すると固く信じていた。私の目の前で、人々は飢えて死んでいった」。(中略)
確かに、卵を割らなければオムレツは作れない。だが、素晴らしい『新世界』を建設するという理由でありとあらゆる殺戮が正当化されたのだ。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P167-168
少なくとも400万から500万にも人が餓死をした。それも人為的なものによって・・・
スターリン時代にこういうことが起きていたのです。
しかしスターリン政権下ではそれすらも「素晴らしい新世界」を作るために正当化されたのでした・・・もはや想像を絶する規模の話と化してきました・・・
レーニンボリシェビズムは宗教に近かった?
「銃殺隊のいない革命など意味がない」。そうレーニンは言ったといわれている。レーニンは生涯を通じてフランス革命のテロル政治を礼賛したが、それはレーニンのボリシェビズムが「流血の上に新しい社会システムを構築する」という独特の信条に基づいていたからである。
ボリシェビキは無神論者だったが、普通の意味での世俗主義的政治家とは違っていた。彼らは自分たちが道徳的に最も正しいという驕りから、あえて人々を殺したのである。
ボリシェビズムは宗教ではなかったが、きわめて宗教に近かった。スターリンは、ボリシェビキとは「一種の軍事的、宗教的騎士団である」とベリヤに言ったことがある。
チェーカーの創設者だったジェルジンスキーの死に際して、スターリンは彼を「プロレタリアートの敬虔なる騎士」と呼んだ。
スターリンの「帯剣騎士団」は従来のいかなる世俗的な運動組織よりも、むしろテンプル騎士団に似ており、さらにはイランの指導者アヤトラに操られるイスラム革命防衛隊に近似していた。
彼らは人類の進歩という歴史的必然への信念のために死に、殺し、自分の家族を犠牲にすることさえ厭わなかった。その情熱の激しさは、中世に―そして現在も中東で―信仰のために繰り返される殺戮と殉教にしか類例を見ないものである。
ボリシェビキは自分たちが「高貴な血の流れる」特別の人間であると信じていた。一九四一年、首都陥落の可能性をジューコフ将軍に確かめようとして、スターリンはこう尋ねている。
「モスクワは持ち堪えるだろうか?ここはひとつ、ボリシェビキとして、真実を言ってくれ」。十八世紀のイギリス人なら、さしずめ「紳士として、真実を言ってくれ」と言うところだろう。
「帯剣の騎士」たちには、救世主信仰に劣らぬ信仰心を持つこと、正しい無慈悲さをもって行動すること、そして、自分たちの行動の正当性を他人に納得させることが求められた。
スターリンの「半イスラム的」な狂信は、ボリシェビキ幹部全員に共通する特徴だった。ミコヤンの息子は父親を「ボリシェビキ教の熱心な信徒」と呼んでいた。
幹部たちの大半は敬虔な宗教的環境の中で育った人々だった。彼らはユダヤ教とキリスト教を嫌悪していたが、両親の世代の正教への信仰に代えて、正教よりもさらに厳格な宗教、すなわち一種の体系的な反道徳的信仰を創りあげた。
「この宗教は―その信奉者たちは謙虚にも『科学』と称していたが―人間に神の権威を与えてしまった……この新しい宗教はかつてのキリスト教と同じように勝利を収め、今後千年は続くと多くの人々が二〇年代には信じていた」と、ナッジェージダ・マンデリシタムは書いている。「来世の救いではなく、地上の天国を約束するこの新しい信仰の優越性を誰もが認めていたのだ」
党は信仰の純粋性を理由としてその「独裁」を正当化した。彼らの聖書はマルクス・レーニン主義の教えであり、それは「科学的な」真理であると考えられていた。
イデオロギーはきわめて重要だったので、指導者たちの全員がマルクス・レーニン主義の専門家でなければならなかった。あるいは、少なくとも専門家に見えなければならなかった。
そのため、この無学な無頼漢たちは、奥義体得者の資格を得るために、疲れ果てた身に鞭打って日夜退屈な弁証法的唯物論の勉強に励んだのである。学習はきわめて重要な任務だった。
モロトフとポリーナの夫婦にいたっては、恋文の中でもその間題を論じている。「愛するポーリチカ……マルクスの古典的論文は絶対に読んでおくべきだよ……もうすぐ出るレーニンの著作集も読むべきだし、それにスターリンの本も何冊か……すぐに会いたいね」
「党派性」は「ほとんど神聖な概念だった」と、コーぺレフは説明している。「鉄の規律をもって、党生活のすべての決まりを忠実に守ること、それが絶対的に必要な要件だった」。
ある古参共産主義者の言葉を借りれば、ボリシェビキは単にマルクス主義を信じるだけでは不十分だった。「何があろうと党を絶対的に信ずる人間……自分の道徳心や良心な犠牲にしても、党の無謬性というドグマを―たとえ党が常に間違ったとしても―無条件に受け入れることのできる人間でなければならなかった」。スターリンが次のように自慢した時、そこには何の誇張もなかった。「われわれボリシェビキは、特別仕立ての人間だ」
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P168-170
※一部改行しました
ここはこの本の中でも特に興味深い箇所でした。
ソ連社会では宗教はタブーとされていましたがそのソ連の仕組みそのものが宗教的なものの上に成り立っているという何というパラドックス。
宗教とは何かということをテーマにこれまでも色々と考えてきましたがこれは非常に示唆に富む場面でした。
2019年の6月には私は世界一周の旅の最終目的地として社会主義国家のキューバを訪れました。

この記事でも社会主義と宗教について考えてみましたが2年前に考えていたこととスターリンがつながってきました。
やはりレーニン・スターリンは非常に興味深いです。これからもじっくり考えていきたいと思います。
続く
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

「スターリン伝を読む」記事一覧はこちらです。全部で14記事あります。

関連記事














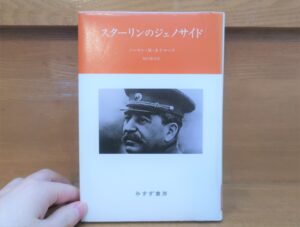
コメント