(3)愛妻の自殺を嘆き悲しむスターリン~スターリンの意外な一面とは

愛妻の自殺を嘆き悲しむスターリンースターリンの意外な一面 スターリン伝を読む⑶

ヨシフ・スターリン(1878-1953)Wikipediaより
引き続きサイモン・セバーグ・モンテフィオーリ著『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』の中から印象に残った箇所を紹介していきます。

1932年、スターリンの妻ナージャの自殺
スターリンが政治局員たちに固まれて到着した。政治局員たちは棺の周囲に立って遺骸を守った。今後、彼らはこの役割にすっかり慣れることになる。その後の数年間、要人の葬儀が次から次に繰り返されるからである。
スターリンはすすり泣いていた。ワシリーがアルチョムを後に残してスターリンに駆け寄り、「父親にしがみついて、『パパ、泣かないで!』と言った」。
ナージャの親族だけでなく、政治局や秘密警察の猛者たちからもむせび泣きの声が漏れてくる中を、首領はしがみつくワシリーを引きずって棺に近づいた。
スターリンが見下ろす先には、彼を愛し、憎み、罰し、そして拒絶した女性が横たわっていた。「スターリンが泣くのを見たのはそれが初めてだった」とモロトフは回想している。「棺の横に立つスターリンの頬に涙が流れるのが見えた」
「お前はまるで敵のように私を見捨てた」とスターリンは苦々しく言った。モロトフはその次の言葉も覚えていた。「だが、私はお前を救ってやれなかった」。
いよいよ棺が蓋われ、釘が打たれる時になって、スターリンは急にそれを制止した。誰もが驚いたことに、スターリンはかがみ込むと、ナージャの頭を抱き上げ、熱烈に接吻した。この姿を目にした人々の間から改めてすすり泣きの声があがった。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P206
スターリンは仕事人間で家庭をまず顧みませんでした。しかしナージャとスターリンは度々喧嘩しながらも心を開いて会話ができる関係でした。スターリンにとって心許せる唯一のパートナーだったのです。
しかしソ連中枢部の異様な状況、つまり政治的策謀やスターリンの奔放な態度にナージャは精神を病んでいきました。そしてとうとう、彼女は自分の心臓を銃で打ち抜き自殺してしまったのです。
さすがのスターリンも妻の自殺にショックを受けたそうです。何百万人もの人を平気で殺した独裁者も妻の死には涙を流し、激しいショックを受けました。
何百万もの人たちの死に対してほんの少しでもそうした死を悼む気持ちがあったとしたら歴史は変わっていたかもしれません。いや、きっとそうならない人だからこそ独裁者になりえたということなのかもしれませんが・・・
妻の死を経て、スターリンは別人となってしまった
今後スターリンは終生ナージャの死の思い出を反芻しながら生きることになる。「ああ、ナージャ、ナージャ、お前は何をしたんだ?」と、年老いたスターリンはつぶやき、そして弁解するように言った。「私にはいつも大きな重圧がのしかかっていたのだ」。
一般に、配偶者に自殺されると、残された者は重大な打撃を受ける。罪悪感にさいなまれ、裏切られ、見捨てられたという苦い思いがいつまでも残るのである。
ナージャに見捨てられたスターリンは傷つき、辱められた。スターリンの中にほんのわずかながら残っていた人間的共感の最後の糸がナージャの自殺によって切れてしまった。
一方、残忍性、嫉妬心、冷淡、自己憐憫などの性向は以前に倍して強まった。もちろん、これには、一九三二年に激化した政治的混乱、特にスターリンが疑っていた一部同志の裏切りも影響していた。
カガノーヴィチは述懐している。「一九三二年を境にして、スターリンは別の人間になってしまった」
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P209
スターリンの負の側面が一気に増幅するきっかけとなってしまったのが妻の死だったとされています。その変わりようは側近に「別の人間になってしまった」と言わせるほどだったのです。
1936年の見世物裁判とイソップ言語
一連の見世物裁判で使われた言葉はまるでヒエログリフのように解読困難である。これを理解するためには、イソップ物語の寓意を解くように、言葉の裏の意味を想像する必要がある。
善と悪とが交錯する閉鎖的なボリシェビキの世界では、たとえば、「テロリズム」とは要するに「スターリンの政策または人格に少しでも疑問を差し挟むこと」という意味であり、政治的反対派であることは、それ自体が「暗殺者」であることを意味していた。
「テロリスト」が二人以上集まれば「陰謀」であり、暗殺者が各方面から集まれば「合同本部」となる。その陰謀の規模は世界的であって、プロフェルド〔007シリーズで世界征服を狙う悪の元凶〕を思わせる。
これは長年の地下生活を通じて形成されたスターリンの内心の妄想とボリシェビキ全般に共通する偏執狂的傾向の産物だった。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P348
見世物裁判とは1936年に行われた政敵を抹殺するために仕組まれた裁判のことです。スターリンは指導部の中で力を持っていた高級官僚を陰謀事件の首謀者としてでっちあげたのでした。
スターリンは見せしめのために周到に仕組んだシナリオを用意しました。基本的に被告は何の罪も犯していません。しかし拷問による強制的な自白を証拠にされ、台本に沿って裁判が行われました。
これは誰であろうとスターリンに歯向かうとこうなるということを知らしめるための裁判でした。
そしてその時に用いられた言葉はイソップ言語と呼ばれ、実際の言葉の意味とは違う解釈を見つけ出さなければいけないという倒錯した心理戦がそこで繰り広げられていたのでした。疑心暗鬼が極限までいってしまった社会がソ連に出来上がっていたことがうかがえます。
スターリンは拷問に立ち会ったことがない
スターリンが拷問や処刑の現場に立ち会ったことは一度もない(もっとも、子供時代には絞首刑を目撃したことがあり、また、ツァリーツィンでも非業の死の現場を多数見たはずである)。
しかし、スターリンは死刑執行人に対して尊敬の念を抱いていた。死刑は公式用語では「最高処罰刑」たったが、普通は略号でVMNまたは「ヴィーシカ」と呼ばれて恐れられていた。スターリンは死刑の執行を「黒い仕事」と呼んで、名誉ある党務と見なしていた。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P357
政策として拷問を命じた人間が実際に拷問をしたことがない。
私はこの事実に戦慄します。
拷問で痛み苦しむ人間の断末魔を聞いてもいず、自分の手を全く汚していない人間がただ「言葉」のみで命令する。
スターリン自身は「拷問せよ」という言葉を発するだけ。
拷問そのものの生々しさや恐怖とは無縁のところに彼はいたのです。
この事実は強調されるべき事実であると私は思います。
テロルは一人ではできない
テロルをもたらした最大の要因がスターリンの意志だったとしても、テロルは一人だけでできる仕事ではない。総会では、血に飢えた十字軍を思わせる熱狂の叫びが飛び交う一方、悲劇と喜劇の境を行き来するような馬鹿げたやり取りも行なわれた。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P370
テロル(暴力による支配)はスターリンによる意志でした。しかしテロルは一人ではできません。
ここで述べられるようにその部下たちも積極的にスターリンの意志に従い、熱狂していました。
テロルはスターリン一人の問題ではなく、彼を取り巻く数え切れない人間たち、そして政治システムそのものがはらむ問題でした。
続く
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

「スターリン伝を読む」記事一覧はこちらです。全部で14記事あります。

関連記事












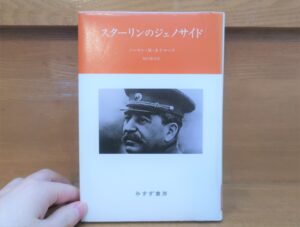
コメント