(1)スターリンとは何者なのか~今私たちがスターリンを学ぶ意義とは

スターリンとは何者なのか~スターリンを学ぶ意義~『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』を読む⑴

ヨシフ・スターリン(1878-1953)Wikipediaより
今回の記事よりサイモン・セバーグ・モンテフィオーリ著『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち』の中から印象に残った箇所を紹介していきます。
スターリンとは何者なのか、ソ連時代に何が行われたのかということを知る上で非常に興味深い箇所ばかりです。
では、早速始めていきましょう。
著者のスタンス。スターリンと廷臣を描く理由
これらの人々について何かを語ろうとすれば、それは必然的に因果応報の物語にならざるを得ない。もっとも、これら大勢の大量殺人者のうち、(罪状が何であれ)罪を問われて起訴されたのはべリヤとエジョフの二人だけである。
これまでは、すべての罪をスターリン一人の責任に帰する考え方が主流だった。西欧社会には彼らを極悪非道な犯罪者集団とみなす固定観念があり、その頭目であるスターリンをヒトラーと比べてどちらが「世界最悪の独裁者」であったか、犠牲者の数の多さを基準にして論ずるようなおぞましくも無意味な議論が行なわれてきた。
しかし、このような考え方は、悪魔学ではあり得ても、歴史学と呼ぶことはできない。事実上ただ一人の人間を狂人に仕立て上げて罪をかぶせる考え方は、ユートピア思想とそのシステムがはらむ重大な危険性についてわれわれに何らの教訓ももたらさないばかりか、人間の個としての責任を不問とする思想だからである。
現在のロシアはまだ十分にその過去に直面しているとは言えない。過去の清算が済んだとはとうてい考えられない。そして、そのことがロシアにおける市民社会の発展に暗い陰を投げかけていることは間違いない。
現代ロシア人の多くは彼らが忘れたいと思い、避けたいと願っている歴史を、その裏面を含めて赤裸々に描き出そうとする私の仕事を歓迎しないかもしれない。
本書はスターリンの大罪を少しも減ずるわけではないが、すべての責任をスターリン一人にかぶせようとする都合のよい作り話を掘り崩すことになるからである。
大量殺人の責任は指導部の全員にあったし、また、指導部の全員にそれぞれの苦悩や犠牲があり、それぞれに特権や犯罪行為があった。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P12-13
※一部改行しました
著者のサイモン・セバーグ・モンテフィオーリはこうした理由からスターリンとその家族、廷臣とのやりとりを中心にこの物語を綴ることになりました。
スターリンとは何者なのか
ここはこの本の中でも特に重要な箇所です。
世界のひのき舞台で英雄として名を残すために私人としての自己を捨てるというやり方は、カエサル以来、世の多くの為政者に共通する習性である。
しかし、スターリンの場合、その習性はやや度を越していた。息子のワシリーが父親の名前を利用したことが発覚した時、スターリンは激怒したが、そのときの言葉を養子のアルチョムが記憶している。ワシリーは、「でも、僕だってスターリン家の一員じゃないか」と口答えしたのである。
スターリンは怒鳴りつけた。「いいや、ちがう。お前はスターリンじゃない。私だってスターリンじゃない。スターリンというのはソヴィエト権力そのものなんだ。新聞に載っているスターリン、肖像画に描かれているスターリン、それがスターリンなのだ。お前や私のような個人がスターリンなんじゃない」
スターリンとは、実はスターリン自身が創り出した架空の人物だった。
歴史を変革し、変革の指導者の役割を演じるという目的のために、名前から誕生日、人種、学歴、過去の全経歴に至るまで新たに創り上げられたこの人物は、意志の力と幸運と手腕に恵まれたおかげで世界秩序の転覆を狙う運動に出会い、しかも、またとない好機にめぐりあったが、さもなければ精神病院で一生を終りかねない存在だった。
スターリンとはそのような人物だった。彼が出会った運動とはボリシェビキ党であり、めぐりあった好機とはロシア帝政の終焉だった。
その死後、スターリンを歴史の逸脱として描くことが長い間一般的だったが、それはスターリン自身の所業と同じくらい乱暴な歴史の改竄でしかない。
スターリンの成功は偶然ではなかった。レーニンの党には、陰謀による政治、石文字のように硬直した理論、殺人を肯定する教義、非人間的なほど厳格な規律などの特性があったか、その特性にスターリンほどぴったり適合する人物は他になかった。
ひとりの人間がひとつの運動と一体化するケースとして、スターリンとボリシェビズムの結合ほど理想的な例は他に見られない。スターリンは、ボリシェビキ運動の美点と欠点のすべてを映す鏡だった。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P30-31
※一部改行しました
スターリン自身が「私だってスターリンじゃない」と述べた。
これは非常に重要な言葉だと思います。
スターリンはソ連の独裁者だとされてきました。しかしそのスターリン自身もソヴィエトというシステムを動かす一つの歯車に過ぎなかったのではないか。スターリンが全てを動かしているようで実はそのスターリン自身もシステムに動かされていたのではないかという視点は非常に興味深いものでした。
独裁者とは何かを考える上でこの箇所は非常に重要であると思います。
レーニンのマルクス主義思想
傲岸な天才政治家レーニンは、マルクス主義思想の基本概念をマキャヴェリ流の実際行動、つまり権力奪取に結びつけ、革命運動の分裂状態を利用してボリシェビキ党を創設し、その指導者となった。
職業革命家によって構成される全知全能の党が労働者階級のために権力を奪取し、いずれ社会主義が実現して独裁が不必要となる時まで、労働者の名のもとにプロレタリアート独裁の支配体制を貫徹するというのがレーニンの主張だった。党を「プロレタリアートの軍隊の前衛部隊……指導者の戦闘集団」と規定するレーニンの見方は、ボリシェビズムに強烈な軍隊色をもたらすことになる。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P68
※一部改行しました
厳密に細かく見ていけば単純にそうとは言えないかもしれませんが、レーニンにとっては実際行動、つまり権力を手中に収めることが目的だった。国の安泰、繁栄よりも権力の確立、維持こそ第一目的。だからこそソ連で大規模な粛清が繰り返されたと言えるかもしれません。
「スターリンは実はロシア皇帝直属のスパイだった」説への反論
一九一三年二月、スターリンは再び逮捕されるが、今回の刑期はあまりにも短かったので、ある種の疑念を招くことになった。
ひょっとして、スターリンはツァーリの秘密警察「オフラーナ」のスパイだったのではないか?しかし、スターリンを二重スパイとするスキャンダラスな歴史観は、当時の地下活動に関する素朴な誤解の結果でしかない。
確かに革命連動にはオフラーナのスパイが無数に入り込んでいたが、その多くは二重スパイどころか三重スパイだった。
コバ(※スターリンの若い時の通り名。ブログ筆者注)も同志の中の敵対派を喜んで警察に売り渡していたかも知れない。しかし、オフラーナの報告書に実際に書かれているように、彼は一貫して狂信的なマルクス主義者だった。重要だったのはその点である。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P72
※一部改行しました
「実はスターリンは皇帝側のスパイだった」という言葉はなかなかセンセーショナルですよね。このキャッチーな話題は様々な本でも語られますが、モンテフィオーリによればそれは素朴な誤解に過ぎないと否定しています。
事実よりもセンセーショナルな話題の方が広まりやすいです。ですがそれの何が本当で何が嘘なのか(あるいはそうあってほしいという願望か)は見分けが難しいです。
私は専門家でありませんのでモンテフィオーリの言葉も本当に正しいかどうかは検証できませんが、この本は膨大な資料に裏付けされた作品ですので信頼度は他の本よりは高いのではないかと思われます。
スターリンによるレーニンの神格化
スターリンが最も有力な後継候補者として浮上しつつあることを見抜いていたのは、レーニンただ一人だった。
そこで、レーニンはスターリンの解任を要求する弾劾の遺書をひそかに口述して筆記させる。
しかし、一九二四年一月二十一日、レーニンは致命的な発作に襲われて帰らぬ人となる。
スターリンは、レーニン自身とその家族の意向を無視して、亡き指導者を事実上神格化する演出を行ない、レーニンの遺骸にロシア正教の聖人のような防腐処置をほどこして赤の広場の霊廟に安置した。
スターリンは亡き英雄の神聖な権威を利用して、自分自身の権力の強化を図ったのである。
白水社、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ、染谷徹訳『スターリン 赤い皇帝と廷臣たち〈上〉』P80
※一部改行しました
レーニンは死ぬ直前、スターリンが後継者の座を狙っていることを見抜いていました。しかも彼の危険性をも察知していました。そのためスターリンが後継者にならないように遺書までしたためたのですが、レーニンは急死してしまい、そのどたばたを利用しその遺書が効力を発揮しないようスターリンは立ちまわります。
さらにレーニンを聖人のように扱い神格化することで自らの権威を高めるという離れ業をやってのけ、独裁者への道をひた走るのでした。
英雄を聖人化し神格化させていき自らがその後継者であると内外に宣伝するのは古今東西の宗教が行ってきたことです。このことからもソ連は宗教を禁じたのではなく、実は自らが唯一絶対の宗教そのものであり、他の宗教は認めないというスタンスであったことがうかがわれます。
このことについては「(16)レーニンの死と今なお生き続ける神殿としてのレーニン廟」の記事でもお話ししましたので以下もご覧ください。

続く
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

「スターリン伝を読む」記事一覧はこちらです。全部で14記事あります。

関連記事






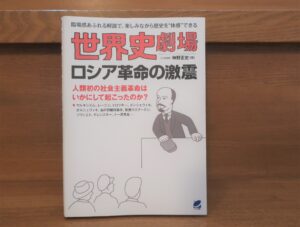





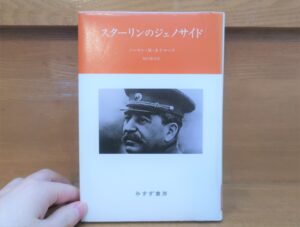
コメント