(11)異端審問を学ぶことは「人間とは何か」「現代とは何か」を考えることである

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑾
今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。
スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。
こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。
異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。
そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。
ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。
では早速始めていきましょう。
人間は不寛容な存在なのか
一九世紀後半、スぺイン史の保守的史観が知識人や政治家の間で再び主流となった。その主唱者の一人がマルセリーノ・メネンデス・イ・ぺラーヨ(一八五六~一九一二)だ。
そのあまりに早い知的早熟ぶりと、あまりに多い言葉の垂れ流しぶりで知られる彼は、ニ七歳のとき、スぺインにおける非正統的な思想と思想家に関する八巻の歴史書を発表した。異端審問に関する資料も多く含んでおり、現在も読むことができる。
その中でメネンデス・イ・ぺラーヨは、異端審問がスぺイン社会の形成に果たした役割を強硬に擁護した。彼は「不寛容は、健全な人間の理解力に本来備わっている法である」とし、人は知性を働かせて真理に到達すると、その真理を他人に押しつけようとし、他人の考えには不寛容になる、と主張した。
当初私は、こうした考えに憤慨していたが、ポルトガルとスぺインの公文書館を訪ねているうちに、別の感情を抱くようになった。この黄ばんだ書類の山は、一つの世界観を押しつけようとした以外に、何の目的があったのだろうか?
ここにあるこの書類は、保護用の箱に納まり、布の紐でしっかりと縛られた状態で、過去の各世代の歴史研究者たちに抽出されバラバラにされるのを、辛抱強く待っていた。書類を読むのは、過去への旅であり、現在を形作った過去の心理への旅であるか、それと同時に、現在の苦痛と不安な、もはや痛みを感じることのない人々のトラウマに移し替えることで、ある程度耐えやすくする旅でもあった。
人間の心に潜む不寛容に対するメネンデス・イ・ぺラーヨの考えを、完全に否定するのは難しくなった。さまざまな悪行に責任があるとされた人物に責めを食わせるほうが、ますます簡単に思われた。
異端審問官を、賄賂と権力に弱いと言って責め、拷問官を、サディストだと言って責め、植民地拡大のため戦争に賛成する者を、戦争をしたと言って責めることができた。
もっとも、そうした戦争は、自由主義的知識人にも間接的にたびたび恩恵を与えてきた。自由主義的世界観に、敵は必要であり、その敵は、異端審問の敵と同じように、学問の流行り廃りや時代の経過とともに、その姿を変えていった。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P490-491
※一部改行しました
学べば学ぶほど、ものごとはそう単純ではないことに気づく。
「異端審問官を、賄賂と権力に弱いと言って責め、拷問官を、サディストだと言って責め、植民地拡大のため戦争に賛成する者を、戦争をしたと言って責めることができた。」と著者も述べています。
残虐行為をした人間を「悪人だ」と断罪し、その悪の責任を彼に押し付けるのは簡単です。しかし、その悪が彼固有のものではなく、人間そのものが背負っているものだとしたらどうでしょうか。彼を責めることは自分を含めた人間そのものを責めることにもなるのです。
異端審問と冷戦時代の東ドイツ、中国共産党との思想的つながり
それなら思想としての異端審問は、ある意味、現在の人類にとっては当然の前身だったのだろうか?あくまでも類推だが、この思想を引き継いだものは確かに多い。
冷戦時代、東ドイツの秘密警察シュタージは、「非公式協力者」と呼ばれる密告者のネットワークを、異端審問所のファミリアールのように、国内全土に張り巡らせ、政治的に正しくない人々を監視していた。
また中国では、文化大革命のとき毛沢東の下で虐殺を繰り返した紅衛兵たちは、犠牲者が声を出して抗議しないよう喉元を切り裂いたが、これはアウトダフェで犠牲者に猿ぐつわをしたのと同じである。また紅衛兵は、犠牲者を殺すのに使った銃弾の代金を故人の家族に請求したが、これも、異端審問の犠牲者が自分を鞭打った役人に費用を払わなければならなかった点と通じるものがある。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P491
※一部改行しました
異端審問のシステムは中世スペインだけではありません。現代に生きる私たちの世界にも連綿と続いています。
ソ連やナチス体制はもちろんのこと、冷戦時代の東側陣営の抑圧体制の悪名高さは有名です。そしてアジアでもそれは変わりません。世界中でこうした異端審問のシステムが存在し続けています。
「異端審問の物語の核心に残るのは、人間の心理である」
管理組織が、失敗を他人のせいにするのに有効な道具であることは、すでに判明していた。そうなると、異端審問の物語の核心に残るのは、人間の心理である。
しかし歴史研究書は、異端審問の組織構成や、アウトダフェに関する統計数値、審問手続きの詳細、イべリア世界全体での活動実態などは正確に教えてくれても、迫害の動機が本当は何だったのかは教えてくれない。出来事の奥にある心理にまで入っていく研究書は、ほとんどと言っていいほどない。
私は常々、これはおかしいと思っていた。しかし実際に研究に携わってみて、なぜ心理面が除かれるのかが理解できた。とにかく情報が多いのだ。残虐行為、徐々に進んでいく迫害の風潮、集まっていく脅威の「証拠」。そうしたすべてに否応なく押されて、この情報を利用する者は自分なりに説明してしまい、そのため情報を外の視点から見て、実際に何が起こっていたのかを心理学的に理解することが難しくなってしまったのである。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P491-492
※一部改行しました
研究書はどうしてもその性格上、情報の羅列になってしまい、そこから広い視野で見ていくということがなかなか難しいという面もあります。一般の読者が読むにはかなり厳しいものになってしまうのは仕方のないことかもしれません。著者は歴史研究という観点からのみでは異端審問の奥底に入っていくのは難しいと述べています。
異端審問の心理探究と文学ードストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」・カフカの『審判』
そこで著者は歴史研究の視点からだけでなく、小説家によってその心理探究の道が開かれたと述べています。
異端審問の消滅後、この制度にまつわる心理力学を理解する作業は、次第に小説家の手に移っていった。その代表例が、ドストエフスキー(一八ニ一~八一)が『カラマーゾフの兄弟』で書いた衝撃的な作中作「大審問官」であり、フランツ・カフカ(一八八三~一九二四)が『審判』で描いた複雑で硬直化した裁判事務の姿である。『審判』で主人公ヨーゼフ・Kが、理由も分からず逮捕され、遅々として進まぬ裁判に振り回された挙句、大聖堂で教誨師と問答した後で、何の前触れもなく処刑されるというのは、なかなか印象的である。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P492
ここで紹介されたのが我らがドストエフスキーの代表作『カラマーゾフの兄弟』とフランツ・カフカの『審判』という作品でした。
「大審問官の章」はまさしく異端審問を舞台にした物語で、世界最高峰の物語として今なお評価されています。ここで語られることのえぐさは衝撃そのものです。以下の記事で「大審問官の章」についてお話ししていますのでぜひご覧ください。

そしてカフカの『審判』も並々ならぬ作品でした。この作品を読むのはかなりの神経戦になります。読み終わった後はかなりぐったりでした。
『審判』は不気味で恐ろしい作品です。読み物としてシンプルに面白いのは『変身』かもしれませんが、不条理の恐ろしさをより感じるのはやはりこの作品です。個人的にも『変身』よりもこちらの作品のほうが印象に残っています。

おわりに~著者からのメッセージ
ああ、哀れなるイべリアよ!ポルトガルとスぺインは、一時は世界最強の帝国の座にありながら、今や廃墟と化してしまった。後に残ったのは分断の溝だけ。
異端審問所は、統一されたイデオロギーを生み出そうと努力し、脅威は時と場所を問わず見つけ次第に弾圧してきたのに、その結果、帝国の衰退を見守ることになってしまった。
敵を迫害することが人々の生活を豊かにし向上させるのに貢献したとは、どう考えても言えまい。迫害の後に抑圧が現れ、さらに欲求不満が続いたからだ。欲求不満から怒りが生まれ、それが互いへの怨恨と憎悪へと繋がった。
これで敵意が燃え上がる用意はできた。やがて分断の溝は、スぺイン内戦という恐ろしい抗争へと変化し、保守派と自由主義者は互いに敵対するようになった。似たようなことは、その後サラザール政権下のポルトガルでも起きた。敵は決して消え去らなかった。異端審問は敵の追及に取り組んだが、そのため生まれた亀裂は、やがて大海原よりも大きくなる。
かくしてポルトガルとスぺインは、繁栄がもたらした富を妄執に吸い上げられて衰退した。堂々たる社会は、不寛容を掲げ幻想の脅威を追いかけたことで、自らの帝国を粉砕し、この国を世界から忘れられて細々と暮らす物悲しい国へと変えてしまったのであった。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P497
※適宜改行しました
これはこの本の最後のまとめにあたる部分です。
著者の思いがストレートに書かれています。
「ああ、哀れなるイべリアよ!ポルトガルとスぺインは、一時は世界最強の帝国の座にありながら、今や廃墟と化してしまった。後に残ったのは分断の溝だけ」
この本の面白い所は所々でこうした著者の思いが吐露されていて、単なるデータの羅列には終わらない点にあります。読み応え抜群です。読んでいて本当に面白い本でした。
この本はとてもおすすめです。ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか。
以上、「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
異端審問: 大国スペインを蝕んだ恐怖支配 (INSIDE HISTORIES)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事


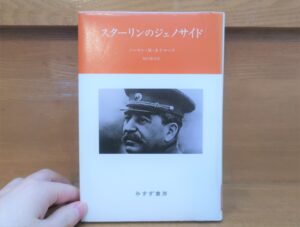













コメント