本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ

今こそチェーホフとゾラを読もう!―時代と世の中の仕組みを冷静に見る視点
これまで当ブログではおよそ1カ月にわたってチェーホフについてご紹介してきました。
ドストエフスキーを学ぶ上では必須という作家ではないチェーホフをここまで読むことになるとは私自身が一番驚いています。
ですがチェーホフを読むことができて心の底からよかったと思っています。
チェーホフは恐るべき大人物です。こんなすごい作家が日本でほとんど知られていないのはあまりにもったいないです。
彼の作品はただ単に面白いというだけでなく、私たちの「ものの見方」や「価値観」を揺さぶります。
ドストエフスキーも読者を混沌に叩き込み、私たちの世界観をひっくり返すような圧倒的な力があります。
強烈な個性で突き進んでいくドストエフスキーは良くも悪くも狂気の作家です。
しかし、チェーホフはドストエフスキーと違ってもっと冷静に、そして優しいまなざしで訴えかけてきます。
私たちを包み込んでくれるような穏やかさがチェーホフにあります。こうしたクールで優しい穏やかさがチェーホフの大きな特徴です。
以前、「帝政ロシア末期を代表する作家チェーホフ―ドストエフスキー亡き後のロシアを知るために」という記事でもお話ししましたが、チェーホフが語る内容というのは現代日本を生きるうえでも非常に重要な警告となっています。改めてここで紹介します。
ところで、当時のロシアには今の日本に似たところがたくさんあります。まず、日本でアニメやマンガが隆盛しているように、ロシアでは滑稽小説の隆盛期でした。人々は「笑い」を求めていたのです。
それには社会的な背景があります。社会改革を目指して、「ヴ・ナロード」のかけ声とともに農村に繰り出した、理想主義的で献身的な青年たちの一大啓蒙運動のはかない挫折は、どこか戦後日本の民主主義謳歌や、七〇年代の学園紛争の嵐とその瓦解・消滅に似ています。
やがて、その熱もさめ、理想主義は地を払い、「理想」めいたことは「ダサイ」こと、「甘い」ことと見なされる時代がやってきました。純真な「理想」に代わって、もっぱら物欲を、金銭を追う「金銭亡者」たちが現われました。どこへ行くべきか、地図を持たない若者たちの続出という点でも似ています。
日本では、「堀江モン」は一時期、ヒーローでしたが、やがて、ふくれあがったバブルが弾け、新しい「金色夜叉」は歴史から消えていき、まもなく海の向うから、マネーゲームの果ての「金融破綻」による大不況の波が押し寄せてきました。この一連の流れのなかに、人々は「狂」を認めないのでしょうか。
「人民主義」挫折後のロシアと現代の日本はどこか似ております。歴史は形を変えて繰り返すものなのでしょう。
日本の場合、生きる目的を失った人たちは、「憂さ」をやる手立てをもっぱらスポーツとグルメ、笑いに求め、ひたすらこれらに癒しを見出そうとしましたが、当時のロシアでは、滑稽小説の耽読か、「鬱」を紛らわせるために、逆に、「鬱」こそ人生の本性なのだと説くショーぺンハウアーの悲観哲学が流行しました。
ロシアでは当時、「詩と密告のほかは何でも書いた」とチェーホフがもらしているように、貧困が世をおおい、「物乞い」の姿はいたるところで、特にロシア正教の寺院の前で見られたのです。自殺者が三万人を超え、「引きこもり」の学生が三万に達するという日本に似て、自殺者の多いことでも、ロシアは昔から知られております。当時のロシア人が笑いに飛びついた事情と、日本のマンガ、アニメ、空虚な漫才の流行する風潮は似ていないでしょうか。
以文社、佐藤清郎『わが心のチェーホフ』p24-26
この文章を書いたチェーホフ研究者の佐藤清郎氏は現代日本に対して上のように警告しました。そしてこうした状況においてチェーホフこそこの問題と真正面から向き合い、私たちは何を考え、何をすべきなのかと語りかけてくると述べるのです。
私もまさしくそう思います。今の時代はコロナによる危機だけではありません。そもそも私たちの心や社会の仕組みそのものが危機に瀕していた。そこにコロナが追い打ちをかけ、これまでの歪みがすべて白日の下にさらされもっと危機的な状況になったというのが実際のところではないでしょうか。
すでに問題はあちこちにあった。しかしそれを経済やさまざまな覆いによって見て見ぬふりをしていた。その結果が今の未曽有の危機なのではないでしょうか。
チェーホフとゾラ
チェーホフはそのような時代と人間の心を凝視しました。
そんなチェーホフの醒めたまなざしはどこから生まれてきたのか。それが医者としてのチェーホフの学びにあったのです。佐藤氏の『わが心のチェーホフ』を見ていきます。
タガンローク市の奨学金を貰い、モスクワ大学医学部に入学してからの彼の人生行路は、一応、順調路線をたどっています。このことの意味は大きいと思います。彼の信念を固めさせていったからです。
ちょうど科学が急速な進歩を見せた時代であったことも考慮に入れねばなりません。特にチェーホフに大きな影響を与えたものは、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』であり、クロード・べルナールの『実験医学序説』でした。二十六歳のチェーホフはダーウィンの著書に感動さえしています。
「ダーヴィンを読んでいます。なんというすばらしさだ。ぼくは彼を尊敬し、愛する」、「ダーヴィンの手法〔実証的帰納法〕―ぼくはあの手法が気に入っている。」
クロード・ベルナールの中心思想である決定論は、当時、ヨーロッパで大きく議論の対象となり、医学生チェーホフも恩師ザハーリンの講義から熟知していました。
以文社、佐藤清郎『わが心のチェーホフ』p12-13
※適宜改行しました
チェーホフは医者でありながら作家であったという異色な経歴の持ち主でした。そのチェーホフは医学生時代にダーヴィンの『進化論』とクロード・ベルナールの思想を学んでいました。
ここで私は「あっ!」となりました。
実は以前私が読んだフランスの文豪エミール・ゾラもダーヴィンとクロード・ベルナールの思想に深く共鳴した作家だったのです。


世界を科学的に、客観的に観察していくこと。ゾラの基本的な執筆姿勢はここにありました。
つまり、チェーホフとゾラはものの見方が似ているのです。チェーホフを読んでいてそれはすぐに感じられました。世界を一歩引いた目でできるだけ客観的に見ようとする、そうした姿勢がこの二人からは感じられたのでした。
先輩作家ドストエフスキーなどは、この決定論を目の敵にして『地下室の手記』を書いています。彼は、生身の人間は決定論によって行動するものではない、「ハチェーニエ(心情の欲求)」によって動かされるものだ、と述べています。「真理を取るかキリストを取るかと聞かれれば、真理を捨ててキリストを取る」と言った人としては不思議ではありません。
以文社、佐藤清郎『わが心のチェーホフ』p13
そして佐藤氏はここでドストエフスキーを引き合いに出します。
たしかにドストエフスキーはこうした客観的、合理的な世界認識を嫌いました。「人間はそんな数学的に解決できるものじゃない。我々は機械じゃないんだ」と「二二が四」の論理を嫌ったのです。

ですがチェーホフはドストエフスキーとは違い、医者として科学者としてダーヴィンやクロード・ベルナールのものの見方に共鳴したのでありました。
医師チェーホフは、ドストエフスキーとは反対にべルナールの思想に共感しています。べルナールはこう言っています。
「自分の学説を余りに信用するひとは、かならず、他人の学説を十分に信用しないということになる。このとき、他人を軽蔑するこの人の脳裏にやどっている思想は、他人の学説の欠点を発見し、これに反対しようと努力しそうである。」
「学説は、ドグマあるいは信仰箇条として教えてはならない。」
「いかなる人の意見も―学説の形であろうと何であろうと―科学においては完全な真理を表わしているとは考えられない。道案内であり、灯明である。しかし、絶対的権威ではない。」(三浦岱栄訳)
科学的真理も「仮説」の一つにすぎないという言葉に、チェーホフはうなずいたにちがいありません。一切は変化する、すべては新陳代謝を繰り返すという意味での進歩を、彼は肯定しています。
以文社、佐藤清郎『わが心のチェーホフ』p13
これはチェーホフとドストエフスキーを知る上で非常に重要な指摘です。
トルストイもそうなのですが、ドストエフスキーは絶対的な真理を追究します。ですがチェーホフはそうした絶対的な真理ではなく、世界は相対的なもので成り立っていると考えます。
絶対的な善も悪もありえない。ものの見方が違えば真理も変わる。いや、真理というものすら本来ありえないものかもしれないというのがチェーホフの立場なのです。
こうした考え方があるからこそ、チェーホフはドストエフスキーのような何かに狂気のごとく没頭する作品ではなく、一歩引いたクールかつ優しいまなざしを持つ事ができたのです。
チェーホフはゾラと同じように科学を大切にした作家です。しかしチェーホフはやはりロシア人でした。読んで比べてみるとわかるのですが、ゾラは徹底して客観的な描写、分析を行います。それに対してチェーホフは感情的と言いますか、詩的な雰囲気が漂うのです。合理的な考えを重んじつつも人間的な感情を大事にするチェーホフの人柄がにじみ出ているのです。
ここがチェーホフとゾラの違いです。
とは言っても、ゾラに人間味がないというのではありません。ゾラもゾラなりの人間愛や優しさが当然あります。
しかし、作風としてはやはりどこか一歩引いたフラットな、科学者的な現実把握が感じられます。
もちろん、だからと言ってゾラがだめだというわけではありません。これまで当ブログでもお話しし続けてきましたように、ゾラの小説はものすごく面白いです。ただ、作風という点で比較するならばドストエフスキー、チェーホフ、ゾラには違いがありますということをここでお話ししたかったのです。
以下当ブログの記事ですがチェーホフやゾラを知る上で参考になると思いますので興味のある方はぜひご覧ください。



チェーホフは人間の心を、ゾラは人間と社会の仕組みを凝視した
チェーホフが活躍した時代はロシア帝政末期という、秘密警察が跋扈する不穏で閉鎖的な時代でした。そこでは人生を問う文学は下火になり、人々は憂さを晴らすために娯楽を追い求める風潮が進んで行きました。
それは先に読んだ佐藤氏の言葉でも出てきましたよね。
まさしく今の日本は経済的にも国際情勢においても危機的な状況です。しかし日々生きることでやっとの私たちは今さら生きるとは何かと問うたりする余裕すら失ってしまったのではないでしょうか。
その疲労とストレスを癒すために娯楽を求めることしかもはや私たちにはできないのではないか。
実際にメディアに流れるのはグルメや温泉、旅、お笑い、スポーツ、お洒落なものなどなど、そうしたもので溢れています。娯楽そのものを否定しているわけではありません。私もそれらが無ければ辛いです。人生の楽しみでもあります。ですが何事もバランスです。どちらか一方に傾きすぎるとそこに問題が起こります。佐藤氏がチェーホフを通して警告しているのはまさにその通りだなと思います。今の時代はチェーホフが生きた時代と似ているのです。これは重要な問題提起だと思います。
歴史は形を変えて繰り返します。
帝政末期のロシアのこうした状況は、結局その後ロシア革命につながり、レーニン・スターリン政権が樹立されることになりました。その結果ロシア帝政どころではない大量粛清や思想弾圧が行われ、自由が失われることになりました。
日本も他人事ではありません。歴史は形を変えて繰り返します。私たちが生きる世界が急に失われてしまうこともありうるのです。
チェーホフやゾラはそれを私たちに警告してくれているのです。
チェーホフはそうした陰惨な時代の中でも「人間の幸せとは何か」、「日々背負わなければならない苦悩に何の意味があるのか」ということを探究します。それが端的にあらわされているのが、『ともしび』や『退屈な話』、『六号病棟』、『すぐり』といった作品です。『かもめ』などの四大劇も家庭におけるすれ違いを通して生きる意味を模索した作品です。
チェーホフは私たちの「当たり前の価値観」を見直させます。私たちがごく当たり前のように「幸せ」と思っていることに対して「それは本当に幸せなことなのですか」と疑問を突き付けます。
チェーホフを読んでいるとどきっとさせられることが多々あります。苦しい時代を確かな眼で生き抜いた彼の鋭い指摘は現代を生きる私たちにも必ず心に刺さるものがあると思います。
そして一方ゾラはと言いますと、チェーホフが人間の心を深く凝視したのに対して社会の仕組み、そしてそれと関わる人間の心理を探究しました。
ゾラはナポレオン三世によるフランス第二帝政期(1852-1870)の時代そのものを解剖しようとしました。彼は当時の異常な経済発展と倫理観の変化、そしてその堕落を分析しようとしたのです。

このフランス第二帝政については以前もこの記事で紹介したのですが、この時代は私たち現代人のライフスタイルを作り上げた時代になります、つまりこの時代を知ることは私たちのライフスタイルのルーツを知ることになるのです。
私たちが普段当たり前のように生活しているこの社会がいかにして成り立ったのか。それはどんな仕組みで動いているのか。そして私たちはそのシステムにどのように動かされているかをゾラは観察し暴露するのです。
私たちの生きる社会が実はどんな原理で動いているのか。私たちが見ようとしない世界をゾラははっきりと見せてくれます。そしてそのような世界に組み込まれ、知らず知らずの内に都合よく動かされてしまう人間のあり方をゾラは教えてくれます。
これはなかなか衝撃です。百年以上も前に書かれたものとはまったく思えません。これはまさに現代のことを書いていると言ってもいいほどです。それほど恐るべき分析力が彼の作品で発揮されています。
何を読むか迷っているならチェーホフとゾラをぜひ!迷っていなくてもぜひぜひ!
私はこれまでずっとドストエフスキーのことについてブログを更新し続けてきました。そんな私がこれを言っては元も子もないのですが、私は「ドストエフスキーは万人におすすめできる作家ではない」と最近感じるようになってきました。
ドストエフスキーは私の最も好きな作家の一人です。それは今でも疑いようがありません。
しかしこのお方を多くの人に「ぜひ読んで下さい」とは薦め難いというのが正直なところなのです。
先にも述べましたがドストエフスキーは良くも悪くも狂気の作家です。そして彼の文体はまるで黒魔術のように私たちを彼の絶大な影響力の下に置いてしまいます。
疲れている時や精神的に落ち込んでいる時は特におすすめしません。おそらく呑み込まれます。精神的に病んでしまってもおかしくありません。これは冗談でもなく私の本音です。私自身、ドストエフスキーに影響を受け体調を崩し、精神的にも不安定になってしまった時期がありました。(ある意味これがドストエフスキーの醍醐味なのかもしれませんが・・・)
ドストエフスキーは人間の奥底のどろどろした混沌を凝視し続けます。どこまでも登場人物の心の奥底に彼は入り込みます。彼のすごいところはそれを読者の私たちにも体験させてしまうところにあります。それを可能にするのが黒魔術的なあの独特な語り口なのです。
ドストエフスキーは社会とのかかわりにおける人間というよりも、人間一人一人に潜む人間の根源に迫っていきました。
それに対しチェーホフは社会の中に生きる人間の心を見つめました。ある環境における人間同士のかかわりの中で一人一人の心を覗いていきます。単なる個の問題というより集団における人間の個が問題にされています。
また、ゾラは社会の仕組みそのものを分析し、そこから人間の心理を研究していきました。
彼らは三者三様でものの見方や観る対象が全く異なるのです。
今の余裕のない世相の中であえて自分自身すら狂気に落ち込みかねないドストエフスキー作品は正直あまりお薦めできません。それでも読んでみたいという覚悟があればぜひ読んだ方がいいです。ものすごくいい読書体験ができるでしょう。やはりドストエフスキーは文学の最高峰であることは疑いようがありません。
ですが、ただ何となく読んでみようかなというのはなかなかリスキーですし、そもそも娯楽小説として気楽に読める本ではないので読むのがつらくなってくると思います。無理して読んでドストエフスキーを誤解し嫌いになってしまうのはもったいないかなと思います。
敷居を高くしてしまったようで申し訳ない気もしてしまうのですが、敷居が高いというのは一概に悪いことではありません。むしろ無理やり敷居を下げて本来の素晴らしさが伝わりきらずに「こんなものか」と誤解される方が悲しい結末なように私は感じます。ドストエフスキーはものすごい作家です。ですが万人にお薦めできる作家ではないというのはそういう意味なのです。
さて、閑話休題。
ドストエフスキーについてお話ししましたが、それに対しチェーホフはまず作品が短いのでとにかく読みやすいです。短いものは数十ページ、長くでも百ページほどです。しかも文体もすっきりして読みやすく現代の小説とまったく変わりません。とにかく読みやすく、わかりやすいです。現代小説と比べても全く負けない、いやそれ以上に面白い作品が目白押しです。
ゾラも多少作品自体は長くなりますが、文体も読みやすくまるで映画を観ているかのように物語が目の前に現れてきます。びっくりするほど読みやすいのでぜひこれは体験して頂きたいほどです。
チェーホフとゾラは間違いなく今の時代に合った作家です。この閉塞し、何が正しくて何が間違いなのかもわからない不確かな時代に改めて光を投げかける作家です。
私たちは何をすべきなのか、何を思えばいいのか。
そしてこの社会の仕組みはそもそもどうなっているのか。どのようにして出来上がり、今なお私たちを動かしているのか。
きっとこのコロナ禍で多くの人がこれらの疑問を抱いたのではないでしょうか。今やネットや本で大量の情報が出回っていますが、ぜひチェーホフとゾラを手に取って頂きたいなと思います。
チェーホフのおすすめ作品5選
ここで簡単ではありますが私が特におすすめしたいチェーホフ作品を5つ紹介していきます。チェーホフのエッセンスが凝縮された珠玉の作品たちです。
チェーホフ小説の極み!『六号病棟』

この作品はチェーホフ作品中屈指、いや最もえげつないストーリーと言うことができるかもしれません。
院長がいつの間にか精神病者にさせられて病院を首になり、あまつさえ精神病棟に放り込まれそこで死を迎えるというあらすじを読むだけでもその片鱗が見えると思いますが、作品を読めばその恐ろしさがもっとわかります。その辺のホラー映画を観るより恐いかもしれません。
ただ、この恐さと言うのが「ホラー映画的な恐怖」ではなく、人間の本性、そして自分自身の虚飾を突き付けられるような怖さです。
この作品を読むと「え?じゃあ自分って何なんだ?この院長や精神病者と何が違うんだ?正気と狂気の違いって何だ?ずるく生きる人間に利用されるしか私の道はないのか?……暴力の前ではすべては無意味なのか?」などなど様々な疑問が浮かんでくることでしょう。
この作品はチェーホフどころか、最近読んだ本の中でも特に強烈な印象を私に与えたのでした。これはもっともっと日本で広がってほしい作品だと私は思います。
Amazon商品ページはこちら↓
『すぐり』

たった15ページにも満たない短い作品ではありますが、チェーホフの人生観、幸福論が凝縮された傑作です。チェーホフ研究者の佐藤清郎氏もこの作品を、
『すぐり』はすばらしい、そしてある意味でおそろしい作品である。小品といってもいい短い形式の中に盛りこまれた内容は一個の長篇小説に匹敵する。
塙書房、佐藤清郎『チェーホフの文学』P104
と絶賛しています。「幸せとは何か」とものすごく考えさせられる作品です。
Amazon商品ページはこちら↓
チェーホフ全集〈11〉小説(1897-1903),戯曲1 (1976年)
『黒衣の僧』

精神を病み、そこから自分が作り出した幻覚と話をする。
これは『カラマーゾフの兄弟』の主要登場人物、イワンを彷彿とさせます。彼も精神を病み、自分の作り出した悪魔と対話します。彼もそれが幻覚だと知りながらも悪魔と対話するのです。
そしてこの作品で興味深いのはやはり「天才と狂気は紙一重なのではないか」という問題です。
この作品もまた私たちをドキッとさせます。チェーホフは問題提起が尋常でなく巧みです。普段私たちがなんとなく見過ごしてしまうものを的確につかみ、私たちが最も驚く形でそれを提示します。この作品もものすごく面白いです。一気に読んでしまいました。
Amazon商品ページはこちら↓
『ロスチャイルドのバイオリン』

この作品も10頁少々という短い作品ですが、これまた内容が凝縮されていてあっという間に引き込まれてしまいます。
そして何より、長年ずっと黙って尽くしてくれた優しい妻に対するヤーコフの後悔。これが何よりもいたましいです・・・
そして真に彼が自らの生き方を振り返ったのが、墓場からの帰り道に妻との思い出の場所に偶然やってきた時だというのですから何ともドラマチックです。
読んでいて泣きそうになるくらい切ないシーンです。
割と淡々とした作品をたくさん書いてきたというイメージがあるチェーホフですが、こうした感動的な作品も書くのだなと驚きました。
これは名作です。映像化したら最高に感動的な作品になると思います。
Amazon商品ページはこちら↓
『かもめ』

『かもめ』はチェーホフの代表作です。
代表作ということはそれはそれは面白いはず。
私はそう思い読んでみたのでありますが、どうもおかしいのです。
どうしてもその面白さがわからないのです・・・
参考書も読んで、それから何度も読んでみたのですがやはり、「面白い!」とはなりませんでした。
もちろん、「つまらない」わけではありません。ですが、チェーホフの他の小説と比べてみると特に思うのですがその面白さがわかりにくいのです。
なぜそうなってしまうでしょうか。
私は色々考えてみたのですが、これはおそらくこの作品は「劇」として観るべきものであって、小説として読むべきものではないのではないかと感じました。
チェーホフ劇には波乱万丈なストーリーがありません。あくまで家庭内のすれ違いを主とした地味なストーリーです。そういう家庭的な繊細な物語がチェーホフ劇の真骨頂です。
本では登場人物の微妙なしぐさや声色、間では感知しきれません。舞台で演者が実際に演じるからこそ観客はそのリアルさに心が打たれるわけです。
『かもめ』は小説ではありません。劇です。もし小説として書くならもっと小説として読めるようにチェーホフは書いたはずです。しかしこの本ではあくまで劇の『かもめ』を文字化したものです。
そこに本を読んでもいまいち入り込めない難しさがあるのではないかと私は思ったのです。この辺の事情については上の記事でより詳しくお話ししていますのでぜひご覧ください。
おすすめ5選には入れましたが、これは本ではなくぜひ劇として皆さんに観てほしいという私の願いです。かく言う私もまだ観たことがないのですが、機会があればぜひこの作品のすごさを生で感じてみたいなと思っています。
Amazon商品ページはこちら↓
ゾラのおすすめ作品

世の中の仕組みを知るにはゾラの作品は最高の教科書です。
この社会はどうやって成り立っているのか。人間はなぜ争うのか。人間はなぜ欲望に抗えないのか。他人の欲望をうまく利用する人間はどんな手を使うのかなどなど、挙げようと思えばきりがないほど、ゾラはたくさんのことを教えてくれます。
ゾラはどぎつい世の中の現実を私達に見せつけます。作中、きれいごとを排した人間のどろどろしたどす黒い感情、煩悩がこれでもかと飛び交います。
まるで「世の中を知るには毒を食らうことも必要さ。無菌室に生きてたら世の中を渡ることなどできるもんか」と言わんがごとしです。
ぜひこちらの記事もご覧ください。
古典だからすごいのではない。名作が時代を経て残ったから古典になった
チェーホフもゾラも百年以上も前の作家です。今の人たちからすれば古くさくて小難しい古典の範疇に入ってしまうかもしれません。
ですが私は言いたい!古典と言ってしまうから敷居が高くなってしまうのです!
たくさんの人が読んで「これは面白い!素晴らしい作品だ!」と納得した名作が、時を経ても全く色あせずに残り続けているから古典になっただけなのです。
古典だからすごいのではないのです。名作だから古典になったのです。
よく「古典を読め」という話が出ますが、「名作を読め」と言われればそこから受けるニュアンスは全く変わりますよね。
それに、そもそもこれら古典の名作は現代語訳されているので、今新しく作られている本と何ら変わるところはありません。「わかりやすさ」「読みやすさ」を売りにした本とはさすがに違いますが、基本的には今作られている小説などと変わらぬ土俵で読めるのです。
最近出た本でもメディアや口コミなどで「これは面白い!名作!おすすめ!」という言葉を受けてその本を読むのがほとんどではないでしょうか。
チェーホフやゾラにしても本来は同じ土俵に立ってもいいのではないかとおもいます。しかしそれを阻んでいるのがやはり「古典」という言葉なのではないかなと私は思っております。
もっと「名作」という言葉を推してほしい!そう願っている今日この頃です。
長くなってしまいましたがこれにてチェーホフについての記事は終了します。
ぜひチェーホフとゾラがもっと世に広まりますように!
以上、「本当にいい本とは何かー時代を経ても生き残る名作が古典になる~愛すべきチェーホフ・ゾラ」でした。
前の記事はこちら

関連記事


















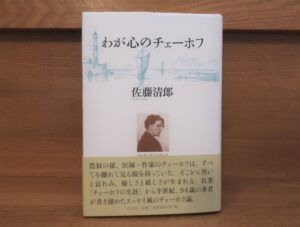


コメント