チェーホフ『かもめ』あらすじと感想~ロシア演劇界に革命を起こしたチェーホフの代表作!
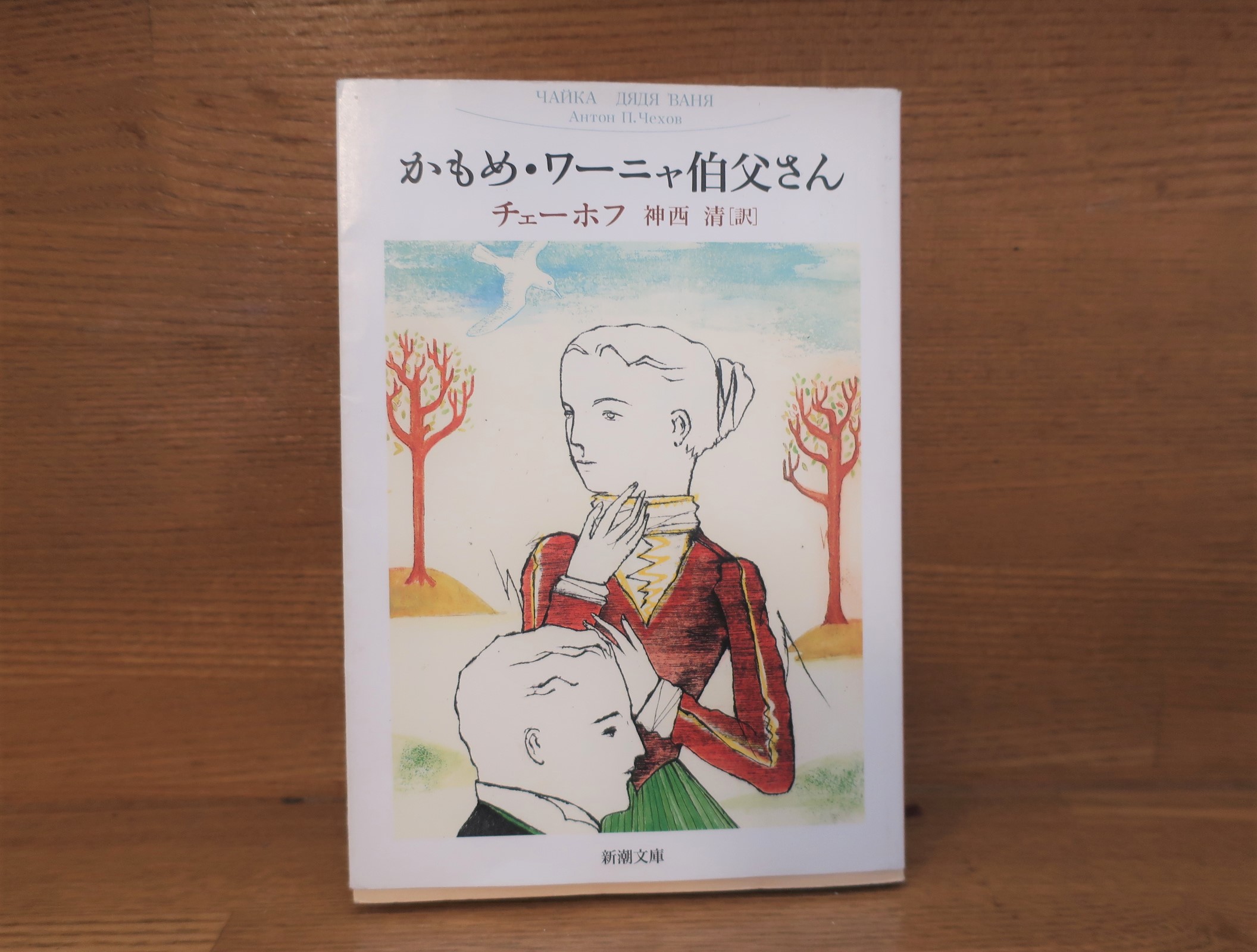
チェーホフの代表作『かもめ』あらすじ解説~チェーホフ劇の真骨頂

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより
『かもめ』はチェーホフによって1896年に初演された戯曲です。
私が読んだのは新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』所収の『かもめ』です。
早速あらすじを見ていきましょう
恋と名声にあこがれる女優志望の娘ニーナに、芸術の革新を夢見る若手劇作家と、中年の流行作家を配し、純粋なものが世の凡俗なものの前に滅んでゆく姿を描いた『かもめ』。
Amazon商品紹介ページより
この一冊には、アントン・チェーホフ(1860-1904)の戯曲『かもめ』と『ワーニャ伯父さん』が収録されている。この二作は、同じ新潮文庫のもう一冊に収められた『三人姉妹』『桜の園』とともに普通チェーホフの四大劇と呼ばれて、演劇史上の傑作に数えられている。
新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』P241
『かもめ』は女優志望の美しい娘ニーナを軸にした劇となっています。ニーナにはモデルがいました。それはチェーホフと親しくしていたリジヤ・ミジーノワという声楽家志望の美しい女性でした。チェーホフは実生活で目にしていたその女性をモデルに『かもめ』のニーナを描いていきました。
ここからは巻末の解説を見ていきます。
さて、劇中の女優志望の娘ニーナの悲恋は、このように作者の身近に起った現実の事件を下敷にしているが、実はこの悲恋のテーマはチェーホフ中期の代表的な小説『退屈な話』(一八八九年)のなかで、すでにきわめて類似した形で取扱われたテーマの繰返しなのである。
この小説は、退職老教授のわびしい心境を冷やかに描き出した名作で、今や全く時代おくれとなった独断的なかつての流行批評家シェストフがチェーホフを絶望の詩人と断罪し、彼の創作を≪虚無よりの創造≫と名づけたその論証の実例に用いた作品であるが、この小説のなかに老教授の養女で、カーチャという女優志望の若い魅力的な娘が登場する。
そうして彼女は『かもめ』のニーナと同様に名声にあこがれて家を出て劇団に加わり、男に身をまかせて子供を生み、やがて男にも捨てられ子供にも死なれて絶望におちいる。
この点ではふたりの娘―カーチャとニーナの悲恋は同一の経路をたどっていると言えるが、重要なのはその結末の相違である。
六年前に書かれた小説のなかでは、女優を志して挫折し絶望におちいったカーチャは、ある日、旅先に老教授を追って来て、「私はもうこんなふうに生きて行くことはできない」と絶叫しながら、「私はこれからどうすればいいのか」と涙ながらにたずねる。
それに対して養父である人生経験ゆたかなはずの老教授は何の助言も与えることができずに、ただ「私にはわからない」と答え、娘はそのまま寂しく立ち去って行く。
これがこの小説の名高い結末であり、それは疲労して人生の意義を見失った中期のチェーホフその人の苦悶と懐疑に明け暮れた心境を如実に表わしているのだが、サハリン島旅行(一八九〇年)をはさんでチェーホフが次第に社会的に目ざめて行ったその六年後の『かもめ』においては、挫折し絶望におちいったニーナは、終幕で今や自分がどうすればいいかを知っている。
すなわち彼女は自分の仕事にとって大切なものが、かつて夢見た晴れがましい名声や栄光ではなく〈忍耐力〉であることをすでに知っているのだ。
このニーナの信念は、『かもめ』のなかではほんの短いせりふで語られているに過ぎないけれども、チェーホフ独特の鬱屈した暗い戯曲の雰囲気のなかできらきらと輝いている。
忍耐力だけで人は大女優にも大作家にもなれるはずはないが、絶望からの脱出、絶望からの救いが忍耐にあると知ったところにカーチャからニーナへの成長が見られ、またそこに作者チェーホフの文学的、人生的な脱皮が認められるだろう。
そうしてまたこの絶望という重苦しい暗い状況から忍耐の必要を知り、その忍耐から希望の必要へ、明るい未来への信念の必要へと転じるその移行が、チェーホフ四大劇の主調低音であるとも言えるのである。
新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』P241
『退屈な話』は以前当ブログでも紹介しました。

この作品に出てくる老教授もカーチャも生きる意味を喪失し「これから何をすればいいのか」と途方に暮れて物語は終わりを迎えます。その答えのない結末は発表当時からものすごい反響を巻き起こすことになりました。
そこから6年、チェーホフは1890年のサハリン島への旅や数多くの作品の執筆を通してさらなる覚醒を迎えます。

その覚醒を経て生み出されたのが『かもめ』という舞台だったのです。
『かもめ』はチェーホフの代表作として今では有名ですが、実はこの劇の初演はとてつもない大失敗だったと言われています。
『かもめ』は当時の劇としては斬新すぎてお客さんどころか演じる役者ですら全く理解できなかったそうです。
一八九六年秋、この戯曲がアレクサンドリンスキイ劇場で初演されてさんざんの失敗に終った時、チェーホフはひどい打撃を受けた。この初演の失敗は、名優中心の当時の演劇界の風潮や、チェーホフ劇の真意を汲み取ることのできなかった演出家、俳優、さらには作者に好意を持っていなかった観客たちの責任であると考えられるが、チェーホフは失笑の渦となった劇場をこっそりと抜け出して秋のべテルブルグの夜を一人寂しくさまよい、二度と戯曲の筆は取らぬという誓いを立てた。
チェーホフに身びいきな妹マリヤは、彼の肺結核のその後の悪化をこの寒い秋の夜の彷徨のせいにしている。
『かもめ』がはじめて成功したのは、周知の通り二年後の一八九八年秋、スタニスラフスキイ、ネミローヴイチ=ダンチェンコのひきいる新設のモスクワ芸術座の再演の舞台である。
モスクワ芸術座は名優中心の当時の演劇界の風潮に逆らって、作品の徹底的な理解と、俳優が役柄に生きる新しい演出、新しい演技をその信条として、アンサンブルと雰囲気の要求されるチェーホフ劇の真価を舞台に表現してみせたのである。
モスクワ芸術座の座章である飛翔するかもめのマークは、この歴史的な『かもめ』再演の成功の記念であり、またこの成功はチェーホフを再び劇作に呼び戻すことになった。
新潮社、神西清訳『かもめ・ワーニャ伯父さん』P246-247
当時のロシア演劇界は役者の大げさな演技やコミカルな筋で笑わせるわかりやすいこてこてのものが主流でした。
それに対しチェーホフは家庭を舞台にした日常の世界を描きます。
笑いを取りに行く大げさな演技ではなく、演者が役になりきるという繊細な演技を彼は求めたのでした。
しかし役者たちはそんな劇では観客にウケるわけがないではないかとチェーホフの意図を拒み、勝手に演じ始めます。そうなると繊細で緻密な演劇である『かもめ』は空中崩壊です。観客も何が何だかわからず大不評となってしまったのです。
『かもめ』は観客の前に役者たちにも不評だった作品だったのです。
実はこれ、かつてのロシアで同じことがありました。
それが1836年に初演されたゴーゴリの『検察官』という作品です。

この劇もロシアを代表する劇として今でも世界中で愛されている作品ですが、この劇でもゴーゴリは役者に大げさに演ずるのを禁じました。
しかしチェーホフと同じように役者たちが勝手に演じ始め、ゴーゴリはひどく落胆したそうです。
ロシアを代表する作家であるゴーゴリがかつてたどったように、それからおよそ60年後のチェーホフも同じような憂き目に遭ってしまったのでした。
しかしその2年後ダンチェンコや名俳優スタニスラフスキーによってモスクワ座で『かもめ』が再演されます。チェーホフの意図するところを深く理解した彼らによって指揮された『かもめ』はロシア演劇界最大級の事件になるほどの大成功を収めます。(このことについては以前当ブログで紹介したジーン・ベネディティ著『スタニスラフスキー伝』にも詳しく説かれています。)
この成功があったからこそ後の『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』という名作劇が作られていくことになったのでした。
感想
かもめはチェーホフの代表作です。
代表作ということはそれはそれは面白いはず。
私はそう思い読んでみたのでありますが、どうもおかしいのです。
どうしてもその面白さがわからないのです・・・
参考書も読んで、それから何度も読んでみたのですがやはり、「面白い!」とはなりませんでした。
もちろん、「つまらない」わけではありません。ですが、チェーホフの小説と比べてみると特に思うのですがその面白さがわかりにくいのです。
なぜそうなってしまうでしょうか。
私は色々考えてみたのですが、これはおそらくこの作品は「劇」として観るべきものであって、小説として読むものではないのではないかと感じました。
チェーホフ劇には波乱万丈なストーリーがありません。あくまで家庭内のすれ違いを主とした地味なストーリーです。そういう家庭的な繊細な物語がチェーホフの真骨頂です。
本では登場人物の微妙なしぐさや声色、間では感知しきれません。舞台で演者が実際に演じるからこそ観客はそのリアルさに心が打たれるわけです。
『かもめ』は小説ではありません。劇です。もし小説として書くならもっと小説として読めるようにチェーホフは書いたはずです。しかしこの本ではあくまで劇の『かもめ』を文字化したものです。
そこに本を読んでもいまいち入り込めない難しさがあるのではないかと私は思ったのです。
『かもめ』についてネットで検索していると、しろくろ猫のおもむくままさんの記事で「読むだけで演技が上手くなる!チェーホフ作「かもめ」のあらすじ」というページがありました。そこでは、
この「かもめ」という戯曲は、まさに演劇なんです!
初めて読んだ時はよく分からなかったのですが、役者として舞台に立つようになってから突然、読めるようになりました。登場人物が(たくさん出てくるわけですが)みんなお喋りで、いつだって会話がかみ合わないのは、それぞれが別のことを考えているから。笑
「なんてみんな神経質なんだ!どこもかしこも恋ばかしだ」と嘆くセリフにもある通り、分かり合えない人達が同じ場所に集まっているせいで(笑)、、、男と女、大人と子供、恋人同士、母親、芸術家などなど、相手やその時の立場によってころころ変わる自分を、一つの場面で同時に演じなきゃならないわけです。(これは、忙しい!)
ただ心情を語るんじゃない。役者にとって最も豊かな台本と呼びたいです!
しろくろ猫のおもむくまま 「読むだけで演技が上手くなる!チェーホフ作「かもめ」のあらすじ」より
なので、本としてではなく、とりあえずでも人物に寄り添ってセリフとして読んでみてください。いつのまにか呼吸が合ってきて心が勝手に動いてしまうような、不思議な体験が待っているはずです。
この記事を読んで「あぁ、なるほどなぁ!」と合点がいきました。やはり「演ずる作品として」この作品は突出しているんだなと。
小説として読もうとしてもこの作品の魅力はあまり伝わらないんだと。
「じゃあ、シェイクスピアはどうなんだい?彼の作品は本で読んでも面白いじゃないか」
そうなんです。ですがシェイクスピアは波乱万丈なストーリー、そして思わず口に出したくなるかっこいいセリフがどんどん出てきます。いわば、派手なのです。だから本で読んでも面白い。(もちろん、劇で観ればもっと楽しい)
それに対してチェーホフはより繊細で、より家庭的なリアルな劇を志向しました。そこに違いがあると思います。
実はこの後も紹介する四大劇『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』も、一度読むだけではなかなかわかりにくく、参考書の助けを借りながら何度も読み返してようやくその面白さがわかってくるくらいでした。
本として読むにはちょっとハンデがあるというのが私の正直な感想です。
ですが、舞台で観たらものすごく面白いんだろなというのは間違いなく感じています。シェイクスピアともまた違う演劇の面白さ、奥深さを体験できるのではないかと強く感じています。
なかなか舞台で観る機会はないかもしれませんがぜひチェーホフ劇を体験してみたいなと思っています。まず面白いことは間違いないと予感しています。
チェーホフ劇は本で読むより絶対に舞台で観た方がいい。
演劇に慣れた方からすると当たり前のことかもしれませんが、シェイクスピアを読むことに慣れていた私にとっては改めて演劇というものを考えさせられた作品でした。
以上、「チェーホフ『かもめ』あらすじ解説―ロシア演劇界に革命を起こしたチェーホフの代表作!」でした。
※2023年1月15日追記
最近読んだ蜷川幸雄、長谷部浩共著『演出術』の中に『かもめ』について興味深いことが書かれていましたのでここに引用します。
特にチェーホフは、立ち稽古をしていると発見があるんです。「へー、この人たち、こんなことを考えているんだ」とわかる。本を読んでいると、つい台詞をしゃべっている人物に意識がいくから、同時に舞台の上にいる登場人物の一人一人が、どこからどこまで黙っているのか、わかりにくいところがあるんです。実際に立ってやってみると、ある人物はその場に、こんなに長くいるんだけれども、ずっと黙っている。「何をしているのかな」と考えはじめる。黙って、自分の好きな男、好きな女のことを、知らない間に見つめているのがわかる。机に向かって台詞だけを読んでいると、どうしてもそこが見えてこない。
ーシェイクスピアは、あくまで台詞をしゃべっている人物が、その場の主体としてあると考えていいのですか。
そうですね。シェイクスピアと違って、チェーホフが近代劇だなと思うのは、一人一人の人間が等価なんですよね。今度演出する上で、気をつけていることは、一人の人物が動いたことを受けて、他の誰が動くのか、ある事件が起きたときにどう人の位置が変わっていくのか、ですね。まるでパズルのように、あるいはさざ波のように、人が入れかわったり、座る椅子の場所が違ったり、人を見つめる目線が変わっていく。玉突きの球が、台を転がっていくように、コンコンコンと動きを作り出していく。玉突きというのはそうじゃないですか。直接、狙った球に当たるだけではなくて、クッションも利用する。それにつれて他の球の位置が動いていくでしょう。ちょうどそういう感じなんです。
もちろん、今しゃべっている人に観客の視線がいくのは当然ですし、主役は当然いるけれども、劇が進むにつれて動いている球の連鎖を考えると、人間の一人一人が等価に置かれている。凝るね、チェーホフは凝る。『かもめ』を読むたびに、「くそー、青春っていうのはこれだよな」と長い間悔しい思いをしてきたんですが、まあ、今や余裕を持って扱えるだろうと思っています。
筑摩書房、蜷川幸雄、長谷部浩『演出術』P279-280
「主役は当然いるけれども、劇が進むにつれて動いている球の連鎖を考えると、人間の一人一人が等価に置かれている。凝るね、チェーホフは凝る。」
なるほど、これはわかりやすいですよね。そして最後の「凝るね、チェーホフは凝る」という言葉がまたぐっと来ます。さすが蜷川幸雄さん。この『演出術』という本は蜷川さんの演劇に対する考え方、向き合い方を知れるおすすめの作品です。ぜひこちらも手に取ってみてはいかがでしょうか。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事












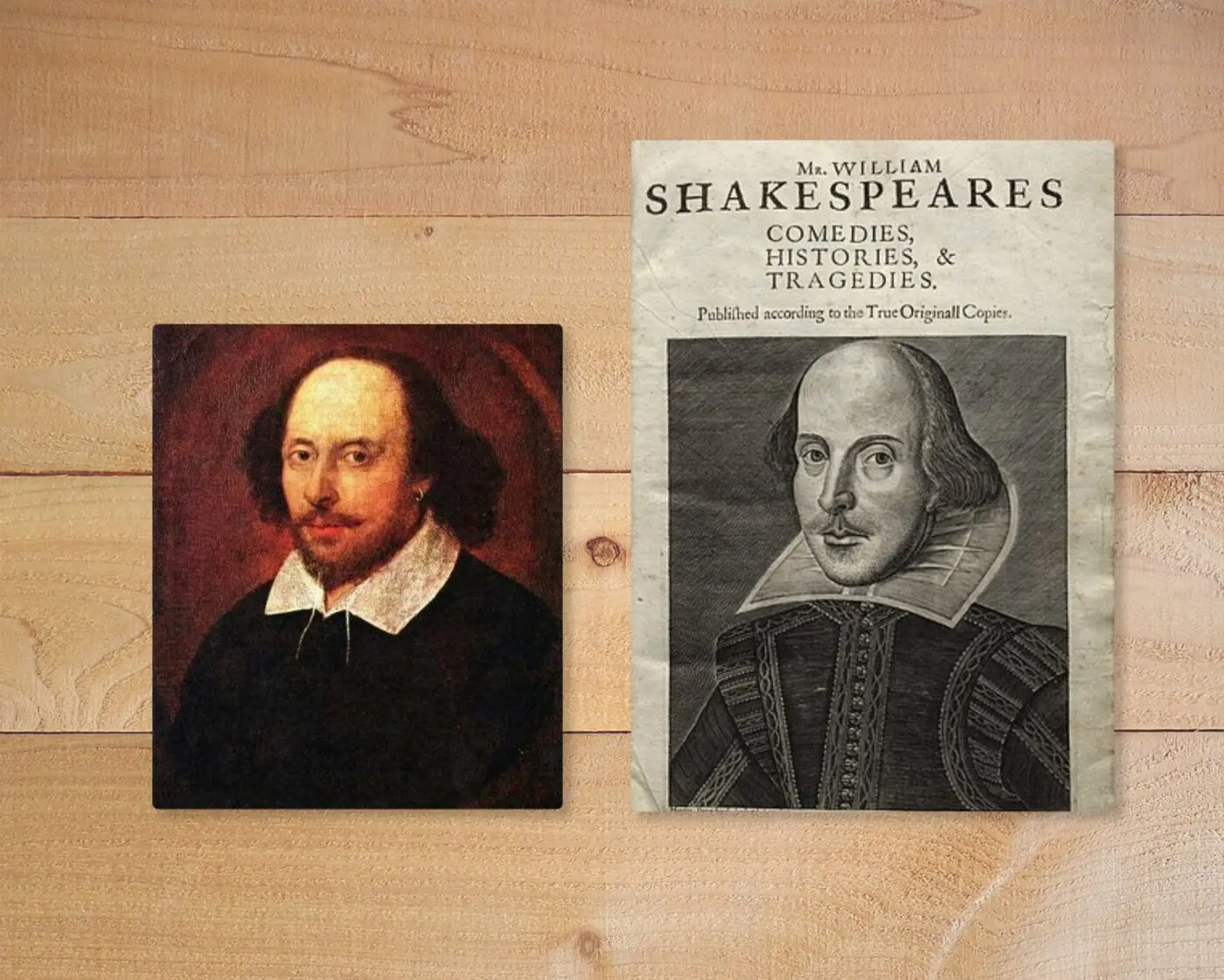


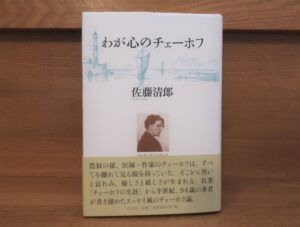

コメント