(6)スペイン料理や名物タパスに隠された意味~食文化と信仰のつながりとは

トビー・グリーン『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑹
今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。
スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。
こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。
異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。
そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。
ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。
では早速始めていきましょう。
疑心暗鬼の隣人たち~スペイン料理や名物タパスに隠された意味

現代のスぺインでレストランに入り、メニューをじっくり見てみると、スぺイン文化独特の特徴に気づく。「ア・ラ・エスパニョーラ(スペイン風)」あるいは「カスティーリャ(カスティーリャ風)」と書かれたスープやシチューは、必ずハムかロースト・ポークのスライスが入っているのだ。
マドリードで人気のあるレストラン・チェーンは、「ムセオ・デル・ハモン(ハムの博物館)」という。店内に入り、天井からぶら下がる何本ものハムを横目に進むと、この店こそハム料理を味わうのに最適の場所だと分かる。料理の中でも特に皮肉な名前を持つのが、「フディアス・コン・ハモン」だ。これはインゲン豆とハムの炒め煮、「フディア」とはインゲン豆のことなのだが(「フディアス」は複数形)、この単語にはもう一つ、「ユダヤ娘」という意味もある。
レストランを出て、スペイン食文化の象徴というべきタパス(おつまみ)を出すバル(居酒屋)へ向かおう。店に入ってカウンター席に座ると、冷たいビールを傾けている間のつなぎに、店員がお通しを出してくれる。出されたお通しを見てみよう。豚の皮のカリカリ揚げ、チョリソ(辛い豚肉ソーセージ)、海老、貝の塩漬け各種。
食べないのは礼儀に反するので、硬かろうが冷めていようが、とにかく食べる。今では気づかない人も多いが、実はこのお通しは、数々のタパスと同様、イスラム教とユダヤ教両方の飲食物に関する戒律に違反する食べ物なのである。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P316-317
※一部改行しました
スペインの食文化を代表するタパスには実はこうした意味があったのです。
スペインではキリスト教徒、改宗ユダヤ教徒・イスラム教徒は共存し、もはや同化していましたので単に見た目だけでは誰が何を信じているのかはわかりませんでした。ですのでこうした食べ物を通して信仰の如何を確かめようとしていたのです。
例えばですが、ある家で会食をしようとなったときに、客たちはそれぞれ料理を持ち寄ることになります。そしてその時に豚肉のソーセージをわざと持ち寄るのです。それで家の主人や他の客人がそれを食べようとしなければ隠れユダヤ教徒やイスラム教徒であることがばれてしまうのです。著者はこのことについて次のように述べます。
この場面には、社会的な力が働いていた。招かれた客は好意で食べ物を持参するが、もしコンベルソ(※改宗ユダヤ教徒 ブログ筆者注)がユダヤ教の戒律の一部を守っていれば、その料理を食べることはできない。つまり客の好意は挑発であり、言外の脅しであった。このやり方は、相手を試し、正統な信仰を守っているか確認し、怪しいと思った相手の首根っこを押さえる方法として、食文化を通じて広がっていった。
イスラム教もユダヤ教も豚肉の食用を禁じていたため、コンベルソやモリスコ(※改宗イスラム教徒)に豚肉を差し出すのは、キリスト教的慈悲の精神を守るふりをしながら相手を侮辱する格好の方法だった。豚肉を拒んだという証言は、コンベルソやモリスコに対する異端審問では必ず登場しており、異端審問のイデオロギーが、食事という最も基本的な人間活動にまで浸透していたことを示している。(中略)
「彼らは、職場や日常生活で非常に厳しく監視されており、キリスト教の習慣から少しでも逸脱すれば、それだけで異端の嫌疑をかけられ罰せられる」ほどだった。モリスコの場合は、これに加えてラマダーンの期間も危なかった。ラマダーン中、日中何も食べないそぶりを少しでも見せれば、それで告発されるかもしれず、異端審問のイデオロギーに後押しされた偽りの好意で罠にはめられる恐れがあった。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P318-319
※一部改行しました
後半の「彼らは、職場や日常生活で非常に厳しく監視されており、キリスト教の習慣から少しでも逸脱すれば、それだけで異端の嫌疑をかけられ罰せられる」ほどだった。」という箇所。
この中の「キリスト教の習慣」というところを「ソ連の習慣」と言い換えたらどうでしょうか。
これまで当ブログではソ連について学んできましたが、私はこの箇所を読んでぞくっとしました。
まさしくソ連で行われていたことが中世スペインの異端審問の世界で行われていたのです。
ソ連については以下の記事でご紹介していますのでぜひご覧になってください。異端審問との類似にきっと驚くと思います。



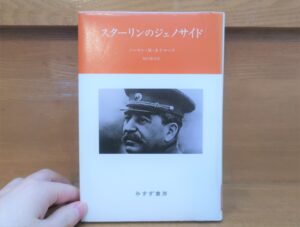

極端な監視社会へ向かって行くスペイン
当然ながら、こうした告発をするためには、疑っていることを決して悟られないようにしながら、疑わしい者を絶えず監視していなくてはならないはずだ。監視している証人たちは、緊張と同時に楽しみも感じていたことだろう。おそらくは、容疑が晴れたときよりも逸脱が証明されたときのほうが嬉しかったに違いない。
極端な監視の風潮は、異端審問の歴史のごく初期の頃に始まっている。コンべルソのマリア・デ・カサーリャは、後に照明派として告発された女性だが、彼女が一五二五年にカスティーリャの町グアダラハラでミサに出席したとき、ディエゴ・カリーリョという男性は、聖体が掲げられるとカサーリャは目を伏せ、それから視線を教会の扉のほうにやったのを目撃したと言っている。
同様の告発は日常茶飯事だった。しかも、告発者の偽善ぶりには、笑うと同時に強い嫌悪を感じざるをえない。誰某は聖体をしっかり見ていなかったと告発する当の本人こそ、監視に気をとられていて、キリストの肉体を象徴する聖体を敬っていなかったからだ。
しかし、異端審問官たちはそんな疑問は抱かなかったらしく、教会を主な舞台の一つにして、コンべルソやモリスコの行動を調べた。一五六六年グラナダで、一人のモリスコが「司祭が聖体を掲げたとき、座ったままで頭を下げ、両手で目をふさいで聖体を見ないようにしていたために」罰せられた。
一三年後には、反乱に失敗してグラナダから追放されていたモリスコのゴメス・エンレイマーダが、八名の証人により、司祭が聖体を掲げたときに疑わしい行動を取ったとして告発されている。
人々がどれほど熱心に他人を監視していたかを物語るのが、バレンシアのモリスコ、ミゲル・メリッチの事例だ。彼は三名の証人から、丸一年間、一度も告解しなかったとして告発された。きっと三人は、四六時中、彼を見張ってはメモを取っていたのだろう。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P319-320
※一部改行しました
著者もセルバンデスのようにピリッとした皮肉を交えて監視社会の実態をここで述べています。
悲しいかな人間にはこういう側面があるということを認めざるをえません・・・
監視社会のさらに極端な例ー監視社会は不信社会になり、分断社会へ
最も極端な例は、一五九七年にモリスコのバルトロメ・サンチェスが一家ともども逮捕された件だ。証人の一人である隣人は、サンチェスが排便後にも体を洗っていたと主張した。現代人なら、排泄という、絶対に他人に見られるはずのない生理活動まで監視の対象になるのかと驚くかもしれない。しかし、当時は洗う行為自体が疑いの目で見られていたのだから、当然と言えば当然のことだった。
とはいえ、他人が大便している現場を押さえてもよいと考えるような社会には、いずれ因果が巡ってくる。社会の一人一人が、同じコミュニティーのコンベルソやモリスコを異常なほど熱心に監視している以上、まさに同じ理屈で自分たちと同じ旧キリスト教徒に監視の目を向けるようになっても不思議ではない。巧みに証拠を集めて他人を告発してきた矛先が、今度は向きを一八〇度変え、社会の主流を成す人々に向けられる。再び迫害機関は、ある目的のために磨いた技能を、機関創設を支持した人々を相手に発揮することになった。
社会に与えた影響は強烈だった。歴史学者ファン・デ・マリアーナの言葉を借りれば、異端審問による秘密調査は、「人々から仲間内で話をしたり聞いたりする自由を奪った」。ほんの少しロを滑らせただけで、告発され、屈辱を受け、名誉を失うため、監視社会は不信社会となり、分断社会となった。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P320-321
この引用の最後の部分、「ほんの少しロを滑らせただけで、告発され、屈辱を受け、名誉を失うため、監視社会は不信社会となり、分断社会となった。」というのは非常に重要な指摘です。
行きつく果ては不信社会、分断社会なのです。
他人の詮索・噂話の快楽・監視社会の弊害ー創意工夫や創造性が社会から失われ、人々の生活は停滞する
異端審問は、社会に相互監視の文化を徐々に植えつける規則を定めていたのだ。監視や告発は、異端審問が直接行なっていたのではなく、その規則が作り出した社会的雰囲気から、自然と行なわれるようになった。
だからと言って、異端審問をスケープゴートにして責任を負わせ、それで人としての過ちを片付けてしまってはならない。他人を詮索してよいと言われ、多くの人は喜んでそれに従った。
現代人である我々も、本音を言えば、ほとんどの人が共通の知り合いの噂話をして盛り上がるだろう。噂話は、人と人とを結びつける楽しいものだし、何よりも、自分の失敗を棚に上げて他人の失敗を気兼ねなく話すことができる。
異端審問は、こうした行為に道徳的なお墨付きを与えることで、噂話の誘惑に善行という仮面をかぶせ、実に見事に民衆からの支持を確かなものにしていった。
噂話にお墨付きを与えた結果、異端審問は国民のありとあらゆる階層に広まった。(中略)
しかし、絶えず画一性を推し進めるやり方は、日照りが川に与えるのと同じ影響を人間社会に与えた。噂話や復讐で満足感や喜びが簡単に得られたため、創意工夫や創造性が社会から徐々に失われ、人々の生活は停滞していった。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P322-323
※一部改行しました
ここも鋭い指摘ですよね。
人間は他人の詮索や噂話が好きです。これそのものが悪いというわけではありません。
ですが、「異端審問は、こうした行為に道徳的なお墨付きを与えることで、噂話の誘惑に善行という仮面をかぶせ、実に見事に民衆からの支持を確かなものにしていった。」というところに危険があるのです。
その結果世の中がどうなっていったかというと、
「絶えず画一性を推し進めるやり方は、日照りが川に与えるのと同じ影響を人間社会に与えた。噂話や復讐で満足感や喜びが簡単に得られたため、創意工夫や創造性が社会から徐々に失われ、人々の生活は停滞していった。」。
なんと恐ろしい社会でしょう・・・
著者は不信社会、分断社会からは創意工夫や創造性が失われ、人々の生活は停滞していくと述べます。
こうなってしまえばその国は新しいものも生み出せず没落していく一方です。
実際16世紀前半に全盛期を迎えたスペインは、その16世紀の末には見る影もないほど没落していました。異端審問の弊害がどれだけ大きかったかは明らかだったと思われます。
続く
Amazon商品ページはこちら↓
異端審問: 大国スペインを蝕んだ恐怖支配 (INSIDE HISTORIES)
次の記事はこちら

前の記事はこちら
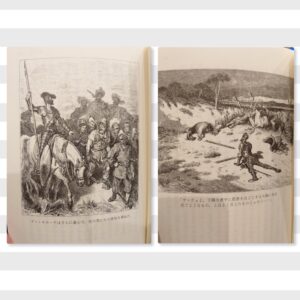
「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

関連記事















コメント