(9)モンテーニュと異端審問のつながり~衰退するスペインとヨーロッパ啓蒙思想の拒絶

『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑼
今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。
スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。
こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。
異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。
そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。
ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。
では早速始めていきましょう。
衰退するスペインとヨーロッパ啓蒙思想の拒絶
スペインは、ポルトガルとその植民地を失ったほか、一六四八年にはネーデルラント連邦共和国の独立を承認した。人口は減少し、国家は実質的に破産状態にあった。スぺイン領アメリ力植民地は、北アメリカの発展によって重要度が落ちた。一七世紀最後のスぺイン王カルロスニ世(一六六一~一七〇〇。在位一六六五~一七〇〇)は、身体的にも知的にも障害があって、ロからはしょっちゅうよだれを垂らし、子供を残すこともできなかった。その死をきっかけに起きたのが、悲惨なスぺイン継承戦争である。
ここで私たちが目にしているのは、かつては世界中に広がっていた植民地帝国の崩壊だ。この状況下でも異端審問の官僚機構は、前章で見たとおり、客観的には無意味な細かい事務処理に没頭していた。その態度は理解に苦しむものかもしれない。
しかし、ひたすら書類を集めることに集中していたのは、彼らの精神構造が目の前の現実に対処できなかったからである。現実として、植民地帝国と社会は急激に衰退していた。その事実に直面できないがために、国家の名誉と尊厳を守るためと称して作成された無意味な書類に逃げ込んだのだ。
だから、自分が見たいと思った現実と異なる意見は受け入れられなかった。真実とは、その真実から次第に離れていく者を最も傷つけ、最も強く怒らせるものである。そのため特にスぺインは、一七世紀後半にヨーロッパ思想の主流が啓蒙思想へと少しずつ向かっていたにもかかわらず、そうした潮流を嫌い、これに国家が汚染されるのを食い止めなくてはならないと考えた。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P359-360
スペイン異端審問によって社会は硬直し、多くのコンベルソ、モリスコを追放した影響で計り知れない経済的なダメージを負っていました。
そんな崩れ行く体制を維持するために思想・言論統制はますます厳しくなっていきます。
一方、そんなスペインを尻目に、ヨーロッパは新たな思想がどんどん生まれていきます。スペイン政府にとってこれも非常に脅威な存在でした。
フランシス・ベーコン〔一五六一~一六二六。イギリスの哲学者。経験論の祖〕、ルネ・デカルト〔一五九六~一六五〇。フランスの哲学者。近代合理主義の祖〕、ジョン・ロック〔一六三二~一七〇四。イギリスの哲学者。人民主権論を説く〕、バルーク・スピノザ〔一六三二~七七。オランダの哲学者。合理主義に基づく汎神論を説く〕といった知の巨人の肩に担がれ、科学的方法による探究を主唱する啓蒙運動は、異端審問の世界観にとっては直接的な脅威だった。
異端審問所は、遠く離れたところからでも、この運動にコンベルソやモリスコたちとはまったく違った形で自分たちに致命傷を与えかねないイデオロギーがあることを察知していた。異端審問所が疑念を抱いたのも当然だった。
啓蒙思想の重要な根源には、たどっていくと、遠い昔に異端審問官たちが情け容赦なく弾圧した人々、すなわちコンベルソに至るものもあったからだ。科学的世界観の発達は、スぺイン衰退の時代からニ〇〇年前の一五世紀末に、異端審問所がスぺインで最初に解き放った迫害の波と、深く関係していた。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P360
※一部改行しました
コンベルソの血筋だったモンテーニュ。彼の思想と異端審問のつながり
そんなスペインの血の流れを引いて生まれてきたのが有名なモンテーニュ(1533-1592)という哲学者でした。モンテーニュはフランス人ではありますがその血筋のルーツはスペインのコンベルソであったと言われています。

一五三三年二月にピエール・エケームとアントワネット・ロぺスの間に生まれた男子は、後のミシェル・ド・モンテーニュである。
モンテーニュは、現代の哲学者から、近代的な懐疑主義思想を展開した中心人物であり、デカルトやデーヴィッド・ヒューム〔一七一一~七六。イギリスの哲学者。経験論から懐疑論へ至った〕の先駆けとして科学的世界観の誕生に貢献したと考えられている。
一六世紀に彼は、ピュロン主義と呼ばれた懐疑論を最も声高に弁護した。ピュロン主義とは、知識を得ることが可能かどうかを決定するに足る証拠は存在しないのだから、いかなる判断も保留すべきだとする考えで、認識の可能性を疑うという意味で不可知論の一種である。
この考え方をモンテーニュは改めて整理し、自著の中で提唱した。それが、その内容とウイットと文体ゆえに今なお読み継がれている代表作『エセー(随想録)』だ。『エセー』に盛り込まれた見解の多くからは、モンテーニュが個人の思想や意見の大切さを認めていたことが分かる。
たとえば「子供の教育について」と題する章で、「この書物にあるものもやはり私の気質であり、私の思想なのです。私はこれを、私の信じていることとして示しているので、人の信ずべきこととして示しているのではありません」と記している(中略)
また、異なる世界観を隔てる溝は深く広く、一つ一つの世界観は、それを抱いている者にとっては正しく見えることも理解しており、そうした態度は、「食人種について」の章にある有名な一節「誰でも自分の習慣にないものを野蛮と呼ぶ」に凝縮されている。
こうした洞察の的確さは、執筆から四〇〇年以上経った今でも色あせておらず、これこそ、モンテーニュが当時の人々に比べて革新的な部分であった。彼が主張した思想と表現の基本的自由を、彼の祖先をサラゴサで迫害した制度のイデオロギーと比較して考えてみるといい。異端審問にとっては、思想信条の自由こそが最も危険なものであり、罰すべきものであった。異端審問が最も危険と見なした思想を、異端審問の犠牲になった人物の子孫が提唱したとしても、至極当然だったろう。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P362-363
※一部改行しました
言葉と行為が一致していなければその言葉は信用できない
異端審問が横行していたスペインの歴史がモンテーニュの思想に大きな影響を与えていたとこの本は述べています。
モンテーニュの思想の一つに、意図と行動の間には隔たりがあることを強調した点が挙げられる。(中略)
モンテーニュは、このニつがまったく別物であることに気づいていた。それによると「行為と言葉とが並んで」行かなくてはならず、「われわれの思想の真の鏡はわれわれの生活の経過」だという。
たとえば、ある人がロでは汝の隣人を愛せだの、慈愛が大切だの、あるいは世界の紛争地域に平和と融和の種をまかなくてはならないだのと、美辞麗句を並べ立てていても、その人が実際には戦争を行ない、憎しみの種をまくだけの人生を送っているとしたら、本気で隣人愛や人類愛を訴えているとは言いにくい。
あるいは、「信仰の自由について」という章で述べている言葉を借りれば、「よい意図が度を越して進められると人間をきわめて不徳な行為に追いやることはよくあることである」。
ここに、人間の生涯で情念の果たす役割にモンテーニュが失望し、中庸を重視していたことが見て取れる。『エセー』収録の懐疑論に関する文章で最も大きな影響力をもったのは「レーモン・スボンの弁護」だが、その中でモンテーニュは、宗教は情念で導かれるべきでなく、信仰によって導かれるべきだと強く主張した。
そして、「キリスト教徒の敵意ぐらい激しいものはどこにもない。われわれの信心は、われわれの憎悪や、残虐や、野心や、貪欲や、中傷や、反逆への傾向を助けるときには驚くべき力を発揮する。(中略)われわれの宗教は悪徳を根絶させるために作られたのに、かえって悪徳をはぐくみ、養い、かき立てている」と書いている。ここでも意図と行動の対立は明らかで、モンテーニュが、真の宗教は情念で導かれるべきでなく、情念は人に道を誤らせるだけだと確信していたことがよく分かる。
「レーモン・スボンの弁護」では、キリスト教の普遍性という概念を攻撃しているが、その論拠として、不合理な情念が宗教の土台となっていることが非常に多い点を指摘すると同時に、相対主義を主張している。
我々は「われわれの宗教を、ただわれわれの流儀とわれわれ自身の手でしか受け取っておらず、その受け取り方も他の宗教の場合と何ら違うところがない」のであり、「もしも、別の地域に生まれあわせて、別の証拠を示され、同じような約束と威嚇をつきつけられたら、同じように、まったく反対の信仰を植えつけられるかも知れないのである。われわれはぺリゴール人とかドイツ人であるのと同じ資格で、キリスト教徒であるにすぎない」。
そして彼は、本質的に欠陥のある私たちの理性では神に至ることはできず、ただ信仰のみが「正しい人(オム・ド・ビアン)」へ向かう道であり、理性を使うことで神の力を人間の法解釈に従わせようとしてはならないと説いた。こうした考え方を、信仰主義と言う。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P363ー365
※一部改行しました
まさしくここで語られたことは異端審問に対する批判であるように思えます。
文面の裏側に隠されたモンテーニュの本当の信条
ここで、コンべルソとモリスコの両者が、迫害によって異端に追いやられた経緯を思い出してほしい。すでに見てきたとおり、両者の場合は、異端審問がある程度自分たちの手で異端を作り出し、それを最大の脅威だと言って迫害したのが実情だった。
啓蒙思想の場合も、モンテーニュの例で分かるように、それとよく似た動きが進んでいた。異端審問の作り出した状況が、科学的世界観という新たなイデオロギーを通して異端審問に反抗する力を生み出したのである。(中略)
先の一文は、文面の裏側にモンテーニュの本当の信条が隠されていることを示唆している。たとえば「レーモン・スボンの弁護」には、「人間を害する病毒は、人間が自ら知識があると思うことである。だからこそ無知はわれわれの宗教によって、信仰と服従にふさわしい特性として、あれほどに讃えられたのである」という主張があり、内容的には信仰主義を支持しているが、これは皮肉と取るべきだろう。
コンべルソや、モンテーニュのようなコンべルソの子孫にとって、「二重の意味を持つ表現と、曖昧な物言い」は、表向き受け入れられる主張の裏に、体制を痛烈に批判する意見を隠す常套手段になっていた。
モンテーニュはたいへんな読書家だったから、この手法を自由自在に使いこなせたはずで、だから、信仰を攻撃する懐疑論という爆弾を、表向きは懐疑論から出発して信仰を深めたようなふりをしながら、一読しただけでは分からぬように仕掛けることができたのだろう。一八五九年にチャールズ・ダーウィンが『種の起原』を出版したときも、これと似たような状況で同様の手法を使っている。
モンテーニュが『エセー』で、相対主義を主張して、宗教における情念の役割を否定し、人を言葉ではなく行動で評価する重要性を強調するという一連の流れを考えると、サラゴサにいた彼の母方の祖先の歴史が、彼の思想形成に少なくとも何らかの影響を与えたに違いないと思われる。
異端審問は迫害を行なうことで、迫害された人々が、それまで真実とされてきたことすべてを疑うようになる雰囲気を醸成した。この雰囲気の中、新たなイデオロギーが誕生する。それは、神の正義や裁きを認める主張すべてを疑うイデオロギーであり、近代の到来を告げる思想であった。そして、この近代という時代が、最終的に異端審問を滅ぼすのである。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P366-367
※一部改行しました
ヨーロッパにおける無神論や懐疑論の萌芽はこうして生まれたのでした。
敵対的な思想を持つ者を抹殺しようとした異端審問でしたが結局こうしたもっと強大な存在を生み出すことになってしまったのです。
教会への不信や懐疑論、無神論の流れは教会の権威を徐々に蝕んでいきます。
近代的なヨーロッパの哲学者がいかに生まれてきたということに異端審問が大きな影響を与えていたというのは非常に興味深いものでした。
続く
Amazon商品ページはこちら↓
異端審問: 大国スペインを蝕んだ恐怖支配 (INSIDE HISTORIES)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

関連記事





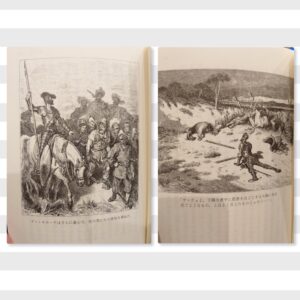











コメント