陶山昇平『ヘンリー八世 暴君かカリスマか』あらすじと感想~王の離婚問題とイギリス国教会創設の流れを知れるおすすめ伝記

陶山昇平『ヘンリー八世 暴君かカリスマか』概要と感想~イギリス国教会の始まりと当時のヨーロッパ事情も知れるおすすめ伝記
今回ご紹介するのは2021年に晶文社より発行された陶山昇平著『ヘンリー八世 暴君かカリスマか』です。
早速この本について見ていきましょう。
500年前のイングランド王の生涯を知ることは、「暴君」とは何者であるかを知る手蔓となるだろう…
薔薇戦争による混乱を解決した先王の跡を継ぎ、テューダー朝の第二代国王として即位したヘンリー八世。華やかなルネサンス君主であるはずの彼の治世から決して血なまぐさい印象が拭えないのはなぜなのか。英国王室きっての怪人の生涯に迫った本格評伝。6度の結婚、ローマ・カトリック教会との断絶、忠臣の処刑などで知られる「悪名高き」国王の真実。
Amazon商品紹介ページより

ヘンリー八世といえばシェイクスピアの『ヘンリー八世』で有名なイングランド王で、16世紀前半から中頃にかけて在位した人物です。
ヘンリー八世は並外れたカリスマ、暴君とも知られており、離婚問題でローマカトリックと対立し、そのままイギリス国教会を立ち上げたことでも有名です。そこからイギリスの反カトリックの流れが出来上がり、陰謀うずめく血みどろの政治闘争が続けられることになります。こうした流れで出てくるのが血まみれのメアリーやエリザベス女王になります。この2人が共にヘンリー八世の子だったというのは興味深いですよね。
さて、私がこの本を手に取ったのは一見ヘンリー八世とは関係のない1527年のサッコ・ディ・ローマ(ローマ劫掠)事件がきっかけでした。私がこの事件を知ったのは前回の記事で紹介した『教皇たちのローマ』のおかげです。

この事件は1527年にローマが攻撃され、虐殺、略奪の限りが尽くされた恐るべき出来事でした。

そしてそれを行ったのが何を隠そうカール5世の神聖ローマ帝国軍でした。

カール五世はスペインと神聖ローマ帝国という二つの国の皇帝です。つまり彼は熱烈たるカトリック国家のトップにいた人物になります。そのカトリック王国の盟主が聖地バチカンを徹底的に破壊し略奪したというのですから私はその事実に頭がくらくらする思いでした。
と言いますのも、私はこれまで、スペインはアメリカ大陸の発見後その黄金を用いてカトリックの繁栄と宗教改革への対抗のために莫大な財と労力を用いていたと理解してきました。
たしかにそれは事実なのですが、そんなスペイン・神聖ローマ帝国があろうことかカトリックの総本山のバチカンを略奪し破壊するなんて想像できるでしょうか。
なぜこのようなことが起きてしまったのかは長くなってしまうのでお話しできませんが、私にとってはこの出来事はあまりに衝撃的なものとなったのでした。これまでもローマ掠奪(サッコ・ディ・ローマ)という出来事自体はキリスト教史を学ぶ上でおそらく目にしていたことはあったはずです。ですがこの出来事の重大さ、深刻さには全く気付いていませんでした。この本を読んで初めてその意味がわかりました。そのような意味でも『教皇たちのローマ』はこれまでのキリスト教観を覆してくれた作品になりました。
そしてこの本を読んでいて私はふと頭をよぎるものがありました。
「あれ?1527年といえば、この辺でヘンリー八世がイギリス国教会を作ろうとしていなかったっけ・・・もしかしてヘンリー八世がこんな大胆なことができたのはサッコ・ディ・ローマでバチカンが弱っていたからではないか?」
私はこれまでシェイクスピアの伝記を読んだ関係で、何となくではありましたがイギリスの流れを知っていました。そしてその歴史とイタリア・ローマ史がビビッと繋がった瞬間でした。これは今すぐにでも確かめたい!あのヘンリー八世はこの時どんな状況だったのだろう!私は居ても立っても居られなくなりこの本を手に取ったのでした。
そして読んでみて驚きました。サッコ・ディ・ローマ事件はやはり大きな影響を与えていたようです。まぁ、正確に言えばそもそもサッコ・ディ・ローマ事件が起きてしまったというそのこと自体がローマカトリックの弱体化とヨーロッパの複雑な政治情勢を示していると言えます。こうした国際情勢の中ヘンリー八世がどのように動いていたのかを知れるこの伝記は非常に興味深いものがありました。
著者は「はじめに」でヘンリー八世とこの本について次のように述べています。現代を生きる私たちの問題と重ねて語られた興味深い前書きですので、少し長くなりますがじっくり読んでいきたいと思います。
ドナルド・トランプがホワイトハウスを去った。ジョー・バイデンの勝利が確実になった後も投票不正を訴え、敗北を認めない彼の姿勢に、バラク・オバマ前大統領は「民主主義の否定につながる。これは危険な道だ」と述べて懸念を示した。もっとも、アメリカ民主主義が危機に瀕しているというのは、ニ〇一七年のトランプ政権発足以来、繰り返し喧融されてきた話ではある。司法省によるロシア疑惑捜査に対する執拗な批判、マスメディアへの露骨な敵視などは、日本でも度々報道されてきたから、読者にも耳馴染みではなかろうか。
民主主義の祖国ともいうべきアメリカ合衆国の大統領が民主主義を危機に追いやっているとの批判はいかにも深刻である。しかし、この第四十五代アメリカ大統領は、こともあろうに民主主義とは縁遠い五百年前のイングランドの絶対君主に擬えられてさえいたのである。エコノミスト誌の二〇一七年五月十二日号は、トランプの衝動的な性格と思慮不足は、法の支配と経済にとって脅威であるとして、次のように説いている。
ドナルド・トランプは国王のようにワシントンに君臨し、ホワイトハウスはまるで彼の宮殿のようだ。威張り散らし、注目のただ中にいなければ気が済まず、衝動的な性格はヘンリー八世を思わせる。異色の経歴ながら最高権力者の座に上り詰めることができたのは、議会や官僚たち、それにメディアが揃いも揃って冴えないからだとの信念に支えられて、邪魔な人間や意見に牙を剥いている。
トランプと(不名誉な形で)共通点があると名指しされたへンリー八世。彼こそが本書の主役である。十六世紀のこの王の事績に明るくない向きであっても、自身の離婚問題をきっかけにローマ・カトリックと断絶し、結局、その生涯に六人の王妃を迎えた(しかも、そのうち二人を断頭台送りにした!)強烈なイングランド国王がいたという事実は聞き覚えがあるのではないだろうか。
二十一世紀のアメリカ大統領と十六世紀のイングランド王という立場の違いはあれど、両者に共通するのは、強烈なエゴと自己愛(もちろん衝動的な性格も)である。トランプの自己愛ぶりに関しては、心理学博士の学位を持つ彼の姪が「自己愛性人格障害」と自著の中で断じているから、まずは折り紙付きといったところだろう。一方のへンリー八世はどうか。
華やかなルネサンス君主であるはずのへンリーの治世から血なまぐさい印象が拭えないのは、自身のために粉骨砕身してきた忠臣を容赦なく処刑する国王の酷薄さのなせる業である。こと信仰や良心の問題に関しては、臣下が国王と異なる見解を持ち得るという事実をどうしても受け容れられないへンリーは、イングランド国王が国教会の首長であることを認めず、「キリスト教世界共通の信仰」を守り抜こうとしたトマス・モアを断頭台に追いやった。その後も何人もの廷臣たちが王の逆鱗に触れ、慈悲をかけられることなく命を落としている。その最たる例が、国王宗務代理として宗教改革に辣腕を振るったトマス・クロムウェルである。自らの右腕を誅殺したへンリーは、怒りに任せて有能な宰相を葬ってしまったことを後悔し、彼を告発した政敵たちに責任転嫁し始める。これを衝動的な暴君の所業と呼ばずして何と呼ぼう。
一方で、自己愛に衝き動かされた人間が、全能感という名のオーラを纏うこともしばしば見られる。アドルフ・ヒトラーやヨシフ・スターリンら独裁者が、強いコンプレックスに苛まれながら、(全く矛盾したことだが)強烈な自己愛の持ち主であったのは、しばしば指摘されるところである。ナルシシズムとカリスマは相性が良いのだ。
興味深い逸話がある。「血まみれのメアリー」の異名で知られる、へンリーの娘メアリー一世は、その渾名のとおり強権的なイメージが強い。しかし、その彼女にして、廷臣たちが反抗的な態度を示すと、「一カ月でいいから父が生き返ってくれれば」と愚痴をこぼしていたという。暴君へンリーは、死してなお「絶対服従」の対象として仰ぎ見られる存在-カリスマでもあったのである。
ところが、実に興味深いことに、この王は終生不安感に苛まれ、人間愛に飢え続けてもいた。離婚へと彼を駆り立てたのは、愛人アン・ブーリンへの執心もさることながら、王位継承への不安であったのは言うまでもない。イングランド王家を二分した薔薇戦争の記憶は、いまだ暗い影を落としていたのである。五番目の王妃キャサリン・ハワードの不貞の事実を告げられたとき、枢密顧問官らの前で流した涙は、夢見た幸福な結婚生活が打ち砕かれた深い失望ゆえのものだったろう。
本書を読み進めるうちに読者は、この王が極めて複雑怪奇な人格を持つことにも気づかれるはずだ。
トランプはホワイトハウスを去った。しかし、エゴと自己愛は政治的人間の動力源でもある。五百年の時を経てトランプがへンリーと重ね合わされたように、いずれ強烈なエゴの持ち主が現れて、世界を再び騒然とさせるだろう。二十一世紀に生きる我々は、今後も強力な権力を振りかざすエゴイストやナルシシストたちと対峙していかなくてはならないのだ。
「汝の敵を知れ」とは蓋し至言である。五百年前のイングランド王の生涯を知ることは、「彼ら」が何者であるかを知る手蔓になるだろう。その上で、へンリー八世という人物の劇的な生涯の物語も楽しんでいただければ、筆者としては望外の喜びである。
晶文社、陶山昇平『ヘンリー八世 暴君かカリスマか』P9-12
これを読むとヘンリー八世への興味が湧いてきますよね。
実際、この本はものすごく面白いです。著者の語りも素晴らしく、歴史の流れがすっと入ってきます。ヘンリー八世という圧倒的カリスマの驚異の人生を私達は目撃することになります。
この本はシェイクスピアファンにも強くおすすめしたいです。この王の娘が後のエリザベス女王であり、その治世で活躍したのがシェイクスピアです。彼が生きた時代背景を知ればもっとシェイクスピア作品を楽しむことができます。時代背景を離れた芸術はありません。私にとってもこの伝記は非常にありがたいものとなりました。
ものすごく刺激的な作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「陶山昇平『ヘンリー八世 暴君かカリスマか』~王の離婚問題とイギリス国教会創設の流れを知れるおすすめ伝記」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事







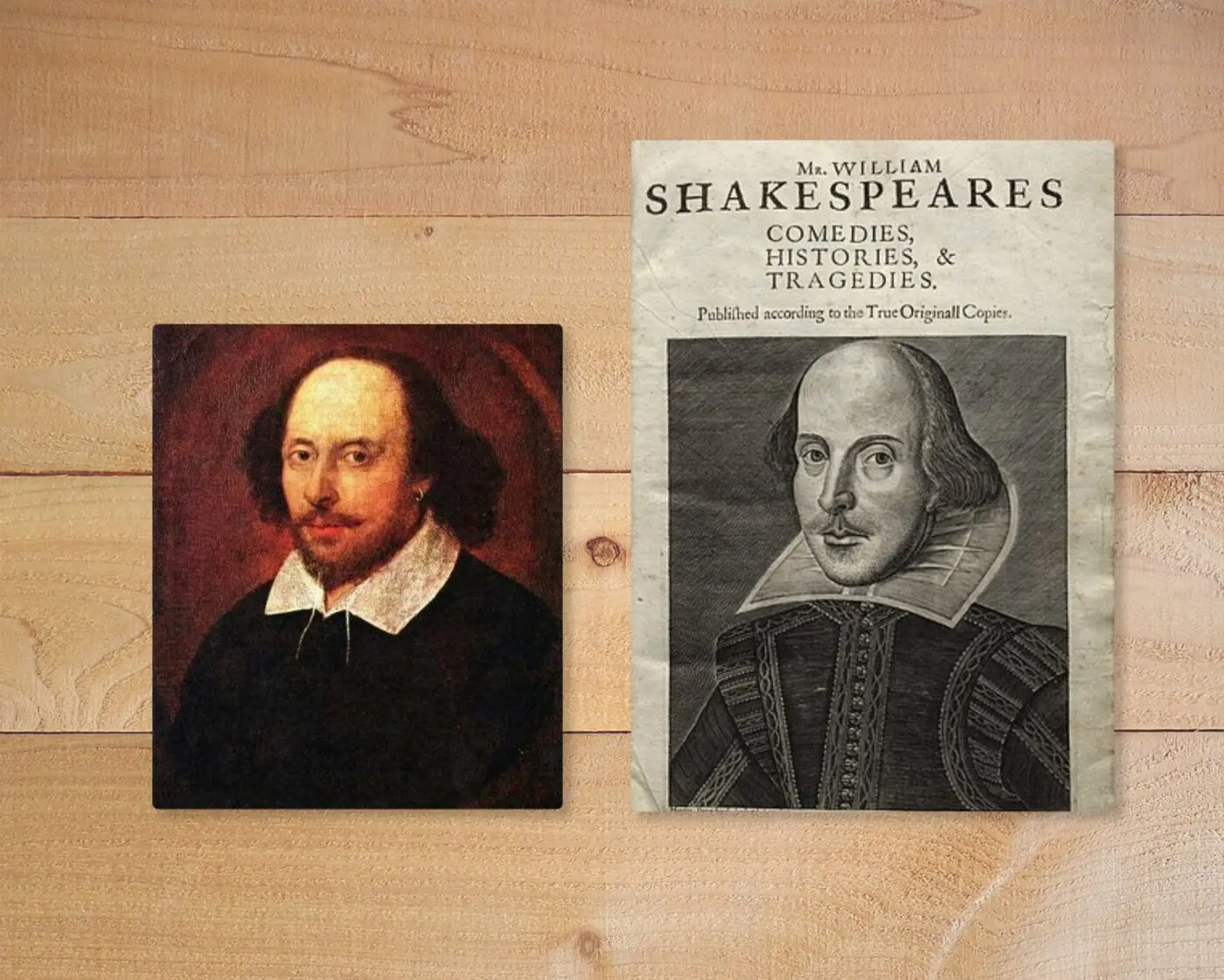





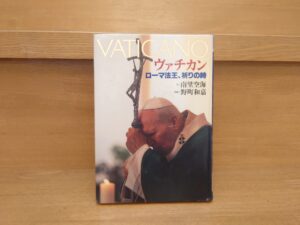



コメント