(20)いざジョージアへ~なぜ私はトルストイを学ぶためにコーカサス山脈へ行かねばならなかったのか

【ジョージア旅行記】(20)いざジョージアへ~なぜ私はトルストイを学ぶためにコーカサス山脈へ行かねばならなかったのか
オランダでフェルメールを堪能した私は、いよいよアムステルダムからジョージアの首都トビリシへ向かう飛行機に搭乗した。いよいよこの旅のメインディッシュが始まるのだ。
さて、ここまで『秋に記す夏の印象』を読んで下さっている皆さんもきっと一度はこう思ったことがあるのではないだろうか。
「ジョージアってどこ?」と。
そう、日本にいてもなかなか話題に上ることもないジョージア。
私が「今度ジョージアに行ってきます」と言うと、たいていの方は「アメリカの?」と返す。
たしかにジョージアと言えばアメリカが思い浮かぶのも無理はないと思う。私もトルストイの縁がなければジョージアのこともわからなかっただろう。
そして「アメリカではなくて、グルジアの方です」と言うと、「あぁ、あのワインのとこね!」と分かって下さる方が多い。旧ソ連時代にはジョージアではなくグルジアと呼ばれていた。その時のイメージが今も根強く残っているのかもしれない。
さて、地図をご覧になって頂ければわかるように、ジョージアはトルコの北東に位置し、そして北にはロシアがある。
ロシアとは古くからの因縁があり、2008年にはロシアとの戦争になっている。現在も国境地点は両軍がにらみ合い、緊迫した状況が続いているというのが現状だ。

こちらはトビリシの旧市街を見下ろした写真。ヨーロッパともイスラム圏とも違う独特な雰囲気がある。


ジョージアの宗教はジョージア正教。カトリックともプロテスタントとも異なる。
正教といえばよく東方正教会という言葉を聞くかもしれない。この正教というのは伝統的なキリスト教のあり方を守ることを重んじている。だからこそ「正しい教え(オーソドックス)」という意味で正教という名となっている。
そしてこのジョージア正教のように、「〇〇正教」というのが世界中にある。例えばギリシャ正教、ロシア正教、セルビア正教など。これは「〇〇」の部分に国の名前が来る。「〇〇正教」というのは「〇〇にある正教」という意味だ。基本的にはどの国の正教も同じ教義を信仰しているということになる。もちろん、厳密に言えば私が述べた定義はざっくりと言い過ぎているかもしれないが、ここではジョージア正教とは何かということの簡単な概略ということでご容赦願いたい。正教についてより詳しく知りたい方には以前当ブログでも紹介した高橋保行『ギリシャ正教』が入門書としておすすめだ。

このツミンダ・サメバ大聖堂はトビリシで最も巨大な教会だが、これが建てられたのはなんと2004年というごく最近のこと。
ジョージアを案内してくれたガイドによれば、ジョージア国民は今でもとても信仰熱心でお祈りは欠かさないそう。たしかにガイド自身も教会に入る時は必ずスカーフを頭に巻き、祈りを捧げていた。そしてジョージアの教会に入ればいつも真剣にお祈りしている多くの人と出会うことになった。

大聖堂内部は未だに工事が続いていた。だがただ大きいだけの教会というのではなくて、祈りの雰囲気がたしかに感じられた。この後の記事でも様々な教会をご紹介するが、どの教会も神聖な空気が漂っていたことは間違いない。祈りの雰囲気がここまで感じられるのも珍しいと思う。ここに来る前に訪ねたパリでは残念ながらそのような空気は感じられなかった。きっと探せばそういう教会もたくさんあるのだろうが、私が行った教会は良くも悪くも観光地化してしまっていた。パリとジョージアの教会のコントラストには私も大きな驚きを感じることとなった。
そしてトビリシに来て驚いたことがもうひとつあった。
それがジョージアが想像よりはるかにアメリカナイズされていることだった。
旧市街の古い街並みを離れると、街の中心部に巨大なショッピングモールがあったり、ホテルや様々なサービスはほとんどヨーロッパと変わらない。一言で言うならばものすごく快適であった。慣れ親しんだ生活をそのまま享受することができたのである。チェーン的なオシャレなカフェがあったり、マクドナルド、ケンタッキーなどなど、困った時に助かる店があったのだ。
想像よりはるかに現代的なジョージアに驚いた私は、そのことをガイドに聞いてみた。
すると、ガイドはこう答えてくれたのである。
「2004年に政治体制が変わってから一気にジョージアは変わりました。それまでの旧ソ連的なあり方から経済成長を目指す方向に切り替えたのです。それまでは道路もひどくて観光客もほとんどいませんでした。街の中心部ですら道路が整備されていなかったのです。街の中心部の道路すらそうなのですから郊外はさらにひどいです。もちろん、観光客が来れるような宿泊施設もシステムも整っていませんでした。」
そしてさらに私は聞いてみた。
「思っていたよりロシア語が聞こえてきませんよね。私はてっきりロシア語がわからないとここで過ごすのは大変かと思っていました」
「基本的には私達はジョージア語を使います。そして今若いジョージア人はほとんどロシア語を話しません。ロシア語を使うのは旧ソ連時代の年配の方だけです。むしろ今のジョージア人からすると、できるだけロシアから離れたいという思いが強いです。第二言語の教育もロシア語ではなく英語を学ぶように今はなっています。ですのでロシア語はほとんど使われません。英語の方が私たち世代にとっては馴染み深いです。」
なるほど・・・。
ジョージアは2004年を境にがらっと変わったようだ。そしてロシア語がもはやほとんど使われていないというのには驚いた。もちろん、年配の方だけでなくともロシア語が分かる人はたくさんいるだろう。だが今やアメリカナイズされたジョージアにあっては、なるべくロシアから離れたいという思いがあるようだ。2008年のロシアとジョージアの戦争も大きな影響があるだろう。さらに言えば今回のウクライナ侵攻でその念はかなり強まっているようだ。
さて、ここまでジョージアとトビリシについて少しお話ししてきたが、皆さんいかがだろうか。
皆さんの中にはきっとこう思われている方もおられるのではないだろうか。
「それにしても、なぜジョージアまで来なくてはならなかったのか。ドストエフスキーとトルストイを学ぶためと言ってもそのつながりは何なのか」と。
実際私も出発前に何度となくそう質問されたものである。「何でジョージアなの?」と。
たしかにこれは不思議に思われるかもしれない。ドストエフスキーとトルストイを学ぶために行くなら普通はロシアだろうと。なぜジョージアなのかという必然性が見当たらない。
もちろん、私は数年前からロシアに行きたいとずっと思っていた。だがウクライナ侵攻によってすべては消えた。
であるならば私に何ができるだろうか。そんな折にちょうど読んでいたのがトルストイだったのだ。
このトルストイがジョージアのカフカース(今はコーカサス山脈と呼ばれている)と並々ならぬつながりがあった。しかも後の文豪としてのトルストイの原点と言ってもいいほどの体験をここでしていたという。
であるならばぜひそのカフカースを見てみたい。私はそう思ったのだ。
さて、この話自体は『秋に記す夏の印象』の序ですでにお話しした。
今回はこのトルストイとカフカースについてより詳しくお話ししていきたいと思う。それを知れば私がなぜジョージアまでやって来たのかということがよりクリアになるだろう。

トルストイは1851年、23歳の年にこのカフカースを訪れている。
その圧倒的な自然やそこで出会った人々、また彼自身命を懸けて戦った経験がトルストイの文学に大きな影響を与えている。
これより藤沼貴著『トルストイ』を参考にトルストイの「カフカース体験」を見ていきたい。
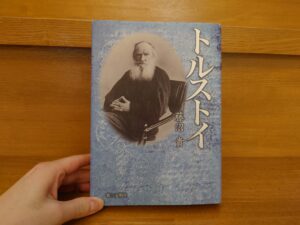
トルストイの人柄や文学の特徴を見ていくためにもこの作品は非常に参考になる。
ではまずはトルストイの出発のエピソードについて見ていこう。
トルストイは五一年四月二十九日、ヤースナヤ・ポリャーナを出発して、カフカースへ旅立った。カフカースの軍隊から一時帰省していた兄ニコライが軍務にもどる時、いっしょについて行ったのだ。
九七~九八ページで書いたように、当時カフカースに行くのは容易なことではなかった。行く以上相当な理由があったはずだ。
この場合、まず考えられるのは、いっさいの過去のしがらみを断ち切り、現在の行きづまりを打開するための脱出ということである。
トルストイは生涯で何度も過激な「脱出」を試みた。一八四七年四月の大学中退・帰郷の行為もそうだし、一九一〇年の死出の旅路となった家出もそうだった。
カフカース行きは、借金で首がまわらなくなり、事業にも失敗した若者が「夜逃げ」をして、異境へ消えたのだ、とも言える。しかし、トルストイの場合、数度の「脱出」のうちマイナス要素しかなかったものは一つもない。また、いくつかの「脱出」がそれぞれ違う特徴をもっていて、同じものはない。カフカース行きをトルストイによくある「脱出」の行為と言って片付けずに、もう少しこまかく見る必要がありそうだ。
カフカース行きの前、トルストイは前章の最後で述べたように、すでに文学創作の道に踏みこんでおり、遅まきながら自分の文学的才能にも気づいていて、作家としてなんとか立っていけるのではないかという曙光を見ていた。それでいながら、書斎に入り、拭き清めた机の前にすわるかわりに、馬車に乗り、船に乗り、馬にまたがって遠くカフカースに行った。
大学中退・帰郷の時も、たしかに「地主の義務をはたす」「自分をしっかり形成する」といった前向きの目的はあった。しかし、それは目的というよりむしろ理想で、まだはっきりした形はなかった。
それにひきかえ、カフカース行きの時は、トルストイはもう出版を予定した「私の幼年時代」の原稿を、つまり、手で触れることのできる確実な「物」を旅行カバンに入れていた。とすれば、何のためにわざわざ遠くて、つらいカフカースまで行く必要があったのか。
第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P138-139
トルストイのカフカース行きは単なる逃避ではなく、何らかの思いや「突き動かされる何か」があった。
そして実際に彼はこの地で「その何か」を掴むことになるのだ。
ヤースナヤ・ポリャーナからカフカースまでは直線距離にしても約二千キロ。トルストイはヤースナヤ・ポリャーナからツーラに出、モスクワを経由してカザンに行き、そこに一週間滞在してから、サラトフに到着した。ここまでは馬車を使ったのだろう。モスクワ・ぺテルブルク間に鉄道が開通したのかちょうどこの年(一八五一年)だから、モスクワより東にまだ汽車はなかった。
サラトフからは船に、それも、大きな客船ではなく、わざわざやとった小舟に乗ってヴォルガ川をくだり、終着港であるカスピ海沿岸のアストラハンに着いた。その後はいよいよカフカース。悪路を馬で越えながら目的地のスタログラドコフスカヤにたどり着いたのはカザンに滞在した一週間を差し引いても、二十五目、距離にすれば二五〇〇キロにおよぶ旅程だった。
現代のわれわれには耐えられない、長くてつらい旅行だが、六一~六ニぺージでも書いたように、当時の人にはこの程度の旅はおどろくに当たらない。まして、トルストイは旅行好きだ。途中いやなこともあったが、大体は長旅を大いに楽しんだ。
大学中退・帰郷の時は肩をいからせ、勢いこんでいたトルストイだが、今度はそのような気負いが見られない反面、しっぽを巻いた負け犬のうらぶれた姿もない。出発直後モスクワで兄ニコライといっしょに撮影した写真を見ると、兄のほうは背をかがめて、さびしそうな様子をしているのに、トルストイは胸を張って、いばった顔つきをしている。
かれはカザンに一週間滞在したが、この予定外の長居の原因は、そこで偶然会った感じのいい若い女性ジナイーダ・モロストーヴァに一目惚れしたことだった。惚れっぽくて、思いこみの強いトルストイのことだから、いきなり愛を告白しようとまで考えたが、さすがにできなかった。
五月三十日、スタログラドコフスカヤに到着するとすぐ、かれはモロストーヴァ家と親しい(のちにジナイーダの妹と結婚した)友人のオゴーリンに、こんな戯れ歌のような手紙を送った。
オゴーリンさん!
大急ぎで
手紙で知らせてね、
皆さんのことを、
お嬢さんの
モロストーヴァのことも。
お願いします
レフ・トルストイそして、トルストイはジナイーダのことをその後何度も思い出したばかりか、この淡い想いを一生忘れなかった。
これも追いつめられて鬱状態になり、蒸発しかけている人間の言動ではない。トルストイはカフカースへ気軽な旅行に行くつもりで、長期間そこで生活したり、勤務したりするつもりはなかったのだろうか?
確かにはじめは、カフカース周遊という気楽な考えもあったようだが、出発の時点では、カフカース行きを生活全体に変化をもたらすかもしれない重要なものと考えていたようだ。
第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P139-141
※一部改行した
カフカースへの旅程がまた凄まじい。著者が述べるように現代人にはまず耐えられないような過酷な旅だ。トルストイがいかに頑健な体だったかがうかがえる。
そしてトルストイの一目惚れのエピソードもトルストイらしさがすでに出ているように感じられはしないだろうか。
スタログラドコフスカヤに到着してからちょうど一か月後の六月三十日に、トルストイは日記にこう書いた。「どうして私はここへ来てしまったのか?わからない。何のために?答えは同じだ」
これを気楽な旅行者の言葉と考えることは不可能だ。何か一つのことをしてしまった者が、ふとわれに返って発した言葉と受け取れる。人間は重大な場合にかぎって、分析や判断より、直感で行動する。しかし、冷静になって、あらためて自分に問い直してみると、自分の行動の意味が自分にもよくわからなかったりする。トルストイのカフカース行きもそのたぐいのものだった。
カフカースに来てから半年あまりたった十一月に、トルストイはタチヤーナおばさんにあてたフランス語の手紙で、この行為は「coup tie tête(ぱっと頭にうかんだもの)」と書いていた。トルストイの記憶は半ば空想的で当てにならないが、これは到着直後の「どうして私はここへ来てしまったのか?わからない」という言葉と符合しているので、真相を伝えているに違いない。
しかも、トルストイは自分の行動を直感的で、衝動的だと認識しながら、その行動が間違っていなかったことも直感していた。coup de têteという語の前後もふくめると、タチヤーナおばさんあての手紙にはこう書かれていた。「いずれにしても、私はカフカースに来たことを決して後悔しないでしよう―それはcoup de têteですが、私のためになるものなのです」
実際、さんざん考え、理性と哲学を基盤にし、マニフェストまで用意して決行されたカザンから郷里への「脱出」はたちまち挫折したのに、「ぱっと頭にうかんで」即行された郷里からカフカースへの「脱出」は、トルストイ自身とその生活に根本的な変化を生じさせ、その後のトルストイを形成する重要なものになった。
カフカースに来てからも、トルストイは相変わらず次の日の日課を作っては実行しなかったり、ギャンブルで負けて借金をこしらえたり、いかがわしい女たちと付き合ったりしていた。しかし、カフカース行きの前と後では、トルストイの生活に明らかな違いが生じていた。
第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P142-143
※一部改行した
トルストイはカフカースの地で様々な経験をすることになる。
そしてそれらの体験が彼の名作『コサック』や数々の短編小説となって結実する。
トルストイ初期の作品はそのほとんどが実体験と密接に繋がっているのだ。
五月三十日スタログラドコフスカヤに着いて、トルストイが最初にした行為は文章を書くことだった。かれは出発前から書いていた「きのうのこと」という短編小説かエッセーのようなもののつけたりとして、「もう一日」という題でサラトフからアストラハンまでの船旅の様子を書きはじめたのだ。この文章は一ページ足らずの断片で終わってしまったが、その内容を見ても、すでにトルストイのなかに作家の意識と習慣ができあがりかけているのが感じとれる。
次にトルストイがしたのはへたなくせに大好きなギャンブルで、六月十三日には八百五十ルーブルもすってしまった。これは今の日本の一千万円以上にもあたる大金だ。
しかし、その直後トルストイはこれまで一度もしなかったこと、しかもカフカースでなければできないことを体験した。それはカフカースの少数民族チェチェン人との戦争である。
トルストイは軍隊に入るためにカフカースに行ったと書いている伝記も少なくないが、かれが軍隊に入ったのは五一年末のことで、六月の時点ではまだ軍人ではなく、軍隊に入ることを決めてもいなかった。
最初は正規の軍人ではなく、ボランティアとして戦闘に参加したのである。それから、二年七か月半、別の戦場(ドナウ地方からクリミア半島)に赴くためにカフカースを去るまで、トルストイは数度戦闘に参加し、死の危険までふくめて、さまざまな体験をした。
第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P144-145
※一部改行した
さらっと書かれているがトルストイがギャンブルで1000万円ほどすってしまっていたというのは驚きだ。さすがトルストイ。負け方もスケールが違う。(当時のロシア貴族の基準からすればこの額は普通なのかもしないが・・・)
そしてそんなトルストイが現地での体験を経て執筆したのが『襲撃』という短編だ。

この作品は後の名作と比べて有名なものではないかもしれないがトルストイの原点を感じるために非常に重要な位置を占めていると私は思う。
ではこの作品について見ていこう。
トルストイはこの作を一八五二年の十二月カフカーズで脱稿して、すぐさま雑誌「現代人」へ送った。処女作『幼年時代』、『地主の朝』のつぎに来た、この人の第三作に相当する。
彼は、カフカーズへ来てまだ間のないころ、兄にしたがってスタールイ・ユルトに滞在中、志願兵の資格で侵入に参加したことがあったが、この作はまさしくその時の体験から生まれたものといっていいであろう。
量からいっても質からいっても、数ある文豪の作品中では、かくべつ主要な地位を占めるものとは言いがたいけれども、彼のカフカーズ時代を代表する作品の一つとして、また、後年この人の牢乎たる特質となった諸条件を、芸術的にも思想的にも、小さいながらにあまさず具現している点において、かなり興味ある作品である。
内容は、カフカーズ駐屯軍の一隊が、ほとんどその年中行事ともいうべき敵地侵入を敢行して略奪をほしいままにし、帰途、カフカーズ戦争の特色である敵の追撃をむかえて退却戦をおこないながら、凱歌を奏してひきあげる―このニ日間のできごとを、なんの奇もなく、順を追って叙述したものにすぎないが、その境がすでに常凡の域を超越した、戦争という冒険生活のひとこまである上に、それを描きだすぺンがまた霊活をきわめて、山地の日の出日没、山や谷をこめる霧の浮動、影と音とによる神秘的な夜景画等、景観の美をもって鳴るその舞台を、絵画的・音楽的にまで紙上に再現させているあたり、後来『戦争と平和』にあらわれる戦争描写のみごとな模型を見せているばかりでなく、ひとりひとり生きいきと描きわけられている人物のタイプにも、それぞれあの特色あるトルストイの目が光っていて、読者につきせぬ興昧をあたえる。
河出書房新社、中村白葉訳『トルストイ全集3 初期作品集(下)』1980年第3刷版所収、巻末解説P433-434
この作品解説にあるように、トルストイが従軍したロシア軍はカフカースの村を襲撃していた。
その襲撃と敵からの反撃を題材にしたのがこの小説の大筋なのだが、この小説の始まりからして私は驚いてしまった。そこにはこう書かれていたのである。
戦争はいつも私に興味があった。しかしそれは、えらい将軍との対戦といったような、大きな戦争の意味ではない―私の想像は、そうした厖大な行動をあとづけることを拒絶する―だいいち私には、そういうことはわからないので、私に興味のあるのは、戦争の事実そのもの―つまり殺人行為だったのである。私にとっては、どんなふうにして、またどんな感情の影響のもとに、ひとりの兵隊が他の兵隊を殺したかを知ることのほうが、アウステルリッツとかボロジノとかの戦争で、軍の配置がどうであったかということより、はるかに興味があったのである。
河出書房新社、中村白葉訳『トルストイ全集2 初期作品集(上)』1982年第4刷版P264
これはこの後10年以上も後に書かれることになるあの大作『戦争と平和』にまさしく直結する考え方だ。
トルストイは作家デビュー間もなく、すでにこうした考え方を持ちカフカースでの日々を過ごしていたのだ。これは驚くべきことではないだろうか。
そしてもう一つ、晩年のトルストイの戦争観につながる言葉もこの作品で述べられている。これがまた興味深いので紹介したい。
戦争?なんという不可解な現象であろう?理性が自分に向かって―それは正しいことであるか、必要なことであるか?こういう問題を課するばあい、心内の声はつねに答える―否と。ただこの不自然な現象のひとつの持続性が、それを自然らしく、自己保存の感情が、それを正当なものとするのである。
ロシヤ人対山人の戦争において、自己保存の感情から流れ出た正義が、わがほうにあることをだれが疑うであろう?
もしこの戦いがなかったら、何が隣接した富裕な、ひらけたロシヤの領土を、野蛮で好戦的な国民の掠奪や、殺害や、襲撃から保証するか?
しかしここにはまず、双方の個人を例にとってみよう。はたしてどちらのがわに自己保存の感情、すなわち正義があるか。
あのぼろ服をまとったどこかのジェミー―ロシヤ人の接近を知って、呪いの言葉とともに壁から旋条銃をとりおろし、容易にははなたぬ三、四発の弾薬を用意して、異端者どものほうへ駆け出し、ロシヤ人が依然として前進をつづけ、彼らの播きつけた畑へ踏みこんでそれを荒らし、彼の小屋を焼き、彼の母や妻子が恐れにふるえながらかくれている谷間のほうへ進んでくるのを見て、これでは自分を幸福にしてくれるものをなにもかもとり上げられてしまうのだと考え―力ない憤怒に絶望の叫びを上げて、まとっていたぼろぼろの外套をかなぐり捨て、銃を地べたへたたきつけて、帽子を目の上まで引きさげ、臨終のうたをうたって、短剣さか手に、死にもの狂いにロシヤ兵の銃剣のなかへとびこんで行く男のほうにあるか?
それともまた、将軍の幕僚のひとりで、私たちのそばをとおりすぎるたびにいかにもうまくフランスの歌をうたう、あの将校のほうにあるのか?彼はロシヤ本国に家族を持ち、親戚を持ち、友人を持ち、百姓を持って、彼らとの関係ではいろんな義務を持っているけれども、山人と戦うべきなんの理由も希望も持ち合わせてはいないくせに、カフカーズへやって来た男である……ただ漫然と、自分の勇気を示したいばかりに。
それともまた、これもやはり、ただすこしも早く大尉に昇進して、いい地位にすわりたいと、そればかり望んでいて、こんどほんの偶然に山人どもの敵となったような、私の知人の副官のほうにあるのだろうか?
河出書房新社、中村白葉訳『トルストイ全集2 初期作品集(上)』1982年第4刷版P279
※一部改行した
ロシア軍はカフカースに生きる人々の村を襲い征服していく。そしてそれはロシアの国土を攻撃してくる「山人」をやっつけるためだと言う。つまり「我々こそ正義だ」と言い、村々を侵攻していくのである。
だがカフカースに住む人からすれば、いきなり攻めてきて村を焼き払い、多くの人を殺し、略奪をほしいままにするロシア人をどう思うだろうか。
抵抗しなければ殺される。そうした状況に置かれたカフカースの人々は必死で抵抗する。
それに対しロシアの士官たちはどんな理由があって戦いに来たのか。
それをトルストイは上の箇所で痛烈に問うている。
トルストイはこの時のカフカース体験に大きな影響を受けている。彼は晩年になると特に強く戦争反対、非暴力を主張した。つまりあの有名な『イワンのばか』や『復活』、さらには宗教論文『神の王国は汝らのうちにあり』につながっているのだ。
こうしたトルストイの主張はこの時に感じた戦争への疑問が残り続けていたからかもしれない。
トルストイにおけるカフカースの意味を考える上で、この作品は大きな意味を持っているのではないかと私は感じている。
そしてもう一作品ぜひ紹介したい短編がある。それが『森林伐採』という作品だ。

この『森林伐採』もトルストイのカフカース従軍を題材にして書かれた。
実はこの『森林伐採』という不思議なタイトルはロシア軍の軍事作戦から来ている。では、これは一体どういう作戦だったのか、藤沼貴著『トルストイ』では次のように解説されている。
一九世紀初頭、ナポレオン戦争終了後、ロシアはチェチェン、ダゲスタンに対する本格的攻撃を決意し、一八一六年アレクセイ・エルモーロフをカフカース独立兵団司令官に任命した。
カフカースの戦争は数世紀にわたってつづいているが、とくにこの一八一七~六四年の時期が数世紀にわたる抗争の山場の一つで、狭義の「カフカース戦争」はこの時期を指す。
グローズナヤ(脅威の)、ヴネザープナヤ(急襲の)、ブールナヤ(嵐の)など、穏やかでない名前の拠点要塞が構築されたのもこの時期で、現在のチェチェンの首都グローズヌイはグローズナヤ要塞の名残である。「脅威市」という露骨な名前の都市は世界でもめずらしいだろう。
また、トルストイの作品『森林伐採』の題名にもなった森林伐採作戦もこの時期にはじまった。森の木を切りはらって見通しをよくし、敵の奇襲を防ぐこと、軍隊の通過を容易にすることなどがその目的だったが、これが生活環境を破壊し、住民を山中に追いやった。べトナム戦争の枯葉作戦を思い起こさせる。
第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P147-148
※一部改行した
「トルストイの作品『森林伐採』の題名にもなった森林伐採作戦もこの時期にはじまった。森の木を切りはらって見通しをよくし、敵の奇襲を防ぐこと、軍隊の通過を容易にすることなどがその目的だったが、これが生活環境を破壊し、住民を山中に追いやった。べトナム戦争の枯葉作戦を思い起こさせる。」
ベトナム戦争の枯葉作戦を思い起こさせる作戦・・・
現地住民からすれば最悪の作戦がカフカースで行われていたのであった。
そしてこの作戦にもトルストイは参加している。
この『森林伐採』ではその作戦に従軍したトルストイが、兵士たちの姿を通して「ロシア民衆とは何か」という問いを探究していく。
トルストイのカフカース体験のなかで、「ロシア民衆の再発見」も戦争否定に劣らず重要だった。ロシアでトルストイは民衆とじかに接触して、よい人間的関係をうち立てようとし、手痛い失敗をした。社会的な構造がそれを邪魔したばかりでなく、農民が心を開かなかったからである。
数世紀にわたる隷属の結果、農民が地主に不信感をもち、反抗的だったというだけならトルストイも納得したかもしれない。しかし、トルストイの目には、農民たちは卑屈で、うそつきで、怠惰で、道徳的に堕落しているように見えた。
ところが、戦場で見たロシア兵は実にりっぱだった。カフカース戦争に題材をとった短編『森林伐採』のなかで、トルストイはロシア兵をこまかく観察し、次のように分類して説明している。
「一従順な者。a 従順で冷静なもの。b 従順で気配りのよい者。
二指図をする者。a 指図好きで厳格な者。b 指図好きで処世にすぐれた者。
三向こう見ずな者。a 向こう見ずで陽気な者。b 向こう見ずで素行のわるい者」。この分類を見ると、よくないのは「三のb」だけで、しかも、それは「ロシア軍の名誉のために言わなければならないが、ごくまれにしかお目にかからないものだ」と、トルストイ自身が注釈をつけていた。
当時のロシアでは、兵卒のほとんど全部が「百姓の野良着を軍服に着替えた農民」だったのに、兵士たちはロシアの村にいる農民とはまるで別の人間だった。いったい、どちらが本当の姿なのか。人間の本性は惰性的に流れる日常生活より、死を目前にした極限状態で現れるものだろう。とすれば、卑屈な農奴ではなく、毅然とした兵士こそがロシア民衆の真の姿なのだ。
この「民衆再発見」にトルストイはおどろいた。農民はわれわれ貴族と同じ人間どころか、われわれよりむしろすぐれているではないか。そして、このすばらしい本性をゆがめている責任は自分たちにあるのではないか?
このようにトルストイはカフカースでいくつもの貴重な体験をした。
第三文明社、藤沼貴著『トルストイ』P153-154
※一部改行した
「この「民衆再発見」にトルストイはおどろいた。農民はわれわれ貴族と同じ人間どころか、われわれよりむしろすぐれているではないか。そして、このすばらしい本性をゆがめている責任は自分たちにあるのではないか?」
この言葉は、後のトルストイの生涯を貫く信念へと繋がっていく。
『森林伐採』はページ数にして30ページほどというコンパクトな作品だが、その中に「情景描写の妙、深い人間洞察」というトルストイらしさが詰まった逸品であることは間違いない。
ちなみにだが上の解説の最初で語られたトルストイと自領の農民とのやりとりは『地主の朝』という作品で赤裸々に綴られている。

みじめと言っていいほど完膚なき失敗。若きトルストイの挫折をこの作品で知ることができる。
さて、最後にトルストイが見たカフカースについて一言お話ししてこの記事を終えたい。
トルストイは『コサック』という作品の中でカフカースの美しさについて述べている。
カフカースの美しさをここまで表現するトルストイにはただただ脱帽するしかない。
〈さあ、そろそろはじまるらしいぞ!〉こうオレーニンはひとりごち、かねて人の話によく聞いていた、雪をいただいた山々の景観の現われるのを、たえず心待ちにした。
一度、夕方まえのことだったが、御者のノガイ人が、雲のかげからのぞいている山なみを、鞭で教えてくれたことがある。オレーニンはむさぼるように目をこらしはじめたが、あいにく曇り日だったので、雲がなかば山々を隠していた。で、オレーニンには、ただ、灰色した、白っぽい、うねうねしたものが見えるだけで、どんなにつとめてみても、あれほど読んだり聞いたりしていた山の美観は、ひとつとして見いだすことができなかった。
そこで彼は考えた、山と雲とはまったくおなじ外観を持っているので、彼がたびたび聞かされた、雪の山の特殊な美などというものは、バッハの音楽や、彼が信じていなかった女にたいする恋などと同じような、いわゆるつくりごとにちがいないと―そうして、山にたいする期待を捨ててしまった。
ところが、翌日早朝に、彼は、馬車のなかの肌寒さに目をさまして、なにげなく右手のほうを眺めやった。澄みわたった朝であった。ふと彼は、自分から二十歩ばかりのところに(最初の瞬間、彼にはそう思われたのである)、華奢な輪郭をもった、清く、まっ白な、巨大な堆積と、その頂きと、遠い空とのつくりだす、くっきりとした、夢のような、空気のような線をみとめた。
そして、彼が自分と、山や空との距離と、山の巨大さとを完全に理解したとき、そして、その美の限りなさを、彼はそれが幻ではないか、夢ではないかと驚き怪しんだくらいである。彼は、はっきり目をさますために身ぶるいしてみた。が、山は依然として変わりがなかった。
「あれはなんだね?あれはいったいなんだね?」と、彼は御者にたずねた。
「山でさあ」と、ノガイ人はこともなげに答えた。
「わっしもずっと前から見ていたんでございますよ」とワニューシャが言った。「なんてみごとなものでございましょう!うちへ帰って話したって、だれもほんとうにゃしますまいね」
平坦な道を進む三頭立ての早い進行につれて、山々はのぼる朝日にばら色の頂きを輝かしながら、地平線に沿って走っているように思われた。
はじめは、山はただ、オレーニンを驚かしたばかりだったが、のちには彼を喜ばせた。けれども、なおしばらくすると、この、ほかの黒い山々のかげからでなく、いきなり曠野からもりあがって、遠く走っている、雪の山嶺のつらなりを見くいるうちに、しだいに、その美の精神に徹しはじめて、ついには、山を感じるようになった。
この瞬間から、彼の見るもの、考えるもの、感じるもののすべてが、彼にとっては新しい、荘厳なまでに偉大な山の性質をおびるようになった。
すべてのモスクワの思い出も、恥も、悔恨も、カフカーズについての俗悪な空想も、そうしたものはみな消えうせてしまって、二度と帰ってはこなかった。〈いまこそはじまったのだ〉なにかの厳粛な声が、彼にこう言ったように思われた。
河出書房新社、中村白葉訳『トルストイ全集2 初期作品集(上)』1982年第4刷版P16-17
※一部改行した
いかがだろうか。こんな文章を書かれたらもうひれ伏すしかない。異常だ。トルストイは・・・
どうしてこんなにも美しい世界を表現できるのだろう。言葉を自在に操るトルストイの巨大さに私は打ちひしがれてしまうほどだった。
そしてこの箇所を読んで私はどうしてもカフカースに行ってみたくなってしまった。
トルストイがこんなにも感動した景色を見てみたい。そこでトルストイは何を見て、何を感じたのだろうか。実際に自分の目で確かめてみたい!私はそう思ってしまったのである。
長くなってしまったが私がジョージアまでやって来たのはこのような理由があったのである。そして以前お話ししたように、トルストイとドストエフスキーは正反対の存在だ。つまり一方を知れば自ずとその反対側も見えてくるということである。
ここでトルストイの原点を学ぶことはきっとドストエフスキーについても見えてくるものがあるに違いない、私はそう思った。そして実際にこの旅で私は大きな収穫を得ることとなった。
そのことはこれから先の記事で明らかになっていくが、まずは先を焦らず、私が訪れたジョージアについて一つずつお話ししていくことにしよう。
続く
Amazon商品ページはこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事











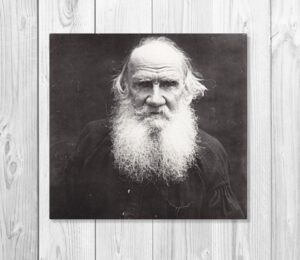





コメント