シェイクスピア『アテネのタイモン』あらすじと感想~金の切れ目は縁の切れ目。お人よしの富豪の悲惨な転落劇
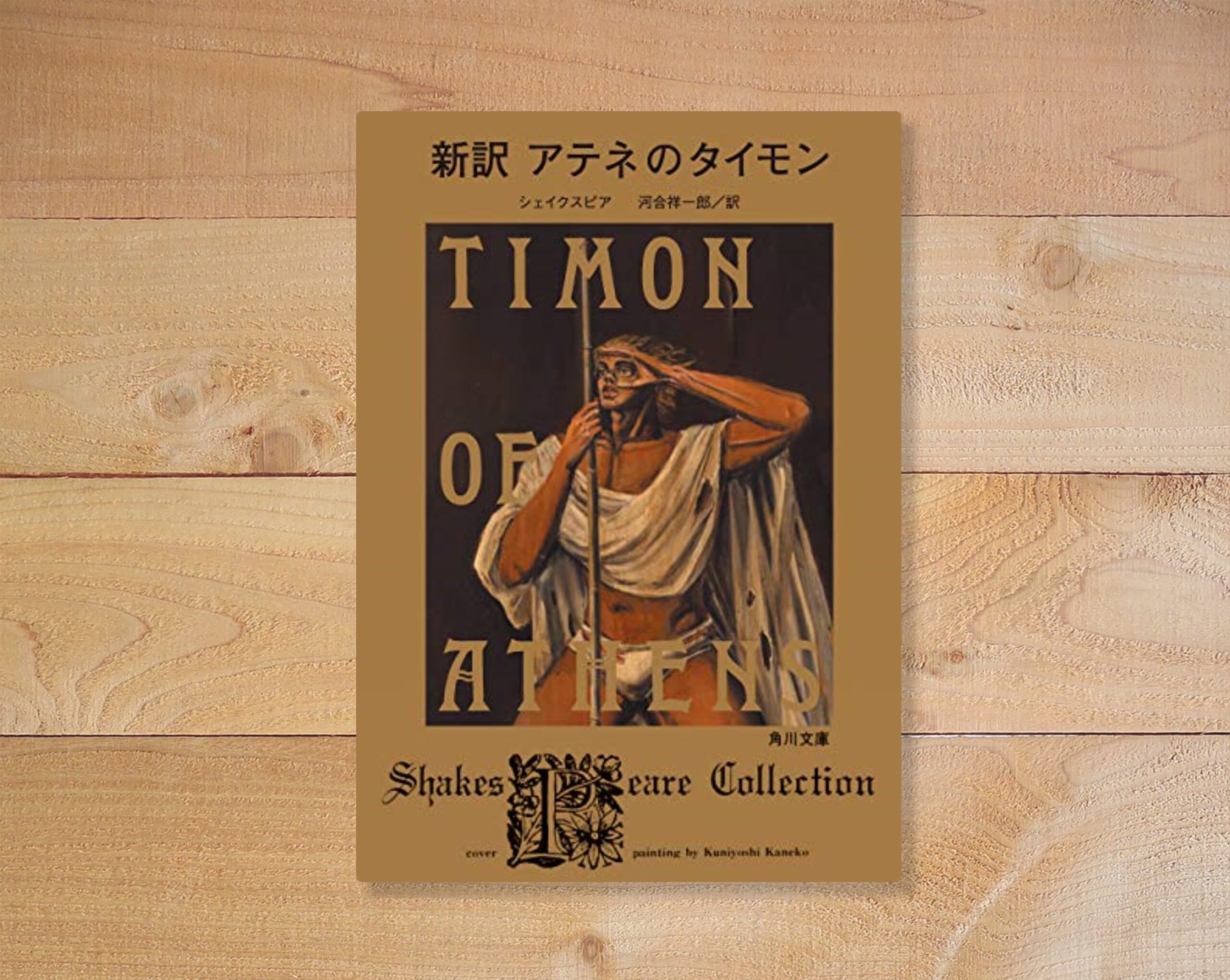
シェイクスピア『アテネのタイモン』あらすじと感想~金の切れ目は縁の切れ目。お人よしの富豪の悲惨な転落劇
今回ご紹介するのは1605年~8年頃にシェイクスピアによって書かれたとされる『コリオレイナス』です。私が読んだのはKindle版の角川文庫、河合祥一郎訳です。
早速この本について見ていきましょう。
財産を気前よく友人や家来に与えることで有名なアテネの貴族タイモン。貯えが尽きることを恐れる執事の忠告も無視し贈与を続けるが、膨れ上がった借金の返済に追われることに。「友達を試す」と他の貴族らに援助を求めるものの、手の平を返したようにそっぽを向かれ、タイモンは森へと姿をくらましてしまい…。忘恩、裏切り、破滅。普遍的なテーマを鮮烈に描く。未完の戯曲として議論を呼ぶ問題作が、瑞々しい名訳で甦る。
Amazon商品紹介ページより
『アテネのタイモン』は紀元前五世紀頃に実際に存在していたアテネの人間嫌いの市民ティノモスをモデルにして書かれた作品です。
タイモンは上の本紹介にもありますようにとにかく気前がいい人物でした。金勘定など全くすることなくとにかく鷹揚に与え続けます。そんなお人よしのタイモンの周りには彼のおこぼれに預かろうとたくさんの人たちが群がります。そして彼らはタイモンにお追従を述べ、たんまりと贈り物をもらって帰るのでした。
道化的な役割のアペマンテスという人物はそんなタイモンに対してこんな言葉を述べます。
俺はおまえにお世辞を言ったりしないからな。ああ、神々よ!何て大勢がタイモンを食いものにして、タイモンにそれがわかっていないことか!こんなに大勢が一人の男の血に肉を浸して食っているのを見ると悲しくなる。しかも、当の本人がそれを焚きつけているんだから、まったくもって狂気の沙汰だ。
Kindle版、角川文庫、『アテネのタイモン』、シェイクスピア、河合祥一郎訳、位置No302-313
タイモンに寄ってくる人物は皆彼からうまいものを引き出そうと揉み手でやって来る者達です。彼らのお世辞やお追従はすべて自分の利益のためであり、友情ではなかったのです。それをタイモンは全く予想もすることができなかった。ここにこの物語の悲劇があります。
そして案の定、タイモンの財産は危機的状況に陥ります。しかもこれまで散々贈り物をしてきた貴族たちに助けを求めるも、誰も助けてはくれません。彼らがタイモンと友人として付き合っていたのはあくまで金をくれるからであって、それ以上のものではなかったからです。
タイモンは全てを失う時になって初めてそれに気が付きました。これまで人を疑うことを全く知らなかったお人よしタイモン。普通の人間ならばこうした現実などとうに知っていてその耐性はできているのに対し、タイモンはいい歳になって、しかもすべてを失って初めてこの現実に直面することになりました。そのダメージは彼にとって耐えられるようなものではなく、それまでの高潔な人格はどこへやら、とてつもない憎悪を人間すべてに向けることになっていきます。
そして舞台は最後の唐突な悲劇へと一直線に進んでいくことになります。
物語の筋としてはシンプルです。シンプルすぎると言ってもいいでしょう。そして実際に読んでみて思ったのですが、たしかに上の本紹介で問題作と言われているのもわかるような気がしました。
『リア王』や『ハムレット』などの傑作と比べるとやはり深みがないといいますか、終わり方もあまりに唐突すぎます。
なぜそんなことになったかというのは巻末の解題で詳しく語られているのでぜひそちらを参照して頂きたいのですが、この作品を評価する声もあるのも事実です。巻末の解題より引用します。
G・ウイルソン・ナイトは、タイモンこそ悲制の主人公の原形だと褒めちぎった(The Wheel of Fire 1930)。『白鯨』で知られるハーマン・メルヴィルも、本作を傑作として褒めちぎっている。
『リア王』との類似性に注目して、本作を『リア王』の死産した双生児だと形容するドーヴァー・ウィルソンの議論(The Essential Shakespeare 1932)は一読に値する。本作が『リア王』(一六〇五~六年頃)と同じ頃に書かれたのではないかとするピーター・アレグザンダーの説(Shakespeare’s Life and Art 1932)も有効だ。
特に忘恩と裏切りを契機に人間への絶望へと追いやられる主人公が、自然の中で裸になって人間を激しく呪う点で、リアとタイモンはたしかに重なって見える。どちらもかつては絶対的な力を持っていたのに、一瞬にしての無力になってしまう。そして、人とのつながりを失ったとき、社会的人間としてのアイデンティティが崩壊する。
リアには道化が途中までおり、ケントが付き従ったが、タイモンは道化と接点を持たず(本作の道化がアペマンタスにだけ付き従うのはなぜか)、ケントに相当するはずの執事フレイヴィアスは、あろうことか、大金を手にしたあとタイモンに対して冷たい態度をとって立ち去ってしまう。最後までタイモンのことを想うのはアルキビアデスのみだが、最後の場ではどこかフォーティンブラスに似てくる。
アルキビアデスは、タイモンは気高かったと言うが、テクストを読んだかぎりでは、見境なく大盤振る舞いをする大富豪の姿が見えてくるばかりで、どこが気高かったのかわかりづらい。しかし、その点は上演が補うべき点なのかもしれない。「ある人物の偉大さとは、その人物のなかにあるのではなく、その人物が社会からどのように扱われるかによって示されるのだ」と、RSC芸術監督グレッグ・ドーランは、『家康と按針』(市村正親主演)の稽古場で述べて、家康に将軍としての威厳と栄光を与えるのはまわりの役者たちの仕事だとして演出していたが、この作品でも同じことが言えるのかもしれない。
Kindle版、角川文庫、『アテネのタイモン』、シェイクスピア、河合祥一郎訳、位置No3253-3264
※一部改行しました
ここで述べられたように、たしかにタイモンのどこが気高いかは一読してもなかなか伝わってきません。単なるお人よしで、おべっかに弱く、人を見る眼がないという印象をどうしても強く受けてしまいます。
しかし、『リア王』の死産した双生児という観点から見ると、たしかにこの作品はやはり悲劇として力強いものを感じるのです。
そして最後の「ある人物の偉大さとは、その人物のなかにあるのではなく、その人物が社会からどのように扱われるかによって示されるのだ」という指摘も非常に重要ですよね。人はその人だけにあるのではなく、他者との関係性によっても自分が成り立っている。そして全てを失って人との繋がりも断ってしまったタイモンはもはやその社会的アイデンティティーも失ってしまったのだと。こういう面から見るとたしかに『アテネとタイモン』もやはりなかなかの作品に思えてきました。
実際、この作品はとても読みやすかったです。何度も言いますが筋書きもシンプルですいすい読み進んでいけます。このわかりやすさもありがたいなと思えます。
問題作として扱われるこの作品ではありますが、シェイクスピアの全体像を考えるためにもこの作品を読むことができてよかったなと感じています。
以上、「シェイクスピア『アテネのタイモン』あらすじと感想~金の切れ目は縁の切れ目。お人よしの富豪の悲惨な転落劇」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事
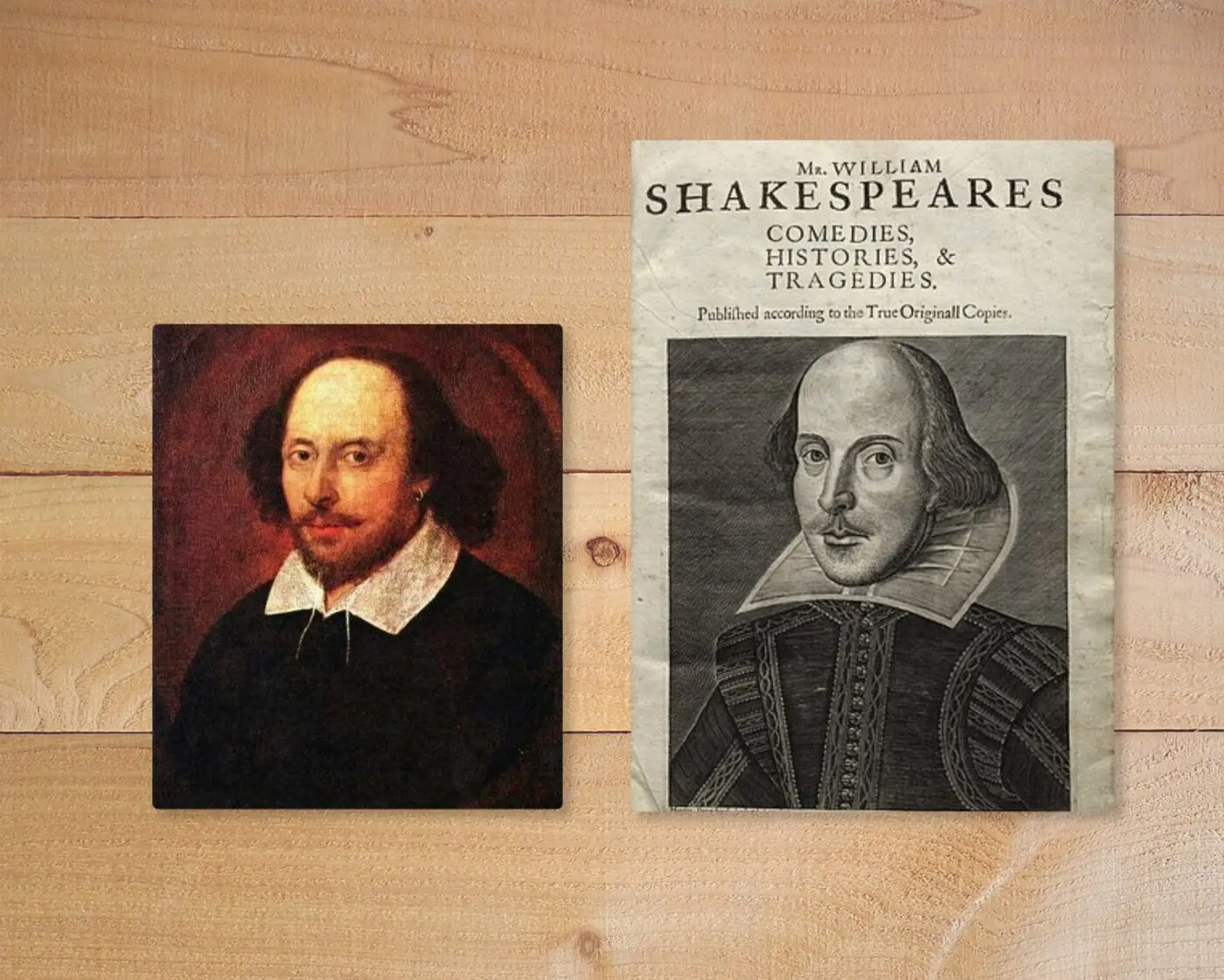
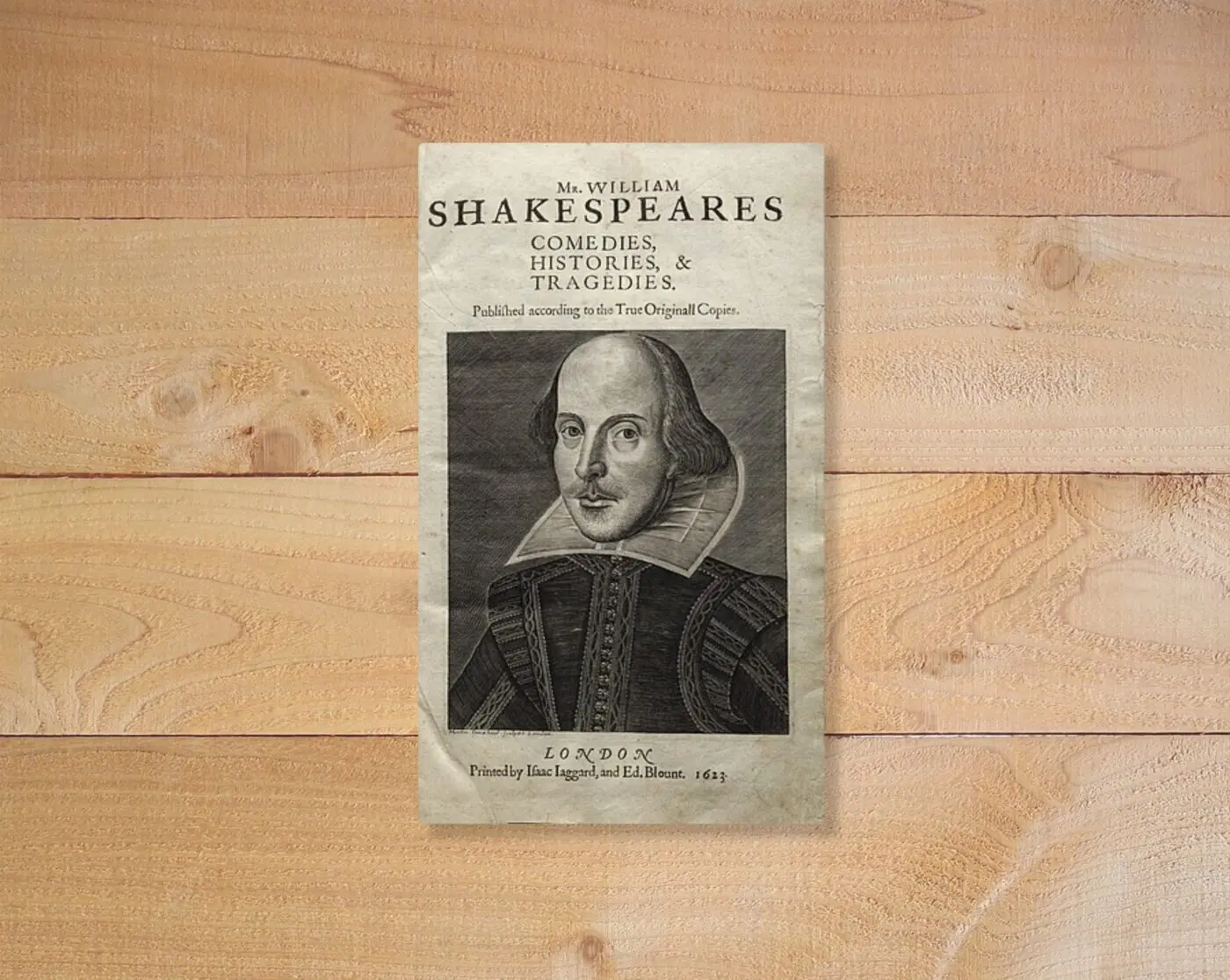


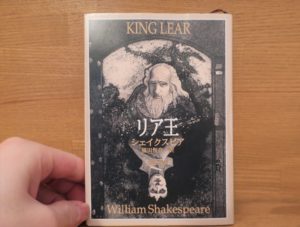



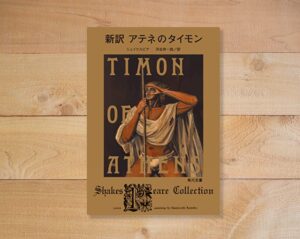






コメント