シェイクスピア『終わりよければすべてよし』あらすじと感想~本当に終わりよければすべてよしなのかが問題だ

シェイクスピア『終わりよければすべてよし』あらすじと感想~本当に終わりよければすべてよしなのかが問題だ
今回ご紹介するのは1602年から1605年頃に書かれたとされるシェイクスピア著『終わりよければすべてよし』です。私が読んだのは筑摩書房、松岡和子訳です。
早速この本について見ていきましょう。
前伯爵の主治医の遺児ヘレンは現伯爵バートラムに恋をしている。フランス王の難病を治して夫を選ぶ権利を手にし、憧れのバートラムと結婚するが、彼は彼女を嫌って逃亡、他の娘を口説く始末。そこでヘレンがとった行動は―。善と悪とがより合わされた人物たちが、心に刺さる言葉を繰りだす問題劇。松岡和子個人訳シェイクスピア全集、完結。
筑摩書房商品紹介ページより
さてこの作品は上の本紹介にありますようにシェイクスピアの「問題劇」として知られる作品です。では、何が問題なのか、巻末の解説を見ていきましょう。
「二人はすえながく幸せに暮らしましたとさ。めでたし、めでたし。」これがおとぎ話のおさだまりの結末である。このおとぎ話のハッピー・エンディングをそのままタイトルにしているのが『終わりよければすべてよし』だ。
タイトルだけではない。劇中ではおとぎ話のモチーフがいくつも使われている。王様の不治の病は見事に癒される。ベッドを共にしようとしない夫の子供を妊むという無理難題も、忍耐と知恵によって乗り越えられる。死んだと思われていた善人が大団円で蘇った姿を現す。病の治癒、難題解決、死者の蘇生とそろえば、幸福な結末は確実なはずだ。だが劇作家バーナード・ショーが「苦いタイトルがつけられた苦い劇」と断じたように、『終わりよければすべてよし』には、おとぎ話の結末がもたらすシンプルな安堵感や達成感はおよそ感じられない。(中略)
つじつま合わせの結末は「めでたし、めでたし」にはならない。持参金をたっぷり与えて夫を選ばせれば女は幸せになると楽観している王でさえ、この劇の結末では「すべてよいらしい」(All yet seems well)と留保をつけている。手放しのハッピー・エンディングなどない。王子様とむすばれたって幸せになるとは限らない。『終わりよければすべてよし』は幻想なき時代の喜劇だ。奇跡が科学にとって代わられたように、おとぎ話は苦い現実の前に敗北している。だがこの数年後、「ロマンス劇」と呼ばれる作品群で、シェイクスピアは再びおとぎ話の世界を書くことになる。失われた子供は見つかり、彫像に命が吹き込まれ、魔法が罪を罰しそして許す。奇跡は過去のものであるとリアルな認識を持ちながらも、それでもなお人は奇跡を願う。いやむしろ、苦い現実を生きてしまったがゆえに、人は起こりえなかったことに起きてほしいと祈る。その人々の祈りをおとぎ話に託す前に、シェイクスピアはいったんおとぎ話に決別を告げざるをえなかった。『終わりよければすべてよし』はそのように位置づけられる作品だろう。
筑摩書房、シェイクスピア、松岡和子訳『終わりよければすべてよし』P220-226
そうです。この作品は『終わりよければすべてよし』とタイトルで言っておきながら、「本当にそうなのか?」と疑問になる作品なのです。
主人公のヘレンは念願叶ってバートラムと結婚することなるも、明らかにバートラムは嫌々でした。舞台演出次第ではもしかしたら何とかなるかもしれませんが、バートラムは最後の最後までヘレンと結婚することを嫌がっていました。だからこそ無理難題を押し付けて遠ざけようとしていたのです。
ですがヘレンの忍耐と機知によってその無理難題も突破してしまった以上、バートラムももはや逃げ場はなし。結婚するしかなかったのでした。
舞台は一応、この結婚で「終わり」を迎えます。
ですが二人の結婚生活はむしろここから始まるわけです。「終わりよければすべてよし」どころではありません。
ストーリー的には困難を乗り越えて一応の大団円ではあるものの、明らかに「ん?」となる終わり方。「これは全然めでたしめでたしじゃないよ」と観客が突っ込みたくなるような終わり方です。シェイクスピアのことですからお客さんのこの反応はきっと予想通りでしょう。『終わりよければすべてよし』というタイトルなのもシェイクスピア流の皮肉であることがうかがえます。
そして上の解説の最後に書かれていたように、シェイクスピアはこの後、「ロマンス劇」と呼ばれる作品を書いていきます。『ペリクリーズ』、『シンベリン』、『冬物語』、『あらし(テンペスト)』のロマンス劇4作品はまさに奇跡による大団円の物語です。悲劇からハッピーエンドへの振り幅がものすごい作品たちです。私もこれらロマンス劇は大好きです。
上の解説で「奇跡は過去のものであるとリアルな認識を持ちながらも、それでもなお人は奇跡を願う。いやむしろ、苦い現実を生きてしまったがゆえに、人は起こりえなかったことに起きてほしいと祈る。」と書かれていたのはまさにその通りだなと思います。
日常から離れた演劇という舞台だからこそ、こうした夢や希望のある作品を観たい。それは本においても同じです。本は日常の世界から私たちを連れ去ってくれます。もちろん、日常に地に足つけて読むタイプの読書も大事です。ですがたまにはファンタジーの世界に行って楽しむのもいいではないしょうか。私だってそんな読書を楽しみたい。
だからこそ気楽に楽しめるシェイクスピアのロマンス劇は面白いんですよね。
となると必然的に今回紹介した『終わりよければすべてよし』のような問題作はやはり「ん?」となってしまうのも仕方ありません。ですがだからといって全くつまらないのかというとそうではありません。この違和感込みで味わうのも悪くないんです。シェイクスピアの皮肉を感じながら読んでいくというのもひとつの楽しみ方です。シェイクスピアの全体像を知る上でもこの作品はある意味興味深い作品であるなと感じました。
それに、そもそも『終わりよければすべてよし』というタイトルがいいですよね。
私はこの言葉が大好きです。どんな人生であろうと最後の最後でいい生き様をすることができたら、それは「終わりよければすべてよし」なのです。これは『レ・ミゼラブル』やゾラの『ルーゴン・マッカール叢書』、ドストエフスキーやトルストイの大作を読んできて私が強く感じたことです。
これら大作にはとてつもない数の登場人物が出てきます。そして大作であるが故に、時間軸も壮大です。そんな中私達読者は多くの登場人物の生き様、死に様を見ていくわけです。人の人生はその最後の生き様にかかっていると私は思うようになりました。どんなに成功して権勢を誇っても、最後の最後であなたを思い泣いてくれる人がいるのか、あなた自身は納得して死んでいけるのか。この最後の生き様、死に様次第で「終わりよければすべてよし」と言えるかどうかが決まってくる。
私は「終わりよければすべてよし」と言える人生を送りたい。
逆に言えば、終わりまでは何があるかわからないし、ダメダメな可能性も大きいのです。でもいいんだと。目先のことでうじうじ悩んで不平を言うより、今やるべきことをやりもっと大きな時間軸で人生を見よとこの言葉は励ましてくれるように私は感じています。
とまあ『終わりよければすべてよし』というタイトルについてもお話ししてしまいましたが、「終わりよければすべてよし」という言葉が個人的に好きであるがゆえに、シェイクスピアの皮肉がピリリと効いていいんですよね(笑)「そんな甘くはありませんぜ」とニヤリと笑っているシェイクスピアが浮かんできそうです(笑)
いずれにせよ、色んな意味で私の中にも「問題」を引き起こした作品でした。
以上、「シェイクスピア『終わりよければすべてよし』あらすじと感想~本当に終わりよければすべてよしなのかが問題だ」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
シェイクスピア全集33 終わりよければすべてよし (ちくま文庫)
前の記事はこちら

関連記事
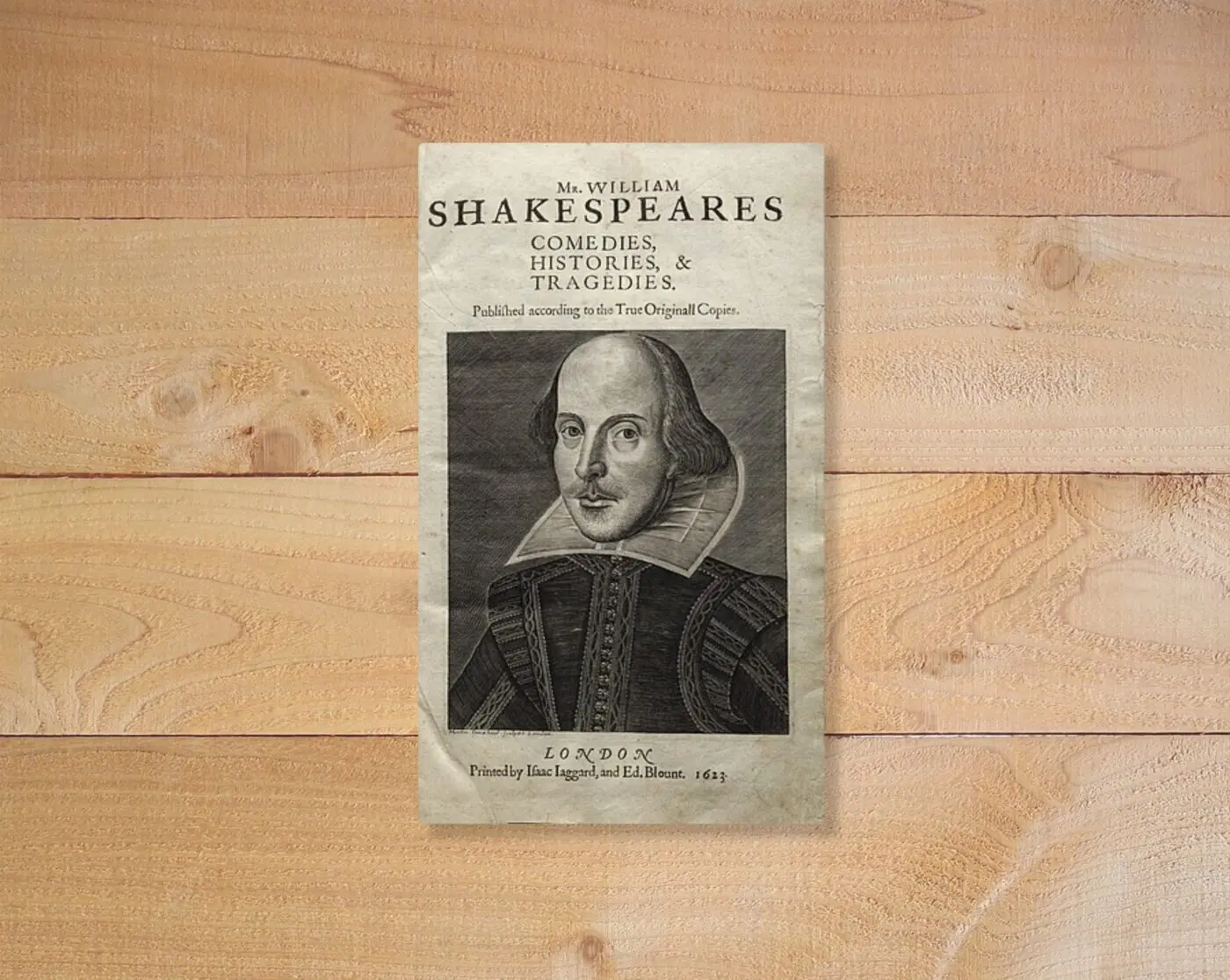
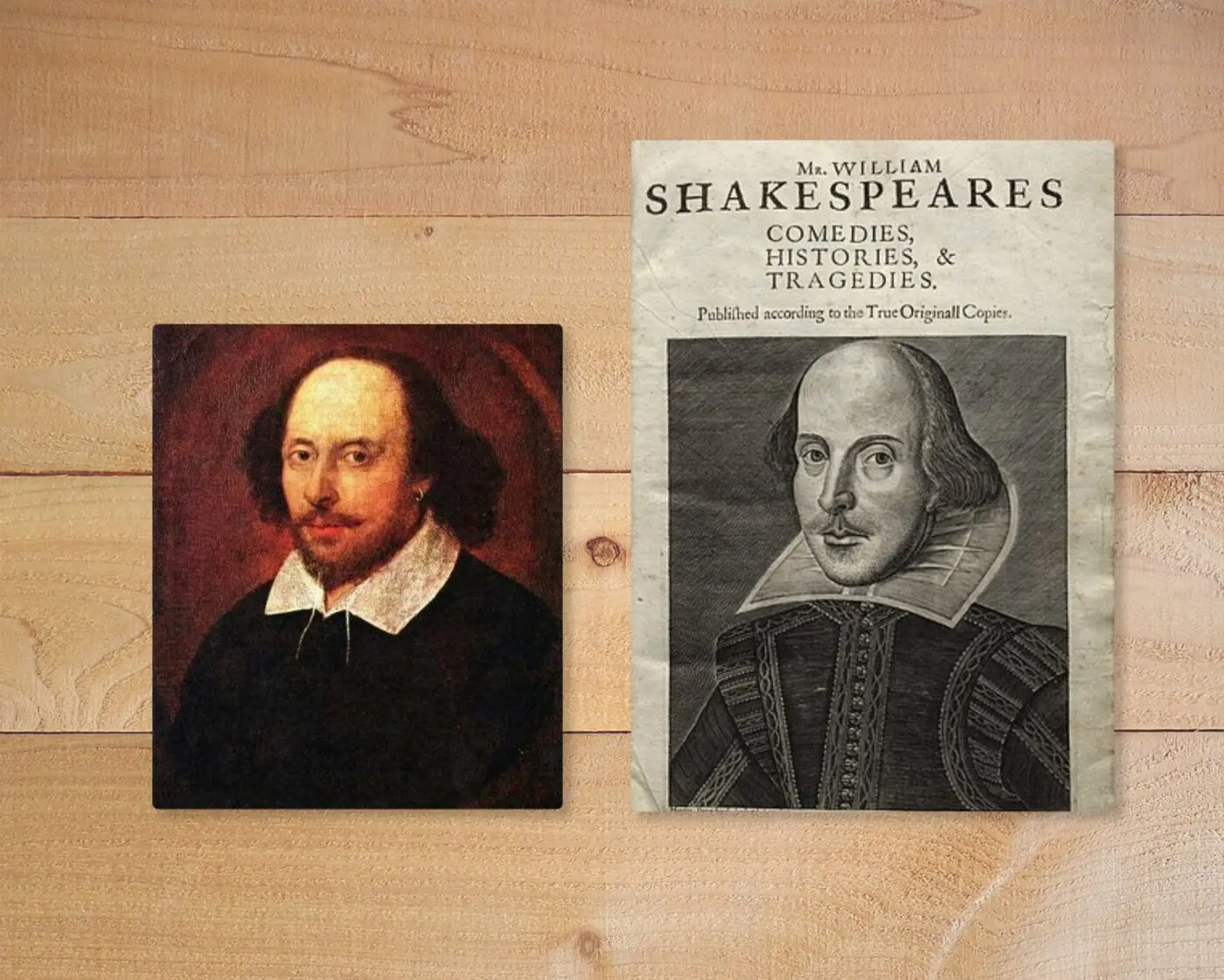














コメント