アダム・ヒギンボタム『チェルノブイリ』あらすじと感想~原発事故はなぜ起こったのか、ソ連の政治経済・官僚システムとの繋がりも知れる名著

アダム・ヒギンボタム『チェルノブイリ』概要と感想~原発事故はなぜ起こったのか、ソ連の政治経済・官僚システムとの繋がりも知れる名著
今回ご紹介するのは2022年に白水社より発行されたアダム・ヒギンボタム著、松島芳彦訳の『チェルノブイリ 「平和の原子力」の闇』です。
早速この本について見ていきましょう。
災厄の全体像に迫る傑作ノンフィクション
『NYタイムズ』最優秀書籍(2019年)に選出「チェルノブイリ後」、そして「フクシマ後」を生きる試練とは? 体制のあり方に事故の深層を探り、未曽有の災厄の全体像に迫る![カラー口絵16頁]
「チェルノブイリ」と「フクシマ」に通底するものとは?
チェルノブイリは「平和の原子力」の象徴として、ソ連で最も安全で進んだ原発と言われていた。しかし、一九八六年四月の原子炉爆発事故によって、歴史に汚名を残す末路をたどった。事故からすでに三六年が経過しようとし、その間にアレクシエービッチ『チェルノブイリの祈り 未来の物語』をはじめ、数多の著作や研究が世に問われてきたが、ソ連やロシア連邦の根深い秘密主義のために、今でも全容が解明されたわけではない。
白水社商品紹介ページより
最新刊の本書は、構造的な欠陥をはらんだ原発が誕生した経緯から、北半球を覆った未曾有の放射能汚染、多くの人々の心身に残した傷にいたるまで、気鋭のジャーナリストが綿密な取材と調査を通して、想像を絶する災厄の全体像に迫った、渾身のノンフィクション作品だ。
「秘密主義とうぬぼれ、傲慢と怠惰、設計と建造のずさんな基準」といった「原子力国家の心臓部を蝕む腐敗」、すなわち体制のあり方そのものに悲劇の深層を探り、人生を狂わされた生身の人々の群像を克明に描いた、調査報道の金字塔。
本書は、『ニューヨーク・タイムズ』『タイム』『カーカス・レビュー』の年間最優秀書籍(二〇一九年)に選出された。

はじめに言わせて頂きます。
「この本はすごいです・・・!」
とんでもない本と出会ってしまいました。
あまりに衝撃的かつ劇的な語りに私は一瞬で引き込まれ、あっという間に読み切ってしまいました。
本全体としては600頁以上あるのですが、本編は450頁ほどで、残りは注になります。この本がどれだけ多くの資料に基づいて書かれたかがうかがえます。
そして上の本紹介に、
『「秘密主義とうぬぼれ、傲慢と怠惰、設計と建造のずさんな基準」といった「原子力国家の心臓部を蝕む腐敗」、すなわち体制のあり方そのものに悲劇の深層を探り、人生を狂わされた生身の人々の群像を克明に描いた、調査報道の金字塔。』
とありますように、この本は単にチェルノブイリ原発の事故そのものだけを語るのではなく、この事故が起きるそもそもの原因となったソ連の構造そのものについても多く言及しています。
これはものすごく興味深かったです。ソ連末期がどのような状態だったのかということもこの本で知ることができます。ソ連末期についてはこれまでも当ブログでV・セベスチェン著『東欧革命1989 ソ連帝国の崩壊』を紹介しましたがぜひセットで読むことをおすすめしたいです。
そして私たちがチェルノブイリ原発のことを考える上で避けて通れないのが「フクシマ」です。この本を読んでいるとどうしても福島原発のことが頭をよぎります。巻末の訳者あとがきでもこのことについて書かれています。重要な箇所ですので少し長くなりますが引用します。
日本においてもニ〇一一年三月の東日本大震災による津波のため、東京電力の福島第一原発が国際的尺度で最悪の「レべル7」と評価される大事故な起こしました。「レべル7」はチェルノブイリに次いで二例目です。どちらの事故も大量の放射性物質の環境への拡散により、広い範囲が無人の地と化しました。地域社会がある日突然、丸ごと消滅してしまう原子力災害の過酷な現実を私たちは二度も目にしたのです。
チェルノブイリで採用された黒鉛減速炉は先行して稼働したレニングラード原発で、部分的な炉心溶融と放射能漏れという重大な事故を起こしていました。しかし、中型機械製作省は事故があった事実と原因を秘匿し、現場の技術者に情報は共有されませんでした。技術者養成の場では、原子炉は絶対爆発などしない、サモワール(ロシアの湯沸かし器)のように安全だ、と教え込まれてきたというのです。
ところが事故の幕を引くために「生贄」が必要になると、「爆発の可能性がある施設」で安全管理を怠った責任を問うため、原発のヴィクトル・ブリュハーノフ所長ら六人を被告とする見せしめ裁判を催し、現場の人為的ミスという決着を演出しました。設計段階の瑕疵を知りつつ黒鉛減速炉の導入を強行した原子力界の大御所らは責任を問われませんでした。ソヴィエトの規定では、「爆発の可能性がある施設」とは化学工場などを指し、原発は除外されていたにもかかわらず現場の所員に罪をなすりつけ、原発そのものには欠陥はなかったという結論を打ち出したわけです。ソヴィエトの科学技術の威信を守ろうという思惑が強く働いていました。
東京電力の指導部も、福島県などが大津波に襲われる危険性について事前に情報を得ていたのに、対策は講じていませんでした。「(情報の)信頼性に疑義がある」というのが理由です。当時の経営陣は刑事、民事の双方で責任を問われ、ニ〇二一年末現在、法廷で係争中です。
どちらにも通底するのが、都合の悪いことには消極的な対処をしがちな心理と、人間は自然を制御できるという科学や技術に対する過信です。そこに体制や企業の利害と惰性が絡むと事態はいっそう深刻な様相を呈します。チェルノブイリで勤務経験がある技術者で著作家のグリゴーリー・メドヴェージェフは、著書(邦題『内部告発-元チェルノブイリ原発技師は語る』)で、このような「沈黙の共謀」について「情報が公開されなければ教訓は得られない」と述べています。指導的な地位にある人々が真実に謙虚に向き合う義務を怠れば、どのような結末を引き寄せてしまうのか。チェルノブイリもフクシマも、人類が幾度も立ち返って見つめなおすべき教訓であり、事故から三〇数年を経て本書が読まれる意味も、そこにあると思うのです。
白水社、アダム・ヒギンボタム、松島芳彦訳『チェルノブイリ 「平和の原子力」の闇』P460-461
ソ連は原発は絶対に事故を起こさない安全なものだと述べ続けていました。そしてソ連の政治経済システムの定番である無理なノルマを原発開発に課し、粗悪な材料や物資の欠乏の中で原発を作っていきました。
ですが、そもそも無理なノルマなため計画通りにはいきません。さらには重大な危険が予想される欠陥も次々出てきます。にもかかわらず硬直した官僚主義によってそれらは改竄されたり、隠匿され、表向きはノルマを達しているかのように振舞い続けていたのです。
行き過ぎた官僚主義、腐敗した政治体制、貧弱すぎる生産システムというソ連末期の限界ぶりが明らかにこの原発事故の背後にはありました。
・・・となると、『では翻って「フクシマ」はどうだったのか』という疑問が浮かんできます。
日本ははたしてソ連のそうした実態を他人事だと言っていられるのでしょうか・・・?
この本を読みながらふと日本のことを考えてしまうと、ぞっとするような思いに駆られます。もし日本が当時のソ連と同じような状態だとしたら、これから先私たちの未来はどうなってしまうのでしょうか・・・?
これはあまりに恐ろしい可能性です・・・ですがそれを明確に否定できない自分がいるのは間違いありません。
また、次のことも非常に重要であるように感じました。以下はチェルノブイリがそもそもどのように国民に受け止められていたのかを解説した箇所です。
物語は一九七〇年二月、チェルノブイリ原発の起工式でソヴィエトの動力電化相が凍土にシャべルを入れる光景から始まります。何もない荒野に巨大な原発と職員が住む街をゼロから立ち上げる途方もない任務を託されたのが、当時三四歳のブリュハーノフです。所長とは名ばかりでまだ部下もいません。ソヴィエト特有の非効率と官僚主義に苦しみながらも、七年半で一号機の稼働にこぎつけた実務手腕は、やはり尋常ではありません。しかし、彼は原子力の専門家ではありませんでした。そこに事故の遠因となった管理体制の欠陥を見いだす人々もいます。
ポレーシェ地方と呼ばれる一帯の人口密度は、原発の建設が始まるまで一平方キロ当たり七〇人ほどでしたが、四号機の事故直前には原発の周辺三〇キロ圏に一一万人が居住し、ブリュハーノフが立ち上げたプリーピャチは五万人が住む近代都市となっていました。市民の平均年齢は二六歳。全土から優れた頭脳が集まる「アトムグラード」(原子力の街)は、まさに未来都市を先取りした若い活気にあふれていました。五号機、六号機が完成すれば、チェルノブイリは世界最大の原発になるはずでしたし、住民は数々の特権に恵まれてもいました。原子力を志す若者には垂涎の的だったのです。
二〇世紀は物理学の世紀、戦争と社会主義の世紀でした。天才アインシュタインらが物質と時空の法則を追求し、人類は原子力という究極の力を獲得しました。それは広島、長崎への原爆投下という悲劇を生み、冷戦時代には核戦争の現実味に世界が怯えたこともありました。しかし一方では原子力の平和利用への機運も高まりました。ソヴィエトは核兵器の開発ではアメリカとイギリスの後塵を拝しましたが、電力を生産する原子炉は世界で最初に導入しています。「平和の原子力」は対外向けプロパガンダの臭気を放ちながらも、ソヴィエト国家の優先事業となったのでした。プリーピャチの街に掲げられた「原子力を兵士ではなく労働者に!」というスローガンには、若々しく楽天的な気分が横溢しています。
ベラルーシ科学アカデミー会員のワシーリー・ネスチレンコはノーベル賞作家スベトラーナ・アレクシエービッチの聴き取りに対して「原子力の歴史は、軍事機密、謎、呪い、といったものばかりではない。これは私たちの青春、私たちの時代、私たちの宗教だったのです」(『チェルノブイリの祈り』)と語っています。宇宙開発とともに原子力はソヴィエトの最も華々しい成果となっていました。
最高政策決定機関である共産党政治局では、チェルノブイリ事故の詳細を公表することに強い異論が出ました。「科学は共産主義の基礎であり、共産主義はソヴィエトの国教である。(事実を公にすれば)国内だけでなく世界中で科学的社会主義の信用を落とすことになる」(ピアズ・ポール・リード『検証チェルノブィリ刻一刻』)というわけです。無神論の国家にあって、科学至上主義は共産主義イデオロギーとともに、体制の精神的支柱として機能していました。このような科学や技術への無邪気なほどの信頼や肯定に、チェルノブイリ四号機の爆発は深刻な打撃を与えました。
白水社、アダム・ヒギンボタム、松島芳彦訳『チェルノブイリ 「平和の原子力」の闇』P461-462
「原子力の歴史は、軍事機密、謎、呪い、といったものばかりではない。これは私たちの青春、私たちの時代、私たちの宗教だったのです」
「科学は共産主義の基礎であり、共産主義はソヴィエトの国教である。(事実を公にすれば)国内だけでなく世界中で科学的社会主義の信用を落とすことになる」
チェルノブイリ原発事故はこうしたソ連の根幹をなすイデオロギーの崩壊をもたらしたとも言えるかもしれません。
ユートピアを謳い、国民を導いてきたソ連が長い時を経て、ついにその限界を迎えてしまった。
その過程をこの作品では見ることになります。
チェルノブイリ原発事故は単なる事故ではありません。これは国のあり方そのものを問う巨大な事件でした。
ロシア・ウクライナ問題に揺れる今、原発の問題が強く注視されています。
日本も全く他人事ではない原発事故について大きな示唆を与えてくれる衝撃の一冊です。
この記事の最初に述べましたが、私はこの本に引き込まれ一気に読み切ってしまいました。まるでドキュメンタリー番組を観ているかのようにどんどんページが進んでいきます。分厚い見た目に圧倒されるかもしれませんが、非常に読みやすい作品です。これはぜひぜひおすすめしたい作品です。
以上、「アダム・ヒギンボタム『チェルノブイリ』原発事故はなぜ起こったのか、ソ連の政治経済・官僚システムとの繋がりも知れる名著」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら
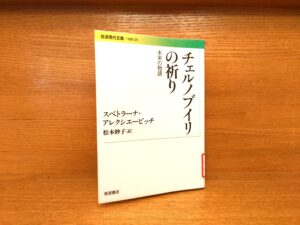
前の記事はこちら

関連記事

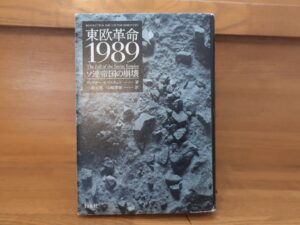














コメント