山崎佳代子『ベオグラード日誌』あらすじと感想~読売文学賞受賞作!空爆後のセルビア生活を紡った珠玉の言葉たち

山崎佳代子『ベオグラード日誌』概要と感想~読売文学賞受賞作!空爆後もセルビアで暮らし続ける詩人が紡ぐ珠玉の言葉たち
今回ご紹介するのは2014年に書肆山田より発行された山崎佳代子著『ベオグラード日誌』です。
著者の山崎佳代子さんは前回の記事でご紹介した『そこから青い闇がささやき』の著者です。

最初は、死者が名前で知らされる。それから数になる。最後には数もわからなくなる…。旧ユーゴスラビア。NATO軍による激しい空爆下で、帰国を拒み詩作をつづけた一人の女性の、胸をうつエッセイ集。
山崎/佳代子
1956年静岡市生まれ。北海道大学露文科卒業。1979年サラエボ大学に留学、ユーゴスラビア文学史を学ぶ。1986年ベオグラード大学文学部修士課程修了。2003年同大学文学部博士号取得(比較文学)。現在、同大学文学部日本学科教官。ベオグラード在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
Amazon商品紹介ページより
この本紹介にもありますように、著者は長年ベオグラードに住み、ユーゴ紛争勃発後の厳しい生活やNATO空爆を経験しています。その時の体験が綴られたのが前作『そこから青い闇がささやき』でした。
では、今作『ベオグラード日誌』について見ていきましょう。
2001年から12年。世界は変わってしまった…。これらの日付のある日々を刻むべオグラード、人々…。こわされたもの、深い闇に沈むもの、幽かな光となって現れ生まれてくるもの。
書肆山田、山崎佳代子『ベオグラード日誌』帯より
この作品はベオグラード空爆後のセルビアの日々を詩人の山崎佳代子さんが綴ったものになります。
あとがきで著者は次のように述べています。この本の持つ雰囲気や意義を知る上で非常に重要な箇所ですのでじっくり見ていきます。
バルカン半島という辺境の宿命について、今、思いを巡らせている。様々な征服者、幾つもの戦争が繰り返されるこの土地では、人の手が生み出したものを守り、文明の形を後世に伝え続けるのは困難だった。大きな国が形あるものを伝えることはさほど難しくはないが、小さな国が形あるものを伝えるのは容易いことではない。
しかし形のないものを語ること、形を失ったもの、これから形が生まれようとするものについて語ることこそが、言葉にゆだねられた仕事であるのだとしたら、南ヨーロッパの辺境で私が三十余年を過ごしてきたのは、それほど悪いことではなかった。悪戯好きの運命が、べオグラードという町で、私という「日本文学の戦中派」を産み落としてしまった。いつのまにか私の日本語が、日本文学の辺境を形作っている。
英語、独語、仏語、露語などの「大きな言語」という大窓から、世界を観るだけでは見えないことが数えきれないほどある。セルビア語をはじめとした「小さな言語」の小窓から眺めやれば、世界は思いがけない表情を見せる。人の心の底を見つめるときも、同じだろう。多くの人々がニューヨークの9月11日やフクシマの3月11日を記憶する。だが、記憶に刻まれるべき日付は無数にある。コソボ、イラン、イラクをはじめ、記憶されないだけではなく語ることさえ許されぬ悲劇の日付が、次々と世界史に書き込まれていく。
しかし国や言葉を越えて、心を開き合える仲間に巡り合うことは、なんという喜びだろうか。人と人との巡り合い、繋がりこそが、眼に見えない小さいカ、しかし、それだからこそ内なる世界を少しずつ変える力となるのではないだろうか。この小さい力さえあれば、様々な土地の歴史に刻まれた記憶の豊かさに触れ、命の重さの等しさを感じとり、自然の力の深さを確かめ合うことができる。生活というささやかな営みに潜む、無数の小さな力が結び合うとき、何かを変えることができる。
書肆山田、山崎佳代子『ベオグラード日誌』P226-227
「生活というささやかな営みに潜む、無数の小さな力が結び合うとき、何かを変えることができる」
この本を読めば、ここで著者が伝えようとしていることがよくわかります。
そしてこの本の中で一番印象に残った箇所を紹介します。
痕跡ー二〇〇四年
一月二日(金)
正月の電車はがらんとしていた。カレメグダンで降りる。動物園の煉瓦塀に沿って坂を下り、陸橋をくぐると、ドナウは霧に眠っている。岸の居酒屋は閉まっていた。暗い雨の支笏湖に行きバスの運転手に自殺者ではと疑われた、十九歳の秋が重なる。ゆきかう人もなく……。波止場には、空っぽの遊覧船が揺れていた。もう還るはずのない夏が、彼方に溶けている。初老の男女が、真剣に言葉を交わしながら足早に去っていく。線路に出た。貨物列車が通りすぎていく。鉄の音は遠ざかり、薄紅の石をふたつ拾った。何かにきっぱりと別れを告げるように、水を振り返る。詩とは、静かな光に身を捧げること。そうでしょう?
書肆山田、山崎佳代子『ベオグラード日誌』P82
あぁ・・・なんと美しい言葉でしょう・・・私はこの箇所に撃ち抜かれてしまいました。
特に、「線路に出た。貨物列車が通りすぎていく。鉄の音は遠ざかり、薄紅の石をふたつ拾った。何かにきっぱりと別れを告げるように、水を振り返る。詩とは、静かな光に身を捧げること。そうでしょう?」という言葉。
情景が目の前に浮かんでくるだけでなく、五感すべてが刺激されるような気がしませんか?そしてそれだけでなく、そこからにじみ出てくるような何かを感じます・・・!あまりの素晴らしさに、読んだ後私はしばらく余韻に浸っていました。
そして最後の言葉、「詩とは、静かな光に身を捧げること。そうでしょう?」です。
何度も申しましたようにこの作品は紛争後のベオグラードの日々を綴った作品です。上のあとがきにもありますように、ユーゴ紛争といえばサラエボ包囲戦や廃墟となった街、爆弾や銃の音が響く映像などが私たちの記憶に残っていると思います。
セルビアが報道されるとすれば、そうした衝撃的な映像が主なものとなると思います。
ですが、そこに生きる人はそうしたショッキングな事態の後もまさにその場所で日々を送っています。
私たちが「何かを記す」時、それは何らかの「いつもとは違った出来事」を記してしまいがちです。そしてそれが世界に発信されるとなると、そこからさらに「日常の当たり前」は無くなってしまいます。そして私たちはそうした「いつもとは違った出来事」をその地の生活の全てだと思ってしまう。これは意外と盲点です。
こうした「目に見える特別な出来事」ばかり世界に流れる現実についてはチェコの作家カレル・チャペックも面白いことを述べています。

上の記事の中でも紹介したのですが、せっかくですのでここでも読んでいきたいと思います。
さて、みなさん方は新聞の中に猫が小鳥を捕まえたとか、三匹子供を産んだとかいう記事を見たことは一度もありませんよね。新聞の記事は常に、特殊な、異常な、しばしば、びっくりするような報道という形でみなさん方の目に止まります。
たとえば、怒った猫が郵便屋に噛みついたとか、ある学者が猫の血清を発見したとか、プリマスとかいうところでは九本の尻尾のある猫が生まれたとか、まあ、そういった類いの記事です。(中略)
したがって私が言いたいのは、すでにチェスタートンをさえも不安にしたように、新聞の世界は例外的な事件、非日常的な出来事、そしてしばしば驚異と奇跡そのものから作られているということです。
だから、もし新聞に家のことが書かれるとしたら、家が建っているということではなしに、焼けたとか、壊されたとか、少なくとも世界で一番大きいとか、とにかくこの世にある、あらゆる家の中でも飛び抜けて何かが普通とは違っているというのでなくてはなりません。
ウェイターは愛人を殺すような異常な性格である。出納係が保管すべき金を持って逃げるが、その愛人はレギオン橋からヴルタヴァ川に身を投ずるという悲劇的結末にいたる。自動車は記録樹立のための、衝突事故のための、子供または老婦人をはねるための機械であるとかです。
新聞に載るものはすべて劇的かつ多少警告的な様相をもってあらわれます。毎日の朝刊とともに世界は無数の驚愕、危険、それに叙事的出来事のひそむ野生の王国に生まれ変わるのです。
社会思想社、カレル・チャペック、田才益夫編訳『カレル・チャペックの闘争』P13-14
こう言われてみると「おぉ~なるほどぉ、たしかに!」と素直に頷ける言葉ですよね。
チャペックは小難しい言葉や文体を用いません。ジャーナリストとして誰にでも読みやすい文章を用い、本質を突いた鋭い見解を説いてくれます。
この新聞論も一見当たり前のことを言っているように見えますが、実はものすごく鋭い指摘です。私達は新聞やメディア、今ではSNS等を用いて世の中の情報を得ていますが、それははたして本当に現実なのかとチャペックは問いを投げかけるのです。
ニュースは非日常を取り上げる。しかしそれを毎日毎日繰り返し見続ければそれが日常の現実に思えてくる。
いつの間にかニュースの世界が自分の世界へと変わっていき、自分達の周りの本当の日常の当たり前が見えなくなっていく。それをユーモアを交えながらチャペックは警告していきます。
ジャーナリストという、ニュースを書く側にいるチャペックだからこその説得力ある見解がここで説かれます。これは非常に興味深かったです。
そして話は戻りますが、山崎佳代子さんの『ベオグラード日誌』はこうした「非日常化された日常」ではなく、まさに「日常を日常として」綴っていく作品です。
「詩とは、静かな光に身を捧げること。そうでしょう?」
私はこの言葉にその姿勢が凝縮されているように感じました。
ユーゴ紛争、NATO空爆を経たベオグラードの街で著者は何を見て、感じたのか。
紛争後も続く何気ない日常。
その日常を綴った言葉の中に、じんわりと見え隠れしてくる紛争の影・・・
わかりやすい「特別な出来事」ではなく、そこで今も生きる人たちの日常を捉えたこの作品は非常に稀有な存在だと思います。ただ単に日常を切り取っただけでなく、そこに何か人間生活の奥深さが感じられてくる不思議。
この作品が読売文学賞を受賞したのももっともだなと思いました。不思議な力がある作品です。
前作『そこから青い闇がささやき』と合わせてぜひぜひおすすめしたい作品です。
以上、「山崎佳代子『ベオグラード日誌』読売文学賞受賞作!空爆後のセルビア生活を紡った珠玉の言葉たち」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事










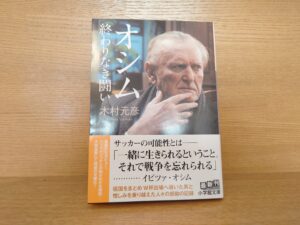
コメント