チェーホフ『三人姉妹』あらすじと感想~悲劇と喜劇の融合!晩年の熟練した技術が詰め込まれた傑作劇!

チェーホフ『三人姉妹』あらすじ解説

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより
『三人姉妹』は1901年に上演されたチェーホフ四大劇の第三作目の作品です。
私が読んだのは新潮社、神西清訳の『桜の園・三人姉妹』所収の『三人姉妹』です。
まず、この作品についての巻末解説を見ていきます。
さて、この一冊に収録した『三人姉妹』であるが、これはアントン・チェーホフ(1860-1904)の四大劇の第三作にあたる戯曲で、年譜によると、一八九九年はじめに着想され、翌一九〇〇年の晩秋に書きあげられている。
一八九九年はじめと言うと、名高いモスクワ芸術座による『かもめ』再演が前年の十月なかばであるからその二、三カ月後で、チェーホフは『かもめ』再演の成功にはげまされて、新しく知り合った劇団のために新作を書き下ろす気になったのだろう。
それにしては、着想を得てから書きあげるまでの期間が長いが、この一年半あまりの時期は結構、身辺いそがしい月日で、チェーホフは自選作品集の編集に忙殺されたり、約束の小説の執筆に明け暮れたりしている。約束の小説とは名高い『犬を連れた奥さん』と『谷間』である。
また結核が進行して、健康状態もよくなかった。ようやく新作戯曲に着手したのは、一九〇〇年の夏で、それからもチェーホフは、今度の戯曲は非常に書きづらい、何かごたまぜの感じで、登場人物がやたらに多いなどとこぼしている。
戯曲が書きあがると、芸術座は待ちかねたように稽古にはいり、翌一九〇一年一月末、モスクワで上演した。作者四十一歳のはじめである。
新潮社、神西清訳『桜の園・三人姉妹』P245
この作品は『かもめ』の再演に大成功したチェーホフ最晩年の熟練した技術が詰め込まれた劇となっています。
続いてあらすじを見ていきましょう。
四幕のドラマの第一幕は、オーリガ、マーシャ、イリーナの三人姉妹のプローゾロフ家。旅団長だった父親の一年まえの葬儀の記憶もようやくうすれて、末むすめのイリーナの名の日の祝いが開かれようとしている。
春、まぶしい陽の光で、うきうきしている。砲兵将校たちが祝いの会に集まってくる。やがては大学教授と期待されている男きょうだいのアンドレイといいなずけのナターシャとの恋。旧知の中隊長ヴェルシーニンの来訪が、三人姉妹にモスクワのなつかしさをよみがえらせる。
第二幕では、アンドレイは俗っぽいナターシャと結婚していて、赤ん坊も生まれ、もはや学者の夢を捨てかけている。学校の教師で家庭持ちの次女のマーシャと不幸な家庭生活を送るヴェルシーニンとの実りのない恋。トゥーゼンバッハ男爵のイリーナにたいする片おもい。ナターシャの俗悪さが次第に一家を支配して行く。
第三幕、近所の大火。焼けだされた人びとを助けようとする長女のオーリガの善良な魂。乳母のアンフィーサを、老いぼれの役たたずとののしるナターシャの醜悪さ。ヴェルシーニンとマーシャの恋が深みにはまって行く。アンドレイのいっそうの堕落。
第四幕、秋になって、駐屯していた中隊は新しい任地へと去って行く。
退役してイリーナと新生活に踏みだそうとしていたトゥーゼンバッハ男爵が、そのどさくさに、同僚のソリョヌイに決闘で撃ち殺される。マーシャとヴェルシーニンとの別れ。
軍楽のひびきがだんだん町を遠ざかって行くなかに、三人姉妹の生きたいという切実な願いのこもった、モスクワへのあこがれのせりふで幕がおりる。
筑摩書房、松下裕『チェーホフの光と影』P166-167
※一部改行しました
この劇もこれまでのチェーホフ劇と同じように、波乱万丈なストーリー展開ではなく、ある家庭における日常、すれ違いを描いていくことになります。
そしてこの作品はチェーホフの劇へのこだわりが強く出ている作品となっています。あとがきにはそのことについて次のように解説されています。
『三人姉妹』については、愉快な逸話がある。これはチェーホフの妻となった女優オリガ・クニッぺルの伝える思い出ばなしであるが、チェーホフが上京して来て、はじめて『三人姉妹』の原稿を朗読した時、それを聞いた芸術座の面々が、「これは戯曲じゃなくて梗概だ、これじゃ演技できない、役柄がない、ヒントだけだ」と、口々につぶやいたという。
この原稿は、今日われわれの読む戯曲のひとつ前の形の戯曲らしいが、これだけの内容を持つ戯曲を、当時の役者が戯曲として聞くことができなかった、舞台上の所作がただちに役者の頭に浮ばなかったという点が面白い。
よく世間では、チェーホフの劇を静劇と言って、彼の戯曲には事件がない、事件が起るのは舞台の外だなどと指摘するが、『三人姉妹』はそうしたいわゆるチェーホフ的な静劇を一そう徹底した形で書かれていたのである。
これに関連してよく語られる話に、作者と演出家とのあいだに起った小さな争いの逸話がある。
初演の演出家は、有名なスタニスラフスキイであるが、彼は終幕の幕外で男爵トゥーゼンバフがソリョーヌイとの決闘で落命したあと、わざわざ男爵の死体を戸板に乗せて、舞台を横切るように演出した。
屍骸はつねに強烈な印象を観客に伝えるはずである。ところが、チェーホフはそれを聞いて憤慨した。戯曲にはそんなことは書いてないというのである。一発の銃声、それでその場は表現できると信じたのだ。
新潮社、神西清訳『桜の園・三人姉妹』P245-246
『かもめ』で圧倒的な成功を収めたチェーホフ。その新しい演劇方式は演劇界に革命をもたらしました。チェーホフは独自な劇をするということが世に広まった後ですら、この台本を読んだ舞台関係者は困惑してしまうほどでした。
最後にこの作品に対する解釈について見ていきます。
『三人姉妹』の解釈は、今日ではだいたい定まっている。以前には、この戯曲は、三人姉妹の悲しい運命を描く暗い憂鬱な物語と考えられていた。これは人間の美しい夢が、俗悪な、日常的な現実のなかで次第にしぼんで枯れてゆく話である。この意味において、戯曲の基調は暗い。(中略)
ところが、作者自身が戯曲の中に書いていることだが、このような暗い憂鬱な日々はこのままつづくはずはない、「今や時代は移って、われわれ皆の上に、どえらいうねりが迫りつつある、こういう時代の認識、時代感覚のもとにこの戯曲が書かれたことに注目するならば、―チェーホフは革命の到来をはっきりと予見していたわけではないが、―『三人姉妹』がただ三人姉妹の悲しい運命を描くためにのみ書かれたはずはないのである。
このことは、戯曲のそこここに語られる、人類の明るい未来への確信を歌う美しいせりふからも感じられるのであるが、同時にまたこの戯曲の登場人物の多くが、行動も行動の意味も知りかねている、また知ろうともしない世紀末の知識人の弱点を表わす、ある意味では滑稽な人物として描かれていることからも理解されるのである。(中略)
このように考え、また前にふれた、戯曲の内部に含まれた各種のドラマに配慮するならば、『三人姉妹』は単なる暗い悲しい劇ではなくて、悲劇的な基調と、喜劇的な色彩の交錯した一種混合的な人生劇であると言うことができるだろう。
モスクワ芸術座の新演出を含めて、今日の『三人姉妹』解釈は、おおよそこんな意味合いにおいてなされているようである。そうしてまた、この悲劇、喜劇のふたつの要素を巧みに取合せたところにも、チェーホフの作劇の見事さが知られるのである。
新潮社、神西清訳『桜の園・三人姉妹』P247-249
※一部改行しました
たしかにこの作品は四大劇の中でも一番暗い雰囲気が漂っています。本で読むと余計それが感じられるかもしれません。
私はまだ劇を観ていないので何とも言えませんが、おそらく役者が演ずることで本では見えにくい滑稽さというのがもっと見えてくるのかもしれません。
ストーリーそのものが持つ滑稽さ、明るい未来を志向する雰囲気もあるかもしれませんが、登場人物達のすれ違いやずれたやり取りの妙が舞台上で現れるからこそこの劇が単なる暗い悲劇で終わらない何かがあるのではないかと思いました。
これも機会があればぜひ舞台で観てみたい作品です。
以上、「チェーホフ『三人姉妹』あらすじ解説―悲劇と喜劇の融合!晩年の熟練した技術が詰め込まれた傑作劇!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事














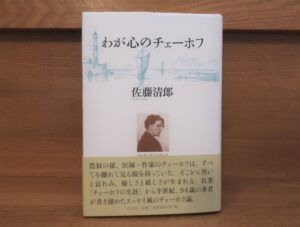

コメント