チェーホフ『僧正』あらすじと感想~幼い頃の幸福な思い出~僧正と母の再会・死別を描いた感動作

チェーホフ『僧正』あらすじ解説―幼い頃の幸福な思い出~僧正と母の再会・死別を描いた感動作

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより
『僧正』は1901年にチェーホフによって発表された作品です。
私が読んだのは中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』所収の『僧正』です。
早速あらすじを見ていきましょう。
徳高く、名誉ある高位聖職者である僧正ピョートルはミサの最中、丸9年も会っていなかった母の姿を見たような気がします。これがすべてのきっかけでした。
僧正は、もう丸九年あわなかった実の母親であるマリヤ・チモフェーエヴナが、群衆にまじって自分に近づいて来るような気がした。それとも、母に似た老婆であろうか。彼女は、僧正からやなぎの小枝をおしいただくと、気のよさそうな、嬉しそうな微笑を浮かべながら、晴れ晴れと彼の顔を見つめたまま、引き下がって人ごみのなかに消えた。
すると、なぜか涙がはらはらと彼の顔を伝って流れ落ちた。心も安らかで、何ひとつ不満の種とてないのに、彼は身じろぎもせずに、朗誦の声の聞える、もう夜闇にかげって誰ひとり定かに見分けられぬ左手の唱歌隊席を見つめたまま、静かに泣いていた。顔や、あごひげに涙が光りはじめた。
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P288-289
そしてミサが終わり僧院に引き上げると、侍僧が僧正ピョートルの母が今日ここに来ていることを告げます。さっき見たあの老婆はやはり母親だったのです。
彼は母のこと、そして幸福な少年時代を思い返します。
僧正はごく幼い時分―ようやく三つになるかならぬかの時分から、母のことを覚えていた。―そして実際、どんなに愛していたことだろう!ああ、なつかしい、得がたい、忘れえぬ少年時代!
なぜあの永遠に去ってしまった、二度と帰り来ぬ時は、なぜあの昔は、実際にあった時よりも明るく、楽しく、豊かに思われるのであろうか?少年時代や青年時代に病気をした時、どんなに母は優しく、思いやりにあふれていたことか!
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P291
翌日、彼は母親と再会することになります。彼は幼い日の幸福な思い出と母への思いを抑えきれません。しかし母の態度は彼が求めていたものとはまったくちがったものでした。
母は最後まで「僧正様」としてのピョートルに対する恭しい態度を崩さなかったのです。かつてのように「パヴルーシャ(ピョートルの愛称)」と接してほしかったピョートルとしてはそれはショックな態度でした。
ピョートルからすれば、僧正となった今も昔と同じく愛する母の息子でした。しかし「僧正」という肩書、「仮装」がピョートルという人間そのものを覆ってしまっているのでした。母はその「仮装」を通してしか今は見てくれない。そのことにピョートルは深い悲しみを抱くのでした。
自分を生んでくれた母が訪ねてきても、この「仮装」の前ではうやうやしい態度をとり、言葉使いまで改まって、わが子を「あなたさま」と呼ぶのである。身も心も裸になりたい。安らぎはそのときにのみつかめるだろう。地位という衣裳が心を曇らせる。幼児のごとき心になりきりたい。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P314
その後まもなくして僧正は体調を崩します。彼は腸チフスにかかってしまったのです。
彼はそのまま死へと向かっていきます。
腸出血のためみるみるうちに彼の顔は青ざめ、げっそりしてしまいました。
年老いた母が来た。息子の皺だらけの顔や大きな眼を見るなり、彼女はびっくりして寝台の前にひざまずき、彼の顔や肩や手を接吻しはじめた。彼女にもなぜか、彼が誰よりも痩せて弱く卑しくなったように思われた。もう彼が僧正だとは思えなくなった。彼女は彼を、身近な生みの子供として接吻した。
「パヴルーシャ、お前」と彼女は言いはじめた。「わたしの息子!大事なせがれ!……どうしてお前はこんなになったの?ね、バヴルーシャ、返事をしておくれ!」(中略)
僧正はもう口を利く力もなく、何ひとつ理解もできなかった。ただ、もうあたり前の素朴な人間に帰った自分が、杖をつきながら素早く陽気に野原を歩いているような気がしていた。頭上には日光の満ちあふれる広い大空が広がっている。そして今や鳥のように自由な彼は、どこへでも歩いて行くことができるのだ!
「ああ、可愛いパヴルーシャ、返事をしておくれ!」
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P306-307
しかし母の懇願も虚しく、彼はそのまま息を引き取ってしまうのでした。
佐藤清郎氏はこの作品について次のように述べています。
『僧正」は、権威と尊敬に輝く僧正のきらびやかな服の下にある生身の人間の苦悩、名声の下にある当り前の人間を描いたものである。生母からさえ「お前」でなく「あなたさま」と呼ばれる名誉に輝く人間の、平凡な、それゆえに愛すべくいじらしい魂を描いたものである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P314
死に瀕し、げっそりとやつれたピョートル。その姿はもはや「高貴な僧正」ではなく、ひとりの死に瀕した人間でした。だからこそ「僧正」という仮装が取れた姿を見た母は愛する息子パヴルージャをそこに見出すことができたのです。
ピョートル自身も最後の最後に「ありのままの自分」としていられたことに満足して命を終えていきます。
地位もあり、徳の高い僧正ではありましたが、そうであるがゆえに抱えていた苦しみが彼にはあった。彼は幼い時の自由で幸福な思い出と母の愛を胸にして亡くなっていったのです。
子の母への思いと、母の子への思い。
この物語は20ページほどの短い物語ではありますが思わずじーんとくるものがあります。母が最期に息子に呼びかけるシーンは何度読んでも泣きそうになります。
この作品が書かれたのはチェーホフの晩年です。
チェーホフ自身も結核でこれ以上あまり長く生きられないことを覚悟していたと思います。そういう時期にこの作品が書かれたというのもチェーホフを知る上で非常に意味があることなのではないかと私は感じました。
この作品もおすすめです。チェーホフ作品の中でも随一の感動作です。
以上、「チェーホフ『僧正』あらすじ解説―幼い頃の幸福な思い出~僧正と母の再会・死別を描いた感動作」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
チェーホフ全集〈11〉小説(1897-1903),戯曲1 (1976年)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事












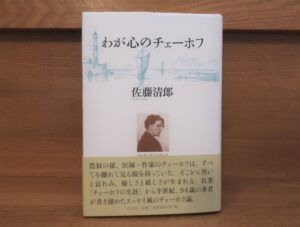


コメント